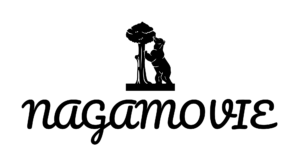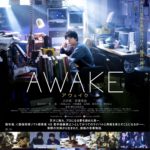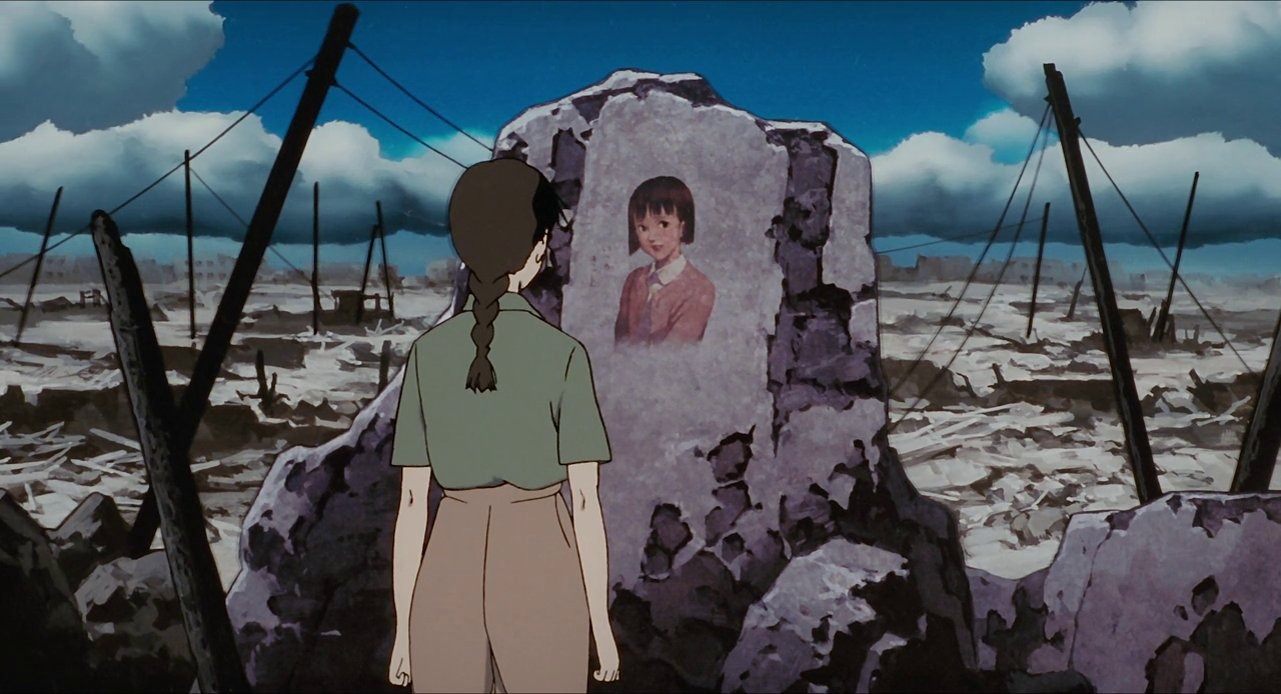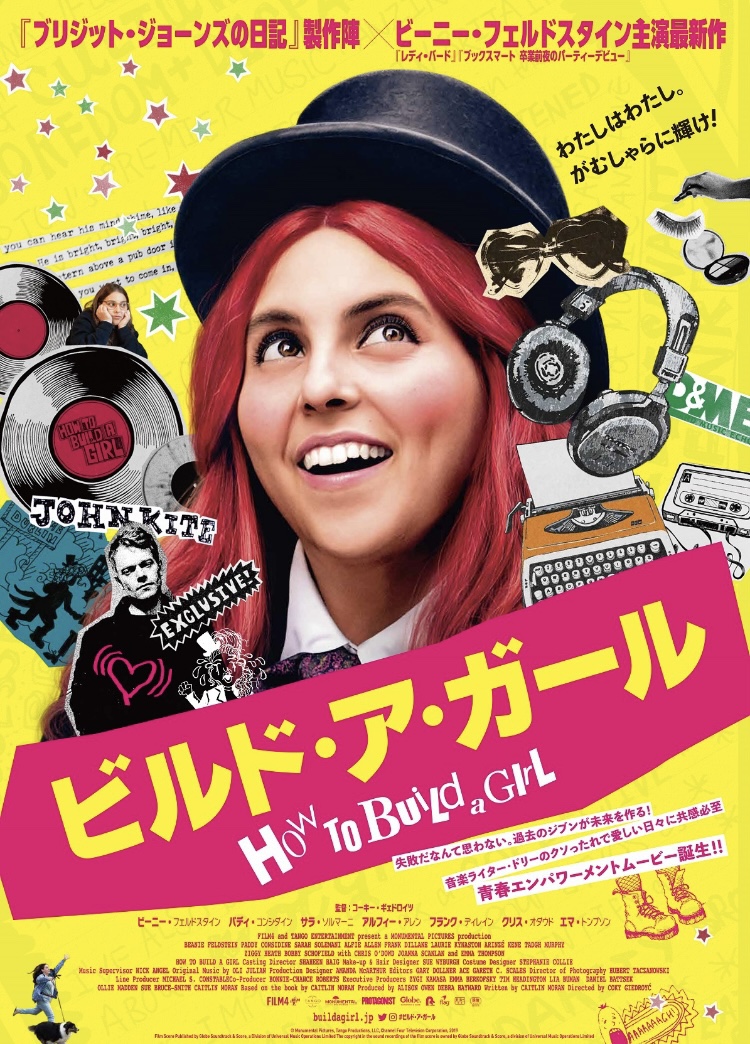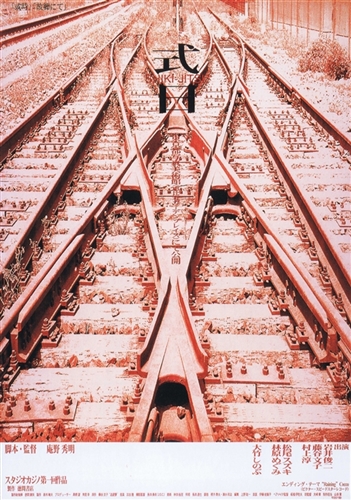みなさんこんにちは。ナガと申します。
新年、あけましておめでとうございます。本年も当ブログ「ナガの映画の果てまで」をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年最初に扱う作品は、映画『Swallow スワロウ』です。
情報が解禁された時から、本当に楽しみにしていた作品で、その冷たくも美しい映像とホラーチックな設定に心を惹かれました。
男性中心社会、家族主義の中で、夫に尽くす役割を、そして何より子どもを産むという役割を押しつけられていく女性の物語なのですが、その欲望のはけ口がすごいのです。

赤ちゃんが、口に入れて確かめて、それがどんな物かを判断する癖があるとしばしば言われますよね。それは発達段階に表出する正常な行動と言えます。
しかし、大人がそんなことをするようになると、一種の「幼児退行」のような趣が出てきますよね。
人間はあまりにもショックな出来事や強いストレスを経験すると、「幼児退行」という心の防衛機能が働くと言われています。
本作『Swallow スワロウ』で描かれるハンターの、ものを飲み込まずにはいられない衝動も、何かしらのストレスやショックから来ていると言えるでしょう。
では、その原因になったものは何なのか。彼女をいかにして追い詰めたのか。
そこをじっくりと描いていくことに、本作の「女性を主人公にした映画」としての意義があるように思います。
設定やプロットの「過激さ」が目について、少し「扇動的」にはなっていますが、描いているものは、そうした表層的な部分と比べても、もっと奥深い人間の心理ないし、女性の抑圧と解放なのです。
今回は、そんな映画『Swallow スワロウ』についてお話していきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『Swallow スワロウ』
あらすじ
ハンターは、大企業の1人息子のリッチーと結婚し、何不自由ない生活を送っていた。
そんなある日、彼女の妊娠が発覚します。
リッチーと彼の両親は、妊娠を喜んでくれるのですが、それから一層彼女は自宅に縛り付けられるようになり、閉塞感に苛まれます。
自分はリッチーの夫としてしか、そして彼の子どもを産むことにしか価値がないのではないか…。
そうして、自らの心身の「自由」を喪失していく彼女は、そのストレスからある行為に及びます。
それは、部屋に置かれていたガラス玉を飲み込むこと…。
ハンターは、その行為に痛みや苦しさを感じつつも、快感を感じるようになり、その頻度や内容をエスカレートさせていき…。
スタッフ・キャスト
- 監督:カーロ・ミラベラ=デイビス
- 脚本:カーロ・ミラベラ=デイビス
- 撮影:ケイトリン・アリスメンディ
- 美術:エリン・マッギル
- 編集:ジョー・マーフィ
- 音楽:ネイサン・ハルパーン
- 音楽監修:ジョー・ラッジ










監督を務めたのはカーロ・ミラベラ=デイビスです。
彼は、本作の着想を、1950年代に執拗に手洗いをしていた作家兼監督だった祖母に得たと語っています。
祖母は、「彼女は1日に4つの石鹸と、1週間に12本の消毒用アルコールを飲んでいた」のだとか。
また、カーロ・ミラベラ=デイビス自身も「性」の面で、複雑な人生を送ってきた人物です。
現在は、男性として自分の「性」を受け入れているようですが、20代の頃には自分が女性であると感じ、名前を変え、女性の衣服をまとって生活をしていたこともあるようです。
そうした時期があるからこそ、彼は、自分事として「女性の抑圧」を描くことができるのではないでしょうか。
こうした背景情報も知った上で、作品を見ていただけると嬉しいです。
劇伴音楽には、『一人っ子の国』や『行き止まりの世界に生まれて』などのドキュメンタリーフィルムの音楽を手掛けることが多い、ネイサン・ハルパーンが起用されています。
シンプルながらも、物語をスリリングに浮かび上がらせる、その独特の音楽には要注目です。
- ヘイリー・ベネット:ハンター・コンラッド
- オースティン・ストウェル:リッチー・コンラッド
- エリザベス・マーヴェル:キャサリン・コンラッド
- デヴィッド・ラッシュ:マイケル・コンラッド
- デニス・オヘア:ウィリアム・アーウィン
- ローレン・ヴェレス:ルーシー










さて、本作の主演を務めたのはヘイリー・ベネットですね。
彼女は、『ガール・オン・ザ・トレイン』などで知られる女優で、女優だけでなく歌手としても活躍しています。
その夫役を演じたオースティン・ストウェルも『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』や『ブリッジ・オブ・スパイ』などの話題作に多数出演した俳優です。
その他にも、『ギフテッド』のエリザベス・マーヴェルや、『ジャッジ 裁かれる判事』などにも出演したデニス・オヘアらが出演しています。










『Swallow スワロウ』解説・考察(ネタバレあり)
静かで冷たい映像に隠された3つの魅力
多くの人がこの『Swallow スワロウ』という作品を見た時に、強い衝撃を受けるでしょう。










今作は、先ほどもお話しましたが、カーロ・ミラベラ=デイビス自身の祖母が経験した「女性として受けた抑圧」と、それに伴って発症した石鹸や消毒液を飲み込む症状に着想を得ています。
彼の祖母は、電気ショック療法とインスリンショック療法、およびロボトミー手術まで受けさせられたということですが、まさしく「女性」であること、そして「妻」ないし「母」であることに縛りつけられ、家父長制の下で「自由」を奪われたのです。
そうしたバックグラウンドを、本作『Swallow スワロウ』の主人公であるハンターは引き継いでいます。
本作のファーストカットはハンターと彼の夫であるリッチーを対比的に映し出します。
ベランダで川の向こう側に広がる広大な景色を見つめるハンターは、従来的なディズニープリンセスのようであり、閉じ込められ、どこにも行くことができない自らの境遇を嘆いているようでした。
一方のリッチーは、自宅で飼育している山羊の1匹を夕飯のために絞める様が映し出されていましたね。
このファーストカットの対比が、2人の「幸せ」という仮面に上塗りされたその背後に隠されたものを端的に浮き彫りにしていたように思います。
そこからは、ひたすらにハンターの経験した家父長制の下での地獄が映し出されていくのですが、まあこれが男の自分が見ても心が痛くなるような言動の連続でした。
多くの映画「女性の解放」を描いた作品は、まず心理的・精神的な部分に焦点を当てますよね。近年の映画を見ていると、その傾向が強いように感じます。
しかし、この映画はむしろ「女性の身体的な解放」に重きを置いていました。
そして、『Swallow スワロウ』はそれを映像で表現するのが非常に巧かったのです。
まずは、そうした本作の映像的な部分の凄みを3つの観点からお話させていただきます。
色温度が計算されつくした映像
まず、本作を見ていて目につくのは、その独特の色彩感覚でしょう。
ポスターは全体的に赤色を基調に作られているので。本編もそうだろうと思って鑑賞したのですが、実は赤色が使われているのは、ハンター周りだけなんですよ。
彼女のリップ、チーク、身につけている服、そして身体から吹き出す血。
色温度の高い「赤」はハンターに関連するものだけに印象的にあしらわれており、それと対照的に、彼女が暮らしている家は、全体的に「冷たい」印象を与えるように色温度が抑えられています。
とりわけ彼女の部屋の窓ガラスに赤色のシートが貼られていたのは印象的ですよね。
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
そこには、彼女があの色のない家で失い、そして取り戻そうとしている「赤=生命」や「痛み」が宿っていたように感じました。
映し出す空間の限定がもたらす閉塞感
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
この映画を通じてなのですが、ハンターがあの家の外に「1人で」出るシーンは基本的に終盤に至るまで皆無です。










時折、家の外のシーンもあるのですが、そういうケースでは夫のリッチーやその家族と一緒にいるので、1人でいることはまずありません。
さらに、彼女が異食症を発症してからは、唯一彼女が1人でいられる場所であった自宅にも看護師の男性が24時間介入することとなり、彼女は「自由」を奪われていきます。
また、劇中で幾度となくインサートされる彼女がベランダから川を隔てた向こう側の世界を眺める描写が残酷でした。
世界は広大で、どこまでも広がっているのに、私はこのベランダの見えない「檻」に囚われていて、どこにも行くことができないという悲哀が際立っていたように思います。
こうした閉塞感を強める演出があることにより、仮初めの「幸せ」という名の牢獄や支配が、いかにハンターを追い詰めていったかが圧倒的な強度で現前していたのです。
脱中心性とハンター
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
最後に、本作の映像的な特徴として触れておきたいのは、アングルです。
この映画の序盤では、ハンターがひたすらに映像の中心から排除されていることが伺えます。
印象的なのは、ハンターと夫のリッチーが2人でディナーを食べているシーンですが、この時カメラはハンター1人を捉えているにも関わらず、彼女を映像の中央から外していました。
その他にも、ハンターが映し出されているシーンでは、必ず他の人物が映し出されており、彼女は映像の中心から排除されているのです。
そんなハンターが映像の中心を取り戻すのは、異物を飲み込み始めてからなんですよ。
ビー玉を皮切りに押しピンといった金属系の異物を摂取するようになるハンターですが、そうした行動を通じて、彼女は映像の中心に立つことができるようになるのです。
カウンセラーとの会話の中で、異物を飲み込むことによって、自分に自信を持つことができると語っていましたが、彼女はそうすることで自分の人生の「主人公」になれるのでしょう。
しかし、その件が発覚し、夫の紹介で看護師が自宅に24時間滞在するようになると、再び彼女は自らの中心性を奪われていきます。
映像の中央には、夫のリッチーや義祖父が君臨するようになり、家父長制のイメージが何度も反芻され、さらに自宅で1人でいるときにも看護師が映像のどこかに映り込み、決して1人にはさせてくれません。
そんな彼女が再び、映像の中心に立つことができるようになるのは、終盤も終盤のことです。
本作は、こうしたアングル的な刷り込みによって、ハンターの置かれている状況や心情を視覚的に表現していたと言えます。
なぜ、ハンターは異物を飲み込むのか?
さて、ここでもう1つ注目したのは、やはりハンターがなぜ異物を飲み込むのか?という点ですよね。
この解釈は難しいのですが、私は次の2つの意味があったと考えています。
美しく安定したものを取り込む
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
1つ目は、自らの中に「美しく安定したもの」を取り込みたいという欲求なのではないでしょうか。
とりわけ彼女が最初の方に飲み込んでいた氷やビー玉は「美しい」に該当すると思います。
氷やビー玉はキラキラとしており、美しいモチーフとして描かれていました。
一方で、彼女がしばしば取り込むようになった金属類ですが、鉄は全ての元素の中で,最も原子核が安定しているとも言われます。
カウンセリングの中で、ハンターはその「ひんやりとした」感触が好きだと語っていましたが、鉄という元素が内包する「安定」を彼女は摂取していたのではないかとも考えられます。
そこには、彼女の生い立ちないしバックグラウンドが大きく紐づいていると言えるでしょう。
ハンターは母親がレイプされ、さらにキリスト教の右派の教えの下で、中絶を認められなかったが故に生まれた子どもです。
そのため、彼女は自分が汚れた存在、醜い存在、誰からも必要とされない存在だと自嘲しながら育ってきたのではないでしょうか。
そうした背景が垣間見えるのが、彼女が家出をした際に実家に連絡を取るシーンです。
この時、妹夫婦が来ているから、「部屋がないのよ。」と母親はハンターに告げました。
しかし、英語ではこの時母が告げたのは「There is no room.」という言葉です。










roomという言葉には、確かに「部屋」という意味があるのですが、それとは別に「居場所」という意味があります。
だからこそ、このシーンでハンターが唯一の心の拠り所でもあった母親から突きつけられた言葉が意味するのは、「あなたの居場所がないのよ。」なのかもしれません。
自らの存在が醜く、そして不安定に感じられるハンターは、ビー玉や金属類を飲み込むことで、自身を取り戻し、心の安定を取り戻しています。
その点で、異物を飲み込むという行為は、「美しく安定したもの」を体内に内包するためのある種の医療的、儀式的な行為と言えるのではないでしょうか。
自らの身体を感じるための行為
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
ここまでもお話してきたようにハンターは、自らの身体的な自由を奪われています。
とりわけ、彼女が妊娠してからその傾向は加速しました。
ハンターは1人の女性ではなく、リッチーの妻として認識されるようになり、挙句の果てには「後継者を生むための保育器」のような扱いを受けるのです。
彼女が異食症を発症した際も、リッチーや彼の両親の関心は表面的にこそハンターに注がれていますが、彼らの関心の中心はお腹の中の子どもでしかありません。
そうして身体的な自由を奪われながらも、金銭的にも安定し、何一つ不安を抱く必要もない生活に、彼女は自らの存在を感じることができなくなっていったのではないでしょうか。
身体は「自由」を奪われ、心は単調な生活の中に埋没し凪いでいく。
そうした「痛み」や「刺激」を奪われた生活は、彼女から生きている実感そのものを奪っていったと言えるでしょう。
彼女が押しピンのような身体を傷つけるような物体であっても平気で飲み込んでしまい、その痛みに快感を抱いている様子が映し出されました。
つまり、異物を飲み込むという行為は、彼女自身の身体性や生命の確認ないし「自由」の奪還なんですよ。
あの家では、彼女は何1つ自由に決めることができません。
決められるのは、せいぜいカーテンの色くらいで、プールサイドに花を植えるかどうかでさえも夫に確認を取らなければ決めることができません。
しかし、異物を飲み込むという行為に際しては、彼女は自分の身体を自分の裁量で決めることができます。
だからこそ、彼女は自分自身を確かめるために、そして唯一の身体的自由を享受するためにあの行為を続けていたのではないでしょうか。
女性が自らの身体の自由を取り戻す戦い
さて、この映画が描いたのは、先ほども書きましたが、主人公のハンターが自らの身体的な自由を取り戻すための戦いです。
夫のリッチーは表面的には、良い夫を演じていますし、彼の両親もハンターを気遣う素振りを見せています。
しかし、彼らがハンターを気遣うのは、結局のところ彼女が後継者を身籠っているからに過ぎないんですよね。
それが表出するのが、家出をしたハンターがモーテルでリッチーと電話をする際のやり取りです。
当初、彼は「愛している」「戻って来てほしい」などという耳ざわりの良い言葉を並べていますが、ハンターが帰宅を拒否するや否や、「俺の子どもを返せ!」と本性を露にします。
結局のところ、リッチーもハンターの身を案じているのではなく、後継者の「保育器」としての彼女を案じているに過ぎないんですよね。
ハンターは、自らの存在を確かめるべく、実の母をレイプした男の下を尋ねます。
そこで彼女が確かめたかったのは、自分は「恥ずべき存在なのか?」という1点です。
レイプによって産まれた、古き悪しき信仰の産物として生まれた、そして何より望まれずに産まれた自分には価値があるのか。
ハンターは、結婚をし、自らの存在を穏やかに否定され続ける日々の中で、その境遇をフラッシュバックし、自分という存在の価値が分からなくなっていきました。
それでも、アーウィンは自らが犯した行為そのものが「恥」なのであり、君は決して「恥ずべき存在ではない」のだと伝えてくれました。
そうしてハンターは、ようやく自らの「身体」を取り戻すための1つの決断を下します。
それは、中絶を誘発する薬品を服用し、リッチーとの間にできた子を自らの身体から排出することです。










ただ、それは現実世界において「中絶の是非」の議論に終わりがないことと同様ですから、賛否両論で良いのだと思います。
ここで大切なことは、ハンターが自らの「身体」を取り戻すことができたという点なのです。
彼女は、リッチーと暮らしていた家を飛び出してからも、お腹の中に身籠っていた子どもが故に自分自身の人生を取り戻すには至っていませんでした。「自由」を取り戻すことは叶わなかったわけです。
しかし、彼女はラストシーンで、身籠っていた子どもを手放し、自らの「身体」と「自由」を明確に奪還します。
(C) 2019 by Swallow the Movie LLC. All rights reserved.
それは、強烈な家父長制へのカウンターであり、抑圧からの脱却でもありました。
そして、ハンターが自分を「主人公」とした人生を改めて始めるための再スタートを描いたとも言えるでしょう。
映画のクライマックスで、彼女は再び映像の中心に君臨します。
まさしく彼女は自らの「身体」と「心」の主導権を取り戻したのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『Swallow スワロウ』についてお話してきました。










日本というより、アメリカでかなり議論が紛糾しそうだなと思ったのですが、Rotten Tomatoesでの批評家からの支持は80%を超えており、かなり好意的に迎えられていることが分かります。
映像的には、文句なくすぐれた作品ですし、だからこそ、多くを語ることのない映画ですが、ハンターの置かれた境遇がリアルに私たち観客にも伝わってきました。
「幸福な牢獄」の中で、心とそして何より身体の「自由」を奪われていく女性が、「自由」への渇望として、異物を飲み込むという行為に及ぶという動機付けもしっくりきました。
そして、賛否はあるでしょうが、ラストシーンで明確に自らの「自由」を取り戻すハンターの姿に、不思議な解放感を感じましたね。
2021年の最初に適した映画かどうかは分かりませんが、ぜひ見ておいていただきたい1作でした。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。