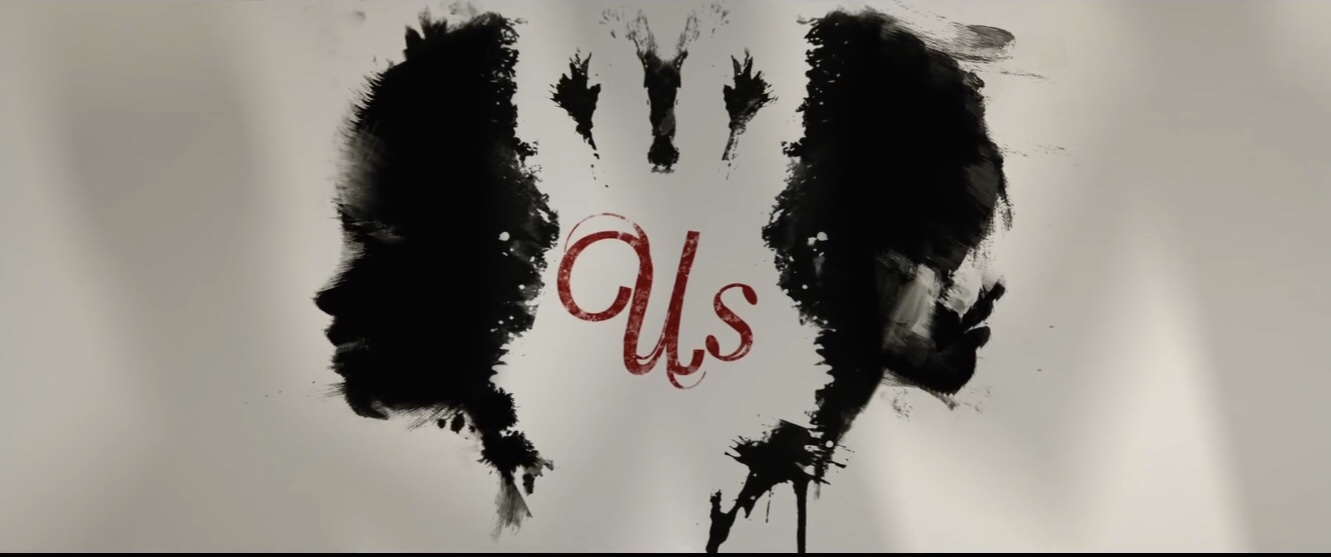みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『コーダ あいのうた』についてお話して行こうと思います。

2014年製作のフランス映画でフランス国内でも大ヒットを記録した『エール!』をアメリカ主導でリメイクしたのが、今作『コーダ あいのうた』となります。
こうしたいわゆる「ハリウッドリメイク」作品は数多く存在しますが、先日Netflixで配信された『ギルティ』などもそうで、オリジナル版と比較されて、高い評価を得られないケースも散見されるんですよ。
ただ、今作はリメイク版も非常に高く評価されていて、北米の大手批評家レビューサイトのRotten Tomatoesでは、批評家の96%、並びにオーディエンスの93%から支持されています。
当ブログ管理人も、オリジナル版の『エール!』と今作『コーダ あいのうた』の両方を鑑賞しておりますが、本当に丁寧に作られたリメイクという印象を受けましたね。
設定や物語の舞台は大きく変わっているのですが、大筋は同じでかつ、演出がオリジナル版よりもブラッシュアップされていた点に、リメイクとしての真摯な向き合いかたを垣間見たような気がしています。
また、楽曲の選曲も素晴らしく、ジョニ・ミッチェルの名曲『青春の光と影』(Both Sides, Now)を扱ってくれたのはグッときました。
この楽曲は「青春時代の光り輝くような体験と、その影として存在する苦労や悲しみといった両面は、振り返ると幻のようであり、人生なんてわからないものなんだ!」というメッセージを内包しており、主人公の心情に寄り添った1曲だと思います。
また、主人公を子役時代から舞台に立ち、ミュージカルなどにも定評があるエミリア・ジョーンズが演じ、今作をきっかけに一気に注目を集めました。
サンダンス映画祭で観客賞をはじめ4冠を達成するなど、本年度の賞レースにも加わっている映画『コーダ あいのうた』についてここからは自分なりに感じたことや考えたことをお話していこうと思います。





『コーダ あいのうた』感想と考察(ネタバレあり)
本作のタイトルは『CODA』となっていますが、この言葉は、「Children of Deaf Adults= ⽿の聴こえない両親に育てられた⼦ども」という意味を持っています。
ちなみに音楽用語にも「CODA」という言葉があり、こちらは「楽曲において独立してつくられた終結部分」を意味していますね。
今作のタイトルである『CODA』はこの2つの意味を兼ね備えたダブルミーニングとしてつけられたものだと思います。
前者は設定的な言及を為している一方で、後者は本作が主人公のルビーにとっての1つの「終わり」を描いているという点での物語的な言及を為しているのです。
こうしたタイトルが内包する二重構造は、映画本編の物語や演出の中にも溶け込んでおり、それらが作品を豊かで、重奏的な味わいに仕上げていました。
今回の記事では、そうした作品の持つ二重構造をいくつかの観点から解説してみようと思います。
青春と大人、海と湖
本作の主人公であるルビーは「Children of Deaf Adults= ⽿の聴こえない両親に育てられた⼦ども」であり、両親と兄は耳が聴こえません。
そうした家庭環境によってルビーは、他の子どもたちとは少し違った幼少期を過ごしてきました。
劇中でその例の1つとして、彼女が両親と共に訪れたファミリーレストランで、両親が飲むビールを注文していたというエピソードが挙げられていましたね。
また、彼女は高校生であるにもかかわらず、父と兄が携わる家業(漁)の手伝いに追われており、それが学生としての本分にまで支障をきたしている始末です。
こうしたエピソードは、ルビーがその家族の性質によって、「子ども」でいることを許されてこなかったという側面を明らかにしています。
幼いころから両親や兄の「通訳師」としての行動を求められ、家族の収入を支えるために働いてきた彼女は、マイルズが指摘していたように幼いころから「大人」だったのです。
しかし、そんな彼女が歌うことに対する喜びを知り、音楽大学に通ってきちんと学びたいという「子ども」としての本来の願望と欲求に目覚めたとき、周囲の家族との間に摩擦が生じてしまいます。
幼少のころから「大人」だったルビーありきで仕事や生活を成り立たせてきた家族は、彼女が「子ども」時代を取り戻し、自由に自分の好きなことに取り組むという選択を受け入れることができないのです。
こうした「子ども」と「大人」という軸は、本作『コーダ あいのうた』に通底しており、とりわけそれを表象するモチーフとして「海」と「湖」が登場しています。
「海」は父や兄が漁をして稼ぎを得る空間として描かれており、ルビーにとっては「大人」を象徴する場所です。
一方の「湖」はアメリカの青春映画では定番のロケーションであり、『IT』のような青春映画でもしばしば扱われることからも、「子ども」を強く印象づける空間です。
合唱の授業で人前で歌うことから逃げ出したルビーが向かったのが、「湖」であり、そこではありのままの自分で歌えていたことからも、「湖」は彼女の本心を表すものとしても描かれていますね。
「海」では父や兄との漁が描かれ、「湖」では同級生のマイルズとのロマンスが描かれるという対比は、「大人」と「子ども」という本作の軸にも重なります。
今作のラストシーンは、ルビーがマイルズと共に崖の上から「湖」に飛び込むショットになっていました。
これは、幼少期に「子ども」時代をスキップし、必要以上に「大人」であることを強いられてきたルビーが「子ども」を取り戻す瞬間でもあるのです。
子どもであること、大人であること
(C)2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS
先ほどの章では、「海」と「湖」というロケーションに注目して、「大人」と「子ども」という軸を見てきました。
次に、本作を象徴するジョニ・ミッチェルの名曲『青春の光と影』(Both Sides, Now)に焦点を当てながら、同じ軸を違った観点から見てみようと思います。
『青春の光と影』(Both Sides, Now)は、主人公のルビーが音楽大学のオーディションで歌う楽曲です。
この楽曲は「青春時代の光と影」を当事者視点、そしてそれを振り返る者の視点という2つの視点から見るような内容になっており、感覚的でありながら、人生の本質に迫るような1曲であると言えます。
その中でも注目したいのが、この楽曲のタイトルにも含まれている「Both Sides」という言葉なんですよね。
「両側から見る」という行為は、この楽曲の主要なテーマであり、同時に『コーダ あいのうた』という作品のテーマでもあります。
そして、その「両側」は「子ども」と「大人」でもあり、後述するように「音のある世界」と「音のない世界」のことでもあるのでしょう。
まず、「子ども」と「大人」という軸に着目しますが、劇中でルビーが彼女の音楽教師のV先生とこんなやり取りをしていたのを覚えていますか?
ルビーが大学で学ぶことに何の意味があるのか、先生の今の仕事に何か還元されているのかと問うたところ、彼は「君はまだ『人生』を知らない」と返答したのです。
これは、『コーダ あいのうた』の主題を象徴する重要なやり取りでした。
なぜなら、このシーンは、ルビーが自分がまだ子どもであるにもかかわらず、「大人」であると錯覚してきた、あるいは「大人」であることを強いられてきたことを表した瞬間でもあるからです。
彼女の家族は、耳が聴こえないというハンディもあり、娘であるルビーに「大人」でいてもらわなければ困るわけですが、対照的にV先生は教師として、人生の先を行くものとして彼女を「子ども」として見ているわけです。
その上で、まだ自分の「青春」を、そして「人生」を「Both Sides」から見ていないルビーが、「Both Sides」から見た気になって判断してしまうことに警鐘を鳴らしています。
きっと音楽室でオリジナルの楽曲を奏でていたV先生には、彼なりの「青春の光と影」があるのだと思いますし、きっと後悔もたくさんしてきたのでしょう。
だからこそ、あの頃の自分が「何も知らなかった」ことを今は知っています。
そして、そんな彼には自分の「青春」や「人生」がわかった気になって、折り合いをつけようとするルビーの姿がどうしようもなく歯痒いのです。
物分かりの良い「大人」である必要はまだない、「子ども」らしく飛び込んで、失敗して、挫折をして、でもそれに比肩する喜びと幸せを手に入れて欲しい。
V先生はルビーに対して、「きみはまだそうした「青春の当事者=子ども」のままでいいんだよ」と優しく声をかけ、彼女を導こうとしています。
人生を「Both Sides」から見て、酸いも甘いもを知るV先生と、それをまだ知らないのに知ったつもりになっているルビー。
この2人の関わりがもたらす化学反応を『コーダ あいのうた』という作品は非常に丁寧に掬い取っていました。
音のある世界、音のない世界
(C)2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS
そして、先ほども言及した『青春の光と影』(Both Sides, Now)に関連してもう1つお話ししておきたい作品の軸があります。
それは「音のある世界」と「音のない世界」というものです。
劇中でも描かれた通りで、主人公のルビーは健聴者ですが、彼女の両親と兄は聴覚に障がいを抱えており、耳が聴こえません。
そのため、ルビーは「音のある世界」に、そして彼女以外の家族は「音のない世界」に暮らしているという分断が家族内で生じており、これについても劇中で何度も言及されていました。
特にインパクトが大きかったのは、彼女の母親が「ルビーが健聴者であると分かった時、落ち込んだ」という発言ではないでしょうか。
私たちの一般的な感覚からすると、子どもが障がいを持たずに生まれてきたことを喜ぶのではないかと思ってしまうのですが、母のジャッキーは娘が自分とは異なる世界の住人として生まれてきたことにより、母親になれるかどうかが不安だったのです。
この言葉が象徴するように、ルビーの家族には「耳が聴こえない」からこその連帯があり、ルビーはそこから疎外されることによる孤独と彼らを社会につなぎとめる責任を幼少のころから抱えてきました。
「音のある世界」で生きることによる家族との摩擦、「音のある世界」で生きるからこその家族内での孤独。
2つの世界が分断してしまっているが故に、ルビーは苦悩し、だからこそ彼女が「家族」でいるためには「手話師」という役割に従事するしかなかったというのが本音なのでしょう。
「手話」をするという役割を受け入れている間だけは、彼女は「家族」と繋がることができ、必要とされます。
しかし、彼女が歌うことの喜びに目覚め、「音のある世界」で生きることへの希求が高まるほどに、歪ながらも保たれてきた2つの世界のバランスは崩壊していきました。
家族が「音のない世界」に取り残されてしまうことへの不安、「音のある世界」で生きるが故に家族とのつながりが断ち切られてしまうのではないかという懸念。
この断絶を明確に可視化したのが、学校での合唱コンサートのシーンであり、ここでは突然劇場が無音の静寂に包まれ、観客はルビーの家族の視点で彼女の歌を「聴く」ことになるのです。
そして、この演出がもたらす凄まじいインパクトが、私たちに「音のある世界」と「音のない世界」の境界に存在するとてつもなく深い断絶を痛感させる役割を果たしていました。
2つの世界が分断され、繋がっていないことにより、ルビーは「歌う」という夢を追うことを選びきれず、一度は家族と共にいるという選択を下してしまいます。
それでも、家族に後押しされる形で大学のオーディションを受けることになったルビー。
彼女がオーディションで取った行動により、2つの隔てていた分断を軽やかに飛び越え、2つの世界が繋がりました。
ルビーは、観客席にいる両親に向けて、歌いながら「手話」を披露し、自分の感情を彼らにも届けようとします。
このシーンが素晴らしいのは、前述したコンクールのシーンで私たち観客が「音のない世界」を体感しているからこそなんですよね。
あの演出があるからこそ、私たちは家族に自分の思いを「伝えたい」ルビーの視点、そしてルビーが伝えようとしている思いを「受け取りたい」家族の視点のBoth Sidesからこのシーンを捉えることができます。
その両方の視点が担保されているからこそ、見えている視覚情報以上に豊かで重奏的な味わいを孕んだシーンに仕上がっているのだと感じました。
また、ここで物語を通じて積み重ねてきた「手話」という言語に対する意味づけを変化させているのもお見事だと感じましたね。
基本的に「手話」というのは、ルビーにとって自分の思いを表現するためのツールではなく、あくまでも耳が聴こえない家族のためのものであり、家族の思いを代弁するためのものでした。
しかし、クライマックスの歌唱シーンでは、彼女が初めて手話を他でもない「自分の」思いを伝えるために使うという明確なシフトが起きています。
手話、そして「音のある世界」と「音のない世界」の対比といった観点で、丁寧な描写や演出の積み重ねが為されたからこそ、それが交わるクライマックスが一層エモーショナルなものになったのだと感じましたね。





おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『コーダ あいのうた』についてお話してきました。





フェルディア・ウォルシュ=ピーロが出演していることもあって、『シングストリート』的な青春と音楽のストレートな映画の印象を受ける方もいるかもしれません。
しかし、そうした青春音楽映画の面白さを担保しつつ、ディスコミュニケーションを乗り越える家族の物語としての側面を併せ持つことで、非常に奥行きのある作品になっています。
今作は演出や楽曲のチョイスも含めて非常に素晴らしいリメイクですが、あくまでもリメイクではあるので、気になった方はオリジナルの『エール!』の方もチェックしてみてください。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。