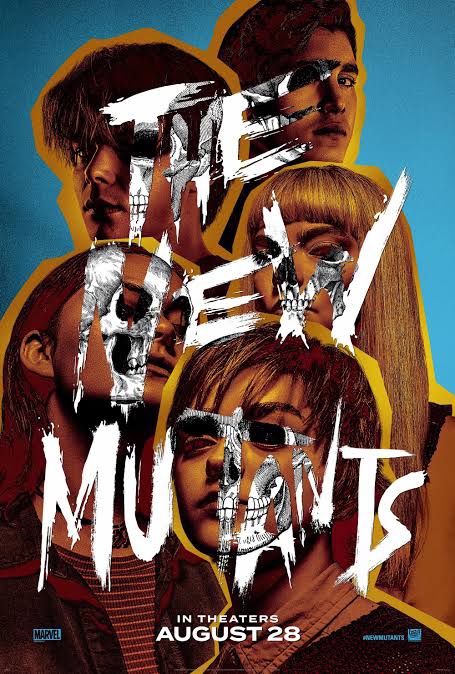みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『さがす』についてお話していこうと思います。

この記事で取り上げる『さがす』という作品は、『岬の兄妹』で大きな注目を集めた片山慎三監督の最新作です。
日本の貧困の極致に向き合うその強烈な作風は、2019年に多くの映画人に衝撃を与え、映画ファンをも虜にしました。
そんな片山慎三監督が手がける最新作は、同様に日本の貧困層にスポットを当てながらも、韓国のフィルムノワール的な空気感を孕み、探偵小説のような趣を感じさせる作品となっています。
特に今作で多くの人が衝撃を受けたのは、主要キャラクターの1人である原田智を演じている佐藤二朗さんの迫真の演技ではないでしょうか。
私も含めて映画やドラマを見ている人だと、どうしても佐藤二朗さんは福田雄一監督作品のイメージが強く、とりわけ「コメディ俳優」という言葉で評することが多いと思います。
片山慎三監督はそうした佐藤さんが持つ喜劇性というものも作品を構築する上で非常に巧くコントロールしていて、それをミステリアスさや狂気と地続きのものとして描写しました。
そして、もう1人触れておきたいのが、同じく主要キャラクターの1人である原田楓を演じた伊東蒼さんです。
2021年に公開された『空白』でほとんど言葉を発しない役でありながら、特大のインパクトを残した気鋭の女優は、今回も圧巻の存在感を感じさせてくれました。
『空白』とは対照的に、関西弁でよく喋るキャラクターを演じているわけですが、個人的には「日常」を作り出すのが巧いな女優さんだなと思います。
(C)2022「さがす」製作委員会
佐藤二朗さん演じる父親との暮らしがこれまでもずっと続いてきたという過去、あるいはこれからもずっと続いていくんだろうなという未来までも感じさせる、「日常」の感覚を見事に体現する演技を披露していたのです。
冒頭の父の万引きで呼び出されるシーンにしても、これまでにも同様の行動があったことを伺わせ、これすらも彼女の「日常」の一部なんだなという印象を与えてくれます。
「暮らし」や「日常」を描くには、現在進行形で起きていることにスポットを当てるだけでは不十分で、むしろそこに至るまでに起きたことの積み重ねを踏まえての「今」を捉える必要があるはずです。
それを肌感覚で自然と表現できてしまう伊東蒼さんのポテンシャルには驚かされますし、それが巧いからこそ、「日常」からの逸脱がより際立つのでしょう。
さて、ここまでは監督やキャストのことについて軽くお話をしてきましたが、ここからはより本編の内容を掘り下げて、自分なりに感じたことや考えたことをお話していきます。







目次
映画『さがす』解説・考察(ネタバレあり)
本作はタイトルが何とも印象的な映画です。
「さがす」というのは行動のことを指しており、目的というよりは手段を指している言葉なんですよね。
何か見つけたい対象がある、あるいは暴きたい真実があるからこそ、その目的を達成するための手段として「さがす」が用いられるわけです。
探偵小説やミステリにおいては、こうした「さがす」プロセスそのものがエンターテインメント化され、多くの人に楽しまれています。
しかし、概してこうした作品に欠けているのは、「さがす」を経て、見つけ出したものに対して当事者がどう向き合い、何を選択するのかという視点ではないでしょうか。
映画『さがす』はポスターや予告編を見ても、楓が父親を「さがす」プロセスや彼女が見つけ出す真実は何か?に観客の注意を向けるように作られています。
それを象徴するのがタイトルであり、観客は「さがす」あるいは暴くことそのものに関心を持ち、それが作品の終着点になるのだろうと無意識のうちにリードされてしまうのです。
だからこそ、片山慎三監督は「さがす」というタイトルの映画の中で、「さがす」のその先を描こうと試みます。
今回の記事ではアウトサイダーとしての「探偵」を引き合いに出しながら、楓という「探偵」の持つ当事者性に言及し、本作が描こうとした「その先」は何だったのかについて自分なりの解説を加えていきます。
探偵小説と「暴く」に伴う客観性
(C)2022「さがす」製作委員会
『さがす』の物語の中心に据えられているのは、原田楓による失踪した父親探しです。
彼女はいなくなってしまった父親を捜索し、警察にも相談に行くわけですが、彼らは事件性がないからと全く掛け合ってくれません。
担任教師は、まだ中学生である楓の生活を危惧し、児童福祉施設に彼女を紹介し、父親の捜索を諦めるよう促しますが、楓はそれでも諦めませんでした。
しかし、警察にも頼ることができない中で、私的に父親を捜索する他に道がなくなったわけです。
こうした経緯で本作において中学生の少女、原田楓は探偵小説における「私立探偵」のポジションに君臨し、手がかりを辿り、徐々に父の真相へと迫っていきます。
ただ、ここで「探偵」というものが、探偵小説あるいはミステリにおいてどんなポジションを宿命づけられているのかを考えておく必要があるはずです。







うろ覚えで恐縮だが、以前横溝正史の発言にこんなふうなものがあったと記憶する。「私の小説の主人公は金田一探偵ではありません。その殺しを引き起こさざるを得なかった犯人や、被害者であります。探偵の金田一君はただのストーリーの狂言回し役にすぎません」
かつて一世を風靡した金田一耕助ですら、それらの作品の主役ではなかったようである。事件を解説するだけの、野球中継で言えば選手ではなくて、野球解説者か無色透明のアナウ ンサーのごとき存在のようである。
(鼬晶「主張する探偵たち」『矢吹駆研究第1集 』より)
ここでも語られているように、探偵小説における「探偵」は物語の主人公ではなく、劇中で起きた事件に対して常に当事者性を持ちえず、アウトサイダー的な立ち位置を保ち続けているという側面があるわけです。
もちろん「ハードボイルド探偵小説」と呼ばれる「探偵」が半ば主人公的な役割で物語に介入するジャンルもあります。
それでも、こうした「さがす」物語としての探偵小説の原型には、常にアウトサイダーあるいは非当事者として事件に携わる「探偵」の存在があるのです。
では、こうしたアウトサイダーとしての「探偵」にとって「暴く」ことはどんな意味を持つのでしょうか。
これは明白で、「探偵」にとっては「暴く」ことが達成された時点で依頼完了であり、それに対する報酬を得ることができます。
加えて、「暴いた」ことによってその事件の当事者にもたらされるものについて、彼らは何の責任も負わず、それ以後関わりを持つこともないはずです。
「探偵」はそのアウトサイダー性故に、「暴く」ことそのものをゴールとして捉え、それがもたらす余波に対して影響を受けないんですね。
先ほどの野球の実況中継の例えと同様で、解説者が解説席で何を言おうと球場で実際に行われている試合そのものには何も影響を与えません。
映画『さがす』は、確かに警察のような機関に頼れないことに端を発した、中学生の少女による私的な父親捜索を描いているという点で、その構造は「探偵小説」的とも言えます。
しかし、明確に異なっているのは、原田楓が「探偵」でありながら、自分が調査している事件の当事者の1人でもあるという点です。
当事者性と「暴く」ことがもたらす余波
(C)2022「さがす」製作委員会
原田楓は『さがす』の物語において「さがす人=探偵」であるわけですが、「探している人」が彼女の父親であるが故に、事件の当事者の1人でもあります。
つまり、アウトサイダーでありながら当事者でもあるという特異な立場に身を置いていることになるんですね。
「探偵」は野球の解説者であり、解説席から試合そのものに影響を与えることはできませんし、そこで起きていることに対して何か責任を負うこともありません。
故に、そこで起きていることを客観的に解説することが手段であり、目的でもあり、それ以上のことは何もないわけです。
しかし、楓は野球の実況者でありながら、グラウンドで実際にプレーをしている選手の1人でもあるという状況が生まれています。
よって、彼女はグラウンドで何が起きているのかを探し、解説する一方で、その過程で見つけ出したものによる影響を、試合の当事者、つまり選手の1人として受けざるを得ないのです。
「探偵」は暴くことそのものに責任を負い、彼らが暴いたことに対しては責任を負わず、影響も受けません。
しかし、原田楓は「探偵」として暴くことそのものに責任を負いつつも、事件の「当事者」であるが故に暴いたことに対しても責任を負い、それを受けての選択を下さなければならないわけです。
まさしくこの責任と選択という部分こそが、映画『さがす』において最も監督が描きたかった部分なのではないかと思いました。
おそらく多くの人が、父親が見つかり、そして彼が懸賞金を受け取って卓球場の営業を再開したところで物語は終わったのだと錯覚したことでしょう。







彼女が真実を見つけた時点で、物語の目的は達成されたのだと溜飲を下げるように観客はタイトルやポスター、予告編の情報によって巧妙にミスリードされていました。
しかし、これで物語が一件落着になるのは、本作における原田楓が完全なるアウトサイダーなのであればの話です。
だからこそ、映画『さがす』は多くの観客が「ここで終わって欲しい」と感じる瞬間の先に、「ポストさがす」の物語を描きます。
そこにあるのは、「さがす」という行為がもたらす、思いがけない発見とそれに伴う選択でした。
靴底にこびりついたガムと真実、暴く側の責任
(C)2022「さがす」製作委員会
楓は、偶然にも父親が多くの人を殺めてきた山内照巳と関わりが深い人間であることを知ってしまい、父親の正体に触れてしまいます。
肉体としての父親を見つけることはできましたが、彼女が当初探していた「父親」の姿はもうどこにも残されていなかったのです。
彼女は僅かばかりの希望を胸に、父親に罠を仕掛け、彼の本心を探ろうとします。彼がまだ自分や亡くなった母親のことを思ってくれているのかを試したわけですね。
しかし、結果は残酷なもので、父親の智は彼が殺めた女性の存在に憑りつかれ、山内照巳亡き後も、私的に他人を安楽死させる活動に従事しようと考えていました。
楓はそんな真実を前に当事者として選択を迫られることになります。
見て見ぬふりをして、何となくこれからも父子の生活を続けていくのか、それともここで父の罪を断罪するべきなのか。
真実は「靴底にこびりついたガム」のようなもので、その存在を知りさえしなければ、特に気にすることはありませんが、一たび気づいてしまうと、それがもたらす異物感や嫌悪感から逃れられなくなります。
仮にブラシでこすって物体としてのガムを靴底から取り除いたとしても、それが付着していたという事実は消えず、自分の靴を汚されたような、傷物にされたような緩やかな嫌悪感は持続し続けるのです。
楓が前者の選択をし、父親との暮らしを継続したとしても、彼女は自分が探し、見つけ出してしまった真実から解放されることはありません。
もはや事件以前の日常を取り戻すことは叶わず、何か喉につかえたものを感じながら、変わらない日常を演じ続けることになるだけです。
これも1つの「暴いた」側の責任のカタチと見ることができますよね。
そして、もっと難しいのが、自らが暴いた真実を明るみに出し、父親に罪を償わせるという決断であり、劇中での楓の選択はこちらでした。
この選択がもたらすのは、父親不在の暮らしであり、犯罪者の娘としてのレッテルを貼られる過酷な人生なのかもしれません。
しかし、そうした苦しい決断をしてもなお、彼女が求めていたのは、彼女が愛したかつての「父親」だったのです。
彼女が探していたのは肉体としての父親ではなく、もっと抽象的で可視化することも難しい「父親」とも呼ぶべき何かだったのだと思います。
それをあえて言語化するのであれば、眠っている楓にそっと毛布をかけなおしてくれるような優しさや温もりでしょうか。
だからこそ、彼女は自分が見つけたもの、暴いたものに対する責任を負い、選択を下したうえで、まだ見つかっていない「父親」を「さがす」ための選択をするのです。
家族の思い出の場所とも言える卓球場。そこで卓球のラリーが続き、劇場にはボールが卓球台に一定の感覚でバウンドする音が鳴り響き続けます。これは父子の「日常」の象徴です。
そこに、遠くから迫りくるパトカーのサイレンが介入し、その「日常」の終わりの到来をじわじわと印象づけました。
それでも2人はラリーを続けます。
いつの日か「父親」が戻り、ここでまた卓球ができる日を夢見て。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『さがす』についてお話してきました。







『岬の兄妹』も見終わった後に、いろいろな感情が心の中に渦巻いて、そのざわざわからなかなか解放されない不思議な映画だったと記憶しています。
今回の映画『さがす』も、「さがす」というプロセスやゴールのその先に言及することで、それがもたらす責任や選択の重みを感じさせる作品になっていました。
本作は真実そのものが重要な作品ではありません。
真実を見つけ出したことに伴う余波こそが重要なのです。







良かったら最後までお付き合いください。