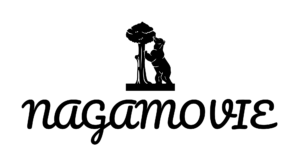みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね毎年年明けごろから話題になる日本アカデミー賞についてお話していこうと思います。

実は、日本には数多くの映画賞が存在しています。

- ブルーリボン賞
- 報知映画賞
- ヨコハマ映画祭
- 高崎映画祭
- TAMA映画賞
- 毎日映画コンクール
- キネマ旬報ベストテン(雑誌)
- 映画秘宝(雑誌)














ただ、今回話題に挙げるのは、テレビ中継もされ、良くも悪くも最も注目を集めやすい日本アカデミー賞についてです。
この記事では、日本アカデミー賞がそもそもどういう仕組みで決められているのかを解説した上で、当ブログ管理人の考える今の日本アカデミー賞の課題と期待について語っていこうと思います。
目次
日本アカデミー賞とは?
まず「日本アカデミー賞」とは?という概要の部分をお話していきますね。
「日本アカデミー賞」は、本家である米国のアカデミー賞より許諾を得て、1978年に発足された日本の歴史ある映画賞です。
毎年2〜3月くらいに、新高輪にあるグランドプリンスホテルで授賞式を開催して、日本テレビ(日テレ)が中継放送しております。
そして例年、年が明けた頃に、この日本アカデミー賞の優秀作品賞のラインナップが発表されるのですが、その度に映画ファンの間では、溜め息が聞こえてきます。














2022年に開催される第45回で言うと、「TAMA映画賞」などでも高く評価され、映画ファンの間でも大きな話題になった『あのこは貴族』や『サマーフィルムにのって』などが完全にスルーされていました。
とは言え、地上波のゴールデンタイムで、映画がテレビでフィーチャーされる機会は少ないので、個人的には応援したいところです。
ただ、やっぱり問題点も多数残っていて、映画ファン含め、一般的にまだ完全には認められていない賞なのかな?という印象は受けますよね。
ここからは、そんな日本アカデミー賞について、みなさんも気になるであろう「映画ファンの間で評価の高い作品がノミネートされないロジック」を解説していこうと思います。
検索サジェストにも「日本アカデミー賞」「いらない、茶番、やらせ」なんてキーワードも見かけますが、一体何が問題なのか?














- 大手配給関係者が会員総数に占める高い割合
- 全会員が全部門に投票する方式
- インディペンデント作品に厳しい選考条件
では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
映画ファンの間で評価の高い作品がノミネートされないロジックとは?
①大手配給関係者が会員総数に占める高い割合
まずは、大手配給関係者が会員総数に占める高い割合についてです。
日本アカデミー賞を巡ってよく取り上げられるのが、2014年の北野武監督のこの発言ですよね。
「日本アカデミー賞最優秀賞は松竹、東宝、東映、たまに日活の持ち回り。それ以外が獲ったことはほとんどない。賞を選定するアカデミー賞の会員なんてどこにいるんだ。汚いことばっかやってる。」
うーん、でも、これって本当にそうなんでしょうか?ということで調べてみました。
2000年~2019年に実施された同賞の最優秀作品賞の内訳は、こうなります。
- 東宝:9
- 東映:1
- 松竹:6
- 日活:0(製作に関わっている作品は有)
- その他:4
最優秀作品賞20回の内の15回を東宝と東映が独占しているという現状ですから、大手配給会社の作品が割合的に多いという印象が間違っていないことは分かります。














その原因は、この賞に対して投票権を持つ会員に占める大手配給会社の社員の割合が高すぎるという背景にあるんです。
公式サイトを参照しますと、2021年度時点での日本アカデミー賞全体の会員数が3952名と発表されています。
この4社の会員数を以下にそれぞれ示します。
- 東宝:277
- 東映:268
- 松竹:306
- 日活:49
ちなみに全体に占める割合は約17%となりました。














そう思った方もいるかもしれませんが、実はここに1つからくりがあるんですよね。
実は公式サイトの方で「賛助法人:1685」という数字が書かれていることが分かります。
賛助法人つまり、このアカデミー賞協会の事業を援助する個人又は法人の会員が1685人と記載されているわけです。
そして実は、この「賛助会員」には、東宝や松竹、東映の子会社も多数含まれているんですよ。
つまり、それらを含めると、大手配給の息のかかった人が会員に占める割合はもっと高くなります。
それに加えて、日本の大手配給が手がける大作映画は基本的に「製作委員会方式」が取られていて、そこに映画業界以外の企業も絡んできます。
そうした関連企業にまで賛助会員がいて、彼らは当然映画をそれほど見ているというわけでもないでしょうから、自分たちが携わった作品から選ぶ傾向が当然強くなりますよね。
こうした会員に占める、
- 大手配給とその子会社の関係者
- 大手配給作品の製作委員会に入っている企業関係者
の割合の高さが日本アカデミー賞で扱われる作品の偏りを生んでいるという事実がある限り、サジェストで「茶番、やらせ」と出るのも分からなくもないですよね。
また、2008年にはその年の多くの賞レースで各賞を総なめにしていた『それでもボクはやってない』を差し置いて『東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜』が、主要賞を独占するという事件が起きました。
この背景にあるのは、日本アカデミー賞の放映権を持っているのが日テレで、同作が日テレ主導で作られた作品だったという事実です。
『東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜』に出演し、その年のに同作で最優秀主演女優賞を受賞した、樹木希林さんも受賞時のインタビューで
「これは組織票だ、この結果はおかしい。」
と審査結果を痛烈に批判していました。














2000年から2009年にかけての10年で日テレが製作委員会に入っていた作品が最優秀作品賞を受賞した回数は10回のうち4回でした。
これを多いと見るか、少ないと見るか…は個人によって異なると思います。
ただ、これについては2008年の日本アカデミー賞に対するバッシングも相まって改善されていき、2010年から2019年の10回で見ると、日テレが製作委員会に入った作品が最優秀作品賞を受賞したのは1回だけとなっています。
②全会員が全部門に投票する方式
続いて、全会員が全部門に投票するという日本アカデミー賞の投票方法について言及していこうと思います。
日本アカデミー賞の放送を見ていて、こんなことを思ったことはないでしょうか?














はい。私自身も毎年のようにそう思っております。
というのも、日本アカデミー賞は毎年テレビ中継されるのですが、実は中継されるのは役者関係の賞と、監督・脚本・作品賞などのごく一部の主要部門だけなんですよね。
そのため、例年、撮影や照明、編集といった技術部門の賞はダイジェスト映像でしか扱われず、冷遇されている印象が拭えないのです。
当ブログ管理人も映画ファンのが端くれなので、映画という文化が育っていくためには、こうした技術部門の受賞者がもっとフィーチャーされるようになって欲しいとは思っています。
ただ、やはりテレビで放送する都合上、視聴率が取れないと厳しいですから、そういった「オトナの事情」もある程度は理解はできます。
できるんですが、日本アカデミー賞の技術部門の賞のラインナップって毎年どうしても疑問を感じるんですよね。
例えば、第45回の撮影賞の優秀賞にノミネートされている作品を見てみるとこんな感じです。
撮影賞
- 近森眞史『キネマの神様』
- 加藤航平『孤狼の血 LEVEL2』
- 笠松則通『すばらしき世界』
- 四宮秀俊『ドライブマイカー』
- 鍋島淳裕『護られなかった者たちへ』














作品賞
- 『キネマの神様』
- 『孤狼の血 LEVEL2』
- 『すばらしき世界』
- 『ドライブマイカー』
- 『護られなかった者たちへ』














つまり、優秀作品賞に選ばれている主要な5作品が金太郎飴みたいな状態で、技術部門の優秀作品賞を受賞していると言うのが、日本アカデミー賞の現状なのです。
アメリカの本家アカデミー賞の第91回の作品賞と撮影賞のラインナップを比較すると、こうなります。
作品賞ノミネート
- 『グリーンブック』
- 『ブラックパンサー』
- 『ブラック・クランズマン』
- 『ボヘミアン・ラプソディ』
- 『女王陛下のお気に入り』
- 『ROMA/ローマ』
- 『アリー/ スター誕生』
- 『バイス』














撮影賞ノミネート
- アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』
- ウカシュ・ジャル『COLD WAR あの歌、2つの心』
- ロビー・ライアン『女王陛下のお気に入り』
- キャレブ・デシャネル『ある画家の数奇な運命』
- マシュー・リバティーク『アリー/ スター誕生』
このように、扱われている作品の顔ぶれも微妙に異なり撮影部門は撮影部門としてしっかりと評価されていることが伺えます。
でも、なぜ日本アカデミー賞はこんなに技術部門で登場する作品の多様性に乏しいのかでしょうか。
それは、日本アカデミー賞公式サイトの投票方法の欄を読めば一目で分かります。
協会員全員が全部門(新人賞を含む16部門すべて)を投票します。
こう書かれているのです。
つまり、先ほども述べたように映画業界ではない関連企業の社員も多数含まれているような会員3953名全員が、優秀賞選考時に技術部門にまで投票するわけですよ。
そうなると、結局何がすごいのかわからないからとりあえず作品賞と同じにしておこうという人が多くなり、同じような作品が並ぶという結果が起こることは容易に想像がつきます。
ちなみに本家アカデミー賞では、ノミネート作品選考時については、
監督賞→ハリウッドで映画監督として活躍する会員
撮影賞→ハリウッドで撮影に携わる会員
というように、投票権が与えられるので、きちんと同業者が専門的な視点で見て、選考するという側面が強くなっています。
日本アカデミー賞がこれから日本における映画文化の発展に一役買う存在になるためには、優秀作品賞の投票方式を見直して、技術部門の賞の地位を向上させていく必要があると個人的には考えています。
③インディペンデント作品に厳しい選考条件
最後に解説するのが、日本アカデミー賞の選考対象作品になるための条件についてです。
みなさんは優秀作品賞のラインナップを見ていて、














なんて思うことはありませんか?
でも、その映画、もしかすると選考対象にすら入っていないかもしれません。
なぜなら選考対象になるための条件があまりにも厳しいからです。
日本アカデミー賞の公式サイトに記載されている選考基準に、書かれていた基準から4つ抜粋してみました。
①東京地区に於ける商業映画劇場にて有料で2週間以上映画館のみで公開された作品。
②東京地区の同一劇場で1日3回以上、かつ2週間以上継続し上映された作品。
③ドキュメンタリー、オムニバス映画、再上映映画、映画祭のみの上映作品、2週間限定公開作品、イベント上映作品、昨年度対象になった作品は除きます。
④同日含め先に配信、TV放送されたもの及びそれの再編集劇場版は新作映画とみなしません。但し、放送後に新たに撮影された部分が大半の場合のみ新作とします。
①は本家アカデミー賞に近い内容なのですが、②がとにかく厳しいですよね。
インディペンデント系の映画で②の条件を満たすのは、意外と難しいと思います。
例えば、2020年に公開され、雑誌『映画芸術』の発表するランキングでベスト1に選ばれた『れいこいるか』なんかは上映規模が小さすぎて、選考対象にすらなっていません。
また、あと③については、アカデミー賞はドキュメンタリー映画の部門を作っていないので、やむを得ないのかもしれませんが、そもそもドキュメンタリー映画は除外と言うのも、映画賞としてどうなのかとは思いますけどね。
加えて、④もなかなか厳しい条件でして、例えば第44回だとベルリン国際映画祭で銀獅子賞を受賞した『スパイの妻』や映画ファンの間で話題になった『本気のしるし』はこれに引っかかって、選考対象外になっています。
こうしたある程度の規模で上映された作品でないと選考対象にすらならない厳しい条件や良作を締め出してしまうような条件が入っていることも、この賞の大きな問題点と言えるかもしれません。
日本アカデミー賞はどうすれば改善されるのか?
ここまで日本アカデミー賞の課題について解説してきましたが、とは言っても、近年は日本アカデミー賞も改善傾向にあります。
例えば、大手配給会社の関係者が会員総数に占める割合が高いとお話しましたが、最優秀作品賞ベースで見ても、2000年以降の最初の10年は
2000年~2009年
- 東宝:4
- 東映:1
- 松竹:4
- その他:1
となっていましたが、その後の10年では、
2010年~2019年
- 東宝:5
- 東映:0
- 松竹:2
- その他:3
こんな具合に大手強しな状況も少しずつ改善されてきております。
また近年は『新聞記者』や『ミッドナイトスワン』などインディペンデント系の配給作品が最優秀作品賞を立て続けに受賞するなど、流れが変わってきているのも事実です。
ですので、個人的にここからやって欲しいなと思うのは、次の3点です。
- 会員の構成員を見直す
- 優秀賞選出時の各部門の投票権は各部門の専門性がある会員に限定する
- 選考対象にする条件をもう少し緩和する














加えて、会員の大多数を占める賛助会員が映画に関係のない業界の人たちと言う現状もやはり何とかしなければ、日本アカデミー賞の権威性もついてこないでしょうね。
まずは、映画を作る人が受賞できることを心から誇りに感じられるような、映画を作る人が受賞できることを1つの目標にできるような賞になることが第1ステップだと個人的には思っています。
また、日本アカデミー賞は、数少ない映画がテレビのゴールデンタイムに大々的に取り上げられる非常に重要な場です。
だからこそ、公開時に一般層にはなかなか届かなかった素晴らしい作品たちを再評価し、広める役割を果たしてくれることも期待してしまいます。
こうした場でもっと映画が日本の文化として育つために有益な働きかけをしてくれると、映画ファンの端くれとしても嬉しい限りです。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。