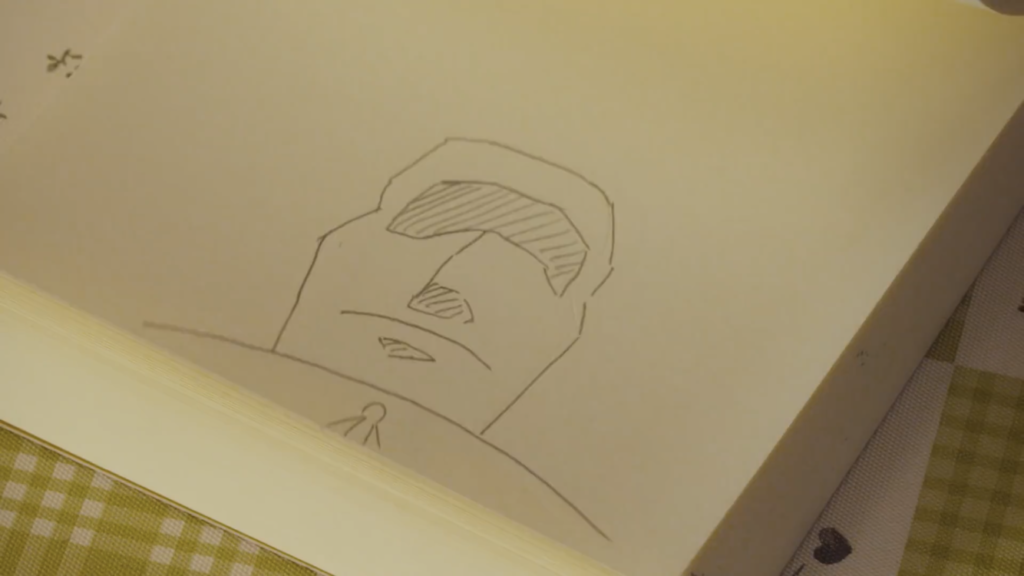みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね『青くて痛くて脆い』についてお話していこうと思います。

予告編がかなりミスリードを煽るように作ってあるのも非常に巧いなと思いますが、原作も叙述トリックのエッジが効いた作品になっており、読みごたえがありました。
とりわけ、この手の叙述トリック主体の作品は、そこで生まれる衝撃や裏切りで読み手を欺くことに主眼を置きすぎて、そのトリックが作品に取り入れられる正当性に欠けるものも多いように思います。。
しかし、住野よるさんの『青くて痛くて脆い』はとにかくそのトリックが作品の主題と密接にリンクしているのです。
だからこそ、トリックそのものに驚きがあると共に、それが作品の展開の中できちんと意味づけされていき、読み終わった後に2度驚かされるようなそんな趣向が凝らされているんですね。
一方で、この作品はSNSでの誹謗中傷が話題となり、それが原因で芸能人が自殺するなんて悲しいニュースが飛び込んでくる今だからこそ鑑賞しておくべき1本だと思います。
自分の中にある「青さ」と向き合い、きちんと「痛み」や「脆さ」に向き合う、全く新しい青春譚ではないでしょうか。
個人的には鑑賞していて「痛さ」の部分が大きくて、思わず苦しくなりましたね。






















とあるアイドルを必死に支えるたった1人のファン。
アイドルに徐々に注目が集まり全国区に知れ渡る人気グループに。
古参ファンのわい、彼女たちはこんなのじゃなかったし、昔の方が良かったとネットに書き込み始める。
かつての彼女たちは「死んだ」から自分の手で、昔の輝いていた彼女たちを取り戻すんや!と意気込み、ストーカー紛いの行為をして、黒い噂をかき集め、ネットにリーク。
その影響で、すっかり人気を失い、デビュー当初のような小さな箱に逆戻りしたアイドルたち。
その古参ファンは、会場を訪れて、「君たちのためを思ってやったんだ!だからまた一緒に頑張ろう!」と告げますが、彼女たちはそれを受けつけず、会場から出て行けと一言。
古参ファンのわい、彼女たちのためにやったのに何でこうなるんや…と号泣。






















どんな話だよ!思われるかもしれませんが、こんな話ですよ…?
と、少しジョークも書かせていただきつつ、本論に入っていきますね。
さて、ここからはそんな本作について個人的に感じたことや考えたことを綴っていきたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『青くて痛くて脆い』
あらすじ
田端楓は大学4年生で、無事に就活も終わり、あとは卒業を待つだけという身であった。
彼は、大学生活を振り返り、どうしてもやっておかなければならないことが1つあったと思い至る。
それは入学当初に理想を語り合い、共に「モアイ」という世界を変えるためのサークルを立ち上げた秋好寿乃という同級生の女性のことだった。
彼女は、入学当初から大学の講義で理想論のような青臭い意見を述べ、周囲から浮いていたが、同じく大学で浮き気味だった楓と意気投合したのだ。
しかし、そんな彼女は「この世界」から消えてしまったのであり、「モアイ」はコネ作りや企業への媚売りを目的としたいわゆる「意識高い系」のための就活サークルと化していた。
そんな現状を憂いた楓は、今の「モアイ」を破壊することで、かつての純粋な「モアイ」を取り戻すのだと意気込み、戦いを挑むことを決意する。
彼は親友である董介と結託し、「モアイ」への潜入や情報収集を開始する。
そこから見えてきたのは、「モアイ」という組織が内包する黒い噂であった。
勧善懲悪の名目を得た楓は、もはや止まることができなくなり、組織を自分の手で断罪しようとその行動をエスカレートさせていき…。
スタッフ・キャスト
- 監督:狩山俊輔
- 原作:住野よる
- 脚本:杉原憲明
- 撮影:花村也寸志
- 照明:志村昭裕
- 編集:木村悦子
- 音楽:坂本秀一
- 主題歌:BLUE ENCOUNT






















あらゆる要素がクソださでプロットも散々だった『妖怪人間ベム』の実写版の監督を務めたのが、ちょうどこの狩山俊輔さんですね。
もちろん監督だけの責任であんな映画が出来上がってしまったとは思いませんが、本当に酷い出来なので、あまり擁護はしません。
そんな彼が実に8年ぶりに監督を務めたのが今回の『青くて痛くて脆い』ということになります。
そして今回の映画の原作を著したのが『君の膵臓をたべたい』でお馴染みの住野よるさんですね。
個人的にはラノベテイストの小説を書く方だなという印象はありましたが、今回の作品を読んでそのイメージは大きく変わりました。
住野よるさんは既存の「青春譚」を下地に据えたうえでそれを脱構築するかのように新しい物語を作り上げていくのが巧いと思います。今回の『青くて痛くて脆い』もそうしたある種の「裏切り」に裏打ちされていました。
脚本には『ニセコイ』や『貞子』の杉原憲明さんが起用されていますね。こちらも最近の脚本作品の出来から考えると不安要素ではあります。
撮影には『センセイ君主』や『かぐや様は告らせたい』などのコメディよりのティーン向け映画を多く手掛けている花村也寸志さん、照明には『羊の木』や『銃』などで知られる志村昭裕さんが起用されていますね。
作品の印象を決定づけると言っても過言ではない重要な編集には、『ヒキタさん!ご懐妊ですよ』や『ステップ』など最近高評価されている作品を立て続けに手掛けている木村悦子さんがクレジットされました。
劇伴音楽を提供したのは、日本映画界の青春映画の旗手的存在である山戸監督の『溺れるナイフ』や『ホットギミック』をも支えた坂本秀一さんです。
主題歌にはBLUE ENCOUNTの「ユメミグサ」が選ばれていますね。






















- 田端楓:吉沢亮
- 秋好寿乃:杉咲花
- 前川董介:岡山天音
- 本田朝美:松本穂香
- 天野巧:清水尋也
- 西山瑞希:森七菜






















まず、主人公を演じたのが、吉沢亮さんですね。
既にその演技力は「イケメン俳優」の域を脱していると思いますし、今回のような青臭くそして感情をむき出しにする役は吉沢亮さんにすごく合っていると思いました。
そして、ヒロインの秋好寿乃を演じたのが、当ブログ管理人が毎週欠かさずラジオを聴いている杉咲花さんです。
本当に彼女の声が大好きですし、だからこそ予告編のラストにインサートされている彼女の「気持ちわるっ」という声に何度も悶えております(気持ち悪い)。






















また、西山瑞希役には、当ブログ管理人が写真集を2冊予約してしまうほどにのめり込んでいる森七菜さんが起用されています。
もうこの2人が起用されているということで、私は耳も目も幸せということになりますね…。
その他にも岡山天音さん、清水尋也さんら若手実力派キャストたちが集結しましたね。






















『青くて痛くて脆い』解説・考察(ネタバレあり)
憎しみの対象が血の通った人間という当たり前の事実の放念
(C)2020「青くて痛くて脆い」製作委員会
さて、貴時の冒頭にも書きましたが、本作『青くて痛くて脆い』は、いわゆる叙述トリック系の仕掛けを内包した作品となっております。
映画のあらすじ等では「秋好寿乃が死んだ」かのようなミスリードが為されていて、それは原作でも当然為されているのですが、作品の中盤過ぎにそこにとある「嘘」があったことを知らされます。
彼女が「消えた」というのは、物理的に消えてしまったわけではなくて、むしろあの頃の純粋に理想を追いかけていた彼女が消えてしまったという意味だったわけです。
そして、この事実が、楓が今の「モアイ」を壊し、かつての純粋だった頃の組織を取り戻そうとする理由なのだと思いますし、そこにはある種の恋心にも似たドロドロとした執着も混ざっています。
というのも寿乃は、「モアイ」を”2人きり”で作りながらも、そこにメンバーを入れて次第に組織を大きくしていきましたし、さらには彼氏も作り、徐々に”2人きり”の世界を壊していきました。
だからこそ、彼はかつて2人きりだったあの頃の「モアイ」に固執するのですが、その過程で彼は勧善懲悪の大義名分を獲得し、寿乃が自分と同じ血の通った人間であるという事実を放念していきます。






















あの「クソリプ」は、もはやツイート主が自分と同じ1人の人間であるという当たり前のことが放念し、無機物的な壁に石を投げつけるかのような勢いで繰り出されたものです。
私は、今作の楓が批判への欲求の高まりに伴って、寿乃の人間性が見えなくなり、彼女を否定することに躊躇がなくなっていく様と、Twitterのクソリプに不思議なリンクを感じました。
作品でもまさしくそんなSNSを経由した匿名の人間たちによる批判や誹謗中傷が描かれていますが、こうした人間は自分は「悪を断罪している」のだから正義だというある種のビジランテ的な立場にいると錯覚しているのではないでしょうか。
しかし、少し冷静になって考えてみて欲しいのは、あなたが石を投げつけているのは無機物的な壁でも、1つの電子データでもなく、1人の人間なんですよ。
憎しみや自分こそが正義なのだという歪んだ感情が、徐々にそうした冷静さを人間から奪っていき、普段なら絶対にやらないであろう、他人に石を投げつけるという行為を平気で可能にしてしまうのです。






















そして、今作が取り入れた叙述トリックがまさしくそんな主題を補強する方向に働いています。
というのも、この叙述トリックは、物語の中盤に至るまで、「モアイ」の代表を非人間化・アイコン化することに成功しており、それ故に楓が為す勧善懲悪に正当性を感じさせるようになっているんですよね。
憎しみの対象が人間的に描かれないことによって、私たちは楓が為そうとする「断罪」に対して自然と背中を押せてしまいますし、同時に途中で降りた董介に「意気地なしだなぁ」というネガティブなイメージを抱くことになります。
ただ、董介の方がずっと冷静に物事を捉えていますし、今から攻撃しようとしているのが1人の自分たちと同じ人間であるということを理解しているのです。
そういう当たり前を放念して、楓のビジランテ的な行為に読み手を加担させてしまうのが、この叙述トリックの巧妙さであり、だからこそ彼の憎しみの対象が寿乃であると突きつけられた時に私たち読み手もひどく動揺することとなります。
僕は、秋吉の人格を無視して、考え、行動を決めていた。
つまり、彼女を人間として見ていなかった。
記憶の中にある、形の決まった存在のようにして決めつけていた。傷つくはずのない、ただの記憶だけを見ていた。
(住野よる『青くて痛くて脆い』より引用)
同じ血の通った人間の、人格を、やって来たことを、そしてその存在そのものを否定してしまうということの危険性をヒリヒリと感じさせられるのです。
この叙述トリックと主題の親和性の高さは本作の肝になる部分だと感じましたし、そこにこそ『青くて痛くて脆い』の素晴らしさが内包されているのではないでしょうか。
「大きくなる」ということは「変化する」ということ
(C)2020「青くて痛くて脆い」製作委員会
皆さんは、自分の応援しているミュージシャンやアイドルが売れて、多くのファンを獲得していく過程で、その活動スタイルや音楽性が「変化」していると感じた経験はないでしょうか。
いわゆる「古参ファン」とされる人たちの中は、しばしば自分たちの応援しているグループが売れると「昔の方が良かった」「もうファンやめようかな」なんて考えに至る人も多いですし、新規ファンに攻撃的な意見を発信することも少なくありません。
こうした感情は人間であれば、誰しもが抱いて当然だと思いますし、当ブログ管理人自身も感じたことがあります。
この感情を紐解いた時に見えてくるのは、自分が初期から応援していたというプライドだったり、誰も認知していない彼らを応援していることに対するある種の優越感のようなものなのかもしれません。
つまり、ここには「自分」とそして「彼ら」だけという狭いコミュニティが形成されていて、だからこそそこに内包されている自分に特別感を感じるのだと思います。かくいう私もそうでした。
ミュージシャンやアイドルが売れていないときは、心の底から彼らに売れて欲しいと願えるのに、いざ売れてしまうと、「なんか変わっちゃったよな…」と感じ始め、逆にこれなら昔の方が良かったと思い始めるのです。
このプロセスで1番大きく変化したのは、「彼ら」と「自分」の距離であり、それが広がることで自分が「彼ら」を支えているという特別感や優越感が消失してしまうのが1つの大きな根本でしょう。
そうした過程を物語の中に上手く溶け込ませているのが、今作『青くて痛くて脆い』でもあります。
というのも、作中に登場する「モアイ」や寿乃に対する楓の感情の変化はまさしくそんな「古参ファン」の抱くそれと類似するものなのです。
最初に2人きりで「モアイ」を立ち上げた時、楓は大学で浮いていて、周囲から痛いと嘲笑されていた寿乃を支えられるのは自分しかいないと思っていたはずです。
そして何より2人きりだったが故に、彼と寿乃の距離が非常に近かったんですよね。
それがメンバーが増え、組織が大きくなり、更には寿乃に彼氏ができたことでその状況が一変していき、自分の特権的な立場は失われていきました。
つまるところ、楓が取り戻したかったのは「モアイ」でも、あの頃の寿乃そのものもなく、あの頃の彼女との「距離感」だったのではないでしょうか?
思えば、この『青くて痛くて脆い』という作品は冒頭から「距離感」という言葉を作品のキーワードとして反芻しています。
しかし、組織を大きくするということは、人間関係を広げるということは、同時に今まで付き合ってきた人間との距離感を変化させるということにも繋がりますし、それは人間が生きていく上で当然のものです。
ただ、人間は誰かを独占したいと望む生き物ですし、それ故に自分と相手の距離感や関係性が変わってしまうことに不安や恐怖を抱いてしまいます。
だからこそ、そうした距離感の変化を受け入れ、柔軟にその人との付き合いや関係性を変化させ、再構築させていける姿勢にこそ「青さ」からの脱却が内包されているのかもしれません。
楓は寿乃との関係性を徹底的に破壊してしまいましたし、もうそれは修復不可能なものなのかもしれません。
それでも彼は、物語のラストで寿乃との関係の再構築を試みます。
あの頃は、変化に怯え、逃げ出してしまった…。
自分の「青さ」と「痛さ」と「脆さ」を知って、その上で、そんな自分でもう一度彼女との関係を望むのです。
人と人との距離感は絶えず変化するものですし、どんな人もあなただけに依存しているなんてことはあり得ません。
だからこそ相手の世界の広がりを受け入れてあげられるかどうか、自分の立場や存在の重みの変化を受け入れられるかどうかが、人との関わりにおいては大切なことなのだと思いますし、『青くて痛くて脆い』が描こうとしたのも、まさしくこのことなのではないでしょうか。
青春を「痛み」で終わらせる
(C)2020「青くて痛くて脆い」製作委員会
本作のタイトルは『青くて痛くて脆い』となっていますが、その中でも特に強いのが「痛み」の部分でしょう。
楓と寿乃は大学生という設定になっていますが、この時期というのは大人になることを猶予されたある種の人生のモラトリアムなわけです。






















今作の楓と寿乃の壮絶な論戦を見ていると、思い出すのは朝井リョウさんの『何者』でしょうか。
十点でも二十点でもいいから、自分の中から出しなよ。自分の中から出さないと、点数さえつかないんだから。これから目指すことをきれいな言葉でアピールするんじゃなくて、これまでやってきたことをみんなに見てもらいなよ。自分とは違う場所を見てる誰かの目線の先に、自分の中のものを置かなきゃ。
(朝井リョウ『何者』より引用)
寿乃は何とか「モアイ」を大きくして、自分なりに理想を実現しようと紛いなりにも努力してきた人間です。






















彼女は自分の「青さ」と「脆さ」を知り、それでも自分の信じた道を「痛み」を伴いながらも進み続けてきました。
その一方で、楓は「青さ」や「脆さ」から目を背け、「痛み」に鈍感なふりをして、何からも逃げて生きて来たタイプの人間です。






















だからこそ、今の楓には寿乃の思いも痛みも何もかもが理解できないのです。
自分では何もしてこなかった、向き合ってこなかったからこそ、それをやって来た人間の心情が理解できません。
しかし、彼はそうして寿乃を全否定してしまったことで、自分が如何に「青くて」「脆い」人間なのかということをまざまざと突きつけられる結果となります。
だからこそ、この作品は楓が「青さ」や「脆さ」に向き合い、「痛み」を受け入れる形で青春の終わりを描きました。
組織が、人間関係が大きく広がっていく中で、それでも必死に「モアイ」を支え、理想を追求しようとした寿乃。
そんな彼女を全否定してしまったことで、彼は自分の行動を後悔し、恥じることができました。
その「痛み」は理想に逃げ込み、「モアイ」の変化という現実から逃れ続けてきた彼の負うべき業とも言えるものなのかもしれません。
モラトリアムというのは、大人になること、そして様々な社会的責任を負うことを猶予された最後の「青春」です。
それを終えるということは、向き合う必要のなかった「青さ」や「脆さ」を突きつけられ、「痛み」を背負うことでもあります。
しかし、それこそが社会の中で生きていくということであり、「大人」になるということなのではないでしょうか。
『青くて痛くて脆い』が描いた青春の終わりは、そんな「痛み」に満ちています。
そのヒリヒリするような痛みは、誰しもが感じたことのあるものであり、同時に誰しもがこれから感じることになるものなのです。
映画と原作の違いについて
(C)2020「青くて痛くて脆い」製作委員会
さて『青くて痛くて脆い』の映画版と原作の違いについてお話していきましょう。
まず、最大の違いは森七菜さんが演じる瑞希というキャラクターの存在です。彼女については完全に映画オリジナルの要素となっております。






















彼女のキャラクターとしては、高校を何らかの理由で逃げ出してしまい、通学することが困難になってしまい、施設で生活を続けているというものです。
作品の中盤にその原因の1つになったであろうと推察される高圧的な元担任教師が登場するのですが、そもそも彼女の物語の前後関係があまりにも示されていないため、イマイチ感情移入も理解もできません。
制作側の思惑としては、おそらく一番やりたかったのはあの元担任教師が瑞希を問い詰める描写と主人公の楓が秋吉に「何か気になることがあったら言ってね。」と声をかけられている描写をシンクロさせるあの演出だったのでしょう。
しかし、単純に瑞希というキャラクターがどういう経緯であの状態になって、どういう経緯で成長出来て、結果的にどんな未来を選択したのかをほとんど言及しないままに物語が終わってしまうので、せっかく登場させたオリジナルキャラクターなのに勿体ないという印象しか持てませんでした。
そういう意味で言うと、もう1人原作とはその役割が大きく変化したキャラクターがいます。
それが松本穂香さん演じる朝美です。
彼女は原作だと、それほど物語に大きく絡んでくるポジションではないのですが、映画版では妙に察しの良いキャラクターになっており、楓と董介の計画に気がつき、それを引き止めようとするような立ち回りをします。
ただ、キャラクターとしてのフェードアウトの仕方が原作と全く同じなので、キーパーソンだった割には終盤の展開にあまり噛んでこないという妙な仕上がりになっていました。
このあたりは映画オリジナルパートを足し込んだものの、上手く脚本に融合させることができず、苦心の跡が見られました。
その一方で、終盤の楓のIF世界の見せ方なんかは原作にはありませんし、個人的にはすごく感動出来たポイントです。
「なりたい自分」になれなかったという後悔の念を直接的に表現するというよりは、少し遠回りをしてナラタージュにIFを乗せて見せたのは演出として最適解だったと言えます。
「あの場所」にいたかったのに、「あの場所」に立つ選択を、決断をしてこなかった自分自身を恥じ、自身のツイートに記載した「なれるならば…」という表現を「なれなかった。」という断定の表現に変えるシークエンスは感情が伝わってきました。
また、楓が自分自身の頃を晒し上げるようなツイートをするという描写そのものも実は映画オリジナルの要素です。
ここについては「傷」という言葉が非常に垣間見える描写の追加だったと思います。
というのも、楓は勝手に自分が「傷」つけられたと思い込んでおり、それ故に自分と同じだけの「傷」を秋吉に負って欲しいと願ったのです。
しかし、彼は一連の行動を経て、自分が勝手に「傷」ついたと思い込んでいただけなのだと悟ります。
だからこそ彼は自分自身をネット上の晒し物にすることで、今度は秋吉に負わせた「傷」と同等の「傷」を自分自身が背負おうとしたというわけです。
ただ、それではお互いに「傷」ついただけで2人は前に進むことができません。何よりツイートの反響は薄く、彼は「傷」を負うに至りませんでした。
そこからラストシークエンスの2人の再会へと繋がっていきます。
楓はあの時に自分が負うことができなかった「傷」を負うことを選び、そして彼女に再び話しかけるのです。






















こうしてちゃんと「痛み」を受け入れる、「傷」を負うことを選択するプロセスを丁寧に描こうとしたのは、映画版の1つの良さだったと言えるのではないでしょうか。
パラパラマンガというモチーフの意味
(C)2020「青くて痛くて脆い」製作委員会
さて、本作の主人公である楓は劇中でパラパラマンガを描いています。
それは彼の人生の「暇つぶし」のようなものであり、大学の講義の最中に退屈そうにメモ帳の端っこにコツコツと描き進めていきました。
本作『青くて脆くて痛い』の映画版は、そもそも彼のパラパラマンガの描いた世界からスタートし、それが彼の現実へと変化していきます。
つまり、そこには楓がパラパラマンガという「暇つぶし」に自分の人生を重ねる様子が垣間見えます。特に意味のないもの。何の役にも立たないもの。
学校に行けなくなった子供たちの施設で瑞希にパラパラマンガを見られた時も、彼は「暇つぶし」「役に立たないもの」と自嘲的に表現していました。
物語と妙にリンクしているのも面白いのですが、彼が徐々に「モアイ」を去る方向へ動いている時のパラパラマンガは大きなモアイに主人公がぶち当たり、跳ね返されてしまうというところで終わっています。
その一方で終盤に描かれる彼のIF世界では、その大きなモアイを主人公がよじ登り、新しい世界を垣間見、青臭い理想を具現化していくような内容が描かれていました。






















彼は誰かに必要とされたかった、価値があると思われたかったのですが、そのために自分が選択したり、決断したりすることができないまま大学生活を送ってしまいました。
彼が人生の「暇つぶし」のように大学生活というものを解釈している素振りが見られたのも、そのためでしょう。
しかし、終盤のIFの世界で彼が望んでいたのは、そんなパラパラマンガが子どもを勇気づけ、そしてゆくゆくは戦争を止め、平和な世界を到来させるという壮大なビジョンです。
何の役にも立たないと思われた「パラパラマンガ=自分自身」が誰かの力になれると、彼はそう信じたかったのです。






















自分は誰の役にも立てないし、世界は変えられないからと選択を放棄してしまった彼と、それでもそのための選択を続けてきた彼女と。
だからこそ、エピローグ的に挿入された後日譚で彼は恵まれない施設の子どもたちにパラパラマンガを教えて回っているような様子でした。
それは、ある種の社会の王道からドロップアウトしてしまった子どもたちに、自分自身には価値があると、何か意味があると感じて欲しいという思いの表れなのかもしれません。
そしてパラパラマンガを描き続けているという彼の現在そのものが、同時に彼が「理想」を捨てずに持ち続けているということの表出にもなっています。
秋吉が掲げるような理想は、所詮は絵空事なのかもしれません。それでも自分はそんな彼女の意志を継ぐと紛いなりにも誓ったのだからと、パラパラマンガを描くという形で「理想」を描き続けているんですね。
映画版で新たに挿入されたサブモチーフではありますが、パラパラマンガという誰もが教科書の端に書いたことがあるような「暇つぶし」感とそこに宿る可能性という点で、効果的に機能していたと言えるでしょう。
役者陣の「演じ分け」の凄みに触れた
『青くて痛くて脆い』は、演出面で若干「狙いすぎ」な印象も受けますので、好みが分かれる部分だと思います。






















とりわけ今作の見どころは役者陣の「演じ分け」だと思いました。
まず、1人目のキャラクターの心情の劇的な変化を表現するための「演じ分け」が特に主演の2人に関してではありますが、非常に上手いんですよね。
杉咲花さんが演じたの秋吉の天真爛漫そうな表の部分と、ナイーブで傷つけやすい内面の対比、そして怒りや嫌悪感を全面に出した時の冷たい空気感を身に纏う感じ。
一方の吉沢亮さん演じる楓の世の中を俯瞰で冷笑的に見るような表情、そして秋吉に対してむき出しにする負の感情の表現、そこから生じる深い後悔の念と焦燥感…。
1人のキャラクターの心情が、劇的に変化していく物語であるだけに、それを表現する役者側にも技量が求められますが、そこをしっかりとクリアしてきた役者陣の貢献は大きいですね。
その一方で、これは監督らの演技面のディレクションの巧さだと思いますが、キャラクター間の「演じ分け」がきっちりと出来ていました。
例えば、楓と秋吉は対照的な人物として描かれますが、それ故に演技のトーンは徹底的に分けられています。
楓と董介は逆に似た者同士的に最初は描かれていくのですが、董介の心情が徐々に変化していくにあたって、徐々に演技のトーンにも違いをつけていくんですよね。
2人でモアイに対して冷笑的に振舞っていたところでは同じだった空気感や表情のディテールが、怒りに身を任せて行動をエスカレートさせてしまう楓と彼らに共感し牙をしまう董介では、決定的に変化しています。
また、秋吉や理沙のような確固たる自分を全面に出したキャラクターがいる一方で、瑞希のようなヘラヘラとしていて、場や相手によって自分を操ることのできる特異点の存在が際立ちますよね。
ただ、彼女は「自分」を持っていないように見せかけて、むしろ「自分」をしっかりと持ったキャラクターです。
ここは本当に松本穂香さんの演技の技量の高さだと思うのですが、彼女の「ヘラヘラ」感をしっかりと出して、表面的な部分では、秋吉や理沙との対比を際だたせつつ、彼女の持つ「自分」の部分もきちんと表現しているんですよ。
ヘラヘラとしていて、どこかのんびりとしていて、それでも時折見せる表情や目の雰囲気の変化に、強い意志を感じさせてくれました。
他にも清水尋也さんのどこまでも突き抜けたいわゆる「パリピ」でありながら、ナイーブな内面を抱えているという二面性の使い分けも良かったですし、その裏の部分で董介との共通点のようなものを見出せるような演技に仕上げてきたのも驚かされました。
1人のキャラクターとしての表の顔と裏の顔、建前と本心の「演じ分け」
キャラクター間に垣間見える共通点と差異を表現するために物語の状況や展開によって為される「演じ分け」
この2つの「演じ分け」が『青くて痛くて脆い』という作品を支える根幹にもなっていると思います。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は住野よるさんの『青くて痛くて脆い』についてお話してきました。
住野よるさんの『君の膵臓をたべたい』は余命ものの在り方を激変させたとも言える衝撃的な1作でしたが、今作もSNS描写や叙述トリックを盛り込み青春譚の在り方を書き換えたと言えるでしょう。
映画版に関しては、吉沢亮さんと杉咲花さんという優れた演者がメインの2役に起用されているので、終盤のヒリつくような舌戦も本当に楽しみですね。
冷静で温厚そうな印象の吉沢亮さんが感情を爆発させる姿。
天真爛漫で笑顔の似合う杉咲花さんの表情から笑みが失われ、どす黒く染まっていく様子。






















ただ、今作が取り入れた叙述トリックについては、個人的に活字で読むほうがインパクトは強いかなと思いますし、映像で表現するのはなかなか難しいかなと思っています。
なぜなら、本作のトリックは「モアイ」の代表を「見せない」ことによって成立しているので、映画という視覚メディアに落とし込んだときに、どうしてもその「見えない」ことが違和感を生んでしまうからです。
そこをどう乗り越えてくるのかが、今回の映画版のスタッフの腕の見せ所でもありますね。






















ただ原作と映画版では主眼の置き方が微妙に違うと感じていて、原作では「傷」という痛みの部分にフォーカスした一方で、映画版は「傷」を負ってからの後悔と選択にフォーカスされていたように感じます。
ですので、叙述トリックの印象が強かった原作とはがらりとイメージが変わったようには思いました。
それでも、杉咲花さんと吉沢亮さんの圧巻の演技力と劇伴音楽を排した演劇的な終盤の口論の演出により、原作の特徴であったヒリつくような痛みは担保されていたと感じました。






















この2人は、まさしくこれからの邦画界を代表する俳優になっていくと思いますし、これからも目が離せません。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。