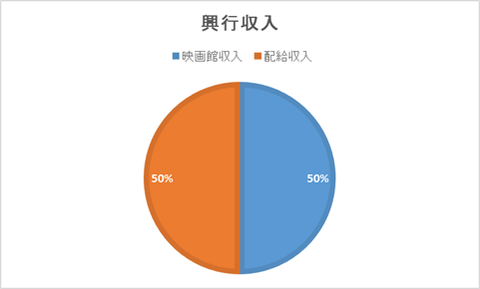みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章前半がいよいよ実装となりましたので、その内容についてお話していこうと思います。

『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』は第2章も第3章も「キャラクターの死」という形で、明確にプレイヤーの心を抉るような展開を描いてきました。
しかし、今回の「第4章前半」に関して言うと、これまでとは少し毛色が違います。
第2章と第3章は「キャラクターの死」を受け止め、時間をかけて咀嚼していくというもので、受け取り手のスタンスとしてはいたってシンプルなんですよね。
ただ「第4章前半」は、正直どう受け止めていいのかが分からないので、これまでと比較すると圧倒的に複雑です。
時間が解決してくれるとも思えない、心に突き刺さって抜けない棘が、プレイを終えても、じわじわと心を痛ませるような、奇妙な感覚が残っています。
この『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第2章と第3章の描写から、「死」よりも心を打つ何かをこの物語が描けるのか?という疑問を、私も含めて多くの人が持っていたのではないでしょうか。
だからこそ、このシリーズは次々にキャラクターに「死」をもたらしていって、その「死」がどうもたらされるか?に「切なさ」を宿らせていくに過ぎないのではないかと、私も本シリーズの将来を危惧していました。
しかし「第4章前半」は、まさしく「死」よりも重く、そして深い「絶望」を描いた物語であり、このシリーズの「切なさ」の新しい地平を開いたと言っても過言ではありません。
そして、私はこの種の「絶望」を麻枝准さんが描いたからこそ、苦しいのです。
今回の記事では、麻枝准さんの過去の作品も少し振り返りながら、『ヘブンバーンズレッド 4章前半』が描いた「絶望」について自分なりに考えてみたいと思います。
本記事は、都合上、『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未プレイの方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン) 第4章前半』考察(ネタバレあり)
「何もできないきみ」を肯定してきた作家、麻枝准
麻枝准さんが作詞・作曲家として残してきた楽曲は数多く存在しますが、その中でも自他ともに認める最高傑作の1つが『karma』です。
この楽曲の中に、次のような一節があります。
何もできないきみだって 僕は好きなままいるよ
運命というものなんて 僕は決して信じない
卵も割れなくていい いくつでも僕が割るよ
歌が下手だっていいよ こうして僕が歌うよ(麻枝准『karma』より引用)
麻枝准さんはこの『karma』を非常に大切にしており、自身の「原点回帰」を掲げた『神様になった日』というテレビアニメの中でも挿入歌として採用し、さらにはこの歌詞の世界観を物語の根底に据えました。
「何もできないきみ」への肯定というのは、麻枝さんの中にずっと存在していた考え方なのだと思います。
『karma』の歌詞もそうですが、2010年に放送されたテレビアニメ『Angel Beats』の中でもその考え方が、日向とユイの関係性に落とし込まれていました。
ユイ「そんな・・・先輩はほんとのあたしを知らないもん」
日向「現実が・・・生きてたときのお前がどんなでも、俺が結婚してやんよ!もしお前が・・・どんなハンデをかかえてでも」
ユイ「ユイ歩けないよ・・・立てないよ」
日向「どんなハンデでもっつったろ!歩けなくても立てなくても、もし、子供が生めなくても・・・それでも、俺がお前と結婚してやんよ!・・・ずっとずっとそばにいてやんよ・・・。ここで会ったお前は、ユイの偽者じゃない、ユイだ。どこで出会っていたとしても、俺は好きになっていたはずだ。また60億分の1の確率で出会えたら・・・そん時もまた、お前が動けない体だったとしても・・・お前と結婚してやんよ。」
(『Angel Beats』第10話より)
ユイという少女は、死後の世界では何不自由なく暮らせていますが、死ぬ前は身体にハンディを抱え、不自由な生活を強いられていました。
日向は死後の世界の活発なユイだけではなく、死ぬ前に存在していたハンデを抱えた「何もできないユイ」をも丸ごと肯定し、彼女の心を救うのです。
そして、麻枝准さん本人は、2016年に、国が指定する心臓の難病を患い、「自分の心臓じゃ生きられないみたいです。」とコメントを残します。
その後、手術を経て、奇跡的な復活を遂げるのですが、彼はさまざまなインタビューで、入院中の経験について述べてきました。
病院でたくさんの医療機器に接続され、何もできない自分の命が自分以外の何かに生かされているような状況は、彼に多大な影響を与えたと言われています。
だからこそ、彼は復帰作として『神様になった日』を作らなければなりませんでした。
それは麻枝さんにとって、「何もできないきみ」の肯定を介して、「何もできない自分」を肯定する究極の自己肯定でもあり、彼が大切に抱き続けた思想への回帰でもあったのです。
このように麻枝さんは、作品を通じて、「何もできないきみ」を肯定する物語を紡ぎ続けてきました。
そして、それは自分自身が「何もできない」状況に置かれた病床での経験によって、さらに強まり、確固たる考えとして彼の中に君臨していたはずです。
「何もできないわたし」の絶望と救われなさを描く
そんな麻枝さんが、今回『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章前半で、めぐみの物語にあのような幕切れを用意したことに、私はかなり驚かされました。
というのも、彼がこれまでに描いてきた「何もできないきみ」の物語は、基本的にそれを受け入れる側の人間の視点で描いてきたんですよね。
「何もできないきみ」に対して「それでも、きみはここにいていいんだよ。」と告げる構図を、告げる主体の側から描くことによって、彼はそれをある種の「美しい神話」に変えてきました。
しかし、この物語の構図には、重大な落とし穴があります。
それは、「何もできないきみ」が「何もできないまま」で受け入れられることをどう思うか?という、受け入れられる客体がどのように考えていて、感じているのかに関する視点が抜け落ちていることです。
『神様になった日』は、それを問題として認識しつつも、曖昧なままにして、主人公の圧倒的なエゴによってねじ伏せてしまったようなところがあります。
それゆえに、『神様になった日』の結末は、視聴者に一抹の気持ちの悪さと共に受け取られる結果になったのだと思います。
「何もできないきみ」を「受け入れてあげる」ことは、確かに尊い行為なのかもしれません。しかし、それが受け入れる側のエゴなのではないかという検証が正しく為されてきただろうか。
『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章前半におけるめぐみの物語は、まさしくここに切り込んだものであり、麻枝さんが自身の描いてきた物語に内省的な視点を投げかけるようなものになっているのです。
逢川めぐみは、自分に自信がない少女でした。
そんな彼女は、自分が何か他の人よりも秀でていることを見つけようとし、サイキック能力に目覚め、活躍するようになります。
そして、サイキックの組織から一目を置かれ、その組織に属する運びとなるわけですが、そこには自分よりも優れたサイキック能力を持った人がたくさんいました。
めぐみは、そこでもまた劣等感に苛まれることとなります。
自分が存在する意味、価値。それを探し求めていた彼女を救ったのは、組織のリーダーのある言葉でした。
「あなたは救世主。まだそれを知らないだけ。」
劣等感を抱えて生きてきた彼女にとって、その言葉は自分の存在を唯一肯定してくれるものであり、自分の生きる支えになりました。
そんなめぐみが、直面する自己の喪失。「救世主」であるという言葉をかけられたのは、自分であって自分ではないという現実。
彼女は自分の存在を肯定し、成立させてくれた大切な言葉を喪失し、生きる意味と自分の価値を見失ってしまったのです。
それでも、めぐみは戦いました。いつかのリーダーの「救世主」という言葉が、自分であって自分ではなくなってしまった今の「自分」に向けられたものかもしれないと、信じてみようと試みました。
しかし、戦いの中で突きつけられたのは、己の無力感と自分が「救世主」ではないという現実だけでした。
「何もできないわたし」になってしまっためぐみには、もう存在する価値などないと、セラフ部隊を去ることを決意する他ありません。
きっと、これまでの麻枝さんの物語であれば、彼女の仲間が「何もできないきみ」としてのめぐみを肯定し、彼女の存在と価値を担保したはずだと思います。
ただ、『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章前半はそうならないのです。
主人公の月歌とめぐみと親交のあるタマは、今のあなたのままでも私たちにとっては「救世主」なんだと彼女を肯定し、受け入れる意志を見せます。
それでも「何もできないわたし」の絶望は救われないのです。
他者の無条件の受容、無邪気な肯定は、「何もできないわたし」の絶望を救わない。
麻枝さんは、これまでに作り上げてきた自身の物語における「美しい神話」を明確に破壊して見せました。
もちろん『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の物語はまだ途中であり、めぐみの物語についてもこれが完結というわけではないのかもしれません。
しかし、「何もできないきみ」を受け入れることの美しさや尊さを描いてきた麻枝准さんの物語において、「何もできないわたし」の救われなさや身の置き所の無さにスポットを当てたという衝撃はとても大きいものがあります。
おわりに:いつか、救いを求めて
今回は『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の第4章前半についてお話してきました。
物理的な人間の「死」はとても大きな悲しみを伴います。
『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の切なさは、そうした悲しみに裏打ちされてきたところがあります。
ただ、第4章前半の切なさの背後にあるのは、むしろ「苦しみ」です。
麻枝准さんは、『神様になった日』の放送当時、大量のアンチコメント、作品に対する批判的なコメントに耐えきれなくなり、一度そのTwitterアカウントが「失踪」しました。
数々の名作で一時代を築き、「天才」だと自分を賞賛する声に支えられながら創作を続けてきた彼が、それを否定され、信じられなくなる。その絶望。
その絶望は、第4章前半におけるめぐみのそれに、確かに重なるものです。
『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』はまさしく、その絶望の淵から麻枝さんが立ち上がり、前に進むために書き始めた物語であると言えます。
だからこそ、彼自身の苦悩や葛藤と重なるものを抱えためぐみというキャラクターにも、物語の果てに救いがもたらされるのだと私は信じています。
なぜなら、麻枝さんは、物語の中に「自己救済」を込めるクリエイターだからです。
「何もできないきみ」が受容される側に立つ客体の物語ではなく、「何もできないわたし」が自分の力で存在と価値を取り戻す主体の物語がいつか紡がれる日を、心待ちにしながら。
これからも『ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)』の物語を追いかけていこうと思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。