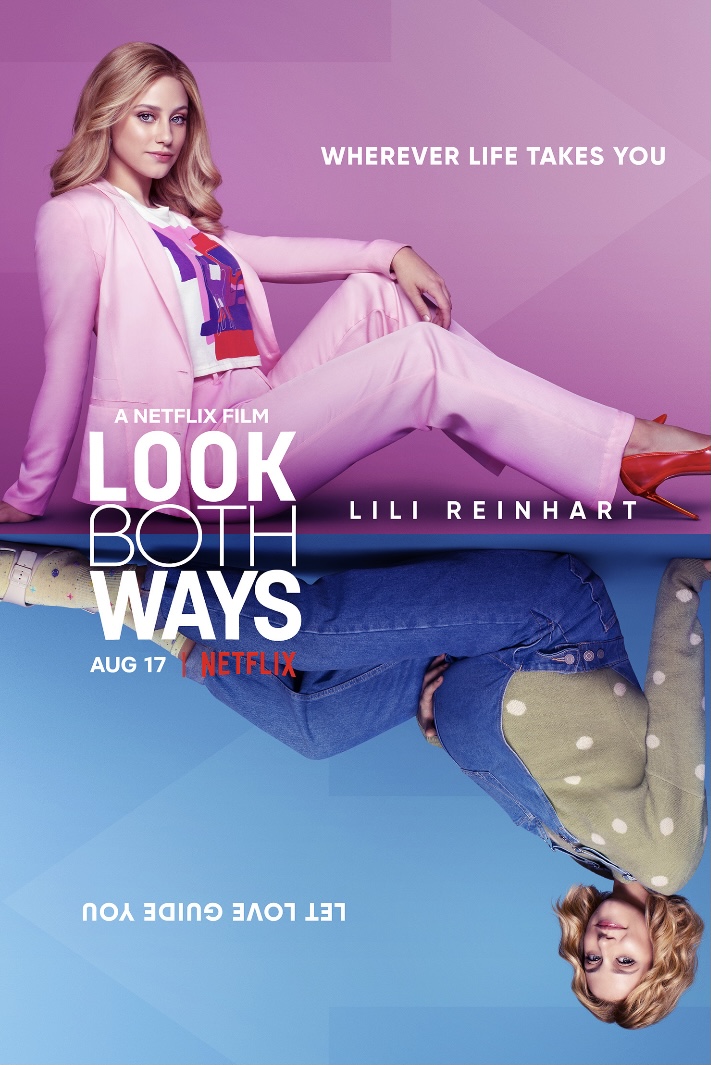みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『異端の鳥』についてお話していこうと思います。

まず、最初に断っておきますが、この『異端の鳥』という映画に関して、動物の虐待シーンが苦手だという方はご覧にならないことをおすすめします。
おそらくですが、開始1分のとある描写で心が折れます。端的に言うと、主人公が犬を助けようとして森の中を逃げているのですが、村の子どもたちに捕まり、その犬を火あぶりにされてしまうというものです。
しかも、その犬が燃えながら苦しんでいる様子まで鮮明に描かれていますので、かなり心を抉られます。当ブログ管理人も犬を飼っている人間だったら、この時点で劇場を後にしていたかもしれません。
という注意を前置きとしたうえで、本作の簡単な概要にでも言及していきましょう。
まず原作を著したのは、ポーランドの作家イェジー・コシンスキです。彼もまたホロコーストの生き残りであり、ユダヤ人なんですね。
さて、そう聞くと、この『異端の鳥』という作品は、彼の自伝的小説なのではないかと容易に予測がつきますよね。ただ、実のところこの本は彼の自伝ではありません。
彼は何とかホロコーストを生き抜き、アメリカに亡命して、そこで大学にも通い、後に作家としてデビューすることとなりました。
しかし、今作が「自伝」ではないということで、東欧諸国の人間はこのような作品を作ったコシンスキに対して当然反発するようになります。
そうして激しい誹謗中傷に晒されることとなったコシンスキは、57歳の時に自宅で自殺によりその生涯を終えることとなりました。
本作の原題は「The Painted Bird」であり、これは劇中の「レッフとルドミラの章」で描かれた白いペンキを塗られた鳥からとったものでしょう。
同じ種類の鳥なのに、白いペンキが塗られていて、他と色が違うというだけで迫害され、命を奪われる…。
皮肉にも、この作品を著したコシンスキ自身がそんなThe Painted Birdになってしまい、激しい誹謗中傷に晒されながら、命を絶ったと考えると、人間とはかくも恐ろしい生き物なのかとしみじみ感じさせられます。
映画に関して非常に面白いのは、主人公の設定でしょう。
本作は事前の予告でホロコーストを扱った作品と謳われていますが、そもそも主人公がユダヤ人なのかどうかって映画を見ている私たちも知り得ない情報なんですよ。
主人公の容姿の設定は「ブロンドの髪と青または灰色の目で色白」となっているわけですが、これだけでは当然「ユダヤ人」かどうかは分かりません。劇中のレッフという鳥売りの男が「ユダヤ人かジプシーか?」と聞いていましたが、彼らもまた分かっていないんですよ。
ただ、東欧のスラブ系民族とは明確に違う見た目をしているので、迫害を受けるわけです。
その点で容姿の「色」で判断され、主人公は迫害を受けることになるわけで、これがタイトルの「The Painted Bird」にリンクしています。
そして映画についてもう1つ面白いのが、この作品で使われた言語です。
当ブログ管理人も作品を見ていて、一体主人公が出会う東欧系の農民たちが話している言語は聞いたこともなくて、土着の言葉だったりするのかなと想像を膨らませておりました。
ただ、パンフレットを読んでおりますと、これがスラヴ諸国間に存在する人口共通語であるインタースラヴィックというものなんだそうです。



この言語を用いたのは、ポーランド語やチェコ語など特定の国を指し示す言語を用いてしまうと、その言語が登場する人間の残忍な振る舞いとダイレクトに結びついてしまう可能性があるからとのことです。
こうした国を特定しないというアプローチは良かったと思いますし、『ミッドサマー』を思わせるような、自分の知らない言語が用いられているコミュニティに足を踏み入れる感覚があり、地獄観が増していました。
さて、最後に監督についてご紹介して、作品を詳しい話に移っていきましょう。
監督を務めたのは、ヴァーツラフ・マルホウルです。
今作は『ジョーカー』が最優秀賞を獲得した昨年のヴェネツィア国際映画祭にて、大きな話題を集めました。絶賛と共に迎えられると共に、そのあまりにも残酷な描写から途中退出者も続出したのです。
そんな作品が描きだしたものとは何か、人間の本質的な恐ろしさとは何なのかを作品を振り返りながら今一度考えてみたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『異端の鳥』解説・考察(ネタバレあり)
短編が繋ぐ少年の変質と成長
COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY
今作は、全部で9の章に分かれており、それぞれ主人公の東欧諸国を巡る旅を描いているのですが、何の脈絡もない短編の連続を見ているように思う方もいらっしゃるかもしれません。
とりわけ本作は残酷描写が際立っていますので、そうしたセンセーショナルな視覚的描写に気を取られて、この9の章がどんなつながりを持っているのかが見えづらくなってしまうという側面も十分にあると思います。
しかし、そんな一見すると何の脈絡もない本作の9の章は、主人公の少年の変質や成長を描くという点で、密接なつながりを持っているんです。
というのも、主人公が冒頭に受けた仕打ちや理解できなかったことに対して、作品の後半になると主人公が自分なりのレスポンスを示すようになっていきます。
例えば、3つ目の「ミレルの章」で、少年はとある夫婦と若い男の使用人が暮らしている家に居候することになりました。
そこで、妻と使用人の不倫を疑った嫉妬深い夫が怒り狂い、使用人の目玉を抉り取って捨ててしまうという事件を目撃することになるのです。
しかし、この時の主人公は、おそらくあの夫が感じていた激しい嫉妬や怒りの心情をまだ理解できていなかったのではないでしょうか。
そして4つ目の「レッフとルドミラの章」では、主人公が鳥を売るレッフという男とその恋人であるルドミラの情事を目撃します。草むらからそれを覗く、主人公は彼らが何をしているのかを理解していないことでしょう。
その後、ルドミラが村の女性たちからリンチを受けて死亡すると、レッフも後を追うように自殺を選択します。
この時、レッフがどんな怒りと悲しみに包まれながら、自死の決断をしたのか。これもまた当時の主人公には知り得なかったことです。
そして、7つ目の章に当たる「ラビーナの章」でこれらの「理解できなかった感情」が主人公に内在化され、一応の伏線の回収が為されます。
主人公はラビーナという女性の家で暮らすようになるのですが、彼女は主人公を性の対象として求めるようになりました。
しかし、直前の章でガルボスという男から性的な虐待を受けていたことも関係しているのか、彼は上手く立ち振る舞うことができず、それに失望したラビーナは主人公を拒絶するようになります。
加えて、ラビーナは自分の性的欲求を満たすために、飼っている山羊と交尾をするようになり、その様を主人公に見せつけるのです。
この時、彼の心の内に燃え上がったのは、ミレルが感じていた激しい「嫉妬心」であり、レッフが感じていた「怒りと悲しみ」なのでしょう。
物語の冒頭にはそうした感情を傍観する側にいた主人公が、ここで明確にその感情の主体へと転換され、そして行動を起こします。
彼はラビーナと交わった山羊の頭部を切り落とし、家の中に投げ込んで、その場を後にしました。
この行動はもちろんミレルが不倫の疑惑があった使用人の目玉をくりぬいて床に投げたあのシーンと重なります。
また、主人公は徐々に自分が受けた仕打ちをひたすらに耐え抜くのではなく、それを跳ね返すようになっていきました。
2つ目の「オルガの章」で主人公は呪術師の女性に買い取られます。そしてその助手として働くわけですが、ある日風邪をひき、治療のため顔だけを地上に出した状態で地面に埋められます。
すると、カラスが集まってきて彼の頭部をつつき始めます。一命はとりとめましたが、その後、彼は村の若い男に突き飛ばされて川に落ち、コミュニティを追われることとなりました。
6つ目の「司祭とガルボス」の章では、ガルボスという男に性的虐待を受け、更にはミスをすると、狂暴な犬のいる部屋に縄で縛られて、天井から吊り下げられ、命の危険を感じます。
彼は、そうした仕打ちを受けてきたわけですが、「司祭とガルボス」の章の最後には自らが縄をひき、ネズミが大量に生息している穴の中にガルボスを引きずり落としました。
主人公は自分が受けた苦しみや痛み、生命の危機を跳ね返すということをある種の生存本能として身につけたわけです。
しかし、「人を呪わば穴二つ」という言葉もありますが、その後主人公が心優しかった司祭の葬儀に際して神聖な聖書を落としてしまい、町の人々から暴力を受け、肥溜めに放り投げられという苦難を経験します。
6つ目の「司祭とガルボス」の章は言わば、本作の明確な転換点になっています。
COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY
基本的に主人公は暴力を受ける側の人間です。
しかし、第5章「ハンスの章」と第6章「司祭とガルボス」に登場する2人の人物だけは主人公に暴力を振るったり、性的に虐待したりすることもありません。
それが第5章の老兵と第6章の司祭です。彼らは、主人公を何とかして助けたいとそう願っていました。
つまり、ここまでひたすらに暴力に晒されてきた主人公に、もう1つの光の道を示すのが、この2人の人物なんですよ。
他人に暴力を振るうだけではなく、優しさを与えるような存在。きっとこんな人たちが周りにいてくれれば主人公は幸せになれるだろうと思わせてくれるような人たち。
しかし、そうした優しさは、怒りや憎しみ、暴力、虐待と言ったものに対して無力であり、簡単に上書きされてしまいます。
結果的にガルボスを明確な意思を持って殺害した主人公の行動は大きく変質していきました。
第7の「ラビーナの章」の冒頭では、自分よりも弱い存在である老人に暴力を振るって身包みを剥ぎ、さらには山羊の頭を切り落とすなどの蛮行にも及びます。
加えて、第8の「ミートカの章」ではロシア軍の兵士から「目には目を歯には歯を」という戦争における原則のようなものを教えられ、銃を渡されました。
第9の章で彼は孤児院に入っているのですが、自分をユダヤ人であると罵る人間がいれば、持っている銃で射殺するという恐ろしい子供に成長しました。
彼は旅路の中で、人間の優しさと暴力性の両方に触れ、自分が生き抜くためにはどちらが必要かを天秤にかけ、後者が必要なのだと本能的に感じ取ったのではないでしょうか。
このように、9つの章から成る地獄めぐりが犬を助けようと必死になる心優しき少年に「生きるため」の選択を迫り、その結果として暴力に傾倒していくという恐ろしいプロセスを今作『異端の鳥』は描き出しています。
一見脈絡のない、9つの章はこのように見事なまでにリンクしており、行動や感情が主人公の外部にあるものとして描かれ、後にそれが内部化していくという形で彼の変質に寄与していく構成になっていたわけです。
3時間近い尺のある『異端の鳥』ですが、こうした1つの物語の軸が明白であるため、飽きることなく物語に没頭できました。
主人公の沈黙と虐待される動物
さて、記事の冒頭にも書きましたが、本作を見ていて印象に残っているのは、やはり動物の虐待シーンです。
ただ、そうした虐待シーンは何も視覚的にセンセーショナルな作品にするために取り入れられたというわけでは決してありません。物語において重要は意味を孕んでいます。
というのも、本作において動物たちと言うのは、主人公と重なる存在として描かれていました。
例えば、映画開始から1分足らずで焼かれる犬、食料にするために首を切り落とされる鶏、ペンキを塗られて仲間にリンチされる鳥、足が腐っているからと殺処分される馬、籠に捕らえられて食料にされる魚。
COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY
動物ないし人間以外の生き物は言葉を持ちません。そのため、人間に殺される算段になっても、言葉でもって意思疎通を図ったり、抵抗したりすることができないのです。
ただ、暴力を耐え忍び、殺されるのを待つことしか許されない、「寡黙な」動物たちと言うのは、物語の中盤までの主人公に重なります。
主人公もまた作品の大半において沈黙を貫いており、とりわけ序盤から中盤にかけては、周囲の人間からの暴力や虐待をただ耐え忍ぶことしか許されません。
しかし、先ほども説明したように6つ目の「司祭とガルボスの章」で主人公は明確に自分の意志で暴力を振るう人間に抵抗します。自らも暴力に手を染める選択をしたわけです。
この選択が意味するのは、動物的なものから人間へと、主人公が変質していったことなのだと思います。
物言わぬ傍観者的な存在だった彼は、生きるために自分に降りかかる暴力や虐待に対して抵抗するようになっていきました。
暴力を振るう主体と化し、第7の「ラビーナの章」の冒頭では、生きるために自分よりも弱い存在である老人に暴力を振るうという残忍な行動を取ります。
これも人間としての彼の生存本能に近い行動であり、人間という存在から切っても切り離すことのできない1つの側面なのです。
しかし、この映画はそのラストシーンにおいて明確に1つの希望を示します。
それは、主人公が父親と共に乗っているバスの窓の結露に自分の名前を書くシーンです。
人間は確かに暴力を振るったり、集団で誰かを攻撃したり、挙句の果てには戦争をしたりと暴力的で、野蛮な性質を内に秘めた生き物だと思います。
ただ、人間らしさとは何かと考えた時に、動物と決定的に違うのは、やはり「言語による意思疎通」なんですよ。
人間は言葉でもって分かり合える可能性を秘めているのに、それを言葉にすることなく暴力で解決してしまおうとしてしまい、それが「戦争」という形になって表面化します。
アウシュビッツのような強制収容所では、人間から「名前=言葉」を奪い、番号で管理することによって人間性をはく奪しました。
確かに暴力を用いれば、簡単に相手をねじ伏せて、自分の欲求や要求を通すことができますから、言葉でコミュニケーションをとるよりも、はるかに「楽だ」と考えるのも無理はないのかもしれません。
劇中で聖書を読んでいる敬虔なキリスト教徒が主人公に暴力を振るうという場面がありましたが、あれは言葉というものの無力さを強調するシーンでもあったと思います。
いくら聖書の教えがあったとしても、司祭の言葉があったとしても、人間の暴力性は抑えることができない。皮肉なものです。
それでも、この映画は人間と動物を隔てる「言葉」の可能性に賭けています。
ラストシーンは主人公が「ヨスカ」という名前を取り戻す重要なシーンであり、これは同時に人類に暴力ではなく言葉というツールを今一度思い出してほしいという願いが込められたシーンでもあるはずです。
沈黙を貫く動物のような主人公の少年が暴力と言語という2つの「人間らしさ」に目覚めていく物語こそが『異端の鳥』の本質だと思います。
しかし、言葉というものを持ちながら、閉口し暴力に傾倒していく。それでは空を飛ぶあのPainted Birdをリンチして叩き落した鳥たちと何ら変わりがないではないですか。
人間が「言葉を語る」ということの意味を再考させるという点で、本作は非常に重要な作品になっていたと思いました。
鑑賞する主体としての「私たち」
COPYRIGHT @2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN CESKA TELEVIZE EDUARD & MILADA KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKY
最後にこの作品私たちが見ておくべき意義のようなものについてお話させてください。
もちろん「言葉」という人間らしさを今一度取り戻していくという形で暴力性に立ち向かう作品ではあったと思います。
ただ、映画というものはあくまでも鑑賞する観客がいて完成するものだと私は常々考えております。
そう思った時に、この映画を観客が見ることには、どんな意義があるのだろうかと考えてしまうのです。
ひたすらに暴力性と人間の狂気、悪の部分が映し出されていく本作は、その視覚的な描写の過激さも相まって、見る人に衝撃を与えます。
見ている私たちもまたそんな人間の1人なのだと思うと、たまらなく嫌悪感に襲われるのですが、この映画を見ているともう1つ感じることがあります。
それは主人公に手を差し伸べてあげたいという慈悲の心や愛情です。司祭が彼に向けたような心からの善性を、映画を見ている私たちもまた与えてあげたいとスクリーン越しに願うようになるわけですよ。
確かに映画の中で描かれた残忍な行動や狂気、暴力は歴史的に見ても、人間が繰り返してきたことですし、それを切り離すことはできません。
何かのトリガーで私たちの内に秘められた暴力性が表に出てしまい、劇中の人物と同じような行動を取ることは当然あり得るわけで、それを否定することはどんな人にもやっぱりできないと思います。
しかし、この『異端の鳥』という作品を見ながら、彼に何とか手を差し伸べてあげたいと願う私たちもまた「人間」なんですよね。
虐げられている人、弱い立場の人、苦しんでいる人、悲しんでいる人を見た時に、手を差し伸べてあげたいとそう思えることもまた「人間らしさ」なのです。
本作は3時間近い長尺の中で、ひたすらに主人公が暴力や悪に直面する様を描き、観客の中にそうした「温かい気持ち」を呼び起こします。
そうした気持ちを呼び覚ますことができたのであれば、きっとこの映画にも意味があるのだとそう思えますね。
暴力とやさしさの「あわい」に生きるものとしての人間。そのどちらに傾くか。
この映画を見た私たち1人1人が抱く「やさしさ」はきっと本物です。