映画『ブリキの太鼓』より引用
目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですねギュンターグラス著(フォルカーシュレンドルフが映画化した)の『ブリキの太鼓』についてお話していこうと思います。
本記事はネタバレになるような内容を含む作品の解説・考察記事になります。
良かったら最後までお付き合いください。
『ブリキの太鼓』
ギュンターグラス年表
| 1927年 | 食品料理店の息子としてダンツィヒに生まれる。 |
| 1944~45年 | 武装親衛隊に入隊、敗戦を迎えると、アメリカの軍捕虜収容所に半年間収容。 |
| 1947年 | デュッセルドルフで石工の見習いとして働く。 |
| 1953~56年 | ベルリンの造形芸術大学で学ぶ。 |
| 1955年 | 南ドイツ放送の叙情詩コンクールで『眠りの百合』が3位に入賞。 |
| 1958年 | 『ブリキの太鼓』が47年グループ賞を獲得。① |
| 1959年 | 『ブリキの太鼓』を出版。 |
| 1961年 | 短編小説『猫と鼠』を発表。 |
| 1963年 | 小説『犬の年』を発表。 |
| 1972年 | 小説『蝸牛の日記から』を発表。 |
| 1977年 | 小説『ひらめ』を発表。 |
| 1986年 | 『女ねずみ』を発表。 |
| 1992年 | 小説『鈴蛙の呼び声』を発表。 |
| 2006年 | 自伝『玉ねぎの皮をむきながら』を発表。② |
| 2015年 | 死去 |
① 1947年に創設された戦後派新進作家の集まり。ハンナ・ヴェルナー・リヒターが主催した。1967年まで続いた。
② 自伝の発売当初、グラスがナチスの少年親衛隊に入隊していたことを告白したため、非難を浴びた。このような経歴を隠しながら、どうして戦争批判をすることができたのかというのが非難の中心であった。
あらすじ(ネタバレ注意)
第1部
精神病院の住人である30歳のオスカルが自らの生涯を語る形式で物語が始まる。
1899年にジャガイモ畑でオスカルの祖母アンナは逃げてきた放火魔をスカートの中に匿う。アンナはその男との間にオスカルの母アグネスを授かる。
(この子作りの方法が斬新すぎて笑ってしまうのですが、スカートの中に隠れた男がそのままアンナに〇入してしまうという・・・。)
アグネスはドイツ人のアルフレートと結婚するが、ポーランド人のヤンとの間にオスカルを授かる。
3歳になったオスカルは母親からブリキの太鼓をプレゼントされると同時に大人への抵抗から彼は3歳で成長を止めてしまう。またこの時から太鼓を叩きながら叫ぶと、ガラスが割れるという力を身につける。
ある日4人で海岸に出かけた際に、引き上げられた馬の頭からウナギが大量に出てくるのを見て、母アグネスは嘔吐し、その後狂ったようにウナギをはじめとする魚を食べ続け、魚中毒で命を落とす。
第2部
1939年に起こったポーランド郵便局襲撃事件で、オスカルの父ヤンが死亡してしまう。
そして、マツェラート家には母親代わりのお手伝いとしてマリーアがやって来る。オスカルは彼女に好意を抱き、彼女と唾液を媒介とした奇妙な関係を結ぶ。
しかし彼女はオスカルの父アルフレートの妻となり、息子クルトを授かる。
オスカルは、クルトは自分の唾液を媒介として生まれた息子だと信じてやまない。
彼はそののちに小人のベブラたち慰問団と軍の基地等に慰問をするための旅に出た。
彼は慰問団のロスヴィーダと恋仲になるが、彼女は連合軍の爆撃で命を落とす。
その後オスカルはダンツィヒに戻るが、ソ連軍の侵攻により、父アルフレートが射殺されてしまう。
父の葬儀の日に彼はブリキの太鼓を棺の中に投げ入れる。彼は西方のシュトルプ行の貨車に乗り、その中で成長を再開する。
(映画版はここで幕切れとなります。)
第3部
ここから戦後の場面。オスカルはマリーアの姉を頼ってデュッセルドルフに行き、彫刻の勉強を始める。
そこでオスカルはヌードモデルにスカウトされる。彼をモデルにして書かれた絵が評判になり、そのためにマリーアと喧嘩が起き、別居することになってしまう。
引っ越し先で彼はジャズバンドを結成し、地下の酒場である、玉ねぎ酒場で演奏することとなる。そのバンドを辞めたのち、太鼓の演奏でもってレコードを出し、多額の収入を得る。そのお金でマリーアに商店を始めさせる。
ある日、オスカルは犬を連れて散歩をしていたところ、犬が人間の薬指をくわえて持ってくる。これはのちにわかるが、オスカルが心を寄せるドロアーテ看護師のものだった。
これを見ていたヴィトラールがオスカルを警察に通報、オスカルは殺人の疑いをかけられる。オスカルは逃亡するも最終的には逮捕されてしまう。
精神病院に収容されたオスカル。30歳の誕生日に事件の真犯人が逮捕され、釈放されることとなる。
スポンサードリンク
『ブリキの太鼓』解説・考察
オスカルという特異点
世界文学全集から出版された『ブリキの太鼓』解説を担当された池澤夏樹氏が「世間」というものを描くための主人公像について語っています。
歴史を描く際に、「社会」ではなく、「世間」を描こうとするならば、平凡な主人公ではうまくいかない。「世間」を上から下まで、東から西へと縦横に走り回るような人物を用意しなければならない。
(世界文学全集『ブリキの太鼓』解説「太鼓が叩き出す幻想と現実」より引用)
まず、「世間」と「社会」がどう違うのかという点について指摘しておかなければならないでしょう。
大前提として異なるのがその指し示す範囲ということになるでしょう。
「社会」は「世間」より圧倒的に指し示す範囲が広いと言えます。
また、「社会」を描くとなるとその時代の法律や経済状況といったものがイメージとして浮かんできますが、一方で「世間」と聞くと、その当時の人間の生活や人間関係にフォーカスされるのではないかということが予見されます。
確かに戦後ドイツの「社会」を描いた作品というものは多く存在しています。
ドイツ映画にはヒトラーやアイヒマン、アウシュビッツなどを題材にした作品が数多く存在しています。
参考:ヒトラー・アイヒマン・ホロコーストに関連した映画20作品をご紹介します!
ただ、これらの大半は当時のドイツ「社会」を描いたものでしかありません。
しかし、ギュンターグラスは明らかに戦後ドイツの「世間」を描いていました。
ギュンターグラスが生み出した『ブリキの太鼓』の最大の意義は、ドイツ民衆がナチスの熱狂に飲まれていくまさにその様をその「世間」の様相を鮮烈に描き出したことにあります。
その独特な視点が戦後、戦争犯罪から目を背け、責任逃れをしようとしていたドイツ民衆に「自分たちの罪」を突きつけたのでした。
そしてそんな視点を実現するに当たって大きな役割を果たしたのがオスカルという主人公でもあります。
彼は3歳の時に自分の身体的な成長を止めてしまいます。
それは、彼が大人というものは汚らわしいものであると感じたからであり、自分はそんな汚れた存在になるまいと信じていたからなのです。
オスカルという主人公は子供であることを「免罪符」のように考え、成長を止めることで当時の大人たちを、時に上から、時に下から、時に斜めから捉えたわけです。
この子供でも大人でもないというオスカルの「特異点」こそが、戦後ドイツの罪の一端を有しながら、そこに無自覚なふりをしていたドイツ民衆の表象とも言えます。
ギュンターグラスがドイツの「世間」を描くに当たって、選択したこの主人公像が如何に革新的で、的確であったかは作品を鑑賞すれば、すぐにお分かりいただけると思います。
オスカルという主人公の魅力
依岡隆児氏がオスカルに関して興味深い点を指摘しています。
作品後半では、彼ははるかにまともで、それゆえ迷える人間となっている。・・・読者はそこにシェルム(いたずら好き)のような機能的存在ではなく、むしろ生身の人間を認め、以前よりもずっと身近なオスカル像を抱くことになる。(依岡隆児)
作品前半のオスカルは先ほども指摘した通りで、「世間」を上から、また下から特異的な立場から見るための一種の道具的、手段的な役割を果たしています。
しかし、後半になるとオスカルは、非常に人間味溢れたキャラクターへと変化していきます。
「なすべきか、なさざるべきか。」(p406~407)というオスカルの父アルフレートの葬儀の場面でのオスカルの自問自答は、物語上は彼が成長を再会するか否かというものでしょう。
しかし、オスカルが当時のドイツ民衆の姿に重なるのだとすると、それは今まで自分が距離を置いてきた、戦争やナチスへの熱狂といった目を背けてきた罪を自分のものとして受け入れるか否かという自問自答にも思えます。
そして彼は「なすべし。」という答えを出し、成長を再開しました。
子どもというペルソナを脱ぎ捨てたオスカルは読者と同じ、人生に悩む一人の個人へと変貌します。
オスカルは子供でも大人でもないという特権的立場を自ら捨て去り、何の変哲もない1人の人間としてドイツ「世間」の中に放り出されるわけです。
映画版では先ほども書きましたが、オスカルが成長の再会を決意するまでの第2部までしか描かれていません。
一方で、原作には主人公の特権的立場を追われたオスカルの物語たる第3部が描かれます。しかし、そのオスカルの人間味溢れる姿に無性に共感を覚えるのもまた事実です。
このあたりもやはりギュンターグラスという作家の巧さと言えるでしょう。
フォルカーシュレンドルフが指摘する本作の凄み
映画『ブリキの太鼓』のBlu-rayには、監督を務めたフォルカーシュレンドルフのコメンタリーが収録されています。
その中でこんな言葉がありました。
「1950年代ドイツ人たちは、自分たちはヒトラーに騙されたのだと考えていた。これは自分たちの誇りと尊厳を守るためであり、戦争の責任から逃れるためだった。そんな時代にギュンター・グラスによって出版されたこの作品には自分たちもヒトラーに魅せられ、進んでヒトラーのその情熱の中に身をささげていったのだということを描き出した点である。」
(『ブリキの太鼓』コメンタリーより引用)
シュリンクの『愛を読むひと』なんかを鑑賞してみると、戦後ドイツの民衆たちが孕んでいた空気感が伝わってくるのではないでしょうか。
参考:【ネタバレあり】『愛を読むひと』』考察:「変わる」こととその受容
当時のドイツ民衆が戦争犯罪人を裁くという行為を通じて、自らをナチズムの熱狂に自ら身を捧げていったという「罪」切り離し、正当化しようとしていた様が伺えます。
1959年に発売された『ブリキの太鼓』がそんなドイツ「世間」に衝撃を与えたことは言うまでもないでしょう。
ただギュンターグラスは晩年に自伝を発売した際に、ナチスの少年親衛隊に入隊していたことを告白したため、非難を浴びることとなりました。
このような経歴を隠しながら、どうして戦争批判をすることができたのかというのが非難の中心でした。
しかし、グラスは『ブリキの太鼓』において自らの存在を棚に上げていたというよりも、自分自身に対しても批判的であると言えるのではないでしょうか。
彼が描き出したドイツ「世間」の中には紛れもなく彼自身も含まれていたのですから。
ギュンターグラスという作家のすばらしさは、既に多くの人に指摘されている通りで、自らの存在を相対化し、自己と距離を置いた視点から客観的にドイツ「世間」というものを捉える視点を有していたことにあるのだと思います。
『ブリキの太鼓』以上に当時のドイツの街の隅々に満ちていた独特の空気感を閉じ込めた作品はないと断言できるのではないかというくらいに、当時の熱狂の渦の中にいながら、渦の外からの視点で切り取ってしまっているのです。
ギュンターグラスという作家自身がオスカルのような「特異な」性質を持っていたとも言えるのかもしれません。
スポンサードリンク
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回はギュンターグラス著(フォルカーシュレンドルフ監督)の『ブリキの太鼓』についてお話してみました。
正直本気で批評してくださいと言われれば2万字くらいはゆうに語りたいことがある作品なんですが、今回はあくまでも概要的なものだけに留めておこうと思います。
グラスの原作小説が素晴らしいことはもちろんなのですが、ニュージャーマンシネマの代表的な映画監督の1人でもあるフォルカーシュレンドルフが撮った映画版も名作です。
ぜひぜひ映画と小説、併せて鑑賞してみていただきたいと思います。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。





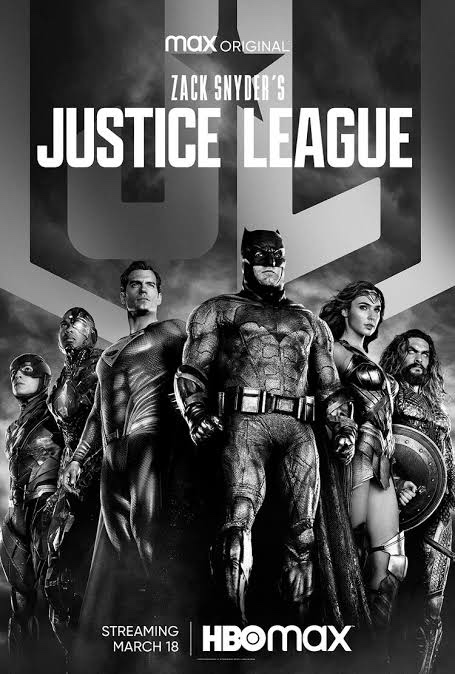





コメントを残す