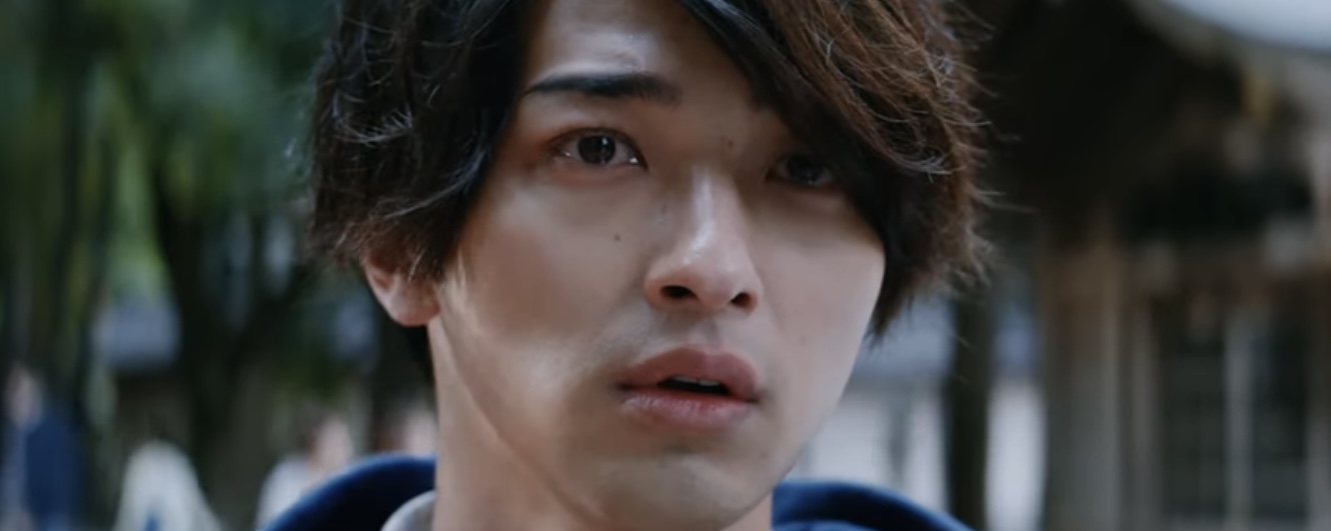みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね、いよいよ映画が公開される『去年の冬、きみと別れ』の原作本を読んでの感想や解説を書いていこうと思います。
記事の都合上ネタバレを含みますのでご了承ください。
また映画の方も鑑賞する予定ですので、映画を鑑賞した暁には映画の講評も追記しようと考えています。
映画を鑑賞してきましたので、映画に関する追記を加えています。映画の感想と解説の後に原作本の詳しい解説という順番になっております。どちらもネタバレ含みますのでご注意を。
良かったら最後までお付き合いください。
スポンサードリンク
目次
あらすじ・概要
芥川賞作家・中村文則のサスペンス小説を、「EXILE」「三代目J Soul Brothers」のパフォーマーで、「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」などで俳優としても人気の岩田剛典主演で実写映画化。婚約者との結婚を間近に控えた新進気鋭のルポライター耶雲恭介は、盲目の美女が巻き込まれた不可解な焼死事件と、容疑者の天才写真家・木原坂雄大について調べはじめる。しかし真相を追ううちに、いつしか抜け出すことのできない深みに飲み込まれていく。耶雲の婚約者・百合子役に「ピーチガール」の山本美月、事件の容疑者・木原坂役に「昼顔」の斎藤工。「犯人に告ぐ」の瀧本智行が監督を務め、「無限の住人」の大石哲也が脚本を担当。(映画comより引用)
予告編
映画『去年の冬、きみと別れ』感想・解説(ネタバレあり)
まさに映像化不可能?な叙述トリック
「映像化不可能」というキャッチフレーズはミステリー小説が映画化される時にしばしば付いてまわりますよね。まあ大抵は誇大広告で、原作を読んでみると決してそんなことは無いだろうと思ってしまうわけです。
ただこの『去年の冬、きみと別れ』という作品に関して言うならば、それは微塵も誇張ではありません。本作はそれだけ小説と言うメディア、つまり活字の持つ特性や小説の構造を利用した叙述トリックに溢れていて、これを単純に映画にはコンバートできません。
そもそも小説とメディアにおいて人は「見る」ことができません。読者に可能なのは、あくまでも文字から「イメージ」することだけです。それを逆手に取るのが叙述トリックであるわけです。読者に真実とは異なる「イメージ」を促したのちに、それをひっくり返して、あっと言わせるというわけです。
ただ小説のその仕掛けをそのまま映画に持ち込む事ができないのは自明ですよね。なぜなら映画というのは「見える」メディアだからです。「見えない」からこそ成立していたトリックは「見える」ようになると突然その効力を失っていきます。
だからこそこの『去年の冬、きみと別れ』というまさに「実写化不可能」な作品を如何にして映画に落とし込むのかに注目したいと思います。
監督を務めるのは「脳男」や「グラスホッパー」の監督としても知られる瀧本智行監督ですね。彼がこの最高の不可視叙述トリックの映像化にどう挑むのか?注目です。
こんなアプローチが残されていたのか!?主人公が岩田剛典でなければならなかった理由とは?
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
今回の映画『去年の冬、きみと別れ』はそもそも原作とは大きく異なっています。
レビューを読んでいると「騙されなかった!」という声も多く見かけますが、まあ中盤で物語の核心が提示されるのは原作も映画も同じですから。
そこが本作の本質だと勘違いしてはいけませんよ。(まあそれを宣伝文句にしているのも悪いですが)
本作の構成は映画も原作も同様で、物語の中盤までミスリードをしておいて中盤でそれを裏切り、後半でその解説を加えていくというスタイルなんです。
ただ原作には最後の最後に献辞のギミックがありましたから、最後まで驚かされるんですが、映画でそれを再現することは難しいので止む無しです。
さて、ここから原作と比べながらこの映画の素晴らしいポイントをお話していきたいのですが、まず先ほど述べたことを今一度思い返してほしいのです。
小説版では「見えない」という特性を利用して叙述トリックというギミックを作品全体に働かせていた本作ですが、それが「見える」という特性を持つ映画になった時にどうなるのか?という話でした。

結論から言うと映画版はそれを再現しなかったのです。
どういうことなのか。「見えて」しまってはこの作品は成立しないんじゃなかったのか。
確かにそうなんですが、本作はむしろ映画の特性を逆手に取って「見える」ことで成立するギミックを構築しているのです。
小説においては記述されていないことはどうしても読み取ることができません。だからこそ記述されており「見える」ことの方が疑わしく、「見えない」ものには疑いが及ばないという特性があります。
原作は、この法則を使って、編集者という存在しているはずなのに見えづらいキャラクターを設定し、そこにミステリーの核を仕込んだわけです。
一方の映画版はと言いますと、逆に一番「見える」ところにミステリーの核を仕込んだんですよね。映画において基本的に「見える」情報を観客は信用してしまうんですよね。「見える」のことで安心感があるんですよ。逆に中途半端に「見えない」人物はかえって怪しく見えるんです。
本作を見てみると、主人公の耶雲視点で物語が動いていますから、彼の行動は基本的に全て「見えて」いるんです。一方の編集者の小林やカメラマンの木原坂雄大についての映像は断片的にしか提示されず、「見えない」ために怪しいんですよ。
そういうギミックが効いているからこそ中盤で本作のミステリー部分の核が提示されるまでなかなか主人公に疑いを投げかけられなくなっているんです。
「見える」ことの安心感というと劇中の耶雲が恋人の亜希子をストーキングした理由でもあるんですよね。
別々の時間を過ごしていると彼女の「見えない」部分が膨らんでいって不安になってしまう、だからこそ彼女の全てを「見た」くてストーカー行為に及んでしまったのです。
人間というのは「見える」ことで安心感を得る生き物です。その人間の本能と映画の特性を見事に利用したのが、映画版のギミックとなっているわけです。それでいてミステリーの本筋はほとんど原作通りで、きちんと「去年の冬、きみと別れ」の映画版として成立しているわけですからこんなに素晴らしい映画版もないですよ。
そしてこのギミックを機能させるために岩田剛典というアイドル・俳優を起用する必要があったのです。イケメンで好青年であれば、演技力があれば誰でも良かったということは決してないんですね。
例えば耶雲に藤原竜也を起用したとしましょうか。彼は二枚目ですし、演技力は岩田剛典よりもはるかに高いレベルでしょう。さらにはこういう狂った役どころにもぴったりです。
ただ彼には狂う演技のイメージがついているんです。
『カイジ』であったり『デスノート』で彼が魅せた演技の印象が強いために、彼が映画に出演しているとどうしても彼が狂うビジョンが見えてしまいます。それではダメですよね。
では阿部寛なんかを起用したとしたらどうでしょうか。
彼は昨今のイケメンという感じではないですが男前で、演技力も高く、狂った役のイメージもありません。
しかし彼を使ってしまうと、後半の北村一輝との対面シーンが「テルマエロマエ」になってしまいます(笑)
顔が濃すぎて肝心のミステリーがどうでも良くなってしまうのです。
ジャニーズやアイドル俳優なら誰でも・・・とは言ってもこの難しい役を演じきれるだけの実力を持った俳優となると限られてきます。
そう考えると岩田剛典はこの難しい役を演じられる数少ない候補の1人だと思いましたし、映画を見てこの役は彼でなければいけなかったとすら思いました。
岩田剛典は基本的に「王子様」というタレント性が強い人だと思うんです。三代目JSBのメンバーとして活躍し、その爽やかなルックスを見ると納得できる肩書きではあります。さらには大ヒットした映画「植物図鑑」などのイメージが強く、優しい好青年というイメージがついています。
この岩田剛典というタレントないし俳優そのものが持っているイメージが本作を作る上で欠かせなかったと私は考えています。
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
作品の前半部分で魅せた情熱的なライターであり、彼女とも円満な優しい好青年の顔はいつもの彼が持っていたものです。だからこそ見ている我々はそれを信じてしまうのです。なぜなら違和感がないからです。イメージ通りだからです。
そして後半にそのイメージを見事に裏切ってくれます。「砂の塔」というドラマで一度本作のテイストに近い役どころを演じていたように記憶していましたが、その時の演技はまだまだ俳優を名乗れるレベルにはないと思ってしまいました。
しかし、本作『去年の冬、きみと別れ』で見せた演技は間違いなくその時のイメージを払拭してくれました。
後半の眼鏡を取り、髭を生やした彼の表情が徐々にカメラマンの木原坂雄大に近づいていくのも面白い演出でしたが、何より彼の狂った演技が作品の後半部分を一層迫力のあるものにしてくれたと思いました。
「見える」という映画の特性、「見える」ことに信用性を感じる人間の本能、岩田剛典という俳優のイメージ、それらを全て調和させることで原作にあった「見えない」ギミックが「見える」ギミックへと進化したように思います。
そして映画版のラストシーンは完ぺきだったと思います。亜希子との思い出のフラッシュバックの後に耶雲のやりきれない表情が映し出されます。
これってまさに原作にあった「僕は化物になったはずなのに・・・・・・、僕は今でも、きみが好きだ。」というセリフの再現なんですよね。化物になったはずなのに・・・なったつもりだったのに。
彼は化物になどなれなかったんです。彼はどこまでも人間だったし、心の中から亜希子を消し去ることもできなかったのです。化物になれず、復讐を果たしてもどこか満たされない空っぽの人間の表情。
原作『去年の冬、きみと別れ』では明確に描かれなかった復讐者の末路を可視化した素晴らしいラストシーンでした。
*ここから原作のネタバレを含みます。
*ここから原作のネタバレを含みます。
原作「去年の冬、きみと別れ」の叙述トリックの凄さ
原作『去年の冬、きみと別れ』のギミックとしてまずミステリー小説では定番の一人称でのミスリードが挙げられます。これは読者もかなり注意深く読み解こうとするポイントですよね。
この作品は、様々な人が著した、または撮影した手記や手紙、資料を繋ぎ合わせることで構成されています。そのため、それぞれの章で「僕」や「男」または「女」という人称名詞が指示している人物が異なるんですね。
読者はもちろんそれに注意を払うんですが、かなり曖昧に書かれているためにやはりぼんやりと「イメージ」することしかできません。するともう作者の思うつぼなんですね。読者が読み進めながら「イメージ」によって物語を作り上げていきます。もちろん真実とは正反対の方向にです。
そして終盤まで読み進めると、徐々に物語の真相が明らかになっていきます。
どうやらあの時の「僕」というのはあのキャラクターのことだったみたいだ、あの時の「女」というのはあの人物のことだったのか、と気がつかされるわけです。
読者が独善的に作り上げていく虚構の「イメージ」に真実を突きつけ、それをボロボロに崩壊させてくるわけですよ。しかも資料や手記の登場順がそれを上手くミスリードしてきます。
その一人称のギミックが最大限に発揮されるのが、本作の中盤ですね。
本作では序盤からおそらく主人公に宛てた木原坂雄大のものだろうと思わせる手紙の記述が何度か登場するんですね。もちろんこの手紙は主人公に宛てたものだろうと納得して読めば、何ら違和感なく読む事ができます。



なんと中盤で、その手紙の宛て先は主人公ではないことが明かされるんです。主人公は刑務所の面会室に会いに来ていましたが、その手紙の宛て先の人物は、木原坂雄太には会いに来ておらず、手紙だけのやり取りで、彼についての本を書きたいと言っているわけです。
小説を書こうとしている人物であり、かつてK2のメンバーであった人物。確かに主人公のことのように読む事ができるのですが、実はそうではないんですね。
本作にはこのようなミスリードが数多く登場します。今回は映画版を見た方が比較できるように原作について細かく章立てて解説してみようと思います。
<1>
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
・主人公と木原坂雄大が初めて拘置所の面会室で会った時の記述。
冒頭の記述「あなたが殺したのは間違いない。・・・・・・そうですね?」はもちろん最初に読んでいるときは、雄大に向けられたものだろうと思うのですが、終盤になるとそれが編集者の小林に向けられたもののようにも感じられます。
もう1つ重要なギミックは雄大の心の声で「なぜ?・・・・・・きみもK2のメンバーだから?」という記述がある点です。これに対して主人公は何も答えていないんですが、この一節があることは重要です。
<資料1>
・木原坂雄太から「姉」に宛てた手紙
読んでいる時点では、雄大が姉である朱里に書いたもののように読めるのですが、「姉」というのは既に別の人物ですからね。これもかなりのミスリードです。
この手紙で重要なのは、この手紙の内容が「姉」が自分が朱里であることについて語るための1つの足掛かりにもなっているように感じられる点です。
そしてもう1つ重要なのが、弁護士という存在です。
雄大には国選の弁護士ではなく、「姉」が雇った弁護士がついているんですね。
これも1つ注意しておかなければならないポイントでした。
<2>
・主人公が雄大に手紙を書こうと決めるシーン
最初読んでいるとこのシーンは普通に<1>のシーンの続きで、主人公が雄大に手紙を送ろうと決めたシーンに感じられるのですが、読み返してみるとどうも違うんですよね。
というのも手紙を書いていたのは、編集者の小林でしたからね。
つまりこのシーンというのは、<1>の続きに見せかけた巧妙なトリックです。
後に彼は手紙を1通も出せていないことを自分で明かします。
<資料2>
・雄大が主人公に宛てた手紙
ここも一見<2>で手紙を書いた主人公に対する雄大の返事という風に見えるんですが、<2>で主人公が手紙について言及しているのがミスリードで、これは雄大から小林に宛てた手紙ということになります。
ただ雄大自身はこの手紙を誰に書いているのかははっきり知らないようです。
<3>
・主人公が「姉」と初めて会うシーン
このシーンで1つ重要な記述は、「この取材には、この本を出す予定の版元、その編集者の手を借りています。彼らには、彼らのルートがある。警察とはまた別の。」という記述ですね。
あまり違和感なく読み進められてしまうのが怖い点なんですが、読み返してみるとハッとさせられる一節ですね。
またこのシーンで「姉」が雄大について多くを語らないのは、おそらく彼女が朱里について小林から聞いたものと、雄大との手紙のやり取りで知り得た情報という断片的なものしか知らないからでしょう。
また昔の写真をこの時に見せなかったのも、1つ重要なポイントでした。
<資料3>
・雄大が「姉」に宛てた手紙
このシーンで注意したいのが、「姉」は雄大にしきりに裁判のことについて聞いてくること。
そして雄大が後に姉に送ることになる写真についての記述ですね。
「そしてこの表情の奥に、姉さんの正体がある。」という描写ですが、これは雄大にとっては朱里の本性という意味だったのでしょうか。
<4>
・主人公が雄大の友人加谷に会うシーン
この章の頭に不可解に主人公の恋人(元恋人)の雪絵に関する描写があります。これに関しても後に意味が明かされる点ですね。明らかに取ってつけたような記述なのがポイントです。
このシーンではこの本に関する「ルール」が明かされるんですね。それはこの本は出版される際に登場人物を全て「仮名」で表現しますという点です。
つまり本名では表記しませんよと言うルールを示しているわけです。
さらにはこのシーンで吉本亜希子と小林百合子が殺害されたという1つの事実が提示されます。実はこの名前も重要なポイントだったんですが、意外と気がつかないものです。
本作において重要な要素である芥川龍之介の「地獄変」もここで登場します。狂った絵師が実際に自分の娘が焼け死んでいくところを描き、それが素晴らしい作品となったという小説です。
またここで主人公の口から自分がK2のメンバーであることが明かされ、読者は完全に手紙の差出人も主人公だろうと推測してしまいますね。
<資料4>
・雄大から主人公に宛てた手紙
これも主人公というのはミスリードで実際は編集者小林に宛てた手紙ですね。この資料では雄大がK2に行くようになった経緯が明かされていますね。
また、意味深なキーワードとして「もうオリジナルなんてどうでもいい領域があるような気がしてね。その領域にいる感覚はとても心地いいものだったんだ。」という一節があります。これは本作の展開を暗示するような言葉ですね。
また雄大が手紙の中で相手に対して「きみは誰かを亡くした経験があるのか?」と聞いているのが後に意味を成してくる点ですね。
<5>
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
・主人公が「姉」と2度目に会うシーン
このシーンで、雄大が「姉」に先ほどの「姉」の正体が写っているという写真を送って来たことが明らかになります。そして「姉」はその写真には自分の「本性」が写っていると発言しそれを主人公に見せようとはしません。
「本性」という言葉は面白いですね。まあこの写真には「姉」がすり替わっているという決定的事実が残っているわけですから。まさに言葉遊びですよね。
この章の最後に「姉」は「私を助けて・・・」と主人公に告げます。
<6>
・主人公が雄大と2度目の面会をするシーン
雄大が朱里のことについて語るのですが、ここで朱里に関わった2人の人物が自殺に追い込まれたという事実が明かされています。
<7>
・主人公の家に斎藤がやって来るシーン
斎藤という男はなぜか主人公の家にやって来るんですよね。
主人公はその点を不審に思うのですが、斎藤は「わかりません。」と答えます。これはもしかすると編集者小林の根回しだったのでしょうか。
<8>
・斎藤との会話
この章では斎藤という男がストーカーをした女性の人形をK2で制作してもらったことを明かしています。
そしてその実在の人物が交通事故で死亡してから、その人形が一層美しく見え始めたとも語っていますね。
さらにこのことを雄大に話したことや雄大が他人から影響されやすい人物であることを明かしています。
これが読者を雄大が殺人鬼であると納得させる1つの要因になるのですが、斎藤に小林からの根回しがあったとしたら完全にミスリードですね。
<9>
・主人公が3度目に「姉」と会うシーン
ここから物語が核心へと動き始めます。「姉」がようやく例の写真を主人公に見せるんですね。
つまり彼女は自分が朱里でないことを主人公に明かしたわけです。その上で彼女は「殺してほしい人間がいるの。」と彼に迫ります。
<資料5>
・雄大からXへと宛てた手紙
ここが物語のターニングポイントになりますね。
面会に来ていたのも、手紙を書いていたのも主人公だと思っていた読者は完全に裏切られます。面会に来ていた主人公と手紙の差出人は別人だということですね、
そして雄大はその顔の見えないXに手紙で問いかけます。「きみは誰だ?」と。
<10>
・主人公が人形師に会うシーン
ここで人形師は雄大が他人に影響されやすい人物であることや、他人の模倣を自分の欲望と捉えてしまうような人物であることを明かしています。
さらには自分がかつて自分の妻の人形を作り、彼女の死後人形が一層美しく見えるようになったという人形師の話を彼にしたことも。
ここで人形師から主人公に雄大が燃える2人の女性を撮影した写真を渡されるのですが、主人公はこの写真に一抹の違和感を抱いている様子が見て取れます。
「蝶」の写真は合成に見えるが合成ではない点が素晴らしかった。という冒頭の彼の作品への講評がここで生きてくるのは面白いギミックですね。
そしてかつて「朱里」がとある女性の人形を製作してほしいと依頼したことも明かされ、主人公はようやく事件の真相に辿りつきました。
<(11)>
・主人公が編集者と話しているシーン
ここで主人公は編集者の小林にもう本を執筆できないと告げます。
<資料6>
・謎の映像ルポ
突如挿入される謎の映像資料なんですが、これは後に意味を成すものですね。実は「男」というのは編集者の小林で、「女」というのが雄大の姉である朱里ということになります。
<資料7>
・雄大が10歳の頃の作文
家族がおらず、施設に預けられていた頃の雄大が家族に憧れたことを綴っていますね。
ここに友人の加谷の名前も登場しています。
<資料8>
・雄大が主人公に宛てた手紙
雄大は1人目の吉本亜希子の死に関して、彼女を半ば監禁したことは事実ですが、火がついたのは事故だったと釈明しています。
2人目の小林百合子に関しては彼女が「殺してくれ」と懇願してきたことを説明しています。
<資料9>
・小林百合子のTwitter・手記
これは確かに辻褄が合ってはいるんですが、完全に後付けの資料なんですよね。
真相としては、編集者の小林が仕組んで百合子に書かせたというのが正しいと思います。
つまり雄大が殺人したように見せかけるための演出ですね。「孝之さん」という名前が登場しているのが意味深です。
<資料10>
・謎の映像ルポ2
この映像資料はいわばこの事件の真相を映し出したものであるわけです。
編集者小林が百合子と結託して雄大を陥れたという恐ろしい事実がここに残されています。
先ほど登場した手記(メモ)が仕組まれたことであることも、そして燃やされたのが百合子ではなく朱里だったこと、雄大は確かに写真を撮影したが、放火には関与していないことなどが明かされています。
<資料11-1>
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
・編集者小林の過去
この資料はかつて編集者小林が1人目の被害者吉本亜希子と恋愛関係にあったことや彼女にストーカー紛いの行為をしたことなどが明かされています。
そして彼が亜希子と距離を置いた頃にあの事件が起こり、彼女は命を落とします。これが編集者小林の原動力となったわけですね。
これまで手紙の中で雄大が「きみは大切な人を亡くしたことがあるのか」としきりに問いかけていましたが、その質問を彼がはぐらかした意味がここで明かされるわけです。
さらにここで主人公が雄大の撮った、燃えている女性の写真に感じた違和感の正体が明らかになります。つまり合成写真であるということですね。
<資料11-2>
・編集者小林の過去2
ここで「姉」が後に雇うこととなる弁護士が登場するわけです。また彼は朱里に人生を壊された1人だったんですね。
そして小林が朱里を抱いた時に、彼女は自分が亜希子の誘拐に関与したことを明かしていますね。
これは小林が復讐心に燃える怪物になった瞬間でもありました。つまりこの時に彼は弁護士らと結託して雄大を陥れ、さらには彼自身に朱里を焼き殺させる計画を立て始めたのです。
さらに計画のために編集者の小林と百合子は結婚しています。苗字が同じであるという指摘は後に主人公の推理で成されます。
ここで百合子のTwitterや手記が全て仕組まれたものであったことやあの謎の映像ルポが朱里が犯されている描写であることなどが明らかになりました。
犯行の計画性や妥当性、犯行後の辻褄合わせなんかは少しご都合主義的なところはある印象ですね。
<11>
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
・主人公の推理シーン
主人公が状況を整理しつつ真相を解き明かしていきます。
ここで編集者小林と主人公の間に在ったルールがもう1つ明かされます。
それは主人公はメールで逐一取材の動向を編集者に知らせなければならないというものです。つまりこの小説において<1>といった通常のナンバリングになっているものは全て主人公から編集者あてに送られたレポートというわけです。
ここまで本作の解説を詳細に書いてみましたが、ここでもう1度言っておきたいのが、やはり本作では「不可視性」が非常に重要なんですね。まず編集者小林の存在感が薄く、見えづらいこと、これはとても重要です。
映画版をまだ見れていないので、どのように描写されているのかは不明ですが、映画版の小林はやけに存在感が強く、怪しさがプンプンとしていますね。
そして何よりこの一人称・人称名詞のトリックは登場人物の顔が見えない前提で成立しているものなんですよね。手紙の資料に関しても映画にするとなると演出に工夫がないと蛇足感が出てしまうと思います。
これだけでも本作の映像かはとても難しそうなんですよね。
『去年の冬、きみと別れ』のタイトルの意味、そして本作が「実写化不可能」な最大の理由について
この作品のタイトルの意味は小説内でも明かされていますが、編集者の小林が去年の冬に朱里を抱いた時のことを指していますね。彼は、自分の恋人を、愛した人を陥れた女性と寝たわけです。
この時に彼は化物になろうと決意したと話しています。
つまりは復讐心に燃え、雄大と朱里をあまりにも残酷すぎる方法で陥れてしまう怪物になると決めたわけです。
そして亜希子のような純粋で美しい女性の傍にいる人間が化物であってはならないからと、彼はその時にようやく彼女との決別が出来たわけです。
ただその後に「僕は化物になったはずなのに・・・・・・、僕は今でも、きみが好きだ。」と小林は述べているんですね。
この意味を考えた時に、小林は化物になどなってはいなかったんだと思うんです。この作品では狂った人形師のエピソードや芥川龍之介など、化物になったような芸術家が登場しています。
しかし彼らは本当に化物だったのでしょうか。それは違うと思うんです。彼らも、そして化物になろうとした小林も人間だったんですよ。そして姉が燃えるさまを見ながらシャッターをきり続けた雄大も人間なんです。
本作が示したのは、どんな人間も何かの拍子に狂ってしまうという人間の正常と狂気の表裏一体性だと思うんです。人間は化物になどなることもなく、あくまでも人間として静かに狂っていくんです。それは人間が後天的に獲得するものでは無く、むしろ先天的に備わっていたものの表出という形でだと思うんです。
「真の欲望は隠される。」
まさにこの言葉通りで、人間の真の欲望、つまり本能というものは常に隠されているんです。ただそれは隠されているだけで、確かに全ての人間の中に備わっています。何かのトリガーが「蝶」を取り払い、そして人間の本能を呼び覚ますのです。
本作のタイトルは小林という1人の男が狂い始めた瞬間を表しているわけですが、まさに彼の中から「蝶」が飛び立ち、彼の剥き出しの欲望が表出した瞬間だったのでしょうね。
人間は人間として音もなく狂っていく。化物よりもよっぽど人間の方が恐ろしいですね。
そして最後に本作が実写化不可能である最大の理由ですが、それは本作のメタ構造性にあるんですね。というのもこの小説は、小説それ自体が作品の中に組み込まれているというギミックがあるわけです。
冒頭に献辞で「M・Mへ そしてJ・Iに捧ぐ」とあるんですが、これは本作の終盤でも明かされるように編集者の小林がつけたものです。
つまりこの『去年の冬、きみと別れ』という小説そのものが小林が作成したものということなんです。
M・Mは憎悪の表れ、つまり木原坂雄大のこと、J・Iは愛情の表れ、つまり吉本亜希子のことを指示しているわけです。ただイニシャルが一致しませんよね?
そこで本作の作品内ルールを思い出して見て欲しいのです。「登場人物は全て仮名で登場させます。」というものですね。つまり本作の登場人物というのは全員本名ではないんですよ。
M・MとJ・Iという2人のイニシャルは仮名ではなく、本名のイニシャルであるということになりますね。
このメタ構造があまりにも見事すぎて小説を読んでいるとハッとさせられるのですが、このギミックをどうやって映画で再現するのかが個人的には気になるところですね。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『去年の冬、きみと別れ』について原作と映画の両面からお話してきました。
個人的には小説の段階では完全に騙されました。ただそれに関しては活字メディアの持つ不可視性がすごく重要だったと思うんですね。
ですので、映画になった時にその不可視性のベールが無くなり、本作の持つギミックやトリックが維持できるのかと言うところにすごく疑問を感じます。まあ見てみないことには何とも言えませんが。
原作との比較ということで、その点に着目しながら鑑賞したいと思います。
原作にはいない山本みつき演じる主人公の婚約者の役どころも気になりますね。もしかして映画はオリジナルストーリーなんでしょうか?
(C)2018映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会 映画「去年の冬、きみと別れ」予告編より引用
今回も読んでくださった方ありがとうございました。
参考記事
同じく実写化が難しかったであろう『愚行録』についてもブログを書いてみました。良かったら読んでみてください。
本作の脚本を担当した大石さんが同じく脚本を担当されたミステリー映画『スマホを落としただけなのに』の記事はこちらから