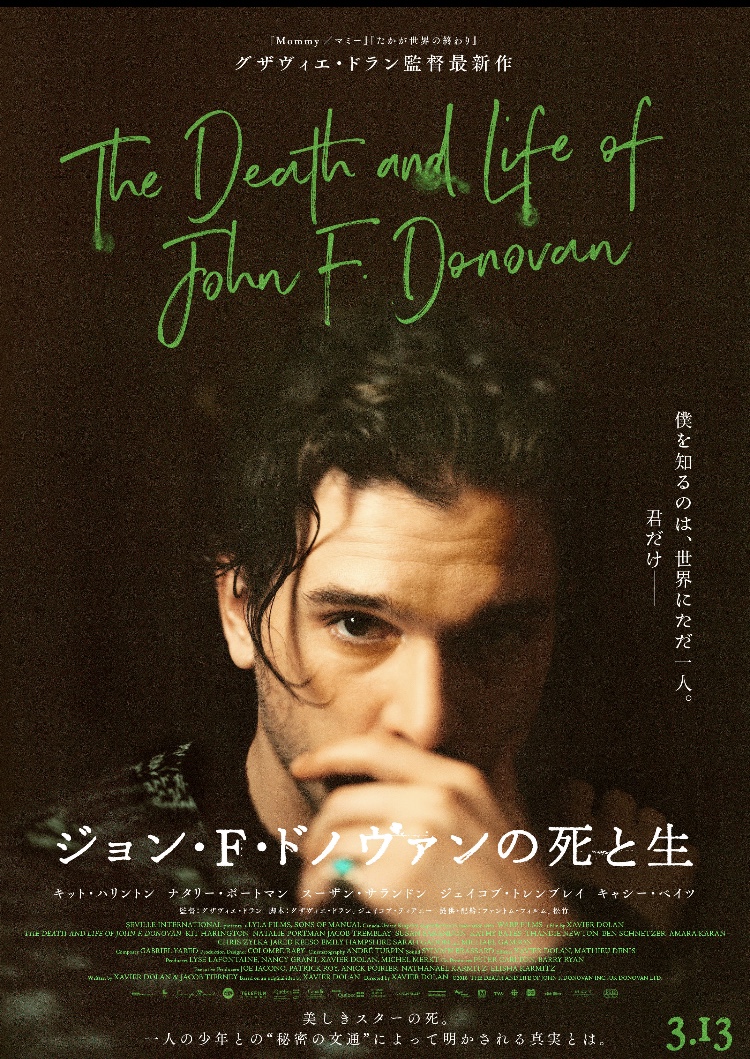みなさんあけましておめでとうございます。
映画ブログ「ナガの映画の果てまで」管理人のナガと申します。

2022年最初の記事で扱うのは、アダム・マッケイ監督の新作『ドントルックアップ』です。
本作は、2021年12月からNetflixで配信されている風刺コメディ映画となっており、レオナルドディカプリオやジェニファーローレンスが出演していることでも注目を集めています。







まず、主人公にあたるのが、天文学者のランドール・ミンディ教授です。
彼はある日、教え子の大学院生ケイトが発見した彗星を調査しているときに、ある恐ろしい事実に気づきます。
それは、その彗星が地球に衝突し、地球に壊滅的な打撃を与える恐れがあるということ。
2人は、巨大彗星により地球に迫りくる危機を、世界中の人々に何とかして伝えようと行動を起こすのですが…。







日本で2016年に話題になった『シンゴジラ』という作品がありますが、同作はポリティカルドラマの側面を持っており、ゴジラ上陸に際しての政治家や専門家たちの水面下での攻防にスポットを当てました。
『シンゴジラ』では、政治家や専門家がかなり優秀で、冷静な状況判断ができる人間というテイストで描かれていた印象を受けませんでしたか?
ただ、『ドントルックアップ』では、登場人物全員「バカ」と言っても過言ではないくらいに、ぶっ飛んだ奴しか出てこないのです。
例えば、ランドール・ミンディ教授から彗星に関する第一声を聴いたアメリカ合衆国大統領の反応はどんなものだったと想像しますか?
彼女は、彗星による危機を解決することよりも、目前に迫った大統領選挙に向けて自分の支持率を高めることを優先し、「静観」という決断を下すのです。
本来なら、こんな浮世離れした大統領の存在を笑って、「現実はそんなんじゃねぇよ!」と言ってやりたいじゃないですか?
でも、そもそもアメリカにしても、日本にしても現実世界の政治があまりにも「浮世離れ」していて、これが「リアルじゃない」と切り捨てられないんですよね(笑)
そのため、本来は「笑えるコメディ映画」であるべきはずの作品が、「笑ってはいけない映画」になっているわけです。
この、複雑な感情を体験していくためにも、『ドントルックアップ』はぜひとも見ていただきたい1本だと思います。
アメリカの政治シーンを風刺した作品ではありますが、決して日本に生きる私たちにとっても他人事ではない内容です。
ここからはそんな『ドントルックアップ』について個人的に感じたことや考えたことをお話していきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ドントルックアップ』解説・考察(ネタバレ)
虚構が現実を凌駕する国、アメリカ
本作『ドントルックアップ』は、アメリカという国を通底する現実と虚構のコンテクストに基づいて作られた作品の1つと言えるでしょう。
その代表格として『キングオブコメディ』なんかが挙げられると思いますが、これらの作品は、虚構が現実よりも「リアリティ」を持つアメリカという国を表現しています。
こうした作品を紐解くにあたっては、カート・アンダーセン著の『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』を読むのがおすすめです。
この書籍の中では、国の成り立ちまで遡って、現代に至るまでのアメリカで虚構が現実を凌駕してきた歴史が綴られています。







世界史の教科書では、イギリスからの移民が未開のアメリカ大陸を開拓し、国を作り上げていっただとか、最初は13の州から成る国だったとか、その後イギリスと独立戦争をしたといった歴史が綴られています。
では、そもそもどんな人々がイギリスからアメリカ大陸へと渡ったのでしょうか。
実は、この時アメリカ大陸へと渡ったのは、主にプロテスタントたちだったと言われています。
そもそもプロテスタントは、16世紀に起こった宗教改革をきっかけに生まれ、16世紀に入るとイギリス内にも持ち込まれました。
そして、これがピューリタンと呼ばれる呼ばれる人たちを形成していくことになったんですね。
とは言え、ピューリタンは当時イギリスで主流だったイングランド正教会からの分離派であり、マジョリティから見れば「異端者」に当たります。
そのため、イギリス本土ではピューリタンたちは虐げられることになり、それが原因で苦境にある自分たちの救いを新大陸、つまりアメリカ大陸に求めたんですね。
こうしてピューリタンたちはアメリカ大陸を「神の国」であると信じるようになります。
そこにどんな運命が待ち受けており、例え現実が幻想と異なるものであったとしても、それを無視して幻想を正当化し、やがては幻想を現実とすり替え始めたわけです。
もちろん新大陸が「黄金郷」や「ユートピア」であるなんてことは幻想にすぎず、移民したピューリタンたちは次々に餓死していきました。
しかし、そうした現実は黙殺され、イギリス本国には依然として「金や銀の採掘される黄金郷」という幻想が流れ続け、移民するピューリタンが後を絶たなかったと言います。
『ドントルックアップ』の、アメリカ大統領たちがファンタジーランドに迷い込んで、悲惨な運命を辿るという結末は、こうした建国の経緯に対するアイロニーではないかと思われます。
地球で受難した自分たちは、長い旅路の果てに、どこか新しい「神の国=新大陸」で救われるはずだという漠然とした希望を抱いて旅に出た彼らが「ピルグリムファーザーズ」を想起させるのです。
そうして彼らが辿り着いたのは、これでもかというほどに虚構性が際立たされた新世界でしたが、そこに待ち受けていたのは救済とは程遠い現実でした。
現実から目を逸らし、虚構を信奉し続けた人間が辿る末路とも言えるラストシーンを、建国の経緯に準えることで、最上級の皮肉に仕立て上げてきたのは、とんでもない切れ味でしたね。
人間は自分が信じるものを変えられない?
『ドントルックアップ』において興味深いのは、彗星が落ちてきているという事実が明らかになってからのアメリカ国民の受け止め方ではないでしょうか。
劇中では、彗星に対して「空を見ろ!」とその危機に直面することを求める人たちと、「空を見るな!」と危機を陰謀論だと断定するような人たちに分かれ、国内でも激しい分断が生じました。
特に注目したいのは、彗星が目視できる状態になっているにも関わらず、「空を見るな!」と彗星による地球の危機から目を背け、陰謀論だと冷笑する後者の人たちです。
彼らは科学者が彗星による現実的な危機を発信したところで、それを真に受けず、自分たちが信じている「虚構」を信じ続けているんですね。
また、彼らと同じ穴の狢だったのが、ピーター・イッシャーウェルでして、彼は周囲の科学者たちがドローンによる彗星の解体計画に無理があることを指摘しても決して自分の考えを曲げることはありません。
彼はアルゴリズムを盾に、論点をずらし、相手の反論を全く聞き入れようともしないんですよね。
これについても、先ほど引用した『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』の中で興味深い言説が取り上げられています。
権威ある専門家が何と言おうと、自分たち一人にこそ、何が真実であり何が真実でないかを決める権利があると考えるようになった。それどころか、情熱的で空想的な信念が何につけても重要なのだと思い込むようになった。
(カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』より)
『ドントルックアップ』の中で起きているのは、まさにこの現象なんですよね。
彼らは一度自分が信じたものについては、それが「現実」であろうと「虚構」であろうと関係なく、それを信じ続けます。
科学者や専門家が何と言おうと、自分が信じたものが真実なのであり、それ以上でもそれ以下でもないというのが、アメリカの国民性だと言っているわけです。
また、フランシス・ベーコンはアメリカ建国当時の植民活動ないしピューリタンたちの行動を次のように評していたそうです。
人間の知性は、いったんある意見を採用すると(一般に受け入れられている意見であれ、自分が賛同できる意見であれ)、ほかのあらゆるものを引っ張り出して、その意見を擁護するようになる。それを否定する重要な事例がいくつも見つかったとしても、それを無視・嫌悪するか、何らかの違いを持ち出して除外・拒絶する。
(カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』より)
ピーター・イッシャーウェルの言動がまさにそうで、彼は科学者であるランドール・ミンディ教授に理論的な指摘を受けたとしても、そこから目を背け、自らの信奉するアルゴリズムで自分の計画を正当化しました。
幻想を信じることに加えて、一たび信じたものが幻想だと分かっても、論点をすり替えてそれを正当化しようとするという建国来のある種のアメリカ人の国民性のようなものを『ドントルックアップ』は見事なまでに描き切っています。
サーカス化する政治と虚構
『ドントルックアップ』の中盤で、ジャニー・オルレアン大統領が宇宙から飛来する彗星に対応するために大規模な作戦の開始を宣言します。
この時の演説が『インディペンデンスデイ』を思わせるようなシチュエーションになっていましたし、そのセリフの中で『プライベートライアン』の劇中のセリフが引用されていました。
また、無人による制御が可能と分かっていながら、「ヒーローが必要である」という単純な理由で政敵をシャトルに乗せて宇宙に送り込むという描写がありましたが、これも彗星への対応を「サーカス」あるいは「ショー」にしようとするアメリカらしさを感じさせます。
こうした一連の描写を「フィクションの世界の話でしょ!」と笑い飛ばしてしまいたくなるのですが、これがあながちフィクションとも言えないので、絶妙に笑えないんですよ。
かつて大統領を務めていたレーガンはアメリカ政治の「サーカス化」のきっかけになった人物であると言われています。
レーガン政権下でホワイトハウスの首席報道官をと務めていたパット・ブキャナン氏がレーガン大統領のことを評してこんな発言を残したんだそうです。
ロナルド・レーガンにとっては、伝説や神話の世界こそが現実だ。彼はそこを定期的に訪れ、楽しい時間を過ごす。
(カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』より)
そもそもレーガンは、過去にアナウンサー、俳優、州知事、そして大統領という異色の経歴の持ち主で、それ故に映画界でのキャリアを政治シーンに持ち込んだと言われています。
例えば、彼は議会に対して増税を可決しないよう警告する際に『ダーティハリー4』のクリントイーストウッドのセリフである「さあ、オレを喜ばせてくれよ。」をそのまま引用したそうです。
また、1985年のトランス・ワールド航空847便ハイジャック事件に際しては、人質解放交渉終了後に「昨晩、『ランボー』を観たよ。そのおかげで、また同じことが起きたときにどう対処すればいいのかわかった。」と発言したと言います。
他にも『スターウォーズ』が大好きだった彼は、ソ連のことを「悪の帝国」と呼称したなんてエピソードもあり、いかに政治の世界に虚構を持ち込んでいたかが浮き彫りになってきます。
こうしたレーガンの言動がきっかけとなり、アメリカの政治に虚構が入りこむようになり、「サーカス化」が進行していきました。
『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』では、ビル・クリントン大統領が、指名された直後にトークショーでレイバンのサングラスをかけて「ハートブレイクホテル」を演奏したことが、大統領選挙が「最高のエンターテイナー決定戦」に変える決定的な出来事だったと綴られています。
少し映画から話題が逸れてしまいましたが、『ドントルックアップ』はこうした「サーカス化」してしまったアメリカの政治シーンに対する痛烈な皮肉なんですよね。
本来、国を守るために最善を尽くさなければならない政府の人間が、自分たちを良く見せるための「エンターテインメント」を作り上げることに終始しており、もはやまともに機能していません。
また、『ドントルックアップ』は体制批判派もまた、こうした構造を作り上げる片棒を担いでいることを示唆していました。
ランドール・ミンディ教授ら反対派も、歌手を取り込み、自分たちのメッセージを歌に載せるというエンタメ化をしており、ハリウッド映画界も地球滅亡をフィクションにした映画を呑気に作っています。
つまり、体制側もそれを批判する側も、どちらもが「サーカス化」されてしまっており、誰も本質を見ていないわけですよ。
これがフィクションではなく、現実なのですから、もう笑えなくなってきます。
ユールが体現した真の祈りと物語のフィナーレ
そして、クライマックスに近づくにつれて、地球は滅亡へと近づいていくわけですが、ここで作品にはユールという重要なキャラクターが登場します。
彼はニヒリズムに裏打ちされたように退廃的な生活を送っている若者で、「空を見上げろ!」と言っている人たちも、また「空を見るな!」と言っている人たちも、そのどちらもを信じていないのです。
彼にとっては何も信じられるものはないわけで、だからこそ地球の滅亡に際しても特に変わらない生活を送っています。
だからこそ信じる・信じないの闘争に明け暮れた大学院生のケイトにとっては、その闘いから最初から身を引いている彼のような存在が新鮮で、惹かれたのではないでしょうか。
アメリカでは、しばしば宗教が政治シーンに持ち込まれ、それが対立を煽る道具にされることも珍しくありません。
もちろん合衆国憲法では政教分離がきちんと定められているのですが、近年の選挙では「宗教票」や「福音派かどうか」といった要素が大きな影響力を持つようになりました。
とりわけドナルド・トランプ前大統領政権を支えていたのは、キリスト教福音派と呼ばれる人たちの強固な支持基盤です。
宗教や信仰というものは、本来祈りをささげることで、自分自身の心の寄りどころにし、心に救いと平穏をもたらす極めて純粋なものであるはずですよね。
しかし、近年のアメリカにおいて宗教や信仰は、政治的なイデオロギーと密接に関わり合い、そうした本来の意味を見失いつつあります。
だからこそ、アダム・マッケイ監督はユールというキャラクターを通じて、宗教や信仰の本来の意味をキャラクターたちに取り戻させようと試みるのです。
政治的な対立、宗教的な対立を乗り越えて、人と人が手を取り合い、たった一つのこと、つまり神に祈りをささげるという本作で最も印象的なシーンは作品に込められた祈りと言っても過言ではないでしょう。
『ドントルックアップ』が、その目まぐるしく移り変わる強烈な風刺劇の最後に穏やかな祈りを描いたのは、それこそがアダム・マッケイ監督の信じる私たちの「あるべき姿」だからなのです。
政治も宗教は対立を煽るための、分断を助長するための道具などでは決してありません。
作品の冒頭に、ケイトは大統領に対して、「私はあなたの支持者ではないけれども、この件についてはあなたを全面的に支持します」と発言していました。
この言葉ないし考え方が、私たちが環境問題をはじめとする未曽有の地球規模の危機に立ち向かうために必要なことなのだと思います。
政治的な考え方の違い、宗教的な思想の違いはもちろんありますし、それは自然なことです。
しかし、私たちは地球規模の大きな課題に際して、そうした違いを乗り越えて、手を取り合い、1つになる必要がなるのです。
風刺に満ちた作品のフィナーレに込められた、そのピュアなメッセージに思わず、心を打たれました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ドントルックアップ』についてお話してきました。







『バイス』でも強烈な政治風刺を展開したアダム・マッケイ監督ですが、今回の『ドントルックアップ』はより一層磨きがかかっていたように感じます。
描写の1つ1つがあまりにも馬鹿馬鹿しくて、こんな人いないだろ!と言いたくなるんですが、そう言えない現実が目の前に広がっているからこそ、複雑な気持ちになりました。
しかし、そうした政治風刺とは裏腹に、本作が打ち出したメッセージは極めてシンプルでピュアなものだと最後まで見れば気がつかされるはずです。
政治や宗教が対立や分断を生み出すための道具になっている現状。しかし、私たちの世界にはそれを超えて、解決していかなければならない問題が山積みなんですよね。
この作品はアメリカを舞台にしており、アメリカの政治を風刺したものですが、日本に生きる私たちにとっても決して他人事ではありません。







今回も読んでくださった方、ありがとうございました。