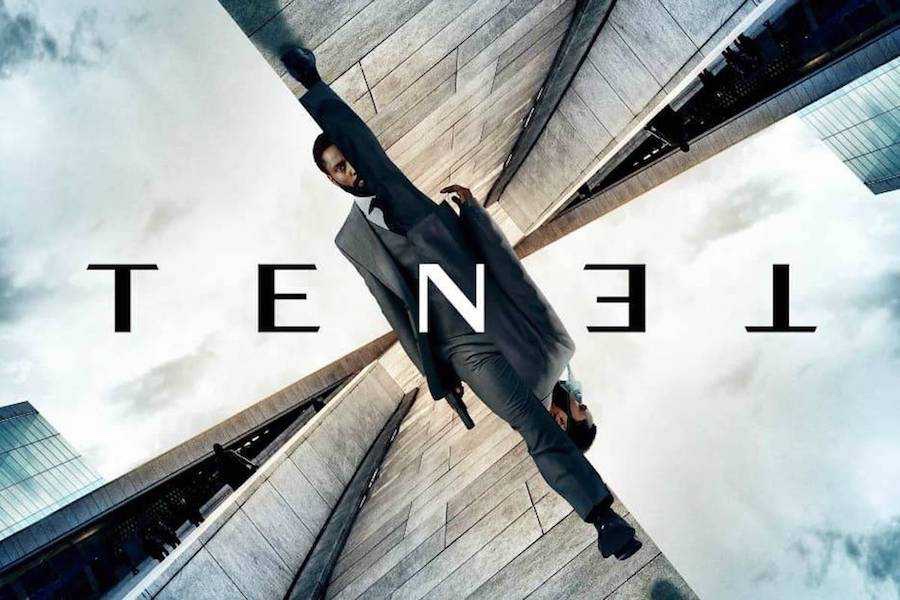(C)2018 Twentieth Century Fox
目次
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『女王陛下のお気に入り』についてお話していこうと思います。
アカデミー賞にも多数ノミネートとういうことで注目の作品です。
参考:第91回アカデミー賞(2019)を予想!当ブログ管理人の願望も交えて徹底解説!
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『女王陛下のお気に入り』
あらすじ:一応史実通りなの?
さて、アン女王が登場するイングランドの物語ということですから、世界史を勉強してきた人にとっては聞いたことのある名前や戦争、事件が登場するだけでワクワクしますよね。
『女王陛下のお気に入り』という映画は、アン女王治世の1700年代初頭のイングランドを舞台にした作品です。
そして本作にアン女王の側近として登場したサラとアビゲイルの2人も実在していた人物と言われています。
物語はアビゲイルがアン女王の暮らす屋敷へとやって来るところから始まります。
彼女は、自分の父親が不倫相手の女と共に去ってしまったことで貴族の娘という地位から没落し、ドイツ人の男の「手込め」にされていました。
ある時、彼女が親族のつてを辿って、女王の屋敷の女侍として働くこととなりました。
しかし、そこで待っていたのは、過酷な労働環境であり、同僚から目をつけられた彼女は過酷な仕事を押し付けられるようになります。
そんなある日、アン女王は足に通風を発症して、炎症を起こし、痛みで眠れぬ夜を過ごします。
それを好機と見たアビゲイルは森の中で痛風に効く薬草を拾い集め、それを調合した塗り薬を女王の足に塗ります。
しかし、サラにその姿を見られてしまい、むち打ちの刑に処されてしまいます。
ただ、その薬草の効果は抜群で、功績が認められたアビゲイルはサラの側近として働くこととなりました。
それは長い長い女同士の権力闘争のほんの序章に過ぎませんでした・・・。

- 1701年:スペイン継承戦争勃発
- 1704年:ブレンハイムの戦いでマールバラ公が戦果を挙げ、公爵の地位を与えられる
- 1705年~:側近のサラに不満をいだくようになり、徐々にアビゲイルを重用するようになる
- 1710年:サラを宮廷から追放し、和平推進派のトーリー党を政権に指名する
- 1713年:ユトレヒト条約が結ばれ、スペイン継承戦争が終結に向かう



















まず『女王陛下のお気に入り』という作品の背後にあるのは、当然スペイン継承戦争ですね。
これがイングランド国内の疲弊を招いているという時代背景が透けて見えるようになっています。
一方で当時政権を握っていたホイッグ党は、1704年にフランス相手に大勝を収めたマールバラ公爵を司令官に据えて、フランスを叩こうとしています。
議会では和平派のトーリ党が政権を争っていますが、サラの傀儡であるアン女王は、唆されるままに戦争の継続へと傾倒しています。
そこに現れたのが、アビゲイルだったわけで、彼女がトーリ党の方を持ったことで、イギリスの政治は大きく舵を切っていくことになるのでした。
他にもアン女王が「17人」の子供を亡くしているというのも一応は史実として残っているものですし、基本的には史実に忠実に作られている印象です。



















このあたりの時代考証が意外と適当だったりするのもユーモアがあって面白かったですね。
スタッフ・キャスト
監督:ヨルゴス・ランティモス
脚本:デボラ・デイビス&トニー・マクナマラ



















『ロブスター』や『聖なる鹿殺し』で知られるヨルゴス・ランティモス監督の新作が公開されました。
とにかく独特で、不可解な物語と生理的な嫌悪感を感じる映像が絶妙にマッチしている作品を生み出している、まさに唯一無二の映画監督です。
これまでの2作品は日本ではどちらもミニシアター上映扱いだったので、まだまだ知名度的には高くないとは思いますが、今後もっと注目されていく映画監督でしょうね。
ちなみに今年度のアカデミー賞では、作品賞と監督賞にノミネートされております。
また、アカデミー賞脚本賞にもノミネートされている本作の脚本を担当したのは、デボラ・デイビス&トニー・マクナマラです。
ちなみにデボラ・デイビスは女王陛下の原作となる舞台の脚本も担当していた人物です。



















- 撮影賞ノミネート:ロビー・ライアン
- 衣装デザイン賞ノミネート:サンディ・パウエル
- 美術賞ノミネート:フィオナ・クロンビー



















後で解説する予定ですが、もうとにかくこの『女王陛下のお気に入り』は映像が素晴らしいので、絶対に見て欲しいところですね。
最後にキャストについてです。
- オリビア・コールマン:アン女王
- エマ・ストーン:アビゲイル・ヒル
- レイチェル・ワイズ:レディ・サラ(サラ・チャーチル)



















いやはや全員とんでもない演技でしたね。
個人的には『ララランド』の時のエマ・ストーンがいまいちピンと来ていなかったので、今作の彼女はホントに素晴らしかったですね。
何というか悪女の役の方が似合っているような気がしましたね(笑)



















とにかくこの3人の女性キャストは全員迫真の演技でした。
より詳しい作品情報を知りたい方は映画公式サイトをご参照ください!!
スポンサードリンク
『女王陛下のお気に入り』解説
圧倒的すぎる映像が衝撃的
『女王陛下のお気に入り』という作品は、プロットそのものはよくある宮廷階級闘争でして、それをヨルゴス・ランティモス監督風味のブラックコメディとして味付けした感じです。
では、何が素晴らしいのかと言われると、それは圧倒的に映像的な部分だと思うんですよ。



















そこには本年度のアカデミー賞の撮影賞にノミネートしたロビー・ライアンがかけた魔法が関係しています。
まずはこのシーンをご覧ください。
(C)2018 Twentieth Century Fox



















このシーンに関して、撮影監督のロビーライアンは6ミリの魚眼レンズを採用したと明言しています。
だからこそ映像に独特の「歪み」が生じていて、それが本作のテーマでもある権力闘争の中で生じる人間の「歪み」を表現することに寄与しています。
そしてもう1つロビーライアンが本作の撮影において用いたと明言しているのが10ミリの広角レンズですね。
広角レンズの特徴ってまさしく被写界深度なんですよね。
本作の冒頭のシーンを引用してみますね。
(C)2018 Twentieth Century Fox



















映画って平面のスクリーンに投影するという兼ね合いもあって、全体的にのっぺりと平面的に見えてしまうことが多いんですよね。
だからこそ3Dという技術が登場し、映画の臨場感やライブ感を高めるための飛び道具として活躍することとなっています。
しかし『女王陛下のお気に入り』という作品に関しては、映像がすごく立体的と言うか、奥に「深さ」があるように感じられて、見ている我々が飲み込まれてしまうかのような吸引力があります。
ファーストシーンでも4人の並んで立っている人物が縦軸で見た時の位置関係の差異が明確になっていますし、その背後に広がる空間の「広さ」をリアルに伝わって来ます。
ぜひぜひこの作品を映画館で見る際は、ロビーライアンが用いた6ミリの魚眼レンズと10ミリの広角レンズによる映像の魔法に着目してみてください。
映像が作り出した物語の円環構造
では、ここからは『女王陛下のお気に入り』の映像によるストーリーテーリングの巧さについて解説していこうと思います。
私が圧倒的に巧いと感じたのは、ヨルゴス・ランティモス監督がこの作品を1つのループとして描いて見せた点なんですよ。
皆さんは劇中でのサラとアビゲイルが対の関係になり、一方は成り上がり、一方は没落していくという描かれ方をしていたことに気がつきましたでしょうか。
では2人が辿った時系列を整理していきます。
・アビゲイル
- 父親が蒸発し、貴族の地位から没落した。
- その後ドイツ人の男の下で「手込め」にされてしまう。
- サラの従妹の好で、アン女王の屋敷で侍女として働くこととなる。
- 馬車で屋敷に向かう途中で馬車から落とされ、臭い土塗れとなる。
- 働き始めるも同僚からの嫌がらせに遭い、灰汁(毒)を素手で触らされ、手が炎症を起こしてしまう。
- その後、アン女王に気に入られ、重用されるようになる。
- アン女王の車椅子を押し、そして肉体関係を持つようにもなる。
・サラ
- アン女王の側近として重用されており、車椅子を押したり、政治をおこなったり、夜な夜な肉体関係を持ったりしている。
- 徐々にアビゲイルにその特権的な立場を脅かされるようになる。
- アビゲイルから紅茶に毒を盛られ、発作を起こしてしまう。
- 毒を盛られたことで、気を失い、馬から落馬し、引きずられる。
- 売春宿にて療養する羽目になり、「手込め」にされそうになる。
- アン女王から見放されてしまい、屋敷から追放されることとなる。



















アビゲイルとサラが経験していることって映像を追い続けていれば分かるんですが、基本的に同じことなんですよね。
ただベクトルが逆方向を向いていて、アビゲイルは下から上へ、サラは上から下へと自身の立場が変化していっています。
このように映像的にアビゲイルとサラが経験することをリンクさせ、成功と没落が1つの円環構造を形成するかのように物語として組み上げられている点が何とも見事だと思いました。
そしてその円環構造が形成されたことで、この類の愚かな権力闘争は繰り返すものであり、1700年代初頭と変わらずに今の世界にも脈々と続いているのだということが示されます。
だからこそアビゲイルは自身が成り上がることに成功したにも関わらず、自分がサラを失脚させたように自らもまた、誰かに蹴落とされる運命なのかもしれないと不安を隠しきれていないのです。
サンディ・パウエルの素晴らしい衣装
(C)2018 Twentieth Century Fox
第91回アカデミー賞に衣装デザイン賞でノミネートされていたサンディ・パウエル。もう衣装デザイン賞には毎年ノミネートしている常連になっています。
ちなみに彼女は今年アニメ空間に実写のキャラクターを融合させた『メリーポピンズリターンズ』の衣装でも同賞にノミネートされています。
さて、ここから映画『女王陛下のお気に入り』における衣装デザインの魅力についてお話していこうと思うのですが、まず何と言っても素晴らしいのは、ヨルゴス・ランティモス監督の世界観を衣装で表現しているところです。
彼の映画の世界観は、これまでの作品を見ていても分かる通りで、基本的に映像がモノトーン調なんですね。それでいて衣装は基本的に簡素でシンプルなものになっていました。



















17世紀イギリスの宮廷絵画やアン女王の肖像画なんかを見ても分かると思うんですが、当時のイギリスの貴族の服装ってあんなにモノトーンではないんですよ。
これに関してサンディ・パウエルも、本作の衣装デザインは史実を忠実に再現するためのものではないことを明確にしています。
あくまでも史実を参考として取り入れつつ、ヨルゴス・ランティモス監督が追求するモノトーンな映像世界と史実のバランスを実現したのが今作の衣装デザインであるということです。
また、ドレスの形状もバリエーションが豊富というよりも、作中のドレスはほとんどが似たような形状で、奇をてらうものはありません。そのシンプルで洗練された様もヨルゴス作品らしさになっています。
その他にもキッチンの使用人の服装なんかを見てみると、これも映像映えを意識してはいるんですが、史実を反映させた点も見られます。
当時のイギリスの使用人ってデニム生地の服装を着ていたと言われているんですが、本作『女王陛下のお気に入り』におけるキッチン等で働く使用人の衣装にもコルセットやベストにデニム生地が使われています。
史実を取り込みつつも、監督の世界観や映像映えを意識した絶妙なバランスを実現できたからこそ本作の衣装デザインはアカデミー賞でも評価されたんですよね。
巧みな映像演出
先ほど映像が物語に関連して円環構造的に構成されていることの素晴らしさについて語りましたが、ここからはもう少し点で、この作品の映像の魅力を捉えていこうと思います。



















(C)2018 Twentieth Century Fox
これは、サラとアン女王の関係性を最も象徴しているシーンと言っても過言ではありませんよね。
確かに衣類や装飾品を外すという日常的な業務の中で行われている作業の一環ではあるんですが、わざわざ王冠を取り外しているシーンにクローズアップするのは実に確信犯的ですよね。
当時のイングランドにおいて実際に実権を握っているのは、この私なのだと言わんばかりに女王から王冠を取り外しているのです。



















(C)2018 Twentieth Century Fox
サラとアン女王の情事を垣間見てしまうシーンというのは、いわばアビゲイルの台頭とサラの衰退へと物語が舵を切っていく潮目に当たる部分です。
このシーンに至るまでは基本的にサラが身分的にも立場的にもアビゲイルより上という事実は明確でした。
では、それを踏まえてこのシーンについて考えていきましょう。
この時、アビゲイルは部屋の上から2人の営みを見ているんです。つまりアビゲイルの立っている位置というのが、サラやアン女王よりも上なんですよ。
これまではサラがアビゲイルを見下す立場ではありましたが、ここからそれが変わっていくのではないかということを2人の立ち位置がぼんやりと浮かび上がらせています。
最後に車椅子を押していくシーンですね。
(C)2018 Twentieth Century Fox
「車椅子を押す」という行為は、つまり女王を操り、政治と経済の実権を握るということを意味しているようにも感じられます。
だからこそ物語序盤では、その役目を任されているのはあくまでもサラであり、それが物語後半に差しかかるにつれて、アビゲイルに変わっていくという演出が生きていくるところですけどね。
いやはやヨルゴス・ランティモス監督の映像の素晴らしさにさらに磨きがかかった印象を受けました。
スポンサードリンク
『女王陛下のお気に入り』考察
なぜ「足」がキーワードだったのか?
(C)2018 Twentieth Century Fox
本作を見ていると、しきりにアン女王が「足を揉んで」と発言したり、彼女の足が痛風になったことがアビゲイルの出世のきっかけだったりしていますよね。
また、彼女が屋敷の中を足を使わずに車椅子や神輿を使って移動していたシーンも散見されました。
では、足とは何を意味していたのか?ズバリそれは、サラとアビゲイルの2人のことです。
アン女王は史実でもブランデーを飲みすぎていて、肥満体形で1人では歩けなくなっていたとも言われていますが、それをこの作品は巧く映画に落とし込んでいます。
つまり彼女はサラとアビゲイルという「両足」がないとまともに立っていることがもはや出来なくなっていたのです。
まあ2人がずっと彼女の傍にいてくれていたならばよかったでしょう。
ただそういう展開にはならなかったわけで、2人は互いに自分が「両足」になろうとして、その権益を争い合いました。
結果的にその権力闘争にはアビゲイルが勝利してしまうわけですが、アン女王は言わば「片足」を失ったわけで、まともに立っていることができなくなるんですよね。



















ラストシーン近くで、窓辺に座ってうさぎを踏みつけていたアビゲイル。それを見て、恐怖に打ち震える女王。
これまで自分が立つための「足」だと思っていた人物に、逆に自分は踏みつけられ、踏み台にされているのではという思いがグルグルと回り始めました。
印象的に足に関連した映像を盛り込んでいたのは、非常に面白かったと思います。
ラストシーンとうさぎに込められた意味
やはりどうしても考えてしまうのが、本作のラストシーンの意味ですよね。
アン女王とアビゲイルのあの表情は一体何を物語っていたというのでしょうか。
それを考えていく時に、1つ重要なヒントになってくるのは、エンドロールで流れたのが、エルトン・ジョンの「Skyline Pigeon」をハープアレンジしたものだったということでしょうか。
この曲における「鳩」が誰のことを表していたのかというと、それはサラのことのように思えます。
サラは屋敷でのアビゲイルとの権力闘争に敗れ、イングランドを追われることとなるのかもしれません。
しかしそれは飛び立っていく鳩のようで、アン女王が作り上げていたあの「鳥かご」から彼女が自由になったことを仄めかすようでした。
一方で対照的なのは、本作のラストシーンに映し出されていたうさぎたちです。
これは一体何を意味していたのでしょうか?
そう考えてみた時に、思い出してみて欲しいのがアン女王にとってあのウサギたちは自分の子供の名前をつけていた点です。
つまり「うさぎ=アン女王の権力を継ぐ後継者」と捉えるのが、自然な解釈かと思われます。
ただ、そこには17匹ものウサギがいるわけで、その中で誰がアン女王に愛されるのかという争いは当然絶えないものとなることでしょう。
思えば、サラってアン女王の「うさぎ」に対して嫌悪感を示していましたし、そこにつけいって「うさぎ」を寵愛することで権力を手に入れたのがアビゲイルでしたよね。



















そういうことです。
サラはあくまでもアン女王のことを利用してはいましたが、友であると思っていたんだと思います。だからこそ彼女は「うさぎ」に対して触れようとしなかったのです。
対照的にアン女王の権力だけを突け狙うアビゲイルは「うさぎ」を寵愛し、アン女王の「お気に入り」になろうと努めました。
その姿勢の違いが権力闘争に白黒をつけることになったのは言うまでもありません。
しかし、あのラストシーンが示唆しているのは、アビゲイルはその「うさぎ」にはなれないということなんですよね。
アン女王は結局のところ気がついてしまいました。
17人の子供を失って、そしてその喪失感を埋めるためにアビゲイルに入れ込み、友であったはずのサラまで失ってしまったという「孤独感」。もはやあの屋敷に彼女を愛してくれる人はいません。
ラストシーンのアン女王の空虚で、空っぽの表情が意味するのは、まさしくそんな愛を失った「孤独感」と「絶望感」なのでしょう。
一方で、その表情を見ながら、苦悶の表情を浮かべているのがアビゲイルですよね。
結局のところ彼女はアン女王の「孤独感」を埋めることなど何一つできないわけで、あくまでも「お気に入り」としてせいぜい足を揉み続け、そして女王の権力を突け狙う他の女の存在におびえ続けるしかないわけです。
またこの後史実がどんな道を辿ったのかを知っておいても面白いと思います。
- アン女王は1714年に崩御してしまった。
- 後継者問題が勃発し、ハノーヴァー朝に移行すると議会制民主主義が発達していく。
- サラは追放された後、ヨーロッパを周遊し、イングランドに戻ると、再び復権していく。
- 一方でハノーヴァー朝に突入すると、アビゲイルは政界から追放される憂き目に遭った。



















人間は高度な知能を持っているなんて言いますが、結局のところ「うさぎ」と変わらない愚かな存在なのかもしれません。
だからこそ王政という愚かな「うさぎ」たちの中から「お気に入り」を選んで、その1匹に政治を任せてしまおうなどという考え方が根本的に間違っているのではないかとも考えられます。
そうして時代は「うさぎ」たちが寄り集まって、集団で国の行く末を決めていく議会制民主主義へと移行していったわけです。
我々が生きている世界がこれからどんな方向へ向かっていくのかは分かりません。
しかし、ヨルゴス・ランティモス監督が『女王陛下のお気に入り』という作品のラストシーンに込めたアイロニーはしっかりと胸に留めておかねばなりません。
あのラストシーンは王政という制度がもたらした空虚で、愚かな権力闘争のなれの果てなのですから・・・。
スポンサードリンク
おわりに
いかがだったでしょうか?
今回は『女王陛下のお気に入り』についてお話してきました。
ヨルゴス・ランティモス監督の作品っていつも後味の悪さを残して幕切れるんですよね。
これまでの2作品と比べると、飛び道具的な変態性や嫌悪感はあまり作品からは感じられませんでしたが、作品全体がじわじわと陰湿に見ている我々を不快にさせていく感じはやはり彼らしいと言えるでしょうか。
またそのラストシーンにてシニカルなブラックユーモア全開で、観客に問いを投げかけて幕切れるのも、これまた彼らしいなと思ってしまいました。
本年度のアカデミー賞にて最多ノミネートの快進撃を見せた本作。おそらく映像関連の賞(撮影、衣装デザイン、美術)あたりは間違いなく受賞することでしょう。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。