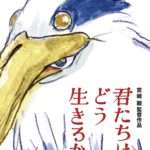みなさんは「団地」という空間に対してどんなイメージを抱くだろうか?
戦後の日本は深刻な住宅不足に追い込まれ、その不足を補うために建設されたというのが、そもそもの始まりだったと言われている。
そして、高度経済成長期に入り、メディアを通じて、団地と家族が強く結びつけられるようになり、「憧れの団地暮らし」というイメージが定着していった。
しかし、建物の経年劣化や子育て世代の転出、高齢化、周辺施設の閉店などに伴い、ゴーストタウン化する団地も増加している。
映画や近現代文学を研究する今井 瞳良氏は、そんな団地に対する世代間のイメージの差異を次のように説明している。
団地が登場した50年代から60年代にかけては、鉄筋コンクリート造で多くが5階建ての高層住宅だった建物や設備自体が新しく、住んでいる人も若くて、憧れの場所でした。
その後、70年代から80年代にかけて一般的な見慣れた光景になり、だんだん古いものになっていくというのが大きな流れです。
90年代頃になってくると、物心ついたときから団地があった人たちが大人になっていき『懐かしいもの』としてのイメージが立ち上がってきます。
理想化された古き良きものとしてノスタルジックに懐古されるイメージと、建設から50年近く経って老朽化しているものというイメージの2つに分かれて今に至ります。
団地は、メディアでそのイメージが爆発的に拡散されたことにより、「家族」の受け皿としての役割を期待され、多大な貢献をしてきたと言える。
しかし、徐々に期待された役割を果たせなくなり、現代の若者が団地と「家族」を結びつけて連想することは極めてまれであると言わざるを得ない。
自身の作品の中でしばしば団地という空間を扱う是枝 裕和氏は『海よりもまだ深く』公開当時のインタビューの中で次のように語っている。
そして、映画の主な舞台になる団地も、建設された当時とは、いろんな意味で違う着地にたどりつきつつある。そうした登場人物と団地の人生を重ねられたら面白いと思ったんです。
是枝監督は、同作の脚本の最初の1行に「みんながなりたかった大人になれるわけじゃない」と綴ったそうだ。
こう考えていくと、「団地」という空間には「なりたかったものにはなれなかった」というコンテクストが内包されているのかもしれない。
前段が長くなってしまったが、『日曜の夜ぐらいは』も団地を舞台にした物語、あるいは映像作品の1つである。
今作における団地も、もはや「家族」の受け皿としての役割を果たしているとはいえず、空室が目立ち、寂れた空間として描かれている。
物語の冒頭時点でそんな団地に暮らしているのは、サチとその母親であるわけだが、この2人の関係も冷え切っており、血のつながった父親はすでに家を出てしまった。
高度経済成長期において団地と結びつけられて拡散された「家族」のイメージ(とりわけ典型的な核家族)とは、かけ離れたものであると言う他ない。
今作のキャラクターたち、とりわけサチ、翔子、若葉の3人は、血のつながった「家族」との関わりにおいて、「なりたかった」を手に入れられなかった、あるいは手放した女性として描かれている。
© ABC All rights reserved.
サチは、甲斐性のない父親と下半身不随になった母親との関わりの中で、自らが当然のように享受するはずだった青春と自分が「なりたかったもの」を手放した女性だ。
翔子は、自分自身の振る舞いが発端ではあったが、不本意な形で血縁家族のつながりを断ち切られてしまった女性だ。
そして、若葉は性に奔放な母親の影響を受けて、自分の望む学生生活や友人関係、異性との関係から遠ざかってきた女性だ。
3人は心の中に「なりたかった」を秘め、それを必死に押し殺しながら、「なれなかった」人生を歩んでいる。
第1話で、サチがこんな言葉を言っていたのが忘れられない。
「楽しいのダメなんだけどな。だって楽しいと。楽しいことあると、キツいから。キツイの耐えられなくなるから。」
(『日曜の夜ぐらいは』第1話より)
この言葉には「なりたかった」を必死に遠ざけようとする意志が感じられる。
「なれなかった」人生を歩んでいくために、「なりたかった」は毒だ。なぜなら、それは自分がいま歩んでいる人生が「なれなかった」人生なのだと思い出させるからに他ならない。
「なりたかった」さえなければ、私は今の人生を受け入れて歩んでいけるはず。
また、『日曜の夜ぐらいは』は男性キャラクター陣や少し世代の離れたサチの母親や若葉の祖母といったキャラクターたちも魅力的に描いている。
後に3人のカフェの創設メンバーに加わるみねは、「男性らしさ」を求められることに苦しんできた男性だ。
そして、カフェのコンサルティング業を営む賢太は、イケメンであるが故の偏見を受けてきた、あるいはイケメンであるが故の「女性を弄ぶ男性像」を押しつけられてきた人物であると言える。
この2人は、『違国日記』の著者であるヤマシタトモコ先生の言葉を借りるなら、「男社会を降りた」いと切望する男性なのである。
もっと言うなれば、誰かに、あるいは社会に求められた自分に「なれなかった」人物と言えるだろうか。
サチの母親も、若葉の祖母も、世代は異なるが、思い描いた血縁家族の枠組みからフレームアウトしてしまった人物だ。
後者は、自分自身がかつてこだわって建築し、居住していた美しい家族の器を、ボロボロの自宅から眺めることしかできない。もうその理想には手が届かないのだ。
そんなキャラクターたちが、出会い、つながり、カフェ「サンデイズ」という場の創出を通じて絆を深めていくのが、『日曜の夜ぐらいは』の物語の軸である。
この過程で、キャラクターたちが1人、また1人と団地に移り住んでいくのが、何とも興味深い演出と言える。
かつて血縁家族ないし核家族の受け皿として、幾度となくホームドラマの舞台となり、家族のイメージを打ち出し続けた空間にやって来るのは、みなそんな「家族」のイメージからフレームアウトした者たちだ。
しかし、彼らはそこに集い、「ホームドラマ」を再構築していく。そして新しい「家族」のカタチを作り上げていく。「なりたかった」に「なれなかった」場と人が交わることで、新しい何かを作り出していくのだ。
それこそが『日曜の夜ぐらいは』が描きたかったものなのかもしれない。
最終回の終盤で、サチの「これは私の想像なのだが…」というセリフを前置きをしたうえで、IFの世界線が描かれる。
ここに描かれた内容はともかくとして、この想像ないし願望の光景を描いたことに重大な意味があったと思う。
第1話の時点で、サチは「なりたかった」や「なりたい」を遠ざけて、「なれなかった」を受け入れる人生を送っていた。
しかし、物語を経て、彼女は「なりたい」を隠さなくなったし、遠ざけなくなった。「なりたい」に自分でも手が届くと信じられるようになったのだ。
だからこそ、この「なれなかった」に満ちた物語を「なりたい」に満ちた空想で終わらせることに意味がある。
最後に、この物語の好転を支えたのが、3000万円の宝くじの当選という事象だったことがこの物語の味わい深いものにしていると思う。
きっと誰もが「宝くじで高額当選したら…」というIFを一度は思い描いたことがあるだろう。かく言う私自身もある。
しかし、そんなIFを私も含めた多くの人はこんな言葉でかき消してしまう。
「そんなの当たるはずないじゃん。」
でも、このドラマが言いたいのは、宝くじを買うという一歩を踏み出さない人に、宝くじは当たらないということなんだ。
アメリカの思想家ラルフ・ウォルド・エマーソンはこう言った。
Every wall is a door.(すべての壁はドアである。)
私たちは、外に出たいと願いながらも、固い壁に打ちのめされ、いつしか諦めて壁の中の絶望に慣れてしまう。
でも、どんな壁も何度も押し続ければ、いつしかそれは「ドア」になるのではないか。
「ドアは自分たちで開けようと思います。」
その言葉が、現代を生きる私たちを包む閉塞感に、少しだけ風穴を開けてくれたような気がした。
© ABC All rights reserved.
ありがとう。