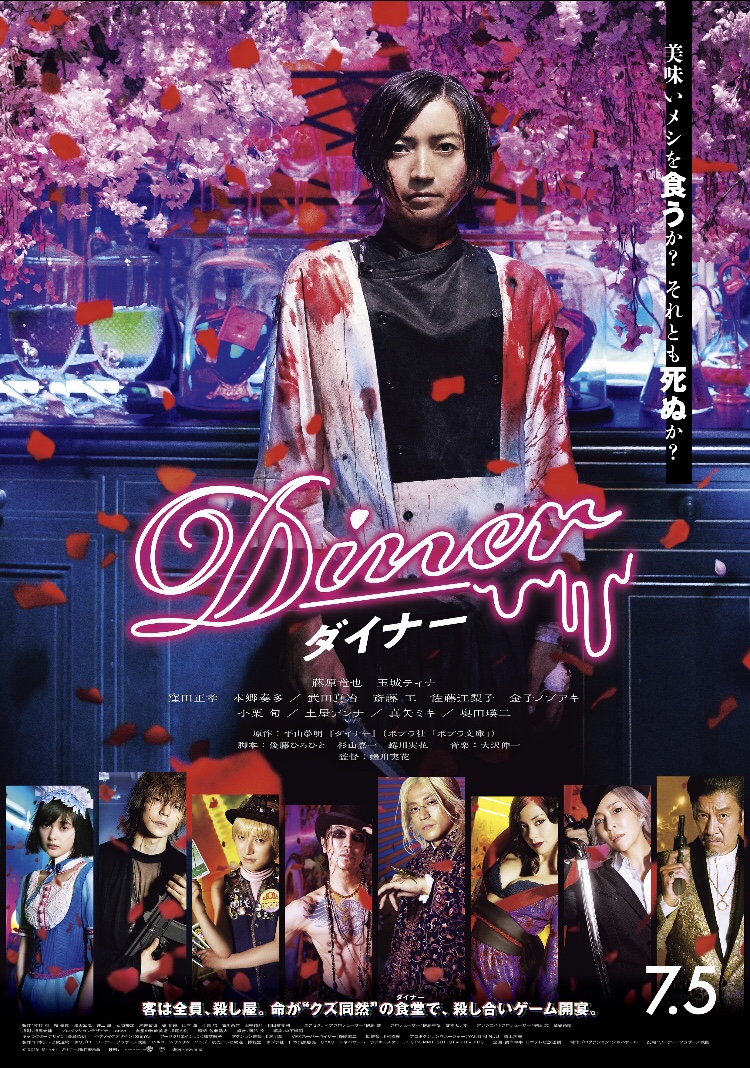まえがき
「行ってきます。」と告げた相手に「おかえり。」と言えること。あるいはその繰り返し。その何気ないルーティンがどれだけ尊く、愛おしいものなのか。
3月11日、あの日がすべてを変えてしまった。私たちの社会には、何かが失われていくような感覚が、何かが終わっていくような感覚がべったりと貼りついて、遅効性の毒のようにじわじわと蝕んでいる。
脚が1本欠けた椅子のように、片足だけが無くなったローファーのように。どこかで満たされない思いを抱えている。
街が消えた。生活が消えた。大切な人が消えた。私たちが生きている間にはもう住めないかもしれないと言われる場所だってある。
そんな緩やかな絶望と虚無感に身を浸していると次第にこう思えてくる。
いっそのこと死んでしまった方が楽なのではないだろうか。
向こう側の世界には、私たちがまだ何もかもを信じられた時代が、大切な人と過ごした甘美な時間が、いつまでも浸っていたい愛おしい思い出たちが輝いている。
生よりも死がキラキラと輝いて魅力的にすら思える時代を私たちは生きてきた。1日、1週間、1ヶ月、1年、そして10年。
そんな私たちを救うものは、やっぱり死でしかないのか。失われてしまったものに縋ることでしかないのか?
新海誠監督が『すずめの戸締まり』を通して、いや創作物(フィクション)を通じて成し遂げたかったのは、この問いへの否定だ。
©2022「すずめの戸締まり」製作委員会
そして、そんな苦難の時代を生きてきた私たちの、あるいは私たちの10年の肯定だ。
荻上直子監督の映画『川っぺりムコリッタ』の中にこんなやり取りがある。
「毎日頑張って、それが1ヶ月、半年、1年、5年…10年になってくんだよ。」
「それって意味あるんすか。」
「あるんだよ。ただそれは5年、10年続けた者にしか分からないんだよ。」
みなさんなら、このやり取りの中で挙げられた「意味」についてどう解釈するだろうか?
新海誠監督は正直な人だと思う。10年を生きてきたあなたが何を得たか、何を成し遂げたか、どこにどんな意味があるのかに対する彼なりの回答を示そうとするわけだが、そこに脚色を施すことはない。
ただ、あなたが10年生きてきたという事実を、あの日から10年間死ぬことなく「行ってきます。」と「おかえり。」を繰り返し続けたという嘘偽りのない真実を教えてくれるだけだ。
しかし、その事実で、その真実でどれほど心が軽くなるだろうか。どれほど心が救われるだろうか。
ただ生きてきた。それがあなたの強さなのだと『すずめの戸締まり』はすずめの自己肯定を介して私たちに伝えようとしている。
別れを告げることは、過去にすることである。その対象が大切であればあるほど、別れを告げるのが難しくなる。
過去にするということは、今の自分から切り離してしまうことであり、大切なものを切り離したらその刹那、自分はポッキリと折れてしまうのではないかと思わず不安になる。
でもあなたは、その大切なものなしの10年間生きてきたんだ。生きてきたんだよ。
大丈夫。もうお別れをしても、過去にしてもあなたは大丈夫なんだ。
だから「戸締まり」をしよう。
でも、さよならと言ってしまうのはやっぱり抵抗があるだろう。当然だ。
それなら別れの言葉は「いってきます。」ではどうだろうか。そうしたら、またいつかどこかで「おかえり。」を言えるような気がする。
力強く生き抜いた私にいつか「おかえり。」を告げるあなたの笑顔を思い浮かべながら、あなたのいない明日を、明後日を、1年を、次の10年を。
そして、目の前の大切なあなたに告げる「おかえり。」の響きの尊さを噛み締めながら。
目次
『すずめの戸締まり』を紐解く4つの視点(ネタバレあり解説・考察)
「震災」にどう向き合ってきたか?
©2022「すずめの戸締まり」製作委員会
新海誠監督は、ちょうど『星を追う子ども』を制作していたころに、東日本大震災を経験したと語っている。
その後、彼は2016年に公開された『君の名は。』、2019年に公開された『天気の子』で寓話の中で震災と向き合ってきたと言える。
『君の名は。』は、ティアマト彗星と呼ばれる巨大な彗星が地球に落下することに伴う災害により多くの人々の命が失われた日本を描いていた。
そして、物語は主人公の瀧とヒロインの三葉の行動により、そんな大災害を回避しようとする方向へ向かっていく。
震災から5年ほどしか経過しておらず、フィクションの中で震災に言及してよいのかどうかがまだ微妙だった時期にフィクションにしかできない震災の向き合い方を示してくれたエポックメーキングな作品だったと思う。
そして、監督は主人公の瀧に自分の思いを一部代弁させていたとインタビューでも語っているが、終盤の面接のシーンで瀧が面接官に告げたセリフは、まさしく監督自身の決意や覚悟だった。
東京だって、 いつ消えてしまうか分からないと思うんです。だから、記憶の中であっても何でいうか人を温め続けてくれるような風景を作りたいのです。
(映画『君の名は。』より引用)
震災が私たちに突きつけたのは、私たちの日常がいかに脆い基盤の上に成り立っているのかということだったように思う。
その脆さに直面したからこそ、新海誠監督は『君の名は。』というフィクションを通じて、現実ではもう取り戻せなくなった何かを取り戻そうと試みたのだ。
それが当時できる精一杯の震災との向き合い方だったように思う。
日本のアラブ文学者である岡真理氏は自身の著書『アラブ、祈りとしての文学』の中で、文学の力を次のように定義している。
その惨状の場にいない者、いなかった者達が、当事者達に捧げる祈りである
(岡真理『アラブ、祈りとしての文学』より引用)
願わくばあの災害が無かったことになって欲しい、失われた多くの命が戻ってきて欲しい。もちろんそんな望みが叶うわけがないのだが、人々は心のどこかでそんなハッピーエンドを願ってしまう。
『君の名は。』は、そんな人々の祈りの器としての震災映画になり得た。
続く『天気の子』では、災害が起きてしまった世界で、あるいはそれが変えられない世界で、そうした現状を受け入れて、前を向いて生きていく力強い決意を見せてくれた。
『君の名は。』では、災害そのものをなかったことにするという形で希望と救済を描いたが、『天気の子』はもっとリアリスティックな路線をとっている。
変えられない世界、起きてしまった災害。そんな世界で生きていくこと。その選択。
ポスト東日本大震災の日本で明日を生きていくための勇気をくれるようなそんな作品だったようにも思える。
そして、今作『すずめの戸締まり』は明らかに過去の2作品とは、異質な震災との向き合い方に裏打ちされていた。
新海誠監督は本作の制作にあたって、企画書の段階で「震災の映画である」と明確に決めていたと語っている。
そして、劇場にも「地震描写や緊急地震速報を受信した際の警報音(※警報音は実際のものとは異なるようです)が流れるシーンがあり…」という注意書きが掲示されるほどに直接的な描写で震災を描いている。
「東日本大震災」という固有名こそ出てこないが、「東北地方」「3月11日」「地震」というキーワードが明確に登場し、映画を見れば一目で「東日本大震災」のことであると分かる作りになっているのだ。
「新海誠本」の最初のページに掲載された、監督自身が企画書の前文として記した文章の中にこんな一節がある。
災害については、アポカリプス(終末)後の映画である、という気分で作りたい。来たるべき厄災を恐れるのではなく、厄災がどうしようもなくべったりと日常に貼りついている、そういう世界である。
(「新海誠本」4ページより引用)
冒頭に震度3レベルの地震が起きるシーンがあるのだが、生徒たちはあまり驚く様子は見せない。日本に生きる私たちにとって、それほどまでに地震は「日常」になってしまったのだ。
『天気の子』では、まだ「地震」という直接的なモチーフに言及していなかったし、厄災の始まりの時期にスポットを当てた作品だったということもあり、ポスト災害の世界を描いていたというよりは、むしろその渦中を中心に描写していた。
しかし、『すずめの戸締まり』において、3月11日の大震災はもはや過去の出来事であり、主人公たちが生きているのは、そこから12年も経過した世界なのである。
この現実との親和性の高さ、生々しい手触りこそ、新海誠監督が『すずめの戸締まり』という作品を通じて追求したかったものなのだと思う。
ただ、今作を見た人の一部はこうも思うかもしれない。
フィクションにおいて「震災」を描き続けることに、より生々しい描写で描き続けることに何の意味があるのだろうか。その役割はドキュメンタリー映画に任せるべきではないかと。
先ほどもご紹介した岡真理氏は別の著書『ガザに地下鉄が走る日』の中で文学とジャーナリズムを比較した。
2014年にガザ侵攻が起きた際に、ガザの若者たちはアラビア語ではなく、英語を用いてSNSで世界中に発信をしたという。その内容は、ジャーナリスティックに何が起きているのかを淡々と伝えるだけでなく、その状況を生きることが人間にとってどんな体験なのかをまざまざと突きつけた。
そんなガザの若者たちが発信したある種のエッセイを、岡真理氏は「情報に還元されない文学的強度をもったそれらのエッセイ」と形容した。
また、こうも述べている。
それは情報として消費されることに抗う、紛れもない「文学」ー緊急のエクリチュールーだった。
(岡真理『ガザに地下鉄が走る日』245ページより引用)
また、さらに別の著書『棗椰子の木陰で―第三世界フェミニズムと文学の力』の中では、もっと直接的にジャーナリズムと文学の差異に言及しながら、文学を次のように定義した。
記号に還元されない、人間が生きる具体的な生の諸相を描き、私たちの人間的想像力と他者に対する共感を喚起するもの、そのひとつが文学作品である…
(岡真理『棗椰子の木陰で―第三世界フェミニズムと文学の力』13ページより引用)
ジャーナリズムは、「今、ここ」を緊急性を持って伝えることはできるが、伝えられるのは表層的な情報あるいは記号的な情報になってしまうと彼女は言及している。
だからこそ、記号に還元されることなく、人間の生の具体的な細部を描き、想像力と共感を喚起する、あるいは祈りを導く文学にも、過酷な現実を前に果たせる役割があるのではないだろうか。
新海誠監督が『君の名は。』以降の作品で貫いてきた震災との向き合い方も、これに近いものを感じる。
ドキュメンタリーやジャーナリズムにはできない、震災を巡る人間の生をアニメーションを通じて、様々な角度から描こうと試みたわけだ。
また、『すずめの戸締まり』は震災の全体像を描こうとは試みていない。終盤にすずめと草太が震災前の街のイメージに触れる描写はあったものの、どこまでも「すずめ視点の震災映画」であるという姿勢は崩さない。
『君の名は。』や『天気の子』は、ボーイミーツガールに軸を置いた閉じた物語ではありつつも、かなり大きな視点で災害を描いていた。
前者では、三葉を救う過程で、最終的に街の人全員の命が救われるし、後者ではさまざまなキャラクターの視点から雨が降り続ける現象を捉えている。
一方の『すずめの戸締まり』は、ひたすら主人公のすずめが経験した震災とそれに伴う消失に向き合う「小さな物語」になっていた。
日本で東日本大震災以後、震災を扱った作品が増えたのと同様に、アメリカ文学でも、9・11同時多発テロが起きた後に、テロを扱った作品が急増した。
そんなテロを題材にした作品を著した作家の中でも特に注目された1人であるドン・デリーロ氏の作品を分析した次のような言説がある。
「大きな物語」へすべてを還元するという暴力に対抗するには、取るに足りない個人の持つ細かなエピソードの一つひとつを、徹底して擁護するしかないではないか。
(『偽アメリカ文学の誕生』230ページより引用)
新海誠監督が自分のもうすぐ中学生になる娘にとって震災は「教科書の中の出来事」であるとインタビューで語っている。
そうやって、東日本大震災はいつしか東日本大震災という「大きな物語」になり、記号化し、その細部は、失われた人々や暮らしの一つひとつは忘れられていくのかもしれない。
だからこそ、新海誠監督は、今まで以上に直接的に震災という題材に手を触れなければならないと感じていたのではないだろうか。
そして、それが震災の全体像を表層的に捉えた作品ではなく、取るに足らない個人のエピソードのうちの一つであるべきだと考えたのではないだろうか。
『すずめの戸締まり』の世界では、『君の名は。』や『天気の子』で起きたような世界や社会の形を大きく変えてしまうような出来事は起こらない。
そこにあるのは、一人の少女の内的世界にもたらされた「小さな変化」だけだ。
しかし、そうした「大きな物語」を前にした「小さな物語」にスポットを当てることこそが、文学あるいは映画の役割なのだと思う。
次第に色褪せ、記号化されていく震災を前に、震災を巡る一人の少女が生きる具体的な生の諸相を描き、その尊厳を取り戻そうと試みた本作に拍手を送りたい。
「距離」にどう向き合ってきたか?
©2022「すずめの戸締まり」製作委員会
新海誠監督は、デビュー作の『ほしのこえ』の頃から「距離の作家」であるなんて言われている。
『ほしのこえ』では、主人公とヒロインの物理的な距離が開くほどに時間的な距離が生まれ、それが心的距離に繋がっていくという悲恋の物語を描いた。
それ以降の作品でも、新海誠監督は「ボーイミーツガール」を取り上げ、その上で主人公とヒロインの「距離」を描いてきたと言える。
彼の代表作の一つでもある『秒速5センチメートル』では「ボーイミーツガール」とそれに伴う「距離」の残酷さを鮮明に描いた。
特にその第1話である「桜花抄」では、東京で暮らす貴樹が栃木に引っ越した明里のもとを目指す過程を描いているのだが、電車での移動の描写を介して、2人の間にある物理的、時間的な距離を露悪なほどに際立たせている。
結果的に、その距離は2人の心的な距離の開きに伝染していき、2人の人生がその後交わることはなかった。
『星を追う子ども』では生と死の途方もない距離を題材にしているし、『言の葉の庭』では新たに年齢という「距離」を持ち出してきた。
『君の名は。』でも、物理的な「距離」あるいは時間的な「距離」が物語のギミックの根幹を成していたし、『天気の子』では地上と空の上という形で物理的な距離を演出していた。
とは言え、そうした「距離」との向き合い方は、『君の名は。』を境にして変化しているようにも見える。
『ほしのこえ』や『雲の向こう、約束の場所へ』あるいは『秒速5センチメートル』といった作品では、「距離」を残酷で抗いがたい絶対的なものとして描いていた。
『ほしのこえ』では、「ながみねみかこ」が高校生のままの姿であるのに対して、彼女と物理的、時間的な「距離」を隔てた「てらおのぼる」が一足先に大人に成長していく。
彼は時間の流れに抗うことはできないし、地球から離れていく彼女を追いかけることもできない。そうして生じたズレが、抗いようのない2人の「距離」になっていくわけだ。
しかし、『君の名は。』や『天気の子』では、そうした「距離」にただただ絶望したり、打ちひしがれたりするのではなく、主人公やヒロインがその「距離」を埋め、得難い何かを掴み取ろうとする姿にスポットを当ててきた。
自身が抗いがたいものとして描いてきた「距離」に懸命に抗う少年少女の姿に新海誠監督はフィクションとしての希望を重ねたのだ。
そして、今作『すずめの戸締まり』もまた、やはり「距離の映画」なのである。
しかし、これまでが「わたしとあなたの距離」についての映画だったのに対して、今作は「わたしとわたしの距離」についての映画になっている。
前作の『天気の子』では、観客が自分を重ねられるようにと、あえて主人公の帆高のバックグラウンドを描かなかった。
一方の『すずめの戸締まり』でも、主人公のすずめのバックグラウンドは物語の序盤時点では、ほとんど開示されることがない。
ただ、これは前作とは違って、作劇上の意味があるが故に描かれていないのである。
なぜなら、描かれないすずめのバックグラウンドというのは、今作で彼女が見つけるべきものだからだ。
すずめは幼少期の記憶をあまり持っていない。自身が経験した震災の記憶、故郷で過ごした時間、命を落とした母親との思い出。
これについて、彼女は自分自身のアイデンティティとの間に「距離」を抱えているという見方ができないだろうか。
つまり、すずめは他者とではなく、自分との間に「距離」を抱えているのだ。
本作はロードムービーの体になっており、すずめは次第に自分の故郷との物理的な距離を埋めていく。
その物理的な距離が縮まるほどに、彼女は思い出や自分の出自を取り戻していく。つまり、アイデンティティないし自分自身を取り戻していくのである。
また、新海誠監督は『すずめの戸締まり』を「場所を悼む物語」と位置づけている。
近代世界では軽んじられるようになったが、「場所」というのは人間のアイデンティティにおいて長らく重要な概念であった。
宮崎駿監督の『もののけ姫』の中で、アシタカが名乗るシーンは有名だが、彼はこのとき次のように述べている。
我が名はアシタカ!東の果てよりこの地へ来た!
(映画『もののけ姫』より引用)
彼は自分の名前の次に、自分の出自あるいは「場所」について言及している。それほどまでに「場所」というのは、自分自身を構成する重要な要素だったわけだ。
『場所の詩学』という書籍の中で、自然保護活動家のゲーリー・スナイダーが「場所はアイデンティティを考える際の新しい概念である」と語り、今一度私たちのアイデンティティの根幹を成すものとして見直そうと呼びかけた。
これに関連して、興味深い言葉をひとつ紹介したい。
先ほども引き合いに出した岡真理氏の書籍『ガザに地下鉄が走る日』の中で「スペィシオサイド」という言葉が登場する。日本語に訳すと「空間の扼殺」だそうだ。
字面から意味を読み取ろうとすると、空間ないし場所を物理的に破壊することではないかと思わず想像してしまうところだろう。
しかし、そういう意味ではなく、岡真理氏は「空間」を「人間が人間らしく生きることを可能にする諸条件のメタファー」と定義づけている。
その上で「スペィシオサイド=空間の扼殺」を次のように説明した。
占領下の生活のありとあらゆるレヴェルで、パレスチナ人が自分たちの土地で人間らしく、ごく普通の暮らしを送る可能性をことごとく潰していくことで、命を直接、奪わずとも、彼らの生を圧殺していくのである。
(岡真理『ガザに地下鉄が走る日』222ページ)
いわゆる「ジェノサイド」のように、人の命を大量に奪うのではなく、人がその土地で済むことができないようにあらゆる諸条件を奪っていくこと、それが「スペィシオサイド」なのだ。
「場所」には人々の歴史、文化、日々の生活や思い出といったかけがえのない記憶が染み込んでいる。そういう場を奪うという行為は、人の命を奪うというよりは、人のアイデンティティを奪う行為に思える。
こうした「スペィシオサイド=空間の扼殺」という言葉が出てくることそのものが、人間にとっての「空間」ないし「場所」の重要性を示している。
話が逸れてしまったが、先ほども述べたように『すずめの戸締まり』はロードムービーの体になっており、すずめは次第に自分の故郷との物理的な距離を埋めていく。
少しずつ自分の「場所」を取り戻す映画になっているのである。「場所」とはつまりアイデンティティのことだ。
『すずめの戸締まり』は「場所」との「距離」を埋めることを介して、失った自分自身の出自やアイデンティティとの「距離」を埋めていく物語なのである。
だからこそ、本作のラストは「いってきます。」で終わる必要があった。
「いってきます。」という言葉をどんなシチュエーションで言うかを考えてみて欲しい。それは自分の帰るべき「場所」に向かって言う言葉ではないだろうか。
つまり、すずめは遠く「距離」を隔てた自分の故郷をちゃんと自分の帰るべき「場所」として認知することができたのである。
それは、すずめが「場所」を取り戻したことの何よりの証左であり、それはすなわちすずめが失われた「自分」を取り戻したことを意味している。
そう考えると、本作の最後にすずめが出会うべき相手が他でもない自分自身だったことも必然だったと言える。
「大丈夫」にどう向き合ってきたか?
©2022「すずめの戸締まり」製作委員会
新海誠監督作品におけるキーワードのひとつに「大丈夫」がある。
辞書で意味を調べてみると「あぶなげがなく安心できるさま。強くてしっかりしているさま。」と書かれている。
彼は自身の作品の中に、この「大丈夫」というキーワードを忍ばせてきた。
まずは、2007年に公開された彼の代表作のひとつでもある『秒速5センチメートル』について見ていこう。
「貴樹くんはこの先も大丈夫だと思う。」
(小説『秒速5センチメートル』新海誠著 53ページより引用)
同作の第1話「桜花抄」のラスト、主人公の貴樹とヒロインの明里が駅のホームで別れるシーンで、明里が貴樹にかける言葉である。
小説版には、映画版では明確に語られていない、この言葉を巡る2人の心情が綴られている。
まずは、明里だが、彼女はあの日貴樹に渡すことができなかった、渡さなかった手紙の中に次のような言葉を書いていた。
私はこれからは、ひとりでもちゃんとやっていけるようにしなくてはいけません。そんなことが本当にできるのか、私にはちょっと自信がないんですけれど。でも、そうしなければならないんです。私も貴樹くんも。そうですよね?
(小説『秒速5センチメートル』新海誠著 178ページより引用)
明里が貴樹に「大丈夫」と告げるのは、貴樹には私がいなくても大丈夫だとエールを贈っているのであり、同時に彼女がひとりで歩いていくことを決心したことの証左だ。
つまり、「桜花抄」のラストで、2人は、とりわけ明里の方は、もう「別れ」を選んでいたとも言える。
一方で、貴樹の方はと言うと、長らく明里のあの言葉に囚われてしまう。
社会人になった貴樹のモノローグの中で次のように書かれている。
そして一度それに気づいてしまうと、今までずっと、自分はそれを求めていたのだということが彼にははっきりと分かるのだった。
ずっと昔のあの日、あの子が言ってくれた言葉。
貴樹くん、あなたはきっと大丈夫だよ、と。
(小説『秒速5センチメートル』新海誠著 161ページより引用)
1つのセリフを巡る貴樹と明里の対照的な受け止め方は何とも興味深い。
貴樹は明里を「大丈夫」にしたかったのであり、そして明里に「あなたは大丈夫」と言ってほしかったのだ。しかし、明里はと言うと、貴樹に「大丈夫」を依存する自分から脱却し、自分一人で「大丈夫」になろうと決意した。
だからこそ、『秒速5センチメートル』のラストは、貴樹がそんな過去の幻影に別れを告げ、明日を生きていく決意をするところで幕を閉じる。
あなたがいなくても、あなたの言葉がなくても、自分はもう「大丈夫」なのだと、貴樹は長い時間をかけて、大好きだったあの人の言葉に折り合いをつけるわけだ。
そして「大丈夫」というキーワードがより前面に押し出された作品として挙げられるのが、『天気の子』ではないだろうか。
同作のエンディングテーマは『大丈夫』という曲名になっており、映画の一番最後のセリフも「大丈夫」だった。
新海誠監督自身も「『大丈夫』という曲に、映画のラストシーンに込めたかったことがすべて入っていた」と公開当時のインタビューで語っている。
その歌詞の中でも特に注目すべき点は次の一節だろう。
取るに足らない 小さな僕の 有り余る今の 大きな夢は
君の「大丈夫」になりたい 「大丈夫」になりたい
君を大丈夫にしたいんじゃない 君にとっての 「大丈夫」になりたい(『大丈夫』作詞:野田洋次郎 作曲:野田洋次郎 より引用)
映画のラストとも親和性の高い歌詞だが、新海監督が作り上げた『天気の子』における帆高と陽菜の関係性を見事に代弁していると言える。
誰かを「大丈夫」にしたいと考えるのは、ある種のエゴであり、傲慢なのかもしれない。
しかし、まずは自分が「大丈夫」であることによって、隣にいるあなたがわたしを見てくれたときに、あなたも「大丈夫」だと思える、そういう関係こそが美しいのではないかと、この歌詞や『天気の子』という作品は言っているのではないだろうか。
帆高は映画のラストで陽菜に「陽菜さん、僕たちは、大丈夫だ。」と告げた。
これは、自分たちが選んだこの世界、あるいは街でこれからを生きていくことに対する決意表明でもある。
このように振り返ってみると、新海誠監督の作品における「大丈夫」は誰かを救うための言葉としては描かれてこなかったことが分かる。
それよりもむしろ、自分がこれからを生きていくための強い決意の言葉として「大丈夫」を描いてきたように見える。
そして、今回の『すずめの戸締まり』では、新海誠監督なりの「大丈夫」がこれまでよりも輪郭を明確にして描かれていたように思えた。
パンフレットの中に掲載されているインタビューでは次のように回答している。
他者に救ってもらう物語となると、まず救ってくれる他人と出会わなければいけないわけです。でも本当に自分を救ってくれるような他者が存在するのかどうか、わかりませんよね。『君の名は。』の瀧に出会えるわけでも、『天気の子』の陽菜に出会えるわけでもない。でも、誰でも少なくとも自分自身には会えるじゃないですか。
(『すずめの戸締まり』パンフレットより引用)
ここに『すずめの戸締まり』における「大丈夫」がこれまでとは決定的に異なっていた理由が綴られているような気がした。
『秒速5センチメートル』にしても、『君の名は。』にしても、『天気の子』にしても、「大丈夫」に到達するためのきっかけを他者に求めているという共通点がある。
それは新海誠監督作品が「ボーイミーツガール」に裏打ちされたものであるという性質の影響も大きいだろう。
『天気の子』のラストシーンでは、そもそも陽菜が「帆高っ、どうしたの?大丈夫?」と帆高に声をかけている。出会いの場面では、彼女が明らかに「大丈夫」ではなかった彼にビッグマックを差し出した。
『秒速5センチメートル』の貴樹が「大丈夫」に至るまでには、明里の存在が必要だったし、逆もまた然りであった。『天気の子』の帆高と陽菜も、そして『君の名は。』の瀧と三葉も同様である。
一方の『すずめの戸締まり』における、すずめを救うのは草太ではない。
すずめを救うのは、他でもないすずめ自身なのである。
「あなたは光の中で大人になっていく」
(小説『すずめの戸締まり』著:新海誠 356ぺージより引用)
すずめは常世で出会った幼少期の自分にこう声をかけた。小説版ではこの言葉の対象を「私たち」と表現している。
つまり、幼少期の自分を励ましながら、高校生になった自分自身にも同じ言葉を言い聞かせているというわけだ。
このようにして、すずめは自分で自分を救う。自分で自分を「大丈夫」にしてみせる。
新海誠監督は、そんな『すずめの戸締まり』を「自分が今までに作ったものの中で、いちばん優しい映画」と表現している。
他者との出会いが救いになる物語、あるいは「ボーイミーツガール」の物語は閉じており、どこかで観客に身の置き所のなさを、物語からの疎外感を感じさせてしまう趣がある。傍観者であって、当事者にはなれないのだ。
しかし、『すずめの戸締まり』が描いた「自分が自分を救う物語」には、観客にそれを自分事に思わせ、物語に巻き込んでいく引力がある。
登場人物が「大丈夫」に至る物語を描き続けた新海誠監督は、『すずめの戸締まり』において、観客をも「大丈夫」に至らせる「やさしい映画」の境地へと至ったと言える。
「正しさ」にどう向き合ってきたか?
©2022「すずめの戸締まり」製作委員会
劇場で配布された「新海誠本」の中に『天気の子』の企画書の一部が掲載されている。
その中にこんな一節がある。
現代の漫画やゲームにおいてさえ、「世界を元通りにすること」は支配的なモチーフである。なぜなら、この種の物語は圧倒的に「正しい」からだ。
(中略)
でも、と思う。この種の「正しい物語」に、僕たちはいつからか息苦しさと空々しさを感じてはいないだろうか。
(「新海誠本」12ページより引用)
『天気の子』は公開当時、かなり賛否が分かれたと記憶している。特に同作のラストは「最悪の現状肯定」とも捉えられ、「正しくない」「適切でない」という意見も見られた。
しかし、新海誠監督はそもそも『天気の子』を「正しくない物語」と自覚し、半ば確信犯的に物語を構築している。
今作『すずめの戸締まり』の主題歌「すずめ」の歌詞にもこんな一節がある。
愚かさでいい 醜さでいい
正しさのその先で 君と生きてきたい(『すずめ feat.十明』より引用)
『天気の子』で「正しくない物語」を志向した背景、そして主題歌に含まれる「正しさのその先」という歌詞。ここから『すずめの戸締まり』でも「正しさ」を追求しない姿勢は明確になっていると言える。
おそらく『すずめの戸締まり』を見た多くの人がモヤモヤを抱えるのは、私自身もそうであったが、猫の姿をした要石のダイジンの扱いではないかと思う。
ダイジンは物語の冒頭に、すずめに「うちの子になる?」と声をかけられたことで、それが心からの願いとなり、結果的に自分がすずめの「うちの子」になる上で邪魔な要素を排除しようと試みる。
要石の役割を自分から草太に移したのも、すべては自分がすずめの「うちの子」になるためだったわけだ。
しかし、すずめの草太を思う気持ちに触れ、自分がすずめの家族にはなれないことを悟ったダイジンは自分が要石に戻ることを受け入れ、最終的にはすずめの手で元の状態へと戻される。
ただ、この一連の過程を見ていてどうしても感じてしまうのは、草太を犠牲にして世界の平和を保つのは非とされ、ダイジンを犠牲にして世界の平和を保つのは是とされるある種の「ダブルスタンダード」だ。
ダイジンは、すずめに「家族にならない?」と声をかけられ、それが唯一の願いとなったわけだが、彼は幼少期に叔母さんに「うちの子になりんさい」と声をかけられたすずめ自身に重なる存在として描かれている。
そういう存在にも関わらず、ダイジンの帰結の描かれ方は一言でいえば、雑であり、命に貴賤を設けているようにすら感じられてしまうのだ。
ここに『すずめの戸締まり』の物語の「正しさ」からの逸脱が見受けられる。
しかし、こうした「愚かさ」や「醜さ」を正面から描き切ったことにむしろ意義があったのではないかと、鑑賞から少し時間が経って思うようになった。
『君の名は。』は、主人公の瀧の行動を通じて、災害により失われた命をすべて取り戻すというフィクションだからこそできる震災との向き合い方を示したと前述した。
この物語は、そういう意味で確かに「正し」かった。
ただ、現実問題として、こうした大きな災害に直面し、自分の大切な人を含めた多くの人が亡くなったとき、自分の大切な人の命と、その他大勢の命を天秤にかければ、あなたにとっては間違いなく前者の方が重い。
どちらかを救えるとしたら、どれだけ客観的に見れば、非合理であろうと、量的差異があろうと迷わず後者を選ぶだろう。
こういう切実さに向き合い、その他大勢よりも大切な人を選ぶという選択を描いて見せたのが『天気の子』だったわけだ。
そして、今回の『すずめの戸締まり』も描いていること自体はそれほど変わらないと思う。
自分の大切な人のために他の何かを犠牲にするという根本は同じだ。
しかし、『天気の子』の犠牲があまりの規模の大きさ故に漠然としている一方で、『すずめの戸締まり』の場合はダイジンという明確な身代わり、犠牲が存在する。
だからこそ、すずめの選択に付きまとう「愚かさ」や「醜さ」の色が濃いのだ。
今作を見た多くの人は、ダイジンを犠牲にしたことに対してモヤモヤを抱えるのではないかと思う。
しかし、あなたがすずめと同じ立場だったとして、ダイジンを犠牲にしないという「正しい」選択ができるだろうか。
あなたの大切な人よりも、ダイジンを選ぶという「正しさ」を貫くことができるだろうか。
きっと、そんなことができるのは、「正しい物語」の中の登場人物だけなのだと思う。
終盤に草太が祈りの中でこんなセリフを残している。
「死は常に隣にあると分かっています。それでも私たちは願ってしまう。いま一年、いま一日、いまもう一時だけでも、私たちは永らえたい!」
(小説『すずめの戸締まり』著:新海誠 343ぺージより引用)
この言葉は、祈りというには、あまりにもエゴがむき出しである。また「正しさのその先で君と生きてきたい」という『すずめ』の歌詞に強くリンクする言葉でもあると言える。
「愚かさ」や「醜さ」にまみれたとしても、そこに「正しさ」が存在しないとしても、わたしとあなたが生きること、それだけが重要なのだという切実さ。
その切実さに直面したとき、私たち観客がすずめたちに「正しさ」を押しつけることはできない。
今作が絶賛一色にならないことは明白であるし、それが本作の望ましい在り方のようにすら思える。そして、観客の中にモヤモヤとしたものを残すことに、本作が「正しくない物語」として描かれた意義があるのではないだろうか。
おそらく『すずめの戸締まり』は、『天気の子』を超えて、新海誠監督作品の中で最も賛否が分かれる作品になることと思う。
そういう状況になることが間違いない作品を世に送り出す彼の勇気に敬意を表するとともに、長くなったこの記事にも「戸締まり」をしよう。