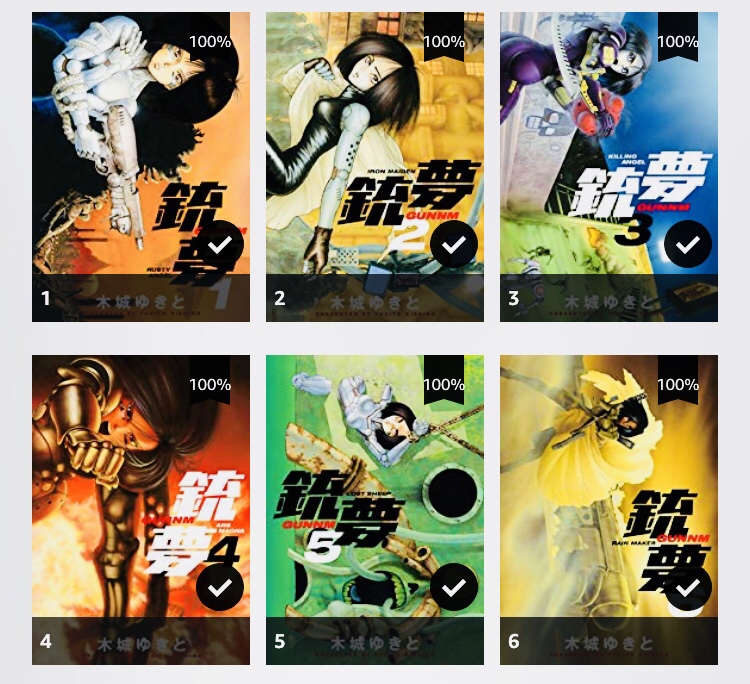まえがき
ヒーローの存在がもたらす希望を描くのが、一般的なヒーロー映画の在り方だと思う。
しかし、『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』が描くのはそれとは正反対の「ヒーローの不在がもたらす絶望」である。
ブラックパンサーないしティ・チャラという人物はあまりにも偉大な存在だった。
その偉大さは、本作で描かれた彼がいなくなったワカンダの混乱にも見て取ることができる。
物語の中で各国の首脳たちは、ティ・チャラを失ったワカンダという国がどのように行動するのかを注視していた。
彼らの関心はワカンダに生きる人たちがどうなるか?ではなく、ワカンダという国がどう動くか?なのだ。
観客の関心の中心もきっと似たようなところにあったのではないか。誰がブラックパンサーを継承するのか?ワカンダという国がどう変わっていくのか?
しかし、本作はそうした劇中の外部の人間あるいはスクリーンの外部の私たちの期待に反して、ひたすらにティ・チャラを取り巻く人々の物語を丁寧に描き続ける。
「大きな物語」は時を止めたままで、それを取り巻く「小さな物語」ばかりが静かに進行していくのだ。
「大きな物語」へすべてを還元するという暴力に対抗するには、取るに足りない個人の持つ細かなエピソードの一つひとつを、徹底して擁護するしかないではないか。
(『偽アメリカ文学の誕生』230ページより引用)
「ティ・チャラの死」というあまりにも「大きな物語」を前にできること。
ライアン・クーグラー監督は、人々の「小さな物語」を束にすることが、「ティ・チャラの死」を超える唯一の方法だと考えたのだと思う。
だからこそ、本作はもはやヒーロー映画などという枠組みに収まる作品ではない。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』は、人の生と死と、営みについてのフィルムである。
目次
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』解説・考察(ネタバレあり)
現実における死、虚構が直面する無力さ
©Marvel Studios 2022
現実世界におけるキャストの死に呼応する形で制作された映画の代表的な例として挙げられるのは、『ワイルドスピード スカイミッション』だろうか。
同シリーズの重要なキャラクターであるブライアン・オコナーを演じてきたポール・ウォーカーがまだ撮影が終わらない中で、交通事故で命を落としてしまう。
それに伴って、同作のラストでは、主人公のドミニク・トレットとブライアン・オコナーの別れが描かれた。
劇中世界におけるブライアンは生きており、主人公とは別の道を選んだという形で、その後のシリーズからはフェードアウトすることとなる。
ポール・ウォーカーが亡くなっても、彼の演じたブライアン・オコナーは『ワイルドスピード』シリーズの劇中世界のどこかで生き続けているという希望を残してくれた。
その後のシリーズでも顔を見せることはないが、彼がまだ生き続けていることを暗示する描写は多く、『ワイルドスピード ジェットブレイク』では、その後ろ姿が描写されている。
これらを踏まえて考えると、同作が選んだ現実世界のキャストの死との向き合い方は、現実の死とキャラクターを切り離すというアプローチであったと言える。
虚構世界が現実世界の死を切り離すことで、虚構世界におけるキャラクターの永遠性を担保する。これもフィクションの成せる現実の死との向き合い方のひとつだろう。
一方で、今作『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』は、現実の死に抗うことができない虚構という立場を取っており、現実と虚構を切り離すというアプローチを選択していない。
ダイレクトに言うのであれば、本来であれば切り離されているはずのチャドウィック・ボーズマンという俳優の死と、劇中のブラックパンサーないしティ・チャラの死が同一視して語られるのだ。
本作は、ティ・チャラが病気で命を落とすシーンから始まる。
映画なのだからいろいろと死の理由は設定できたはずだが、現実のチャドウィック・ボーズマンと同じ死因でキャラクターの死が描かれている。というよりヒーローが「病死」という描写そのものが珍しく思える。
このようにして、映画の中の世界と現実世界が1人の男の死をトリガーにして、鏡像のような関係へと陥る。
現実でチャドウィック・ボーズマンの死を悲しみ、悼む私たちと、スクリーンの向こう側でティ・チャラの死を悲しみ、痛むワカンダの人たちと。
MCUは、虚構ないしフィクションが現実に対してどんな力を持ちうるか、何ができるかを追求してきたところがあると思う。『ブラックパンサー』という映画は、その最たる例だった。
劇中で登場した「ワカンダフォーエバー」のポーズは、SNSで拡散され、黒人アーティストやアスリートの間でも広まりを見せ、今や現実とフィクションの境界を飛び越えて、1つの文化として根付いているようにすら思える。
また、ティ・チャラを演じたチャドウィック・ボーズマンは、現実世界でもヒーローであり続けた。
アメリカのディズニーリゾートにこんな壁画が作られたことはご存じだろうか。
「ワカンダフォーエバー」のポーズでチャドウィック・ボーズマンと患者衣を着た子どもが向き合う絵である。
その背景にあるのは、彼が生前から取り組んでいた黒人の子どもたちのための慈善活動や、自身も患っていたがん患者の人たちへの支援だ。
虚構が現実に対して無力であるという言説を発表し、当時注目を集めたのは、フランスの哲学者サルトルだ。
「飢えて死ぬ子供を前にして『嘔吐』は無力である」
「作家たるものは、今日飢えている二十億の人間の側に立たねばならず、そのためには文学
を一時放棄することもやむをえない」(1964年ル・モンド紙のインタビューより)
しかし、『ブラックパンサー』という映画ないしチャドウィック・ボーズマンという俳優は、虚構と現実の垣根を超えて、現実世界に確かな力を有していた。無力などでは決してなかった。
「賢者は橋を架け、愚者は壁を作る」という劇中での名台詞があるが、彼は虚構世界と現実世界にも橋を架けたと言える。
こう考えていくと、先ほど指摘した本作を巡るスクリーンの向こう側のワカンダの人たちと私たち観客の鏡像関係には、もう一つ重要な側面があるように思えてくる。
それは、ティ・チャラないしチャドウィック・ボーズマンという偉大な人物から何かを受け取った、受け継いだ者同士であるということではないだろうか。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』は、「受け取った者たち」が次にどう行動するのかを問う作品だったのだ。
ティ・チャラの不在がもたらす「混乱」を打破するもの
©Marvel Studios 2022
本作のスクリーンの向こう側で起きている出来事は、一言でいえば「混乱」としか言いようがない出来事の連続である。
ティ・チャラが前作の最後に、ワカンダの資源とりわけヴィブラニウムを世界に共有するという発言をしていたが、その方針は一貫されず、資源は依然としてワカンダが独占したままになっていた。
そのため、ヴィブラニウムを何とかして手に入れようと、先進国は秘密裏にワカンダに対して工作活動を展開している。
それは、かつて、アメリカ大陸やアフリカ大陸を侵略し、そこにいる人々やそこにあった資源を搾取してきた帝国主義、植民地主義の時代の歴史の繰り返しにも思える。
ワカンダの国の中でも、偉大な王の不在により、国内の民族たちの団結が瓦解し始め、リーダーとなったラモンダの求心力は低下の一途を辿る。
さらに、ワカンダは今作においてタロカン帝国という自分たちと同じような状況に置かれた国家の存在に直面した。
タロカン帝国は、圧倒的な力を持っている一方で、アメリカやフランスといった先進国による攻撃、搾取によって自分たちの国土や国民、資源が脅かされるのではないかと怯えている。
本来であれば、タロカン帝国とワカンダは手を取り合えるはずなのだ。
しかし、ここでもティ・チャラの喪失が暗い影を落とす。
自身の夫に続き、ティ・チャラを失ったラモンダは、シュリまでもを失うわけにはいかないとして、強行策で彼女を救出しようと試みる。
その結果として、タロカン帝国の市民を1人殺害してしまい、激怒したネイモアとワカンダは対立関係へと突入してしまう。
対立関係の中で、ラモンダは命を落とし、それに激昂したシュリは、怒りに身を任せてネイモアやタロカン帝国への復讐を誓う。手を取り合えたはずの者同士が戦う戦争が始まってしまうのだ。
他にもさまざまな形で「混乱」が描かれているわけだが、それらはティ・チャラが存命であれば、起こり得なかったものばかりではないだろうか。
ティ・チャラがいれば、先進国がヴィブラニウムを手に入れるために躍起になるような状況には陥らなかっただろうし、タロカン帝国と戦争状態に陥るなんてこともなかっただろう。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』の物語では、描かれる出来事や展開のすべての背後にティ・チャラの不在が影響している。
その状態を打破することができるのは、偉大な王ティ・チャラの存在だけなのだが、彼はもう亡くなってしまった。手詰まり状態である。
そんな絶望的な状況をどのようにして変えればよいのだろうか。
この答えになるのが、「ティ・チャラから受け取ったもの」なのだと思う。
ワカンダの人たちはティ・チャラから「受け取ったもの」を胸に前に進む。とりわけシュリは彼の思いや言葉を思い出し、タロカン帝国との戦いに終止符を打った。
記事の冒頭で、「大きな物語」と「小さな物語」の関係に触れた。
「大きな物語」に該当するのは、ティ・チャラが紡いできた物語、あるいはこれから紡ぐはずだった物語なのだろう。
しかし、「大きな物語」は失われてしまった。
そんな中でできることは、ティ・チャラから何かを受け取った者たちの「小さな物語」を束にして、未来を描き出すことではないだろうか。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』はこのようにして、「受け取った者」たちの物語にスポットを当て続けた。
多くのキャラクターの物語にスポットが当たるため、前作よりも散らかった印象になるのは無理もない。
しかし、束になった「小さな物語」たちが、確かにティ・チャラが紡ぐはずだった「大きな物語」の後を引き継いでいる。もう何も心配ない。
そして「受け取った者たち」というのは、劇中のキャラクターだけではないはずだ。スクリーンの前で映画を見ている私たちも確かに何かを受け取ってきたのだ。
目を閉じて、瞬間、心、重ねて
©Marvel Studios 2022
私たちの生きる現実世界でも、本作の劇中で起きたような様々な「混乱」が生じている。
私たちはテレビの報道やインターネットニュースなどで断片的にしか触れることはできないが、現在進行形でロシアとウクライナの戦争が起きている。
他にも紛争は私たちの知らない世界の片隅で依然として続いており、毎日のように人の命が失われているのだ。
なぜ、人と人は手を取り合うことができないのか、争うことでしか解決できないのか。
ドイツの哲学者であるマルクス・ガブリエルが著書の『世界史の針が巻き戻るとき』の中で戦争が起こるメカニズムについて次のように述べている。
もし我々が皆、普遍的なヒューマニティ(人間性)に気づいていたとしたら、残忍な戦争を始められるはずがありません。真の本格的な戦争を始めようと思ったときに求められるのは、相手の非人間化です。そうでなければ、相手を射殺することなどできません。
(マルクス・ガブリエル『世界史の針が巻き戻るとき』PHP新書)
私たちが残忍な戦争を始められるのは、相手のヒューマニティ(人間性)から目を背けてしまうからだと彼は指摘している。
ティ・チャラは前作でキルモンガーと死闘を繰り広げながらも、彼を生かす道を模索し続けた。そして、残忍に殺害してしまうのではなく、最後は美しいワカンダの風景を彼に見せ、一人の人間としての尊厳を保ったまま死なせた。
復讐心から生じる怒りを乗り越え、彼は相手の中にも同じように宿っている人間性に目を向けたのである。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』におけるシュリも一度は復讐心に囚われ、ネイモアやタロカン帝国を焼きつくそうと試みた。
しかし、目を閉じて彼女は思い出す。美しいタロカン帝国の風景を、そしてそこに生きる人たちの営みを。
自分たちが焼きつくそうと試みているのは、敵ではない、同じヒューマニティ(人間性)を持った存在なのだということを思い出すのだ。
現実世界で生きる私たちは一体何を「彼」から受け取ったのだろうか。そして受け取ったものを胸に何ができるのだろうか。
サルトルは文学は現実に対して無力であると語った。
しかし、ティ・チャラから受け取ったものを胸にワカンダの人たちが行動を起こせたように、この映画からそしてチャドウィック・ボーズマンから受け取ったものを胸に現実世界を生きる私たちが何か行動を起こせたとしたら。
「フィクションが現実に対して無力だ」という言説を覆す力があるのだとしたら、それは「受け取った者」たちの中だけではないだろうか。
物語の最後、ハイチの美しい浜辺でシュリは目を閉じる。そうして彼女はティ・チャラの存在を感じる。そして自分が彼から何を受け取ったのかを思い出す。
思わず映画を見ている私たちも目を閉じてしまう。心の中にじんわりと「彼」の存在が浮かび上がる。彼から何を受け取ったのかを思い出す。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』のラストシーンは、映画館という空間において、スクリーンの向こう側のキャラクターたちと、こちら側の私たちの心が重なる瞬間を演出している。
もちろん、その「架け橋」になるのは、ティ・チャラでありチャドウィック・ボーズマンだ。
現実と虚構の壁を超えて、私たちは「受け取った者たち」としてひとつになる。
偉大な1人が紡ぐはずだった「大きな物語」のその続きを、「受け取った者たち」の「小さな物語」が束になって紡いでいく。
バトンは確かに渡されたのだ。
『ブラックパンサー ワカンダフォーエバー』はヒーロー映画というには、あまりにも歪な映画だ。
なぜなら、そこに明確な「ヒーロー」がいないからだ。
では、どう形容すればよいのだろうかと考えたときに、こう思った。
「ヒーローと私たちの関係についての映画」なのではないかと。