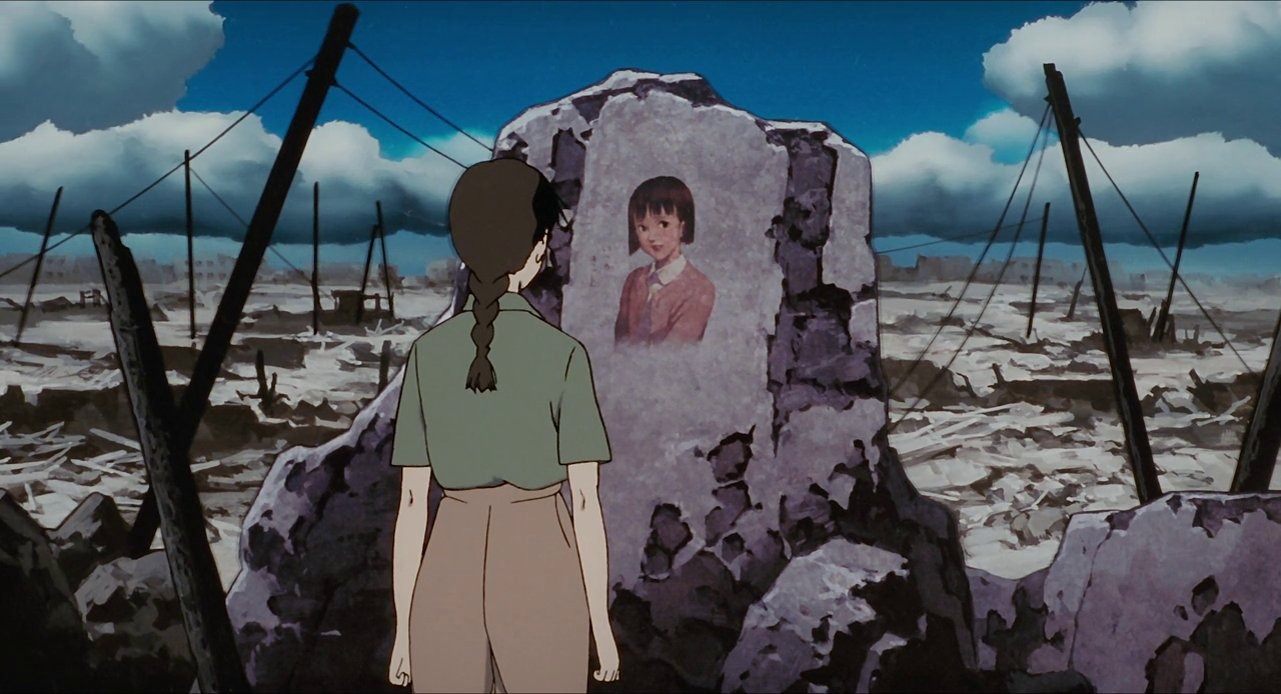『エンパイア・オブ・ライト』の主人公であるヒラリーはフィリップ・ラーキンやW・H・オーデンといった詩人たちと彼らが残した詩を愛している。
フィリップ・ラーキンの詩の中に『Trees』という10行の詩がある。この詩は映画の最後にモノローグで挿入されていた。
The trees are coming into leaf
Like something almost being said;
The recent buds relax and spread,
Their greenness is a kind of grief.Is it that they are born again
And we grow old? No, they die too,
Their yearly trick of looking new
Is written down in rings of grain.Yet still the unresting castles thresh
In fullgrown thickness every May.
Last year is dead, they seem to say,
Begin afresh, afresh, afresh.(フィリップ・ラーキン『Trees』)
この詩の第1節は、木が葉をつけていく希望に満ちた瞬間に言及しながらも、その光景あるいは葉の緑を「ある種の悲しみ」という対照的な言葉でラベルづけしている。
第2節の書き出しでは、私たち人間と葉たちを対比して、老いていく私たちの視点から何度も生まれ変わる葉に対する眺望が描かれた。
眺望がもたらす「彼らは老いないのか?」という疑問に対して「いや、葉もまた死ぬのである」と反語的に応答し、第3節を導く。
第3節では、そんな葉の視点から「去年(の葉)は死んだ、(私たちは)新しくなるのだ、新しくなるのだ、新しくなるのだ。」と力強く述べられている。
フィリップ・ラーキンの詩は、人生における「悲しみとの向き合い方」について教えてくれているのではないか。
生きていく中で、ずっと「光」の中でいられるなんてことはないわけで、時には「暗闇」の時間を経験しなければならないはずだ。
そうした「暗闇」の時間を経験したときに、私たちが前を向くために必要なマインドがこの詩には込められているように思える。
木々の葉たちもまたそうであるように、どんなものも「暗闇」の時間を経験している。それでも、葉が5月が来ればまた青く茂るように、いつかは「光」を取り戻すことができる。
『エンパイア・オブ・ライト』という作品が伝えようとしているメッセージは、このフィリップ・ラーキンの詩に重なっているように感じられた。
とりわけ本作は、映画という芸術とそれを裏打ちする「1秒間に24コマの静止画の光によるファイ現象」にそのメッセージを重ねている。
映画館のスクリーンに投影される映像は確かに暗闇の中でずっと輝いているように見えるが、その実情はそうではない。私たちが知覚できないだけで、光と闇が絶えず繰り返されているのが映画という芸術なのである。
どんなものも「光」と「闇」の間で揺れながら存在している。人もまた。
『エンパイア・オブ・ライト』は一見すると、映画についての映画だが、監督のサム・メンデス本人も述べているように、むしろ友情や愛情についての、そして何より人間についての映画だと思うのだ。
『エンパイアオブライト』考察(ネタバレあり)
細部の変化に託された心の変遷
撮影監督を務めたのが、ロジャー・ディーキンス(『ビューティフル・マインド』や『007 スペクター』でも撮影監督を務めた)であることも相まって、本作の映像は1つ1つのショットが細部に至るまで洗練されている。
例えば、主人公のヒラリーが自宅の洗面所で鏡を見るシーンが何度か使われていたが、この鏡は半分が開く仕組みで、中に洗面用品や薬品などを収納できるようになっていた。
この仕組みのために、洗面所の鏡の中央には「線」が入るのだが、この「線」の位置とヒラリーの顔の位置は、実は彼女の心の状態に対応している。
彼女の精神状態が上向いている、あるいは安定しているときは、彼女の顔が「線」を隔てた一方の鏡に収まるようになっていた。つまり「線」とヒラリーの顔が重ならないように配置されていたのである。
しかし、彼女の精神状態が良くないときには、この「線」がヒラリーの顔に重なるように配置されていた。彼女の顔が中央で引き裂かれているようにも見える、この描写は、彼女の心の模様を視覚的に映し出していると言える。
他にも、目につきやすいところで言えば、ヒラリーの自宅における光の取り入れ方は、彼女の心の状態に連動していた。
彼女の精神状態が上向いている、あるいは安定しているときは、自然光と室内照明のバランスが保たれている。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
カーテンが開け放たれており、窓から自然な白色光がレースを通して室内に入りこみ、それを補完するように室内にはいくつかの間接照明やろうそくの火が温かみのある光を提供していた。
一方で、彼女の精神状態が良くないときには、そのバランスが明確に崩されている。(あるいは彼女が意図してその調和を乱している)
例えば、欠勤が続いたヒラリーを気遣って同僚のスティーブンが自宅にやってくるシーンでは、彼女が自らカーテンを閉め、窓から入ってくる自然光を遮っていた。
ヒラリーがソーシャルワーカーに連れていかれる夜のシーンでは、照明がまばらで、室内が驚くほどに暗く、人物の顔だけがぼんやりと不気味に浮かび上がるような調整になっている。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
もはや光が部屋に行き届かなくなっている様は、彼女の感じている孤独感や閉塞感を視覚的に一層際立たせていると言えるだろう。
その他、飲み物がアルコールに変わったり、ろうそくの火がタバコの火に変わったり、音楽のジャンルやボリュームが変わったりと、さまざまな細部の変化がヒラリーの変化を構成している。
ここまで指摘したのは、ほんの一例に過ぎないが、その他にも挙げていけばキリがないほどに『エンパイア・オブ・ライト』は繊細な細部の変化にこだわっている作品だ。
そして、その細部の繊細な移り変わりにこそ、本作が描きたかったものが宿っているように思えた。
「変化」が教えてくれる「光」の温度、あるいは手触り
先ほどまで、本作の中で描かれた移り変わりについて、具体的な例を挙げながら語ってきたが、そうした「変化」は私たちに何を与えてくれるのだろうか。
『エンパイア・オブ・ライト』は映画の中にきちんと時間が流れている作品だ。
物語の冒頭は冬のシーンであったが、物語のラストシーンは新緑のシーズンとなっている。そこに至るまでの変化が映画を見ていると自然に感じられるのである。
また、朝と昼、夜のシーンが繰り返される構成になっているし、屋内のシーンと屋外のシーンが交互に訪れるのも特徴的だろう。
先ほどまでは視覚的な事物の変化にスポットを当てたが、こうした季節や時間、場所の変化が作品の中で連続的に生じる作りになっていることも、本作において「変化」が重要な意味合いを持っていることを裏づけている。
他にも「形」に注目するという視点も考えられる。
『エンパイア・オブ・ライト』は直線的な形と円形をうまく使い分けている。
エンパイア劇場は、直線的な形の組み合わせで構築された建築物である。とりわけロビーを見てみると、扉や窓、階段やその手すりなどが直線的な形である。故に冒頭のヒラリーの生活風景は、直線的なモチーフに支配されているわけだ。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
しかし、スティーブンと出会ったことにより、そんな生活に円形のモチーフやモーションが増えていくのは印象的だ。
屋上から見た花火は象徴的だが、その他にもローラースケート、社交ダンス、遊園地の回転するアトラクションなどがそうだし、何よりスティーブンがヒラリーに渡すプレゼントがレコードであることからも、意図して円の形を取り入れていることは明らかである。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
ただ、これほどまでに円の形に視線を誘導されてしまうのは、スティーブンが現れるまでの生活風景が直線的な形に支配されていたからに他ならない。
「変化」に伴って何かが与えられる、あるいは奪われると、その何かの存在を私たちは強く意識せざるを得ない。
窓から光が入りこんでいるのが当たり前だったからこそ、カーテンを閉めることでそれが失われることを強烈に意識させられるし、直線的な形に裏打ちされた風景を連続的に映し出してきたからこそ、空に上がった円形の花火に何かが動き出す予感を感じずにはいられない。
「変化」が与えてくれるのは「気づき」だ。
私たちの脳は1秒間に24コマの静止画の連続に騙されてしまうほどに鈍感である。
だからこそ「変化」が生じることでしか、私たちが目を向けない何かがあり、意識することができない何かがある。
本作では、ヒラリーとスティーブンの関係にそうした「変化」の重要性が見て取れる。
物語を通じて2人にとってお互いの存在が当たり前になっていく。お互いの存在が日常になっていく。そして、お互いの存在が失われて、初めて気がつく。
ヒラリーにとってはスティーブンが、スティーブンにとってはヒラリーが「光」だったのだということにだ。
彼らがそう実感することができたのは、「変化」が生じたからであり、もっと言うなればお互いがお互いを失った「暗闇」の時間があったからである。
「暗闇」の中でしか「光」の存在には気づくことができない。
本作のファーストシーンは、主人公のヒラリーがエンパイア劇場の館内の照明のスイッチを入れて回るというものだった。
無機質な建築物に少しずつ命を宿していくような行為にも見えるそれは、私たちに照明の存在を強く感じさせる描写にもなっている。
日常生活の中で照明の存在に思いを馳せる人は少ないだろうし、同様に劇場の館内を何気なく映したシーンを見て、わざわざ照明に目を向ける人は少ないだろう。
しかし、劇場の館内の照明を灯すという行為とそれに伴う風景の「変化」を描くことで、私たちは当たり前すぎて目もくれなかった照明の存在を強烈に意識するようになる。
また、昼の屋外のシーンがインサートされるからこそ、夜の屋外のシーン、あるいは室内のシーンで照明の存在が際立つ。
光が当たり前に供給されている環境に身を置いていると、私たちはそれに注意を払うことはない。しかし、光が失われた環境に身を置くと、それが照らしてくれることのありがたさを痛感せずにはいられない。
『エンパイア・オブ・ライト』は、「光」だけでなく、その温度や手触りを知覚させてくれるものとしての「暗闇」をも肯定していると言える。
そして、それがそのままヘンリーとスティーブンの物語へのアンサーとなっている。
苦痛や恥を経験しなければ、幸福や喜びを経験することもできない。それらは絶え間ない「変化」の中に共存するものである。
『エンパイア・オブ・ライト』の物語の最後には、ヒラリーとスティーブンのしばしの別れが描かれていた。
別れが2人にもたらすのは、「暗闇」の時間なのかもしれない。
しかし、ヒラリーも、スティーブンも、希望に満ちた表情をしている。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
2人はもう知っている。
「変化」を恐れる必要がないことを。
「暗闇」を照らしてくれる「光」の存在を。
夜道はいつだって、少し寂しくて、心細い。
でも、本作を見終えた帰り道は、街灯の光がいつもより明るく、そして温かく感じられた。
その「温かさ」に気づくことができただけで、『エンパイア・オブ・ライト』という作品を鑑賞した価値があると思える。
おわりに:暗闇と光だけの空間としての「映画館」
『エンパイア・オブ・ライト』はここまでも述べてきたように「変化」を描いた作品だ。
そんな作品の中で変わらないものとして描かれていたのが、エンパイア劇場、つまり映画館だったのではないかと思う。
©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
エンパイア劇場は、アールデコ調の建築物で、周囲の建物と比較しても、そしてマーゲイトの海辺のモノトーンな風景の中でも異質な存在感を放っている。
何だかエンパイア劇場だけが、時代や社会、街の「変化」に逆らって、そこに留まり続けているような印象すら与える。
この描写の仕方には、作り手の「映画館」という空間に対する願いが投影されているような気がしたし、何より「映画館」とは何たるかを体現しているようにも思えた。
「映画館」が私たちの日常生活に対して提供してくれるのは、「変化」だ。
暗闇と、そして静寂に包まれた空間で私たちは日常から切り離される。
そこに突如として投影されるまばゆい光は、私たちを「誰かの物語」に巻き込んでしまう。
やがて光は失われ、私たちを再び暗闇と静寂が包み込む。
そうして、ぼんやりと明るくなったスクリーンを後にして、私たちは日常へと戻っていく。
これが「映画館」が提供してくれる体験の本質であり、それに取って代わるものはない。
コロナ禍で映画業界は壊滅的な打撃を受け、映画館もその数を減らしたことは間違いないだろう。それでも、映画館は無くならなかった。
人が「変化」を求め続ける限り、映画館は変わらずそこにあり続けるのだ。
「暗闇と光だけで構築された空間」が長きにわたって人々を虜にし続けるわけが、『エンパイア・オブ・ライト』という作品には確かに描かれていたのではないかと感じた。