アイキャッチ画像:(C)Melinda Sue Gordon/TWC 2008
はじめに
みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『愛を読むひと』についてお話していこうと思います。
本記事は当ブログで現在実施中のリクエスト考察の第2弾になります。第1弾の『ララランド』の考察記事のリンクも以下に掲載しておきますので、良かったらご覧ください。
ではここから『愛を読むひと』の考察へと移っていきます。良かったら最後までご覧ください。
あらすじ・概要
ベルンハルト・シュリンクのベストセラー小説「朗読者」を、「めぐりあう時間たち」の監督&脚本家コンビが映画化。
1958年のドイツ、15歳のマイケルは、21歳年上のハンナとベッドを共にし、彼女に頼まれて本を朗読してあげるようになるが、ある日突然、彼女は姿を消す。時は流れ、戦時中のある罪を問われて投獄されたハンナのために、マイケルは物語を朗読したテープを刑務所に送り続けるが……。
第81回アカデミー賞でケイト・ウィンスレットが主演女優賞を受賞。
(映画comより引用)
ハンナの文盲に見るドイツ人の罪
まずベルンハルト・シュリンクの『朗読者』の映画版である『愛を読むひと』を語っていく際に、ナチスの諸問題から目を背けることはできないでしょう。本作は法律学者でもあるシュリンクが著した作品を原作にしていて、それがゆえにアウシュビッツ裁判を法的な側面から考えようとする姿勢が反映されています。
そのため劇中のアウシュビッツ裁判や、現実の法律学の在り方に乗っ取った講義シーン(教授の解説)なんかも印象的で、作品の重要なパートを構成しています。
当ブログではナチス・ヒトラー・ホロコーストの関連映画作品のおすすめを紹介した記事を書いておりますので、良かったらこちらもご覧ください。
さて、では本作『愛を読むひと』がどういった視点で、ナチスの戦争犯罪に斬りこんでいったのかというと、それはラルフ・ジョルダーノが自身の著書として発表した「第二の罪」に通じる視点です。
この著書の中で述べられている「第一の罪」というのは、もちろんナチス政権下でドイツ人が犯した罪のことです。では、「第二の罪」とは何を指しているのでしょうかと言いますと、それは当時ドイツ人が犯した「第一の罪」を否定し、抑圧することです。
戦後のドイツの歴史はそんな過去の克服の歴史でもあります。国民が自分たちは直接加担していないんだといった責任転嫁、自分よりも罪人はたくさんいるはずだという責任逃れなどに傾倒し、多くのドイツ人が自分がナチスドイツに加担していた1人であるという事実から目を背けようとしたのです。
「法」に則って誕生したナチス政権の「罪」を「法」によって裁くという法の限界を描いたところがシュリンクらしい作品ではあるのですが、それ以上にスポットを当てたいのが、ハンナを巡る裁判のプロセスです。
ロール教授が「アウシュビッツで働いていただけでは罪にならない」と発言していましたよね。大切なのは「意図」があったかどうかで、それを証明するのが裁判であるとしていました。
しかし、そう考えるとナチスドイツの熱狂の渦に自ら身を捧げていったドイツ国民全体にその嫌疑がかけられてしまうのではないでしょうか。ナチスはなんら非合法な手段を使って政権を奪取したわけではありません。あくまでも法に則り、合法的に誕生した政権なのです。
つまり国民全体がその罪へと至るスイッチを押してしまったわけですよ。それにも関わらず、戦争が終わると、一部の関係者のみが戦争犯罪人として「正義」の名の下に裁判を受け、罪を背負っているのです。誰もが自分が犯した「第一の罪」から目を背け、自分の罪はなかったと主張するのです。
劇中の裁判のシーンでハンナの同僚の監守だった女性たちもそうです。彼らもまたハンナと同じだけの罪を犯していたのにも関わらず、彼女に罪を押し付け自らの減刑を図ったのです。そしてそんな裁判の経過を見守りながら、ドイツ人たちは自分の罪から目を背け、「正義」は行使されていると錯覚し始めました。
だからこそハンナが文盲であるという事実がここで重要な意味合いを孕んできます。なぜなら戦後のドイツ人は皆自分が犯した戦争犯罪に対して「文盲」だったからです。彼らは自分がナチス政権に加担していたという過去の事実を「読めない」ふりをし、責任逃れをしてきたのです。
そんな中でハンナは真に「文盲」であり、自分がしたことの意味すら把握できていないにもかかわらず、自分が戦争中に看守として成したことを正直に告白し、そして罪を背負うこととなります。そして刑務所の中で彼女は文字の読み書きを習得し始め、それがために自分が犯したホロコーストの罪をまざまざと突きつけられます。
『愛を読むひと』におけるハンナというキャラクターは当時のドイツ人に対するアイロニーでありながら、今までの、そしてこれからの世界を生きる全人類に対する警鐘でもあります。
人類は重苦しい過去を「読むこと」を放棄し、その事実からどんどんと目を背けていくものです。その結果として記憶や歴史の風化が起こります。そうして人々の間からその「過去」が消え去った時、歴史は再び繰り返されます。大切なことは「文盲」のふりをして、過去から目を背けないことです。「文盲」を恥じ、必死に文字の読み書きを習得しようとしたハンナの姿には、これからの我々のあるべき姿を見ることもできます。
それこそが『愛を読むひと』という作品が、当時のドイツ人に対するアイロニーに留まらず、現代にいたるまで普遍的な影響力を有し続けている所以でもあります。
スポンサードリンク
「変わる」こととその受容を描いた優しい物語

本作の主人公は映画版に関して言うならば、あくまでもマイケルということになると思います。彼に焦点を当てていくと、この映画は「変わる」こととその受容を描いた優しい物語と定義できるのではないかと考えています。
マイケルは15歳の頃に20歳以上も年上のハンナに偶然助けられ、その時の出会いがきっかけで身体を重ねるようになります。2人は何度も何度も逢瀬を重ねるようになり、愛を深めていきます。しかし、ハンナは自分の「文盲」が発覚しそうになると、仕事を変えるようにしていて、そのタイミングで彼女はマイケルの下を去るんですね。
そんな「青い体験」を忘れることが出来ないマイケル。それに加えてその秘密を誰にも語ることが出来ず、同世代の女の子とも上手く関係を結ぶことができないマイケル。彼はハンナに執着するあまり、彼女との甘美な日々が忘れられず、その思い出に囚われて変化することが出来ないんですね。
だからこそ彼は結婚しても妻とは上手くいかず、離婚してしまいますし、娘とも良い関係を築く事ができませんでした。
一方で、ハンナはというとどんどんと変わっていきます。そのためあの頃の「青い体験」の思い出の中にいる彼女に固執し続けているマイケルは、そんな彼女の変化を受け入れることが出来ませんでした。
戦争犯罪人として法廷に出廷した彼女との再会。この出来事がいかにマイケルに心的な影響をもたらしたかは計り知れません。彼の中の綺麗な記憶が音を立てて壊れていったのです。
その後、ハンナの罪が確定するとマイケルは自身が朗読した音声を吹き込んだテープを彼女に送るようになります。それを受けて彼女は少しずつ文字の勉強をするようになり、マイケルに手紙を送るようになります。
しかし、マイケルは彼女からの手紙を机の引き出しの中に保存していくだけで、一向にその返事を書こうとはしないんですね。この点に疑問を感じた方は多いのではないかと思います。ただマイケルが過去の「青い体験」の中のハンナに囚われていることを鑑みると、その理由は極めて単純明快です。
マイケルは「変化」を望まなかったんですよ。自分の中にいるあの頃のハンナを聖画のように捉え、その清く美しい姿が変わっていくのが、あの頃の関係性が変わっていくのが怖かったんです。彼が最初の朗読に『オデュッセイア』を選んだのも示唆的で、これはかつて一度彼が彼女に朗読してあげた作品ですよね。
だからこそ彼はあの頃の関係性のままでいることを望んだのです。それが自分が彼女の「朗読者」という立位置を維持し続けることにありました。そうすれば、マイケルはあの「青い体験」の続きをいつまでも味わっていられるような錯覚を抱いていたのでしょう。
そしてハンナの釈放が決まった際に2人は再会します。しかし、マイケルはハンナに対して冷たく当たります。年月が経ち、容姿は老い、文字が書けるようになり、そして自分の犯した罪に対する認識をも大きく改めた彼女は、マイケルが心の内に秘めている聖画のハンナとは似ても似つかない姿でした。それゆえに彼は、そんな彼女の変化を受容することに葛藤しました。
しかし、そんな矢先にハンナは、文盲を克服したことでホロコーストに関する書物を読み漁るようになり、そして自分の犯した罪の重大性を知り、自らの命を断ちました。
このハンナの死にマイケルは深い後悔と自責の念を感じたのでしょう。自分は「変化」したハンナを受け入れることが出来なかった弱い人間であると突きつけられたのですから。
その出来事がマイケルに小さな変化をもたらします。これまで誰にも話したことが無かったハンナが文盲だったという事実をユダヤ人の生存者に伝えます。さらにはこれまでうまく関係性を築くことが出来なかった娘にも、ハンナのことを話す決意をします。
この映画版の『愛を読むひと』で描かれたラストというのは、まさにマイケルが変化を受け入れて、前に進む決意をした証であり、そんな彼の小さな一歩を優しく包み込むような幕切れでもあります。
その一方で、ハンナはどうだったのでしょうか。彼女はもはやマイケルを愛してはいなかったのでしょうかという問いは当然浮上してくるものと思います。実はこの点に関しては原作の『朗読者』を読むと、それを仄めかす描写がはっきりと書いてあるんです。
残念ながらその描写は映画版ではカットされているんですけどね。ただ注目すべき点があるとしたら、ハンナが刑務所の図書館で「犬を連れた奥さん」を借りるシーンですね。
このチェーホフの小説はかつてハンナとマイケルが逢瀬を重ねていた頃に、マイケルが朗読した小説です。これってすごく単純に説明してしまうと不倫小説なんですが、劇中のハンナとマイケルを重ねることも出来てしまう内容です。
ヤルタでドミトリーという男がアンナという女性と短い期間の間だけですが、結ばれて、その後は別れてしまうのですが、その刹那の記憶が忘れられず、2人は再会し、モスクワで再び逢瀬を重ねるようになるという物語です。
これをハンナが図書館で借りているというワンシーンはまさに彼女のマイケルに対する愛情は変わっていなかったということを仄めかしているようにも取れるわけですね。
年月が経って、多くのものが変わってしまった中で、それでも変わらなかった愛。そんな2人が迎えた結末が切なく、どこまでも哀しいですね。
文盲のユダヤ人支援のための寄付金に



さて、本作の終盤にハンナがユダヤ人の女性のために残したお金をマイケルが手渡しに行くシーンがあります。しかし、その女性はお金を受け取ろうとはせず、代わりにマイケルはそのお金を文盲のユダヤ人支援のために寄付することを提案します。
なぜ文盲のユダヤ人に対する支援金にしようと思ったのか、という点に関して疑問を持った方はいませんか。単純にユダヤ人に対する贖罪ということであれば、何も文字の読み書きを教える施設に限定する必要はなかったと思うんです。
この点について解説していくには、まず映画版では描かれなかった(カットされてしまった)ハンナのとある設定について知っておく必要があります。この設定が彼女が文盲であることにも繋がる重要設定なんですが、映画版ではなぜかカットされていましたね。
その設定というのは、ハンナがロマ族であるということです。このロマ族というのは、実はユダヤ人以上に当時迫害されていた民族なんですよ。「ジプシー」と呼ばれた彼らは長年ドイツないしヨーロッパで迫害の対象とされていました。それこそがハンナが文盲である理由でもあります。
つまりハンナというキャラクターもまた迫害される側の立場だったんですね。そしてそれがために文盲のまま大人になり、そして文盲であるがために、無意識的にナチスの戦争に加担してしまい、罪を背負ってしまったというすごく悲劇的な人生を送っているのがハンナという人物なのです。
そう考えると、マイケルがユダヤ人たちの読み書きのための施設に寄付すると申し出たのには、2つの意味があるように思えます。1つには、ハンナのユダヤ人に対する贖罪を果たすことです。これは自明です。
ではもう1つはというと、それはマイケルのハンナに対する祈りと救済なんですよね。彼はハンナという女性の、文盲がゆえの哀しすぎる人生に触れてしまいました。だからこそそんな哀しみを背負って生きる人がこれ以上生まれないように、マイケルは願っているのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
シュリンクの原作『朗読者』の方が個人的には好きなので、映画版の評価がそれほど高くはないという思いはあるんですが、『愛を読むひと』の方が少しマイケルにもハンナにも希望が差し込む形で物語が描かれている点に関しては良かったと思います。
原作はひたすらに重苦しいので、映画版の新しい解釈として、希望を描いたのは正解だったと思います。ただカットされている部分にいくつか重要な情報が隠れているので、併せて原作も読んでいただきたいというのが本音です。
またナチス映画としても、テーマ性が普遍的で、今を生きる我々が見るべき作品とも言えます。特に第2次世界大戦で敗北したという点で同じ立場にある日本人だからこそ、この作品を見て、学ぶところがあるのではないかと考えています。
今回も読んでくださった方ありがとうございました。










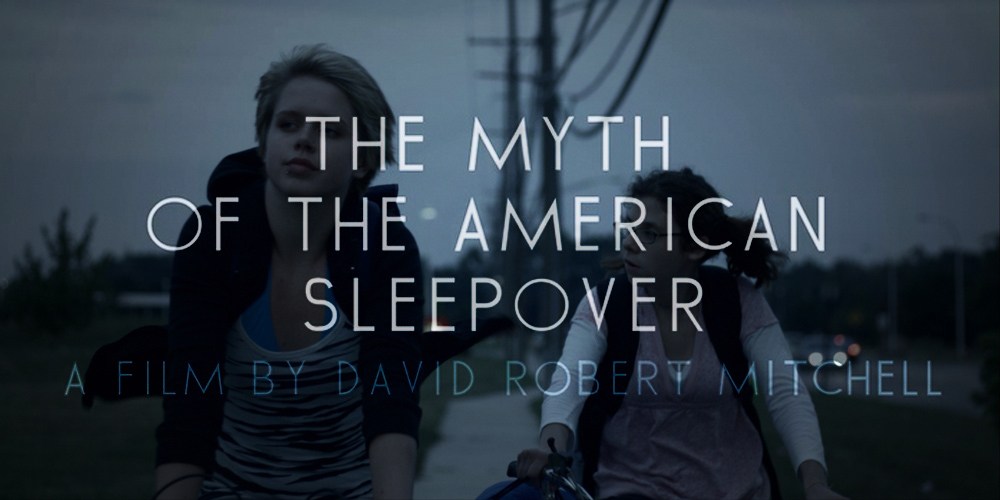
はじめまして。ロシアのウクライナ侵攻が始まってから、この映画の事をよく考えてました。
自分の感じた事を言語化するのが得意ではありません。なので、ナガさんの解説で自分の中のモヤモヤした思いが少し整理されました。ありがとうございます。
私は、幼い頃中東に住んでました。クウェート人やシリア人の友人がいます。仲の良いアメリカ人の友人は、中東での戦争は必要なものだった、と言いました。
今回、日本に住むロシア人の友人は、精神的に動揺し、家から出られなくなってます。ロシア人でいたくない、と泣いてます。彼の弟は、ロシア軍に所属しており、今どこにいるのかわかりません。
人は、国を選んで生まれてはこれません。肌の色や言語も。正義とは何か。育った環境で価値観が変わる。なのに人は人を裁けるのか。正義とは、何か。
2回目にこの映画を観た後、耐え難い過去を持ち続け豪奢なマンションに住み洗練されたで身なりのユダヤ人。文盲を克服し自分の罪を収容所で知り、身なりも構わなくなってしまった年老いたハンナ。両者の対比が心に刺さりました。共通するのはどちらも望んでその立場になったわけではない、ということ。
世界は、何度この悲劇を繰り返すのでしょう。
原作も読んでみます。
ナガさんの考察には、人間愛を感じました。こんな時だからこそ、私も人を信じたいです。