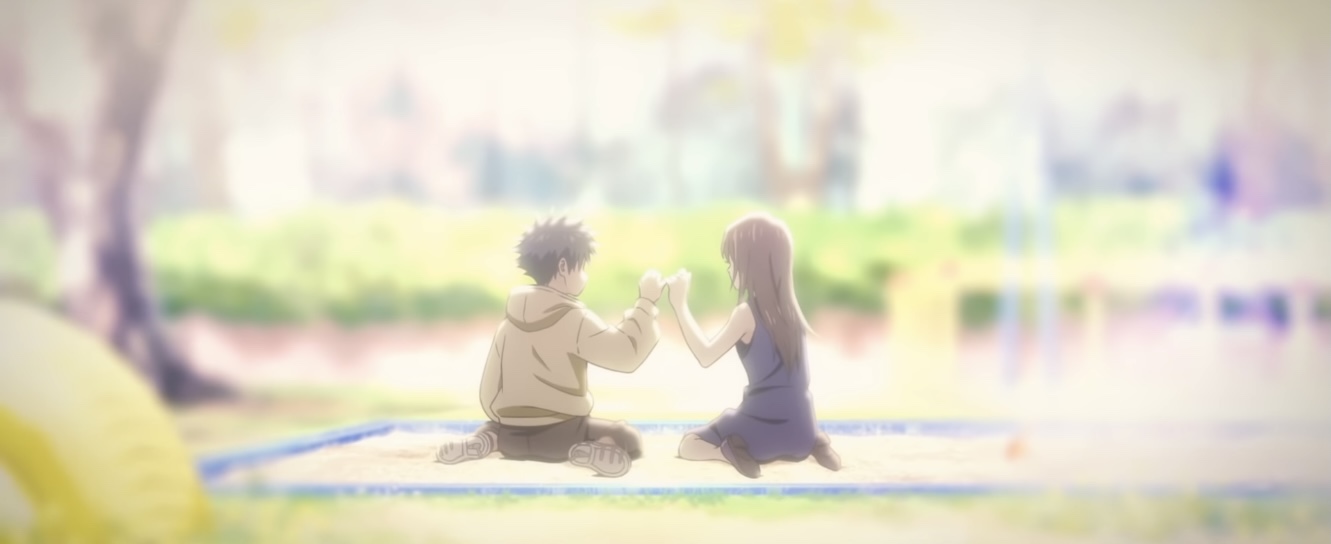本記事は一部、作品のネタバレになるような内容を含みますので、鑑賞後に読んでいただくことを推奨します。
空に煌々と輝く月。欠けのない満月だ。
刹那、月を捉えていた「カメラ=視点」は落下を始め、グルグルと回りながら、どこにでもあるような町の一軒の家の中へと転がり込んでゆく。
文学的な風景描写のオープニングショットからの、観客の不意を衝く落下のモーション。
文学作品でもなく、マンガでもない。これはアニメーションであり、映画なのだという作り手の矜持を感じさせるオープニングシークエンスの時点で、この映像作品への信頼はもはや揺らがないだろうと確信した。
(どことなく『フォレスト・ガンプ』のオープニングシークエンスを思わせるのは、作品に散りばめられた映画へのオマージュの1つだろうか)
実は、映画を見終わった後に、藤本タツキの原作を初めて読んだのだが、前述の描写が存在していないことに真っ先に驚いた。原作はいきなり教室のシーンから始まっていたのである。
加えて、本作のクライマックスのシーンでも、月は映画版では極めて明確に描かれ、存在感を放っていたが、原作では、描かれていなかった。
月は狂気と結びつけて描かれることの多いモチーフである。
英語にmoonstruck「気がふれた」、lunatic「精神異常の」といった言葉が存在することが、それを裏打ちしている。
あるいは『ルックバック』という作品の物語性と月というモチーフをあわせて考えたときに、浮かんでくるのはサマセット・モームの代表作『月と六ペンス』ではないだろうか。
同作の新潮文庫版の訳者あとがきに、『月と六ペンス』というタイトルについて、以下のような分析が綴られている。
「(満)月」は夜空に輝く美を、「六ペンス(玉)」は世俗の安っぽさを象徴しているのかもしれないし、「月」は狂気、「六ペンス」は日常を象徴しているのかもしれない。
(サマセット・モーム『月と六ペンス』(新潮文庫)より)
芸術家ないし創作者にとって、月に手を伸ばすという行為は、創作活動そのものであり、その狂気に身を委ねることで、世俗や日常を手放すということなのか。
映画『ルックバック』の物語の冒頭で、藤野の部屋から見える月は欠けているところのない美しい満月であった。
それは、彼女にとってのマンガ家という職業に対する漠然とした幻想として描かれているように見える。
何も失うことなく、ただ富や名声、その他の何もかもが満たされた人生がイージーに手に入る。彼女はあの時点では、無邪気にそう思っていたのだ。
しかし、京本の描いた4コマのマンガが彼女のそんな幻想を木端微塵に打ち砕いてしまう。
マンガ家というポジションが、何も失うことなく、何も欠けることなく、手に入るものではないと自覚した彼女は、それまでにもまして創作活動にのめり込むようになる。
原作でも、映画版でも、このプロセスは、黙々と机に向かう藤野の後ろ姿と移り行く窓の向こうの風景や、彼女の背後から人がいなくなっていく様の対比によって演出されているが、実に残酷である。

まるで、創作とは、現実に「背」を向けて、孤独にも自分の生み出す世界に向き合い続けることなのだと言わんばかりの覚悟を感じる描写であり、思わず身震いをするほどだ。
そうやって、彼女なりに何かを手放して、創作と向き合ったにも関わらず、京本はその遥か先にいた。どんなに手を伸ばしてもその距離が埋まらないと悟った藤野は創作活動から足を洗ってしまう。
まず、ここまでの一連の描写が原作にしても、映画版にしても、とにかく見事である。
映画版は原作に忠実ではあるが、アニメーションならではの妙が加えられている。
例えば、藤野が初めて京本のマンガを見るシーンで、教室の人間がコピペしたように増殖する原作にはないカットがあった。
このカットには、藤野の自身の才能への過信が打ち砕かれ、自分が凡庸なone of themであることを思い知らされたときの心理を際立たせる効果がある。
話を戻すが、創作から足を洗った藤野を、創作の狂気へと連れ戻すのは、京本との出会いと彼女の言葉だ。
どうでもいいと思っている100人に認められるよりも、一目を置いているたった1人に認められる方が、ずっと自分の身体と心を動かすことがある。そういうむず痒い喜びが雨の中をスキップしていく藤野の表情とモーションに見事なまでに投影されている。
絵を成す線は均質化されたそれとはかけ離れた、荒々しく不安定なものだったが、作り手の魂が宿っていたし、藤野の青くも激しい初期衝動が確かに描かれていた。アニメーションを見る原初的な喜びを感じずにはいられない、本作のハイライトだろう。
『ルックバック』は物語の終盤のセンセーショナルな描写に注目が集まりがちだが、私はむしろ、物語の前半の創作に向き合う者の背中や初期衝動の描き方にこそ感動を覚えた。
ここから、物語の後半部分にも目を向けていくが、藤野が冒頭に見ていた満月に最も手が届きそうになった瞬間は、少年誌のコンペで入選し、10万円を握りしめて、京本と東京へと繰り出した日だったのだと思う。

「おうち買えちゃうよ…」「買う?家」という2人のやり取りにも垣間見える、藤野の10万円に対する過信と無邪気な全能感は、マンガ家になれば、何もかもが手に入ると信じている心情から出たものだろう。
しかし、2人が街に繰り出し、さんざん豪遊した結果として、「じゃんじゃん使ったのに5000円しか使わなかったなあ…」という言葉がこぼれる。
10万円という(中学生にとっての)大金に対する過信と全能感を喪失し、マンガ家という手の届かないものにあった存在が自分の日常になっていく予感をひしひしと感じさせる。
そのセリフを境に、物語のクライマックスに向かって、藤野にとっての「欠け」が描かれていくこととなる。
マンガ家になるという夢を叶えても、やることは窓に向かい、現実に背を向け、ひたすら創作活動に没頭することだけという描写が、思い描いていた理想とそれを手に入れた現実のギャップを強烈に描き出していた。
京本との方向性の違いによる決別も藤野にとっての「欠け」だし、彼女のスマートフォンに仕事の関係者と家族以外の連絡先が少ないことも「欠け」だ。あるいは、彼女の求める水準に達するアシスタントの不在も映画版で加えられた「欠け」の1つだろう。
あの頃、あんなにも満ちていて輝いて見えた丸い月が、思っていたよりもずっと欠けた不完全で満ち足りないものだったと知る。
そんな欠けた月が、映画版では物語のクライマックスで明確に描写されている。(原作では描かれていない)
月の変化に人物の感情の変化を重ねる手法は、どこか中島敦の『山月記』を思わせる。
そして、映画『ルックバック』は欠けた月にどう向き合うかというところに、作り手としての覚悟を示し、物語を締めくくっている。
作者から読者への反転。藤野は作者でありながら、一時的に自身の作品の読者としての立場を追体験する。
すると、欠けた月のようにぽっかりと穴の空いていた心が満たされたような気持ちになっていき、思わず涙がこぼれる。
サマセット・モームの『月と六ペンス』が、世俗から切り離されたところに芸術家の美徳を見出した一方で、『ルックバック』は、藤野の「ふり返る」という行為を通じて、創作者が現実(あるいは日常や世俗)とは完全に独立した存在になることの不可能性を描いている。
私たちの現実は欠けと喪失で満ちている。
それを事実として無かったことにはできない。
しかし、創作はその欠けや喪失を「満たす」ことはできるかもしれない。

有を無に帰す者と、無から有を生み出す者の強烈なまでの対比。
欠けた月を豊かで美しい満月に見せることができるのが、創作の可能性なのである。(あるいは欠けた月そのものを美しいと印象づけることだってできる)
藤野が窓に貼りつけた空白の4コマは、月の欠けた部分に重なる。
現実世界を切り取った窓の風景に、ぽっかりと空いた4コマ。
描き続けることで、自らはすり減り、失い、欠けていく。
そんな宿命を背負いながらも、誰かを、何かを「満たし」続けていくのだという力強い決意表明に、心が動かないはずがないだろう。