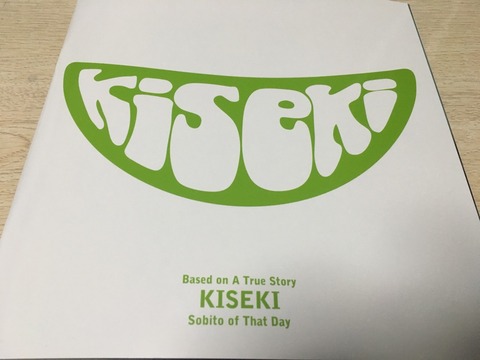みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ドロステのはてで僕ら』についてお話していこうと思います。

劇団ヨーロッパ企画ないし上田誠さんと言えば、やはり『サマータイムマシンブルース』ですよね。
当ブログ管理人の方は、舞台の方は見たことがなくて、映画の方だけなのですが。
昨日と今日を行き来するという何ともミニマルなタイムトラベルSFでして、昨日でめちゃくちゃをしたつじつまを合わせるため過去を元通りにしなければならないという展開になり、奮闘するというコメディタッチの物語になっています。
この『サマータイムマシンブルース』の設定や空気感が好きな人は、今回の『ドロステのはてで僕ら』も絶対に気に入ると思います。
また上田誠さんが原案を描き、それを森見登美彦さんが文章化した『四畳半タイムマシンブルース』という派生作品が最近発売されまして、こちらも非常に面白いのでおすすめです。
プロットは『サマータイムマシンブルース』にそっくりですが、そこに『四畳半神話大系』の個性的なキャラクターたちが絡むことで、また新たな展開が生まれます。









さて、今回お話する『ドロステのはてで僕ら』の方に話題を移していきますが、そもそも「ドロステ」って何だ?と多くの方が思ったかもしれません。
これは、劇中でも登場したオランダで販売されていたドロステ・ココアのパッケージが由来となってできた、1つのイメージが再帰的に反芻されていく視覚的な効果のことを指します。
尼僧がパッケージに描かれているのですが、彼女がお盆にのせているドロステ・ココアの箱にも同じ尼僧が描かれていて、そのパッケージの中の尼僧も同じようにドロステ・ココアの箱をお盆にのせているという構図になっているわけです。
この視覚的な効果を、今回はタイムトラベル系のSFに落とし込み、1つの店とその店主の家を行き来することで展開するミニマルなプロットに仕上げています。
何か大きな展開があるわけではないのですが、何だかばかばかしくて、でも面白いというまさしく劇団ヨーロッパ企画ないし上田誠さんらしい作品になっておりますので、ぜひご覧いただきたいですね。
そしてキャストという側面で見ると、朝倉あきさんが出演しているので要注目です。
朝倉あきさんがこの作品を見て、気になったという方は『四月の永い夢』をすぐに見てくださいね。こちらもおすすめです。
さて、今回は本作について自分なりに感じたことや考えたことを綴っていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む感想・解説記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『ドロステのはてで僕ら』感想・解説(ネタバレあり)
1つのアイデアを絶妙な反芻と多彩な展開で魅せる
(C)ヨーロッパ企画/トリウッド2020
『ドロステのはてで僕ら』という作品は、基本的にドロステ効果を利用したタイムマシン(モニター)が登場するというワンアイデアから発展して作られています。
ワンアイデアものの作品って、最初は奇抜で面白いのですが、30分くらいすると慣れてしまって、徐々に飽きてしまうという傾向がありますよね。
どんなに奇抜で、斬新なアイデアだったとしても、それを反芻し続ければ、当然鑑賞する側はその刺激に慣れてしまいますし、ワンアイデアで60分を超える長編映画を構成するというのは、至難の業です。









ただ、今回のようなドロステ効果を利用したタイムマシン(モニター)が登場するという少し複雑、劇中の言葉を借りるならば「込み入った」設定を扱う際はもう1つ注意すべき点があります。
それは、観客が理解しているであろうという前提で速く物語を展開させ過ぎないことと、その一方で過剰なホスピタリティを見せて説明的にならないようにすることです。
当ブログ管理人はSFが好きなので、結構こういった複雑性のある作品も見たことはあるのですが、自分の頭の中に構造を落とし込んで、理解に至るまでは少し時間と説明を要します。
ですので、ある程度は説明をした上で、観客の理解が追いついた段階で次の展開を見せるというタイミングの見極めが重要になっていきますよね。
それに加えて、説明が過剰すぎたり、分かり切っている展開を見せすぎたりすると、見ている側としては「分かったからそろそろ違うものを見せてくれよ。」という心情になってしまい、物語から心が離れてしまいます。
『ドロステのはてで僕ら』は、さすが上田誠脚本といったところか、そのあたりのタイミングやバランス感覚が非常に優れていました。
冒頭に、主人公のカトウが1人で不思議なテレビの現象を確認し、そしてそこに事情を知らないキャラクターが介入してくる。さらに「ドロステ効果」を持ち込む物語のキーパーソンが現れて、この現象の理解を観客と共に深めていく。
ここまでの展開を過剰に説明的になることもなく、観客の理解を先行させ過ぎることもなく、絶妙なバランスで描き切っています。
そして観客が減少の理解に達したところで、やくざ者が現れて、登場人物たちがピンチに直面するという大きな展開を持ち込み、アイデアを応用していくわけです。
さらには、そこから藤子・F・不二雄的SF展開を持ち込み、もう一捻り加えて幕切れまでもっていくという非常に見事な構成になっていました。
ちょっとだけ過去とちょっとだけ未来を行き来しながら展開するミニマルなSFですし、完全にワンアイデア勝負ではあるのですが、そこを絶妙な見せ方で、観客を飽きさせない作品に仕上げた製作陣の工夫には感動しました。
舞台であれば違和感はないのだろうが…
(C)ヨーロッパ企画/トリウッド2020
今作は劇団ヨーロッパ企画の作品と言うことで、その随所に「舞台演劇的な要素」が散見されます。
まず、カフェとその店主の店という2つの場所を中心にして物語を展開させるという限定的な場面設定は、舞台的と言える最たるものでしょう。
加えて、演者もおそらく舞台仕込みの俳優が多いのだと思いますが、誰かが話している時のサポーティングキャストたちの振る舞いが、良くも悪くも映画っぽくなくて、舞台のそれだなと感じました。
また、用いられている小道具の使い方・使われ方が、舞台っぽいというより映画としては意識が不十分ではないかなと感じました。
まず、本作のキーアイテムとなるモニターについてですが、モニターに接続されているコンセントケーブルの扱いがすごく雑で目につきましたね。
iMacのケーブルが部屋からカフェにもっていくときにどうなってるんだ?とかテレビを5階のやくざ者の事務所にもっていくときにそのコンセントケーブルがどうなってるんだ?というのが非常に気になります。
SFテイストの作品ですし、設定も突飛なわけですから、そこは「あっ、これコンセント抜いても消えないんだ。」的な説明を一言セリフで入れるだけでも違ったと思うんですよね。
中途半端に画面にコンセントケーブルが映り込んでしまっているだけに、観客にはそれが妙に目についてしまい、どういう原理何だろうとモヤモヤ感を抱かせてしまうのが勿体ないと思いました。
あとはやくざ者が登場するという展開ですが、小道具のチープさが際立つというか、妙に劇中で浮いている印象を受けましたね。









おそらく舞台として見れば、何ら違和感なく見られていたと思うのですが、映画としてみるとなると、どうしても視覚的に説得力がないので、冷めてしまう部分があります。
極めつけは、終盤に登場するタイムパトロールと彼らが持っていた光線銃のような小道具でしょう。
こればっかりは、映画として見るには耐えがたいクオリティだった気がします。
皆さんはYoutubeやニコニコ動画、インスタライブなどでいわゆる「生配信」を見ることがあると思います。
こういったライブ感のあるメディアを見ている時って、多少画質が悪かったり、内容がグダグダとしていても気にならないなんてことはありませんか?
しかし、その配信を1本の完成した動画としてアーカイブやタイムシフト等で見るとなると、途端にそういった粗が目についてイライラするという経験が誰しもあると思うんですよね。私自身もあります。
この違いって、おそらくは「ライブ感」だと思うんですね。
舞台は演者と観客が1つの場を共有して行われる芸術ですので、ある程度小道具がチープだったり、演出が現実的には不可能なものだったとしても、「ライブ感」でそれを補完してリアルに見ることができるんですよ。
その一方で、完成された映画としてみるとなると、どうしても映画と私たちの間には埋めようのない距離があるわけです。
そして前者がいわゆる「生放送」に対応し、後者が完成された動画を見るという行為に対応するわけですから、舞台的なチープさが映画に持ち込まれると、どうしても目についてしまうものなんですね。
当ブログ管理人が、いわゆる劇団の演劇をそれほど多く見たことがないという事情ももちろんあるとは思いますが、今作『ドロステのはてで僕ら』の演劇をそのまま映画にしました感が少し気になってしまったのは事実です。
そこを巧くクリアしていたのが『カメラを止めるな!』だったとは、やはり思いますよね。
あの作品は、作りが「チープ」であることに対して、「生放送で低予算映画を撮っているから」とシチュエーションで理由づけをしてあったんです。
こういうひと工夫で、見る側の姿勢も変わってきます。
こういった前例があるだけに『ドロステのはてで僕ら』には、もっと出来たのではないかという思いは持ってしまいました。
おそらく今作も「ワンカット風」を売りにしていた作品なので、その点で「ライブ感」を出して誤魔化そうという意図はあったのかもしれませんが、個人的にはきつかったです。
この題材にあの結末は受け入れ難い
さて、ここからは少し終盤の展開に踏み込むこととなりますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
『ドロステのはてで僕ら』はちょっとだけ過去、現在、ちょっとだけ未来が交錯する不思議な作品となっています。
物語の序盤~中盤では、現在軸から未来を見てしまい、その辻褄を合わせるために奮闘したりする姿が見られたり、未来から情報を得て、それに合わせて「現在」が行動していくという様子が見られました。
つまり、決まった未来に向かって、現在軸の自分たちが行動していくしかないというある種の予定調和を見せられていたわけです。
そして、それを明確に突きつける存在として終盤に未来人(タイムパトロール)が登場し、主人公たちに未来を変えないためにも、記憶を失う薬を飲んで、辻褄を合わせて欲しいと要求します。
時間は過去からの脈々と続く積み重ねの中で存在しているわけですから、そこが変わってしまうと、未来の自分たちの存在が危うくなるというのは当然の主張でしょう。
しかし、カトウとメグミは半ばそれを拒否する形で、記憶を失う薬を飲むことを放棄します。その結果として未来人(タイムパトロール)が消失してしまうという結末を迎えるわけです。









まず、コメディテイストで味つけをしてあるのですが、人が消えるという展開をどうしたって笑うことはできません。
ここがすごく映画の演出と見ている自分の完成との間に齟齬が生じたなと思いました。
このラストを選択したのは、おそらく未来主眼で現在が決まっていくという構図を、現在主軸で未来が決まっていくという構図へとパラダイムシフトさせようとしたからなのだと思います。









そうであれば、自分たちの現在における存在というものは、過去を現在として生きている自分や他の誰かの選択と決断に基づいてい成立しているのだということになります。
では、何らかの影響で、過去の誰かが未来を知り、その未来を選択したくないとして別の行動を取った時、自分の存在が失われたとして、それを受け入れることができるのか?という話になりませんか?
未来人にとってカトウとメグミの存在が過去であったように、彼らにとっても過去という存在があるわけです。
この作品のギミックは、ある種マサチューセッツ工科大学のブラッドフォード・スコウ博士が提唱したスポットライト理論を応用したものだと思います。
スポットライト理論においては時間は流れるものと言うよりは、同時に存在しており、スポットライトが当たった場所が「現在」として認識されるだけであるという内容です。
その一方で、現在の行動によって未来人が消えるといういわゆる「因果律」の話であったり、エントロピーの矢的な時間軸を持ち込んでしまっていて、その点で矛盾めいたものを生じさせているようにも感じます。
だからこそ、今作の選んだラストの展開は倫理的にも少し受け入れ難いものがあり、そして今作のコアになっていたアイデアとの整合性やリンクという側面で見ても、違和感の残るものになってしまったような気がしました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ドロステのはてで僕ら』についてお話してきました。









まあ『サマータイムマシンブルース』的なゆる~いSFなので、あまりディテールの部分を気にしても仕方がないという思いはありますが、それにしてももう少し出来たのではないかと。
未来の予定調和のための現在を生きるのではなく、現在が未来を決定するのだという矢印で生きてみようというラストのメッセージ性はすごく伝わるのですが、せっかくのドロステ効果を活用したギミックとの連動性が薄く感じられるんですよね。
しかも、その一連の流れで未来人を消失させるということをやっているわけですから、余計に腑に落ちません。
ただ、ワンアイデアものとしての展開のさせ方は本当にお見事で、これについては一見の価値ありと思いました。









今回も読んでくださった方、ありがとうございました。