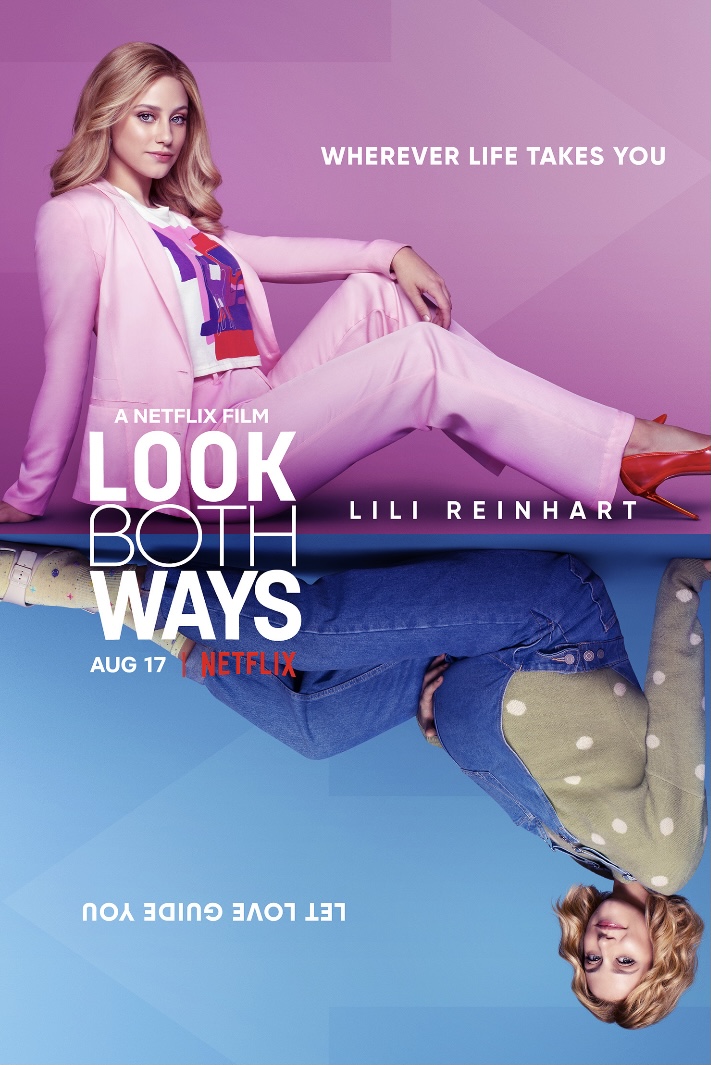みなさんは「川」という場所にどんなイメージを持っているだろうか。
私は子どものころに無邪気な好奇心から両親に「私はどこでどうやって生まれたのか?」と尋ねたことがある。
そのときに「橋の下から拾ってきたんだよ。」と言われたのが忘れられない。
おそらくこの記事を読んでくださっている方の中にも「橋の下で拾われてきた子」がいらっしゃるのではないかと思う。
こうした親の発言の背後には、橋あるいはそれが架かっている川という場所に、生命の生まれる場所という潜在的なイメージがあるからではないだろうか。
川を構成する水という物質に「羊水」のイメージが重ねられることもその一因と言える。
一方でみなさんは「三途の川」という言葉を耳にしたこともあるだろう。これは仏語で「人が死んで冥土に行く途中に越えるという川」を意味する。生と死の世界を隔てているのが川という場所であるという見方だ。
つまり、私たち日本人は「川」という場所に、生と死という対照的な2つの概念を同時に見ているということになる。
生と死が絶えずせめぎ合い、その中で生命のやり取りが為されている場所、それが「川」なのかもしれないとも思う。
今回ご紹介する『川っぺりムコリッタ』は、そのタイトルの通り「川っぺり」にある田舎町が舞台になっている。
『かもめ食堂』や『彼らが本気で編むときは、』などで知られる荻上直子監督の最新作でもある本作は、そんな川っぺりで暮らす人たちの生活に焦点を当てている。
いわゆる「スローライフ系」と呼ばれるジャンルの映画を確立したのが彼女であり、今作も『かもめ食堂』や『めがね』といった作品群に通底するものを感じることはある。
しかし、決定的に異なるのは、今作には色濃く「死」の臭いが立ち込めている点だ。
川っぺりで暮らす人たちの穏やかで自由な生活を描きながらも、そうした生活の終わりや崩壊の予感が常に漂っているのである。
今回の記事では、『川っぺりムコリッタ』が「死」を作品の中に散りばめることで、何を描こうとしたのかを考えてみたい。
目次
『川っぺりムコリッタ』考察(ネタバレあり)
死あるいは終わりと表裏一体の「スローライフ」
(生活の風景にさりげなく映りこむ父の遺骨が入った壺が異質な存在感を放っている)
©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会
荻上直子監督の作品が描くライフスタイルは、常に物質的な豊かさの外にある「豊かさ」を描くものであり、映画を見終わると、思わず自分もそんな暮らしをしてみたいと思わせる引力がある。
しかし、『川っぺりムコリッタ』を見て、登場人物たちと同じような暮らしをしてみたいと考える観客は少数派だろう。
確かにいつも通り、食事のシーンが丁寧に撮られており、劇場を出るときに無性に白米やイカの塩辛が食べたくなる側面があることは否定できない。
しかし、ライフスタイルそのものには、あまり惹かれないのだ。
劇中でムロツヨシ演じる島田幸三という人物が、自分はミニマリストであると自称していたが、彼がミニマリストの代表格として大々的に打ち出されていたとしたら、今の社会でこんなにもミニマリスト的なライフスタイルが流行しただろうか。
『川っぺりムコリッタ』が描くライフスタイルが、本作が荻上直子監督作品であるにも関わらず魅力的に映らないのは、そこに一抹の「危うさ」が内包されているからだ。
島田が志向するミニマリストな暮らしは、劇中で松山ケンイチ演じる主人公の山田たけしも指摘していたように、ちょっとしたことで立ち行かなくなる危険性を孕んでいる。
そうした「危うさ」の最たるものとして描かれているのが、「死」である。
例えば、物語の序盤に主人公のたけしの父が亡くなったことが明らかになり、彼は役所にその遺骨を受け取りに行く。その日から彼の自宅の一室には、遺骨の入った箱が置かれている。この箱が夜になると銀色に輝き、不気味な雰囲気を放つ。
日常生活の中心となる空間にまで「死」が入り込んでくるという状況を見事に可視化したと言える演出と言えるだろう。
その他にも、主人公と同じアパートに暮らしている住人たちはそれぞれの事情で「死」に近い存在として描かれている。
吉岡秀隆演じる溝口健一という男性は、墓石を販売する営業マンとして働いているし、満島ひかり演じる大家の南詩織という女性は、早くに夫を亡くしている。彼らに加えて、中島という完全に幽霊のキャラクターまで登場する。
このように川っぺりに佇むアパートには、穏やかで自由な暮らしの傍らに常に「死」の臭いやが漂っているのだ。
また、「川っぺり」という土地で考えてみても、本作の川の近くにはたくさんのホームレスの人たちが暮らしている。しかし、彼らの生活もまた死と隣り合わせである。
本作の終盤に台風がやって来て、主人公の住む地域に甚大な被害を与えたが、劇中で島田が言及していたように、彼らは台風が来ると、ひとたまりもなく流されてしまうのだ。
先ほども述べたように、荻上直子監督の作品では、物質的な豊かさの外側にある「豊かな暮らし」を常に描いてきた。
しかし、今作では、同様に「豊かな暮らし」を描きつつも、実はその暮らしが死や終わりといった「危うさ」の上に成り立っているものであることを、何度も何度も観客に意識させる作りになっている。
それ故に『川っぺりムコリッタ』を見て、憧れに似た感情は湧いてこないのだ。
では、なぜ荻上直子監督はこのような生と死のせめぎ合いの中に「豊かな暮らし」を位置づけたのだろうか。
死に抗うためのためのルーティンとその多様性の肯定
(風呂上がりの牛乳は、父から子へと受け継がれたルーティンだ)
©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会
今作を紐解く上での1つのキーワードは「ルーティン」ではないかと考えている。
ここで少し質問だが、みなさんは「生活がルーティン化している」という表現を聞いたとき、ポジティブな印象を受けるだろうか、それともネガティブな印象を受けるだろうか。
少し表現を変えよう。「生活が同じことの繰り返しになっている」という表現を聞いた場合ならばどうだろうか。
多くの人がネガティブな印象を受けるのではないかと思うし、私もこの映画を見るまでは何の疑いもなくネガティブなことだと捉えてきた。
主人公のたけしも、これにネガティブな感情を抱き、それを自身の勤め先の社長に思わずぶつけてしまう。
それに対して、社長は同じことの繰り返しを5年、10年、あるいはもっと長い時間続けていくことの大切さを説く。そして、その重要性は、そうして5年あるいは10年を過ごした者にしかわからないのだと告げる。
この社長の発言と、先ほどまで述べてきた本作の孕む「危うさ」はまさしく連動している。
『川っぺりムコリッタ』では、私たちの生活が如何に崩壊と表裏一体の状況で成立しているものなのか、あるいは私たちの生命が如何に死と隣り合わせの状況で維持されているのかが描かれている。
こうした状況においては、生きていくことないし生活を続けていくことが、そもそも難しいことであり、尊いものなのではないか。
社長はルーティンないし同じことの繰り返しを続けていくことを、死や崩壊に抗い続けること、すなわち生きることそのものと同義に捉えているように思える。
例えば、たけしの暮らしはと言えば、仕事に行って単純作業をこなし、自宅ではお風呂に入って牛乳を飲み、炊飯器で炊き立ての白米とイカの塩辛を食べ、隣人の農作業を手伝う、それの繰り返しである。
たけしは、詐欺を働いたという前科を抱えており、その負い目から「死」に引き寄せられそうになっているところがあった。
しかし、彼はそうした日々のルーティンの繰り返しの中で、何とか「死」に抗いながら生活を続けていく。そして次第にルーティンそのものに幸せや安らぎを見出していくのだ。
他のキャラクターにも、そうした「死」や崩壊、あるいは終わりに抵抗するための日々のルーティンが描かれている。
例えば、溝口健一は貧乏な暮らしを強いられているが、高級な墓石の営業マンの仕事を手放そうとしない。
©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会
毎日、少年と共に出かけては墓石の案内をする。しかし、売れない。それでも数か月に1回売り上げが立って、すき焼きやふぐ刺しのような豪華な食事をとる。
そんなルーティンのどこがいいのだろうか、果たしてそれで幸せなのだろうかと思った人も多いだろうが、これが彼なりの生きていくためのルーティンなのだ。
また、強烈だったのは、満島ひかり演じる大家の南詩織のルーティンだろうか。
©2021「川っぺりムコリッタ」製作委員会
彼女は、妊婦を見ると蹴りたくなる情動に駆られると劇中で語っており、そんなときには河原でアイスを食べて気持ちを落ち着かせている。
加えて、彼女は亡き夫を今でも深く愛しており、精神的に不安定になると、仏壇から夫の遺骨を取り出し、それを咥えながら、自慰行為に及ぶという習慣を持っている。
このように『川っぺりムコリッタ』には、観客が共感しやすいものから、思わず嫌悪感を抱いてしまうようなものまで、多様な人間のルーティンにスポットを当てていた。
しかし、共通しているのは、そのどれもが、その人が生きていくために、「死」に抗い続けるために必要であるという点だ。
『川っぺりムコリッタ』はそうした人間誰しもが生きていくために必要としている多様なルーティンを貴賤なく肯定し、温かく包み込んでくれる映画なのである。
おわりに:なぜラストシーンは葬儀なだったのか?
本作が物語の最後に描くのは、たけしの父親の葬儀のシーンである。葬儀は、アパートの住人たちによりまさしく「川っぺり」で行われている。
「川っぺり」は記事の冒頭にも述べたように、生と死の境界であり、生命のやり取りが為される場所であると位置づけることができる。
だとすると、葬儀をラストシーンに持ってきたのは、その行為が人間が「死」に抗うためのルーティンだからではないだろうか。
人が亡くなったら、葬儀をして、供養する。そして定期的に墓参りに訪れる。このルーティンは人が亡くなるたびに時代を超えて繰り返されてきた人間の営みである。
そうした葬儀を形式的なものであり、特に意味はないと切り捨てるのは簡単だろう。劇中でたけしも、父親の遺骨を川に捨てようとするなど、そうしたルーティンから逸脱しようとする姿勢を見せていた。
では、なぜ葬儀をするのか。お墓や仏壇を作るのか。定期的に仏前(神前)で手を合わせたり、お墓参りに行ったりするのか。
それは、その行為そのものが、生と死の境界を明確にするものであり、残された人が死に抗い、生き残るために必要なルーティンだからなのだ。
大切な人の死は、私たちをとてつもない引力で「生」から「死」の方へと引き寄せる。
ムロツヨシ演じる島田幸三は劇中で息子がいたことを示唆しており、映画終盤の空飛ぶイカのバルーンに「俺も連れて行ってくれ!」と懇願する描写から、息子が既にこの世にはいないであろうことも透けて見える。
大切な息子の「死」が、彼を「死」の方へと引き寄せていく。島田はそれに抗いながら、やっとのことで生を長らえている人間だ。
だからこそ、私たちはルーティンを通じて、その引力に抗うしかないのだ。
葬儀をして、お墓を作って、定期的にお墓を訪れて、手を合わせて。そして、その繰り返しが、気がつけば「生きる」ことそのものになっていく。
たけしの勤務先の社長が言っていたことは、まさしくそういうことなのかもしれない。
荻上直子監督は『川っぺりムコリッタ』を通じて、私たちがついネガティブに捉えてしまいがちな「同じことの繰り返し」に「豊かさ」を見出そうと試みたのである。
今作で彼女が描こうとした「豊かさ」はこれまでの作品以上に、深遠なもののように思えるし、作品を見てすぐに分かった気になれるようなものでもない。
しかし、5年後、10年後。自分が人生の中で「ルーティン=繰り返し」を重ねていけば、いつかこの境地に辿り着くことができるのかもしれないとも思う。
いつの日か、「川っぺり」に暮らす彼らと美味しいお酒が飲めるといいな、なんて思いながら、私たちは今日も、そして明日も生きていく。