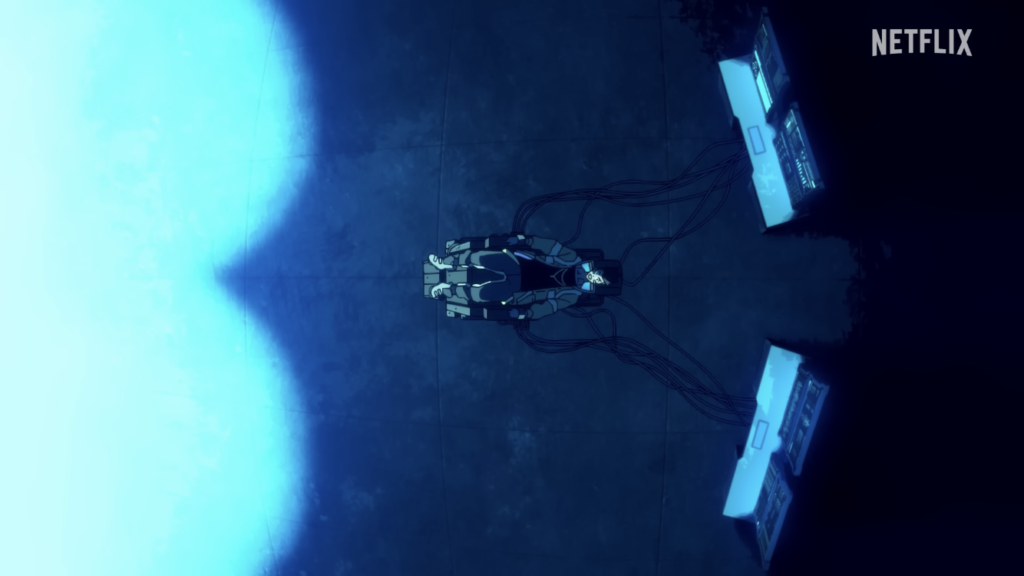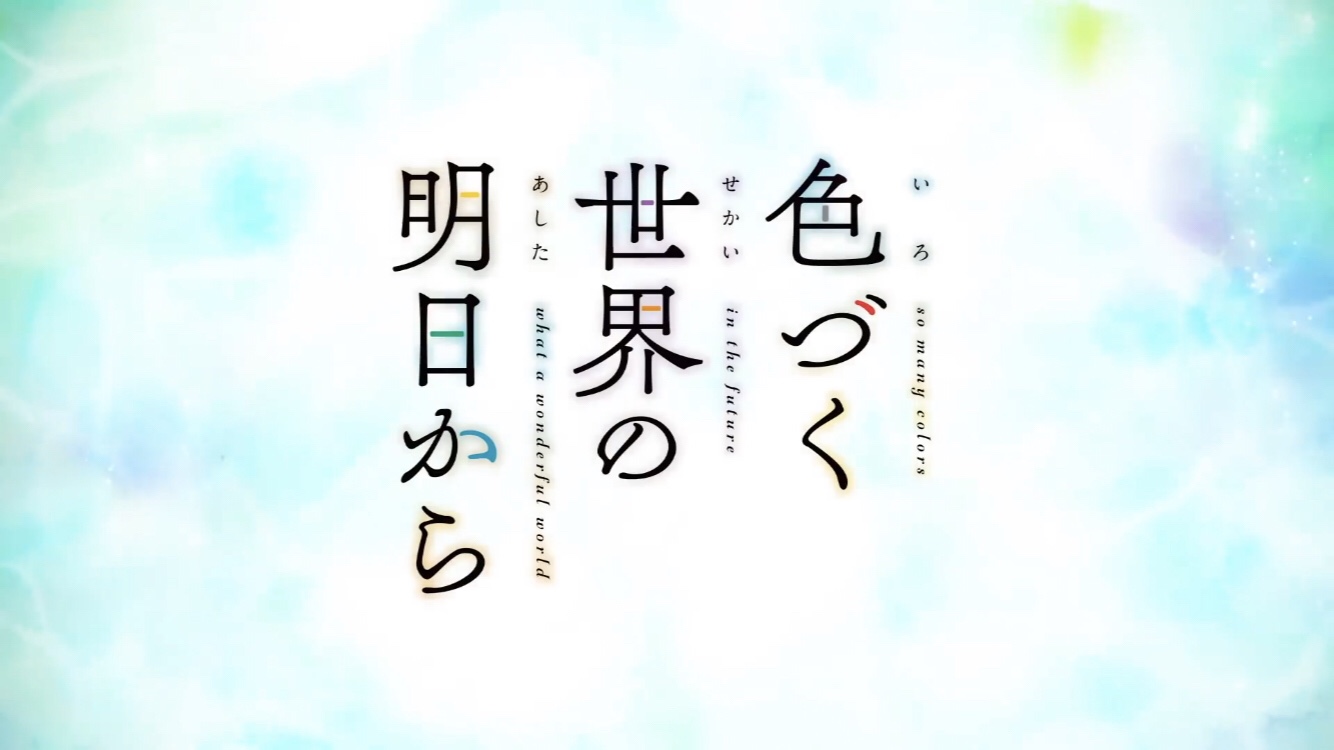作家の村上春樹氏が2009年にエルサレム賞と呼ばれるイスラエルの文学賞を受賞した際のスピーチで次のように述べた。
もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。
(中略)
さて、このメタファーはいったい何を意味するのか?ある場合には単純明快です。爆撃機や戦車やロケット弾や白燐弾や機関銃は、硬く大きな壁です。それらに潰され、焼かれ、貫かれる非武装市民は卵です。それがこのメタファーのひとつの意味です。
(村上春樹のエルサレム賞受賞スピーチ「壁と卵 – Of Walls and Eggs」より引用)
また、彼はこのように続けた。
我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにとっての硬い大きな壁に直面しているのです。その壁は名前を持っています。それは「システム」と呼ばれています。そのシステムは本来は我々を護るべきはずのものです。しかしあるときにはそれが独り立ちして我々を殺し、我々に人を殺させるのです。冷たく、効率よく、そしてシステマティックに。
(村上春樹のエルサレム賞受賞スピーチ「壁と卵 – Of Walls and Eggs」より引用)
これまでにも「勧善懲悪」や「正義による悪の打倒」を描いた作品は数えきれないほどに作られてきたが、フィクションにおいては、この種の善と悪の対峙の構図が単純化されることは非常に多い。
アンパンマンとバイキンマンの対峙の構図のように、善と悪の象徴的なアイコンが戦い、前者が勝利を収めることで問題が万事解決するというのが、その分かりやすい例だろうか。
しかし、現代社会における善と悪の構図がこんなに単純なものではないことは誰もが知るところだろう。
なぜなら、先ほどの村上春樹氏のスピーチにもあったように、現在に生きる私たちが直面しているのは、「システム」という巨大な壁だからだ。
とは言え、産業革命に伴いその複雑さが顔を覗かせ始め、今やその全貌を捉えることが不可能なほどに巨大化した「システム」を2時間の映画、あるいは1クールのアニメシリーズなどで描くことは不可能に等しい。
先ほど挙げたアンパンマンの例で考えてみよう。
『アンパンマン』において、バイキンマンは菌が織り成す巨大な「システム」の1つの表象に過ぎず、彼を打倒したとしてもアンパンマンはその背後にある「システム」に対峙しなければならない。
あるいはアンパンマン自身も酵母菌の恩恵を受けており、彼自身も無意識のうちにそんな巨大「システム」の一部を担っていたことが明るみに出る。
こんな複雑なプロットや構図を持ち込んだとして、『アンパンマン』が子ども向けアニメの体裁を保ち続けられるかと問われると、それは否と言わざるを得ない。
そんな今石洋之監督が手掛けてきたアニメ作品の多くは王道の正義と悪の対峙を描きながらも、悪の側を単体の巨悪としてではなく、集合体の「システム」として描くことを試みてきたように思う。
今回の記事では、そうした試みの極致として『サイバーパンク エッジランナーズ』を紐解いていく。
目次
『サイバーパンク エッジランナーズ』解説・考察(ネタバレあり)
『天元突破グレンラガン』来、描かれてきた「システム」との対峙
本作の「システム」の表象としてのナイト・シティ。第10話でサイバーパンクになりかけているデイビットの意識を捉える牢獄として機能していたのもナイト・シティのイメージであった。
©2022 CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
今石洋之監督を日本を代表するアニメ監督の1人に押し上げるきっかけとなったのは、言うまでもなく『天元突破グレンラガン』だろう。
地下世界で暮らしている穴掘り少年(シモン)とその兄貴分(カミナ)が地上を目指し、地上を世界する螺旋王ロージェノムを打倒し、豊かな社会を構築することを目指すというのが、同作の前半部分のプロットである。
よくある物語であれば、このロージェノムを打倒して「happily ever after」となりそうなものだが、同作はここからさらに世界を拡張していく。
ロージェノムさえも宇宙の巨大な「システム」に組み込まれた1つのパーツに過ぎなかったこと、そして、主人公たちもまたそんな「システム」の中で生かされてきたことが明らかになり、もはやその打倒は不可能にすら思わせる。
だが『天元突破グレンラガン』は劇中でも言及されているように、「宇宙の運命に風穴をあける男の物語」である。そのため、最終的には宇宙を取り巻く巨大な「システム」に立ち向かい、その打倒を実現する。
また、今石監督をはじめとする『天元突破グレンラガン』のスタッフ陣が集結して制作されたテレビアニメ『キルラキル』でも同様の構成と構造が踏襲されている。
同作では、序盤に主人公の纏流子と本能字学園、あるいは学園の頂点に君臨する鬼龍院皐月との対峙構造が打ち出され、物語が進行していく。
しかし、物語の後半に入ると、学園よりも大きな「システム」の存在が顔を覗かせ、学園や鬼龍院皐月という存在すらもその一部でしかないこと、主人公の纏流子(とその相棒的存在の「鮮血」)もそこから逃れ得ない存在である事実に直面する。
『キルラキル』で印象的なのは、第7話の喧嘩部のエピソードだろうか。
同話では、主人公の纏流子とその友人の満艦飾マコが喧嘩部という部活動を立ち上げ、学園の頂点へと駆け上がろうと試みるエピソードなのだが、ここでも「システム」が重要な役割を果たす。
というのも、喧嘩部を立ち上げさせたのは、纏流子と満艦飾マコを学園の「システム」の中に取り込むための学園側(あるいは鬼龍院皐月)の策略なのである。
皐月は、喧嘩部の部長となった満艦飾マコに学園の「システム」に則って恩賞や階級を与え、家族とともに貧乏な暮らしを強いられていた彼女は、そんな「システム」に絡めとられてしまうのだ。
このように、本作では序盤の時点で、纏流子と学園(鬼龍院皐月)という対峙の構図だけでなく、学園を取り巻く「システム」との対峙という視点を盛り込んでいる。
物語の後半になり、鬼龍院羅暁という明確なヴィランはアイコンとして登場するものの、彼女もまた宇宙を取り巻く生命戦維の巨大な「システム」の一部でしかない。
だからこそ、纏流子らは鬼龍院羅暁と対峙しつつも、本質的にはその背後に広がる全貌の見えない「システム」と対峙しているという構図になるわけだ。
劇場アニメとして公開された『プロメア』においても、こうした巨大な「システム」との対峙という構図は変わらない。
今石洋之監督の携わったオリジナルアニメ作品では、このように主人公とヴィランとの対峙という典型的な構図を打ち出しつつも、それらを全て内包する「システム」の存在が明らかになり、最終的には主人公とヴィランが共闘して、「システム」の打倒を目指すという展開が描かれる傾向にある。
明確なヴィランの不在、全貌の見えない「システム」
©2022 CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
『サイバーパンク エッジランナーズ』は、先ほどまでに紹介してきた3つの作品で描かれてきた「システム」との対峙という構図の極致とも言える。
『天元突破グレンラガン』『キルラキル』『プロメア』においては、描かれた「システム」が巨大とは言えど、そのスケールは物語の中におおよそ収まっている。
作品の中である程度その全容が描けており、最終的にはその打倒に辿り着くことができるのである。
しかし、『サイバーパンク エッジランナーズ』における「システム」はあまりにも巨大すぎて、その全容を掴むことすらままならない。
象徴的なのは、本作において過去作の「アンチ=スパイラル」「鬼龍院羅暁」「クレイ・フォーサイト」のような中心的ヴィランが存在しないことだろう。
ファラデイやアダム・スマッシャーがそれに該当するかと問われても、それは否としか答えようがない。彼らはアラサカやミリテクといった軍事企業が織り成す巨大な「システム」におけるちっぽけな駒のひとつでしかない。
アラサカという軍事企業が本作における打倒の対象なのだと捉える見方も存在するかもしれないが、アラサカもまたナイト・シティを取り巻く巨大な「システム」の一部であり、すべてではない。
それゆえにこの物語はたとえ主人公のデイビットが、ファラデイやアダム・スマッシャー、あるいはその背後に控える企業アラサカを打倒したとしても、ハッピーエンドには成り得ない。
なぜなら、それらを打倒することは、ナイト・シティを取り巻く巨大な「システム」の大勢に影響を与えないからだ。
アラサカを打倒すれば、ミリテクが台頭し、同様の「システム」が維持され、ミリテクが打倒されれば、さらに他の企業が台頭して、同様の「システム」が維持される。この繰り返しにしかならない。
『サイバーパンク エッジランナーズ』は、明確なヴィランを提示することなく、さらにはヴィランのはっきりとした輪郭すらも視聴者に提示することはなかった。
そのため、ロールプレイングゲームの中ボスに倒されてゲームオーバーになり、さらにそこでバグが生じてその先に進めなくなってしまったかのような不完全燃焼感を抱く視聴者がいても無理はないだろう。
しかし、これこそが本作が「システム」との対峙を描き続けてきた今石洋之監督作品の1つの到達点とも言える理由だと思う。
記事の冒頭で村上春樹氏のスピーチにおける「卵と壁」のメタファーについて引用したが、卵は壁にぶつかっても潰れてしまうだけで、壁に何の影響も及ぼさない。また、卵が巨大な壁の全体像を捉えることなどできない。
デイビッドたちの戦いは、まさしく「卵」が「壁」ぶつかっていくような行為である。だからこそ、ナイト・シティを取り巻く巨大な「システム」を打倒することはおろか、その全容を把握することすら許されないのだ。
『天元突破グレンラガン』であれば、最愛のルーシーを救うためにナイト・シティとその「システム」を打倒するという展開が描かれたかもしれない。
しかし、そこから時を経て、今石監督作品は「システム」を前にして人は無力であり、デイビッドのようなスーパーな主人公であっても、それは同様だという境地に辿り着いたわけだ。
では、デイビットたちの戦いには何の意味もなかったのだろうか。
いや、決してそうではないと私は強く主張したい。
デイビットたちの戦いが護ろうとした「魂」
©2022 CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
『サイバーパンク エッジランナーズ』の物語の前後において、社会全体で見ると、何も変化していないというのがその実だろう。ナイト・シティはデイビットの死後も、何も変わることなく、これまでの日常を繰り返していく。
では、デイビットの戦いには何の意味があったのだろうか。
それを考える上で、冒頭に引用した村上春樹氏のスピーチに再度スポットを当ててみたい。
私が小説を書く理由は、煎じ詰めればただひとつです。個人の魂の尊厳を浮かび上がらせ、そこに光を当てるためです。我々の魂がシステムに絡め取られ、貶められることのないように、常にそこに光を当て、警鐘を鳴らす、それこそが物語の役目です。私はそう信じています。
(村上春樹のエルサレム賞受賞スピーチ「壁と卵 – Of Walls and Eggs」より引用)
彼が述べたのは、システムにはなくて、人間にしかないのは魂であり、その魂の尊厳や気高さを守り抜くことが、人間が「システム」に絡めとられないための唯一の方法であるということ、そしてそのサポートをするのが作家としての役割であるということだ。
デイビットの戦いは確かに巨大な「壁=システム」の大勢に影響を与えることのない無意味なものだったと捉えられるかもしれない。
しかし、彼は明確に大切なものを護り抜いた。それは最愛のルーシーの「魂」だ。
ルーシーは生まれながらにして、アラサカ専属のネットランナーとして養成され、そこから逃げ出したのちもナイト・シティのシステムに絡めとられたまま生きてきた女性である。
だからこそ、彼女は「ここではないどこか」に強い憧れを抱いている。ナイト・シティから脱して、広い世界へと飛び出すことを夢見ているのだ。
そして、ルーシーにとってはそれが月であった。
デイビットは、おそらく自分がアラサカを打倒できないことも、そしてナイト・シティの「システム」を変えることができないことも全て分かった上で、無謀な戦いに身を投じている。彼が目指しているのは、そんな大きなゴールではないだろう。
彼が目指しているのは、ただ一つ最愛のルーシーを「システム」から解放すること、彼女を「月」へと到達させることなのだ。
また、『サイバーパンク エッジランナーズ』が面白いのは、デイビットとルーシーがお互いにお互いを「システム」から解放しようと試みていたことではないだろうか。
デイビットはインプラントへの適応能力が高く、それゆえにアラサカから新しいサイバーウェア(サイバースケルトン)の実験体として狙われていた。
ルーシーは最愛のデイビットがアラサカに囚われ、ナイト・シティの「システム」に絡めとられてしまうことを懸念し、ネットランナーとして彼のデータを削除するために暗躍を続けるのである。
しかし、そんなルーシーの憂いとは裏腹に、デイビットは身体に次々にサイバーウェア(インプラント)をインストールしていき、身体的にも精神的にもナイト・シティの「システム」に囚われていく。
極めつけは、第9話で描かれたサイバースケルトンのインストールであり、これにより彼は完全に「システム」の一部になってしまうわけだ。
こうした身体機能の外部化の過程は、伊藤計劃著の『ハーモニー』の記述を想起させる。
人間が身体の管理を「外注」に出した、これが結果だ。
WatchMeを使って自分の身体を他人任せにした結果、人は外部のシステムなくしてはその身体を維持することすらかなわず、こうしてそこにつけ込まれる状況を招いた。人は生きることに関する様々な事柄を分業化してきた。
豚を狩ること、豚を解体すること、豚を調理すること。
(伊藤計劃『ハーモニー』199ページより引用)
『サイバーパンク エッジランナーズ』においてサイバーパンクたちが、サイバーウェア(インプラント)をインストールし、身体機能を「外注」する過程はまさしくこの記述に重なる。
そして、『ハーモニー』においては、こうした人間の「外注」が最終的に至るところは、意識の「外注」によってもたらされる完全な調和がとれた社会であるとして描かれる。
同作で人類が向かうのは、「報酬系が調和し、すべての選択に葛藤がなく、あらゆる行動が自明な状態」としての「意識の消滅」であり、先ほどまでに述べてきた人間の「魂」とも呼べるものをシステムに移管してしまうことと言えるだろう。
デイビットたちサイバーパンクたちは、サイバーウェア(インプラント)により身体機能を外部化していく過程で、徐々に「魂」や「意識」と呼ばれるものを蝕まれていき、最終的にはサイバーサイコと呼ばれる状態に陥り、人間としての尊厳や誇りを喪失する。
つまり、人間としての輪郭を失ってしまうのだ。
そうした「エッジ」の上をサイバーパンクたちは走り続けていく。
「システム」に身体を委ねて機能を拡張し、それにより報酬を得て、金銭を得る。その過程で徐々に「魂」や「意識」を「システム」に絡めとられていくのである。
だからこそ、サイバーパンクが辿り着く先は「死」か「サイバーサイコ」の二択であると劇中でも繰り返し述べられている。
権力が掌握しているのは、いまや生きることそのもの。そして生きることが引き起こすその展開全部。死っていうのはその権力の限界で、そんな権力から逃れることができる瞬間。
(伊藤計劃『ハーモニー』291ページより引用)
『ハーモニー』では、システムに絡めとられることの対比として「死」が挙げられているが、この点も『サイバーパンク エッジランナーズ』に重なると言える。
ルーシーが試みていたのは、「死」と「サイバーサイコ」の二択の外にある選択肢をデイビットに選ばせることであり、だからこそ彼女は彼にサイバーパンクとして活動することを望まなかったわけだ。
そして、デイビットがサイバーパンクになってからも、彼女はアラサカから彼の存在を秘匿し続けた。それはサイバースケルトンにより、彼の「魂」や「意識」がシステムに絡めとられてしまうことを知っていたからである。
結果的に、デイビットはその二択で言うところの「死」に辿り着くことになってしまう。
しかし、『ハーモニー』が「死っていうのはその権力の限界で、そんな権力から逃れることができる瞬間」と述べたように、デイビットは「死」によって、「魂」や「意識」を失う寸前に人間として生を全うしたと言える。
最終的には四肢を切断され、肉体的には人間の輪郭をとどめていないとも言えるが、それでも彼は最後まで誇り高き「魂」を有した人間であった。
ルーシーが生き残ったことで護られたもの
デイビットの一連の戦いは、ルーシーの「月が綺麗ね。」に対する力強い「死んでもいいぜ。」だったと言える。
©2022 CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
『サイバーパンク エッジランナーズ』は、そんなデイビットたちの戦いによって「システム」から解放されたルーシーが月を訪れるシーンで幕を閉じる。
月に降り立った彼女の前に現れるのは、出会った頃のように無邪気で愛らしいデイビットの幻影だ。
ここにこそ、ルーシーが生き残った意味がある。
村上春樹氏のスピーチや『ハーモニー』の記述を引用しながら述べてきたように、巨大な「システム」を前にして、人間を人間たらしめるのは「魂」や「意識」と呼ばれるものだ。
ルーシーの「魂」や「意識」を「システム」から解放し、護り抜いたのは、他でもないデイビットである。
そして、デイビットの「魂」や「意識」を護り続けるのは、残されたルーシーの役割となるわけだ。
ルーシーの「魂」や「意識」が見せた光景の中では、デイビットが笑い、太陽のように輝き続けている。そして彼女が生きている限り、彼女の「魂」や「意識」が存在し続ける限り、デイビットはそこで存在し続けることができる。
「魂」や「意識」と呼ばれるものは、「システム」に対して唯一人間が最後まで護り抜くことのできる聖域であると言える。
つまり、ルーシーがその聖域を守り続け、そこにデイビットを「生かし続ける」ことが、彼女なりに成し遂げたデイビットの解放として描かれているわけだ。
『サイバーパンク エッジランナーズ』は、これまでの今石作品と同様に主人公と巨大な「システム」との対峙を描いた作品である。
しかし、これまでの作品と明確に違うのは「システム」の打倒ではなく、「システム」からの解放をゴールに据えた点ではないだろうか。
肉体を「システム」に委ね、徐々に「魂」や「意識」すらも「システム」に絡めとられそうになる「エッジ」の上で、それでも人間らしくあろうとし続ける。大切な人の「魂」や「意識」を護りたいと願い続ける。
「卵」のささやかな抵抗は、「壁」を打倒することはない。
しかし、そのささやかな抵抗は決して無意味ではない。
彼らは確かに大切な何かを護り抜いたのだ。