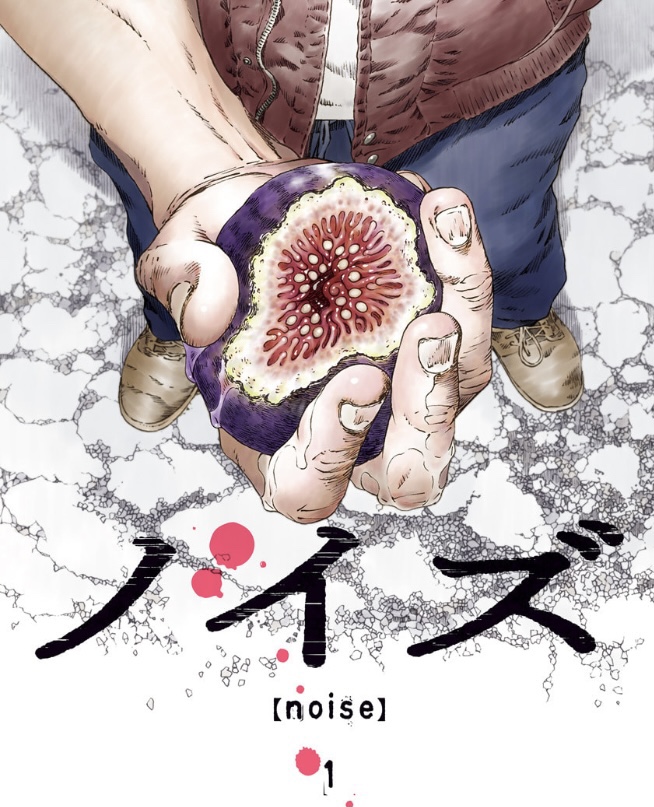私たちはこの世界に生まれ落ちた瞬間に親から「名前」というラベルをつけられ、願いや祈りを託されます。
それゆえに、私たちは自分に名前を与えてくれた人が望んだ自分を生きることから、程度に差はあれど、逃れ難いのです。
「名前」はその人のアイデンティティの主たるものとして捉えられ、その文脈は多くの物語の中に取り入れられてました。『千と千尋の神隠し』はその分かりやすい例の1つでしょう。
それにも関わらず、名前は自分で決めたものではなく、誰かに与えられたものであり、私たちは誰かに勝手に貼られたラベルを自分のアイデンティティだと信じ、疑うこともなく生きているのです。
『犬王』という作品において、主人公の琵琶法師の青年は両親から「友魚」という名前を与えられ「壇ノ浦の友魚」と名乗るように劇中で何度も諭されています。
一方で、彼が琵琶法師として活動するようになり、その座に所属するようになると、今度は組織の長から「友一」という名前を与えられます。
しかし、この名前はいずれも彼自身が望んだものではありません。
前者は両親が望んだものであり、後者は組織に望まれたものであり、そこに彼の意志や決定は介在していないのです。
誰かに望まれた自分を生きること、あるいは自分が望んだ自分を生きること。
私たち人間は常にそのジレンマの中に身を置いています。
『犬王』という作品は、「名前」と「姿(視覚的な外見)」という2つの切り口から、その物語を構築しています。
これに加えて、本作は「物語る行為が孕む傲慢さ」への視座を内包しています。
物語と物語られる対象の関係性の中に先ほどの主題を落とし込み、物語に望まれるキャラクター像と、物語が望まないキャラクターの主体的逸脱のせめぎ合いを描いているわけです。
『犬王』は、そのジレンマやせめぎ合いの向こう側に、一体何を描きたかったのでしょうか。
今回の記事では、自分なりに本作の主題性を掘り下げて、考察してみたいと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含みますので、未鑑賞の方はお気をつけください。
『犬王』考察(ネタバレあり)
望まれない、されど望む「名前」と「姿」で私を生きる
(C)2021 “INU-OH” Film Partners
本作を紐解く上で重要になるのが、「名前」と「姿」という2つの視点です。

「友有」は、生まれた時に両親から「友魚」という名前を与えられ、後に琵琶法師として活動し始めると「友一」という名前を与えられます。
その後、「犬王」と出会い、自らの座を作り、新機軸の琵琶法師として活動し始めたころに、自分で自分に与えた名前が「友有」だったわけです。
一方で、犬王は異形の存在として、この世に生を受けたこともあり、名前を与えられずに生きてきましたが、能楽師として活動するにあたり、自身で「犬王」という名前をつけました。
2人の共通点は、もちろん自分で自分自身の名前を定めたという点ですよね。
しかし、「友有」は自らが定めたその名前を名乗ることを時代に拒絶されてしまいます。
時の支配者である足利義満に目をつけられ、座を潰されると、生きるために「友有」という名前を放棄し、「友一」という名前を受け入れて、自分を殺して余生を過ごすことを要求されるのです。
自分が決めた生き方を、自分が望んだ存在の在り方を赦されないということ、その悲哀を背負いながら彼は斬首により命を落としました。
彼は絶命する瞬間に自分の名前を名乗りましたが、そのとき彼が口にしたのは「友魚」という両親から与えられた名前でしたよね。
つまり、「友一」という時代に望まれる名前を名乗ることはできず、一方で自分が望む「友有」の名前で死ぬこともできず、親から与えられた「友魚」として命を落としたわけで、彼は選べなかったのです。





これは、とりわけ犬王の話になりますが、彼は能楽を演じ、成仏できなかった平家の無念の物語を1つ語り継ぐたびに、自身の姿を変化させていきます。
生まれつき異形だった犬王は、能楽を披露するたびに、少しずつその姿が人間へと近づいていき、最終的にはごく普通の人間の姿へと至りました。
犬王の姿の変化は社会や時代に求められた形での変化だったと言えると思います。
長い腕や背中のうろこ、そして醜い顔は、人々に恐れられ、忌み嫌われ続けたものです。
顕著なのが、その醜い顔であり、彼はその顔を足利義満の前で晒せば、打ち首の刑に処されるだろうと言われていましたよね。
それでも、彼は最終的に人間の美しい顔を手に入れ、足利義満にも受け入れられ、自らの物語を手放し、お抱えの役者として活躍することとなりました。
しかし、彼は異形の姿だった頃に、自分の長い腕を好意的に思っていることを仄めかす発言しており、さらにその腕が人間の一般的な腕に変化したときに、少し寂しそうな表情を見せていましたよね。
つまり、彼はごく普通の人間の姿に近づけば近づくほどに、人々に望まれた姿へと近づいていき、逆に自分が望んだ自分の姿からは遠ざかっていったのです。
このように「名前」そして「姿」という観点で見たときに、「友有」と「犬王」は対照的な結末を辿ったと言えるでしょう。
前者は望んだ「名前=友有」も、望まれた「名前=友一」も選ぶことができず、どっちつかずに「友魚」として死んだことで、亡霊として現代の世に至るまで、彷徨い続けました。
一方で、後者は自身が望んだ姿を手放し、人々に望まれた姿に迎合していくことで、当時の社会で生きながらえることに成功しましたね。
ただ、この2人の明確な共通点は、望んだ自分として生きることを許されなかったことなんです。
死して亡霊として彷徨った「友魚」も、そして亡霊のように生きた「犬王」も、自分が望んだ「名前」や「姿」を奪われてしまいました。
だからこそ、この物語は2人が望んだ「名前」と「姿」を取り戻すところに収束しなければならなかったのです。
(C)2021 “INU-OH” Film Partners
異形の姿で踊る「犬王」と自分が望んだ名前で琵琶を奏でる「友有」と。
社会や時代から解放され、人々の望み、親の祈りからも解放され、ただ自分が望んだ自分として生きること。
長い年月を経て望みが叶えられた2人が、天高く昇っていくその姿は、ただ美しく、どこまでも気高いものに思え、思わず涙がこぼれました。
「物語る」が孕む傲慢、主導権の奪還
(C)2021 “INU-OH” Film Partners





『平家物語』は琵琶法師によって長らく形継がれてきた物語ではあるわけですが、劇中で足利義満が自身に都合のいいように物語を書き換え、定めていたことからもわかるように、それが語られる側の望んだものとして語られてきたかどうかには、疑問符が付きます。
歴史は常に時の支配者や勝者によって都合のいいように書き換えられてきたなんてことが言われますが、物語もまた近い性質を持っていると言えるでしょう。
また、琵琶法師は口承により物語を次の時代へと引き継ぐ役割を果たしています。
しかし、彼らの語り継ぐ物語は、本作で描かれたように支配者に規定され、存在する数多の物語の全てを語り継いできたわけではありません。
そう考えたときに、「物語る」という行為には、2つの傲慢さが見え隠れしています。
1つ目は「物語る」に値するかどうかを物語る人間や時の支配者、あるいはそれを聞く人間が判断するという傲慢さです。
語る価値のない物語は必要ない、支配者が望まない物語は必要ない、人々が関心を示さない物語は必要ない。
そうして有象無象と判断された物語は、語られることもなく、亡霊のようにこの世界を彷徨って回っているのかもしれません。
もう1つの傲慢さは「物語る」という行為そのものに宿っています。
犬王の父親は、他の能楽師が語り継がない平家の物語を探し求め、それを自身が物語ることに執念を燃やし、やがては琵琶法師たちを手にかけるようになりました。
まだ語られていない物語を掬い取って、誰かが物語らなければならない。
(C)2021 “INU-OH” Film Partners
この考え方は、「犬王」や「友有」にも通じており、彼らもまた「物語る」という行為が内包するエゴや傲慢さに無自覚なところがあります。
さて、この『犬王』では、冒頭に現代に亡霊として彷徨っている「友魚」の語りから始めることによって、作品そのものがメタな「物語る」として機能していました。
「犬王」の語り継がれなかった物語を、「友有」の語り継がれなかった物語を、彼は誰にも届かない場所で語り続けています。
しかし、彼らの物語は時の支配者にとって不都合なものであり、価値がないものであり、物語るに値しないものでした。
だからこそ、現代に至るまで語り継がれることもなく、そんな物語を著者の古川日出男さんが掬い上げ、「物語る」ことを試みるという構図になっているわけです。
つまり、この『犬王』という作品によって、「犬王」や「友有」という語られなかった人間について、物語り、彼らに価値を与えようとすることそのものすらもまた傲慢なんですよね。
では、本作は、こうしたウロボロスのような終わりのない「物語る」ことの傲慢さの円環にどう決着をつけたのか。
それは、登場人物を物語の枠組みから逸脱させることでした。
映画のクライマックス、「物語」が亡霊と化した2人を掬い取ろうと試みたその刹那、2人は天高く昇っていき、私たちの手の届かないところへと消えていきます。
その後の2人の物語は誰にも語り継ぐことはできませんし、存在しているのかどうかすらも分かりません。
しかし、語るという行為のテリトリーの中にある物事だけに価値を見出たり、語らなければ存在しないと考えることそれ自体が傲慢だと言えるのではないでしょうか。
「物語る」という行為は、語られる対象を語り手や聞き手の望む姿や在り方に押しとどめ、その枠組みから永遠に出ることの叶わない亡霊へと転じさせることなのかもしれません。
そう考えると、「犬王」と「友有」は語りの枠組みから逸脱することで、初めて物語に希求される自己から解放されると言えるのです。
2人の固定化された物語を永遠に語り続ける「友魚」というストーリーテラーが、「犬王」と「友有」によって打破されるという構図は、語られる側による語る側の打倒に他なりません。
ここで、本作のメタな「物語」に関する視点と、「名前」や「姿」を媒介とした望む自己の希求という主題性がリンクし、ダイナミックな完結を迎えています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『犬王』についてお話してきました。





メタフィクション的な視点を押し出した作品において、語られない物語にも価値があるという考え方はしばしば目にするものです。
しかし、『犬王』は語られない物語を掬い取り、そこに価値を後天的に付与しようとする行為すらも傲慢であり、語る側のエゴであると断罪しているように思えます。
そのため『犬王』は劇中に本作の「語り手」を見える存在として内包し、それを打破するという構図をとり、物語のフレームから逸脱した我々の観測不能領域に全てを委ねたのです。
語り手がそこに触れることは叶わず、彼らの物語を語ることができるのは彼らだけ。
物語の主導権は「語る側」から確かに「語られる側」へと返還されました。
琵琶法師にも、友魚にも、本作の著者や脚本家にも、そして観客である私たちにも手の届かない場所で、2人はどんな生き方をしているのだろうか。
分からない。分からないけれども、それでいいじゃないか。
そう感じさせてくれるような、シニカルでありつつも、優しい視座に裏打ちされた映画だったと思います。