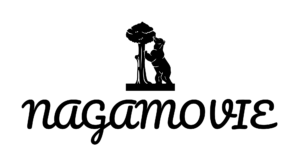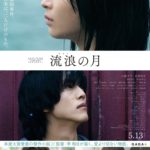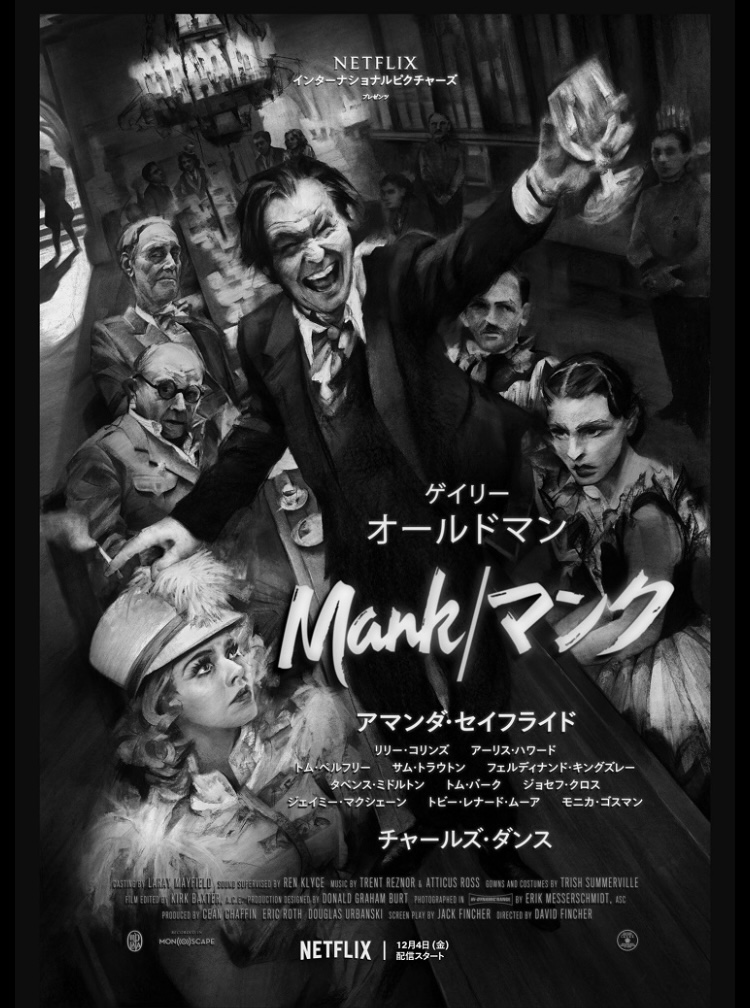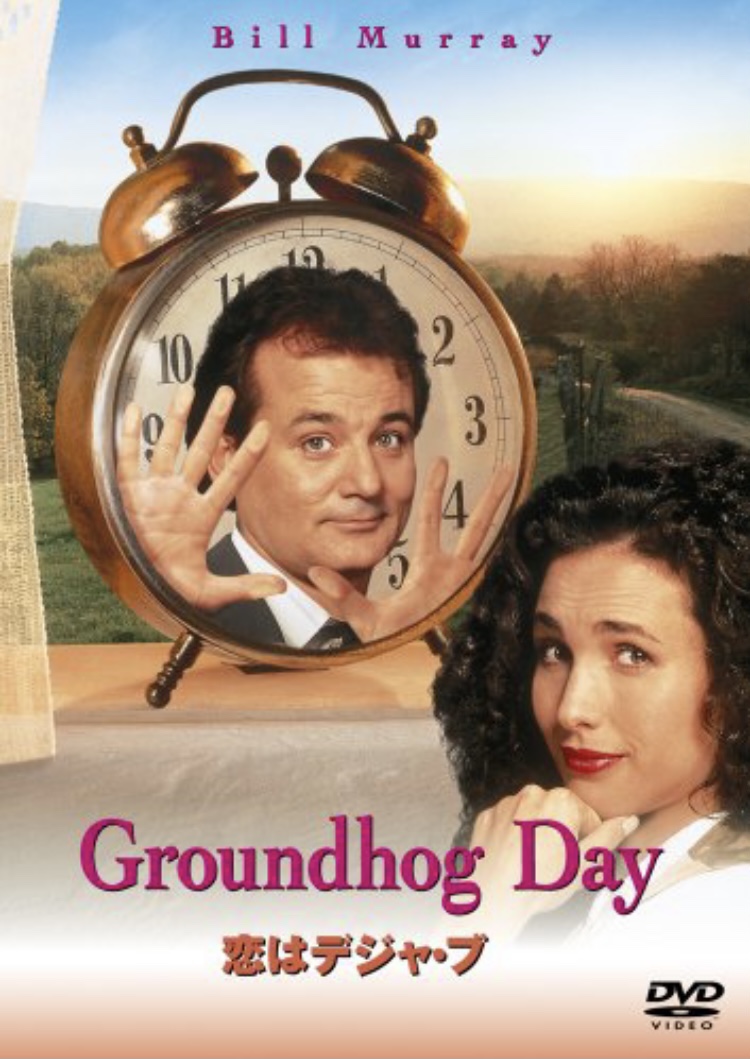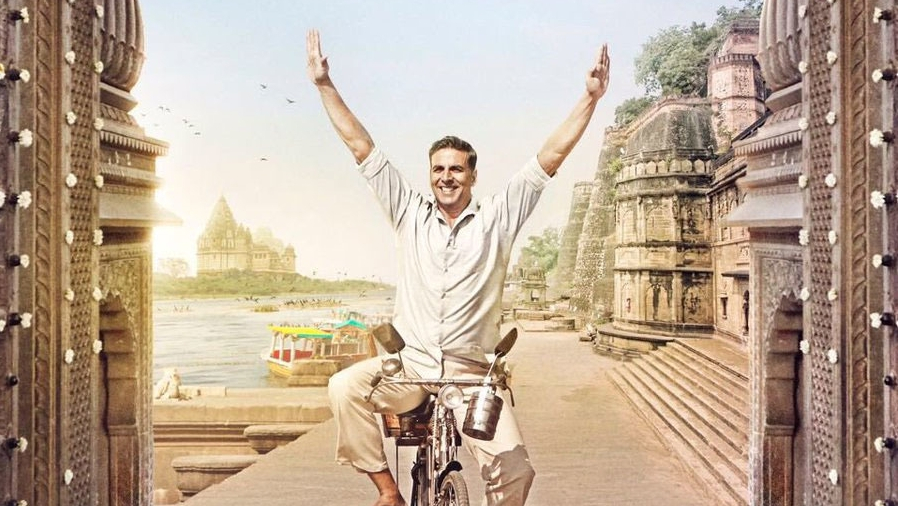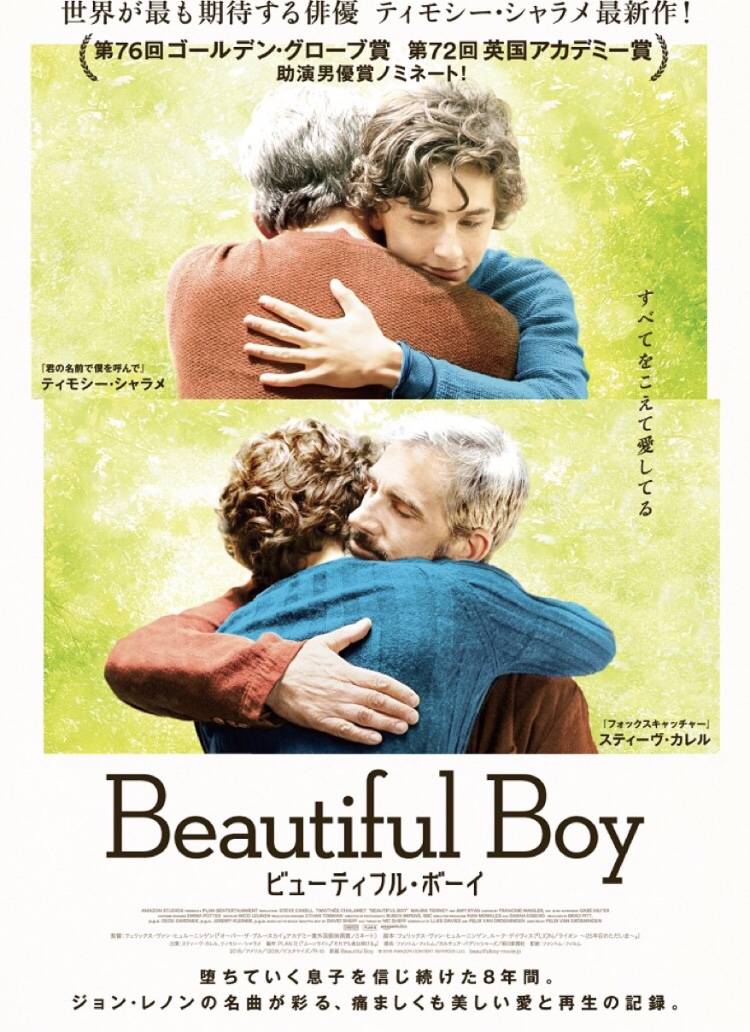みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』についてお話していこうと思います。
2022年5月4日に全世界に先駆けて日本で最速上映となったということで、公開初日に鑑賞してまいりました。
MCU作品で言えば、話題作『スパイダーマン ノーウェイホーム』が日本では、アメリカや他の国から大幅に遅れての公開になったこともありましたので、それを受けての「ガス抜き」的な側面もあるのかもしれませんね。
この『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』ですが、一言で申し上げますとタイトルの「マッドネス」からも分かる通りで、「圧倒的な狂気」です。
MCUのこれまでの作品と比較しても、全く異なるテイストの作品であり、描かれている内容もあまりにもぶっ飛んでいます。
こうした異色のヒーロー映画が生まれる契機となったのは、やはり監督を務めたサム・ライミの影響が大きいでしょう。
ヒーロー映画ファンにとっては、サム・ライミ監督は『スパイダーマン』トリロジーのイメージが強いと思います。
しかし、彼はいわゆる「カルト映画」と呼ばれるジャンルを得意にしている監督で、有名どころだと『死霊のはらわた』や『ダークマン』のような作品を手がけてきました。
そんな彼のホラーテイストあるいはオカルトテイストが今回『ドクターストレンジ』シリーズと魔融合を果たし、完全にイカれた映画が出来上がったということなのでしょう。
今回の記事では、そんな狂気じみた本作について個人的に感じたことや考えたことを綴っていけたらと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含みます。作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
目次
『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』感想・解説(ネタバレ)
ジャンルミックスを志向するフェーズ4の最新作として
MCUは『アベンジャーズ エンドゲーム』という1つのターニングポイントを経て、フェーズ4と呼ばれるステージに突入しました。
フェーズ4に入ってからは、『ワンダヴィジョン』でシットコム、『ロキ』で本格SF、『シャンチー』でファンタジー、『エターナルズ』で神話と様々なジャンルを取り込んできました。
「マルチバース」を物語の中の出来事としてのみ捉えるのではなく、ジャンルミックスという形でメタレベルで捉え、実現してきたわけです。
そんな中で、最新作となる『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』はホラー映画、ゾンビ映画ないし「サム・ライミ監督映画」をヒーロー映画に融合させる新たな試みとなっています。
記事の冒頭にも書きましたが、サム・ライミ監督は『死霊のはらわた』や『ダークマン』などのカルト映画を数多く手がけてきました。
『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』は『ドクターストレンジ』の続編であり、MCUの最新作であり、同時にサム・ライミ監督のフィルモグラフィの集大成的な位置づけにもなっているのです。
確かに『ドクターストレンジ』『ワンダヴィジョン』『ホワットイフ』といった作品を見ておくと、本作の解像度が高まるのは事実で、そういう意味ではMCUという壮大なユニバースの1つの構成要素であることは明白ですよね。
しかし、そんな制約がある中で、監督がここまで自分の色を出せるという自由な風土、作家性を多様性として受け入れる懐の深さに驚かされます。
とりわけ『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』は従来のヒーロー映画としても、「狂気」としか形容できないぶっ飛んだ作品です。
カルト映画的な側面を覗かせる呪文の書、ゾンビ映画を思わせるチェイスシーンあるいは死体の復活描写、ホラーテイストを担保するジャンプスケア演出など、物語的にも視覚的にも、これまでのヒーロー映画からの飛躍が見られます。
それだけでなく、今回はかなり「人間の死」を生々しく描いているんですよね。
MCUで言えば、確かに『アベンジャーズ インフィニティウォー』でサノスの影響で全生命の半分が消失するという事象が描かれてはいますし、犠牲者の数で言えば、相当なものです。
ただ、その死に悲劇性を感じることはあれど、グロテスクさを感じることはあまりありません。
一方で、『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』では、アベンジャーズの一員であるワンダがヴィランとなることで、ヒーローがその力を利用して、他者を殺める光景が描かれます。
それに伴い、焼け焦げた人間の屍が地面に横たわっていたり、人体が損壊するような描写があったりするわけですが、これらはMCUが明確に描写することを避けてきたものばかりではないでしょうか。
劇中に狂気に囚われたワンダが家族を持つとあるヒーローに対して「あなたが死んでも妻が子どもを育てれば問題ないわよね。」といった趣旨の発言をする場面があるのですが、こんなとち狂ったセリフを仮にもヒーロー映画で聞くことになるとは思いませんでした。
DCが『ザ・スーサイド・スクワッド』などに代表されるR指定路線の映画も打ち出していく中で、MCUはその路線には手を出さないのだろうと高を括っていました。
しかし、今回MCUはサム・ライミ監督の作家性を全面に押し出し、PG-13でできる最大限の「グロテスク」を作品の中で表現して見せたのです。
物語やキャラクターの面だけでなく、ジャンルや視覚的な見せ方の面でも多様性を獲得し、世界を広げていくMCUフェーズ4の「狂気」を象徴するような作品になっていたと言えるのではないでしょうか。
禁断の力といかに向き合うか、『ドクターストレンジ』の続編として
『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』は、2017年に日本でも公開された『ドクターストレンジ』の続編です。
前作では、外科医だったスティーブンが、事故に遭い、そこからヒーローとして立ち上がるまでのオリジンが描かれました。
そんな『ドクターストレンジ』の1つの主要なテーマは、「力との向き合い方」にあると個人的には考えています。
前作のヴィランであるカエシリウスは危険な魔術書であるカリオストロの書の一部を持ち出し、それを用いて、ドルマムゥと呼ばれる暗黒次元の存在を地球に侵攻させようと試みていました。
また、スティーブンの師でもあったエンシェント・ワンもまた地球を守るために禁断の力に手を出していた1人であることが物語が進むにつれて明らかになりました。
加えて、ドルマムゥの侵攻に際して、ストレンジもまた時間を操る禁断の魔術に手を出し、それによって地球とそこに暮らす人々を守りましたよね。
エンシェントワンやストレンジの行動に異を唱え、禁断の力に手を出すことはどんな理由であっても許されないと考えるモルドが離反するという展開も描かれています。
このように『ドクターストレンジ』では「禁断の力」に対する多様な向き合い方を描いており、ヒーローが正義のためにそれを行使することを半ば肯定している側面があるのです。
そして、続編となる『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』でも、ダーク・ホールドあるいはヴィシャンティの書といった禁忌とされる力と向き合うキャラクターたちの姿が描かれました。
とりわけ、ここに「ヒーローとして力にどう向き合うか」「人間として力にどう向き合うか」という2つの軸を絡ませているのが本作の特徴です。
この軸は、サム・ライミ監督が『スパイダーマン』トリロジーで追求したものでもあり、それ故に語り口に巧さを感じました。
今作においては、アメリカ・チャベスの能力、そして2つの禁断の書物がキーとなり、それらを巡ってストレンジとワンダの攻防が繰り広げられます。
スティーブンにも様々な葛藤があり、それらがディフェンダーストレンジやシニスター・ストレンジの存在によって可視化されました。
クリスティーンと一緒に過ごしたい、そう願う彼の人間の側面。
一方で、地球に降りかかる脅威から人々を守らなければならないヒーローとしての側面。
そのバランスが微妙なニュアンスで変化しており、マルチバースの中に様々な像を結んでいるわけです。
ワンダやシニスター・ストレンジは、ヒーローというよりも人間として、その力を行使し、自らの欲求を実現しようとしました。
ディフェンダーストレンジは、自分ならば強大な力をコントロールできると過信し、自らではなくチャベスを犠牲にして世界を守ろうと試みましたね。
では、ドクター・ストレンジはどうだったのでしょうか。
確かに彼もまた世界を救うためにダーク・ホールドの力に迷いなく手をつけています。これは前作で彼が迷いなく時間を操る魔術に手をつけたのと同様です。
しかし、彼はクリスティーンの助けもあり、その力に利用されるのではなく、その力を利用する側に回ることができました。
「大いなる力には、大いなる責任が伴う」という言葉が『スパイダーマン』シリーズのキーワードになっていますが、今回の『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』にもこの言葉が通底しているように感じられます。
「禁断の力」に手をつければ、必ず代償を払う必要があります。これは劇中でダーク・ホールドの内なる声がストレンジに語りかけていたことからも明らかです。
そして、その代償を誰が払うのか。
ここに『ドクターストレンジ』シリーズの焦点の1つがあったのではないかと思うのです。
ワンダは、その代償を他の宇宙の自分自身や自分を止めようと試みる人間に払わせようとしました。
そして、そうしたワンダの行動は、冒頭に彼女が「剪定」を行う描写としてアレゴリー化されています。
彼女は自分自身の「幸せ」のために、マルチバースの他の宇宙に生きる自分の「幸せ」を切り捨てようとするわけですから、これは他でもない「剪定」です。
他にも、ディフェンダー・ストレンジはアメリカ・チャベスに、シニスター・ストレンジは他の宇宙の自分にその代償を払わせました。
しかし、ドクター・ストレンジには、その代償を自らが払う覚悟がありました。
「禁断の力」に手を出すことそのものではなく、その力に溺れ、自らがコントロールできなくなり、他者にその代償を払わせること、これが本シリーズにおいて「悪」とされたのだと私は考えています。
ヒーローとしてたくさんの人の命を守るという「幸せ」が、一個人としての「幸せ」と両立しないのは、前者の幸福に伴う力の代償を後者の幸福で支払っているからなのです。
だからこそ、本作のラストでドクター・ストレンジはダーク・ホールドを行使した呪いから逃れることを許されません。それこそが彼がヒーローたる証左です。
ただ、サム・ライミ監督は『スパイダーマン』第1作のラストに通じるロマンをこの映画の最後に残してくれています。
それは、ストレンジが自身の壊れた時計(クリスティーンから贈られたもの)を修理するシーンです。
壊れた時計が象徴するのは、止まってしまったスティーブンという1人の人間としての時間であり、クリスティーンと過ごすはずだった時間なのでしょう。
そう考えると、時計の修理が意味するのは、彼が1人の人間としての幸福を感じられるようになったこと、あるいはマルチバースの壮大な世界観で見たときに、どこかで自分の犠牲の上で流れるスティーブンとクリスティーンの時間があるのではないかという示唆なのです。
そして、もう1つの前作からのストレンジの大きな成長は、彼が最後にチャベスを「信じる」という選択をできたことなのかもしれません。
彼は傲慢でクリスティーンからも「自分でメスを握らないと気が済まない男」と揶揄されることがしばしばでした。
そんな彼が、自分以外の誰かの可能性を信じ、メスを預けることができたのも、やはり大きな成長なのだと思います。
『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』はストレンジの成長という観点で見ても、正しく続編として機能し得る作品と言えるのでしょう。
ワンダの描き方に抱く疑問、ジャンルに消費されるキャラクター

今回の『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』のワンダの描き方に疑問を抱く人は少なくないと思います。
コミックスの『VISION』の中でヴィジョンが「闇堕ち」し、アベンジャーズと対立する展開が描かれていて、『ワンダヴィジョン』が配信開始された頃に、この役割がワンダに与えられるのではないか?という憶測が多くのファンから上がっていました。
一方で、フェミニズム的な視点から考えても、夫を失った女性が狂気に身を委ね、他のヒーローたちと対立するという展開を、今のMCUでは描かないだろうと多くの人が考えていたのも事実です。
結果的に『ワンダヴィジョン』では、ワンダが闇の魔女に力を委ねて幻想の幸せを手に入れるという誘惑を振り切り、「スカーレットウィッチ」と呼ばれるヒーローとして確立されるまでのプロセスが描かれました。
ワンダは夫や2人の子どもたちとの幸せな暮らしという幻想を手放し、ヒーローとしての生き方を選んだかに見えたのです。
ただ、配信シリーズであるが故にいくらかの人が見逃していそうなポストクレジットシーンで、ワンダが今作にも登場する今作にも登場するダーク・ホールドに手を出している描写が出てきました。
つまり『ワンダヴィジョン』の結論としては、「ワンダ闇堕ちコース」を匂わせてはいたわけです。
そのため『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』で描かれるワンダの物語のその後は、『ワンダヴィジョン』のポストクレジットシーンを受けたものになっており、ひたすらに彼女の狂気が描かれます。
彼女は再び幸せな家族の幻影に憑りつかれ、ダーク・ホールドと呼ばれる禁断の呪文書に手を出し、ドクターストレンジと対立する立場に身を置くのです。
この展開そのものが悪いとは思いませんし、『ワンダヴィジョン』から続く物語として矛盾があるとは思いません。
ただ、どうしてもサム・ライミ監督が自身の得意分野をMCUへと持ち込むために、彼女が利用されてしまったような印象が否めないのです。
本作におけるホラーテイストを支えているのは、他でもないワンダの存在であり、彼女がストレンジとチャベスを追いかけてくるという構図で観客の恐怖を煽っています。
とりわけストレンジとクリスティーン、チャベスが研究所から逃亡するシーンにおけるワンダは、子どもが見たらトラウマになるレベルの恐ろしさです。
撮り方もゾンビ映画を想起させるもので、さらにジャンプスケアといったホラー映画特有の演出を盛り込んでいた点も、恐怖を増長させていました。
これらは、間違いなくサム・ライミが本作の監督を務めたことによる恩恵ですし、作品を鑑賞した人が興奮し、絶賛するのも当然でしょう。
しかし、ワンダという確立された女性ヒーローが「狂気」のレッテルを貼られ、映画を通して悪役として扱われ、ホラーテイストを下支えする恐怖の根源としてジャンルに寄与させている様をあまり好意的に見ることはできません。





また、作品を通して、ワンダは理性的ではなく、狂気に身を委ねた女性として描かれ、その一方でドクターストレンジは理性的で、正義を行使するヒーローとして描かれていた点にも疑問が残ります。
近年の映画、例えば『ウーマンインザウィンドウ』や『ラストナイトインソーホー』などがそうですが、男性社会の中で女性の訴えが軽んじられ、「幻想」だと決めつけられてきた状況を描いていますよね。
女性が性加害を受けても「それはあなたの幻想に過ぎない!」「あなたにもその気があったんじゃないか?」と軽んじられ、まともに取り合われなかった。こんなことが現実世界で起こり続けたわけです。
だからこそ、近年の映画では、それに対するカウンターの色が強まり、女性が貼られてきた「狂気」や「幻想」といったレッテルを壊す方向へと進んでいます。
『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』におけるストレンジ(男性)とワンダ(女性)の描き方は、こうした構造の再生産に加担しているようにも見えるのです。
もちろんこの構造を持ち出した上で、それに対するカウンターまでもを作品の中に内包させる手法もあるとは思います。
しかし、『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』に関して言うなれば、そうした描写は存在せず、ワンダが現実を突きつけられ、幻想と狂気に自ら終止符を打つという幕切れが選ばれました。
力をコントロールできない能力者として、あるいは最愛の人を失った女性としての彼女は『アベンジャーズ エイジオブウルトロン』や『ワンダヴィジョン』で既に描かれてきたはずです。
それでもなお、その構造を本作で繰り返す必要があったのか、あるいは飛躍させる必要があったのか。
『エターナルズ』などで、物語とキャラクターの両面における多様性の表現について、大きな進歩を見せてくれたMCUがなぜ、今になってこんなステレオタイプ的な女性の物語の描き方にこだわったのか…。
そこが私個人としてはどうしても腑に落ちなかったのです。
確かにMCUという巨大なフランチャイズの中で、これだけ自身の作家性を表現できるサム・ライミ監督は素晴らしいと思いますし、その手腕に疑いの余地はありません。
ただ、その表現や作家性のために、ワンダというキャラクターが利用されてしまったように感じさせる本作には少しモヤモヤが残るのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』についてお話してきました。





主人公の成長もそうですし、視覚的な表現の面でも前作から正統な進歩を経ていると感じました。
加えて、MCUという巨大なユニバースの中の1つとして位置づけられる作品で、ここまで個人の作家性を出せてしまうサム・ライミ監督の手腕にも驚くばかりです。
MCUとしては初めてホラーテイストを盛り込んだこともあり、これまで直接的に描いてこなかった「グロテスクさ」が顔を覗かせた本作。
間違いなくこれまでのシリーズのイメージを壊す「狂気」であり、同時にこれからの作品の可能性を大きく広げてくれる作品になったのではないでしょうか。
映画『ドクターストレンジ2 マルチバースオブマッドネス』の鑑賞に当たっては『ドクターストレンジ』の第1作と『ワンダヴィジョン』の鑑賞が推奨されます。
ただ、この2作品を知らなくても十分に楽しめる内容ですので、ぜひ肩の力を抜いて劇場に足を運んでみてください。





今回も読んでくださった方、ありがとうございました。