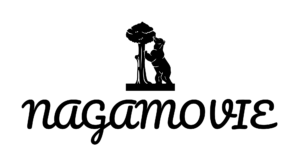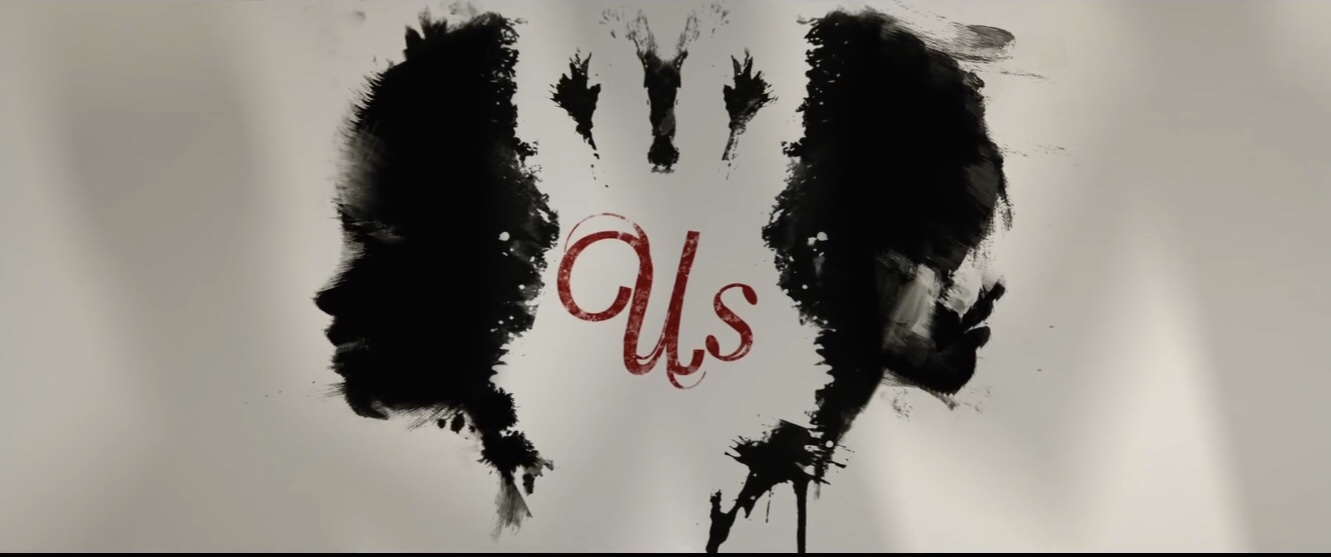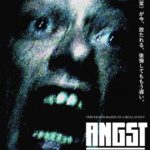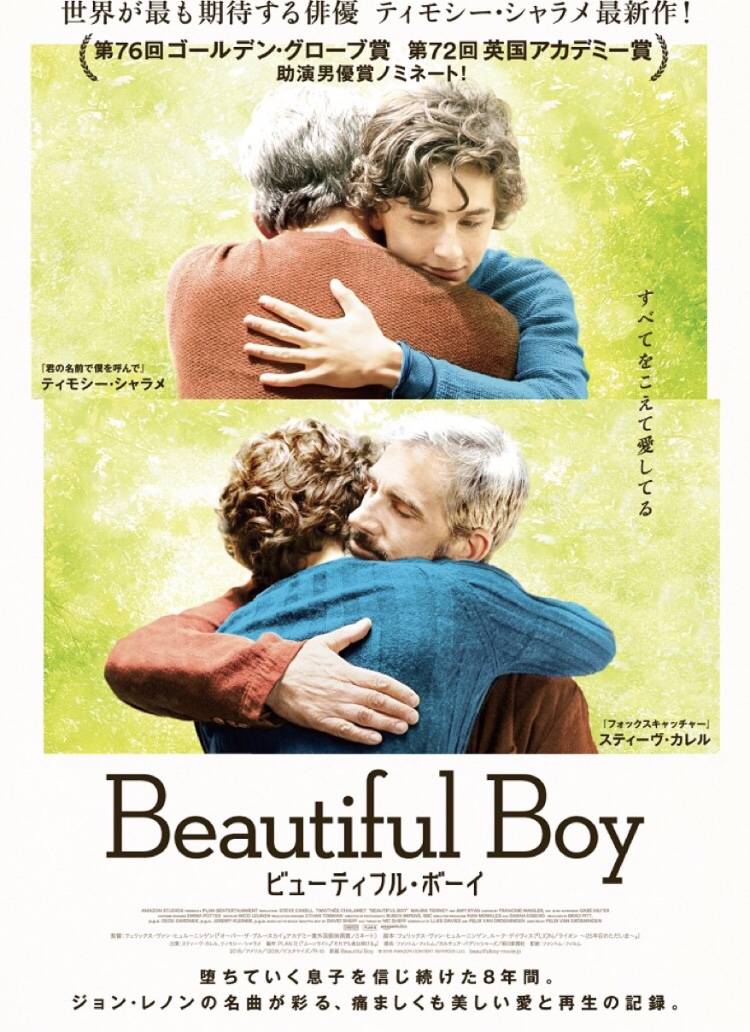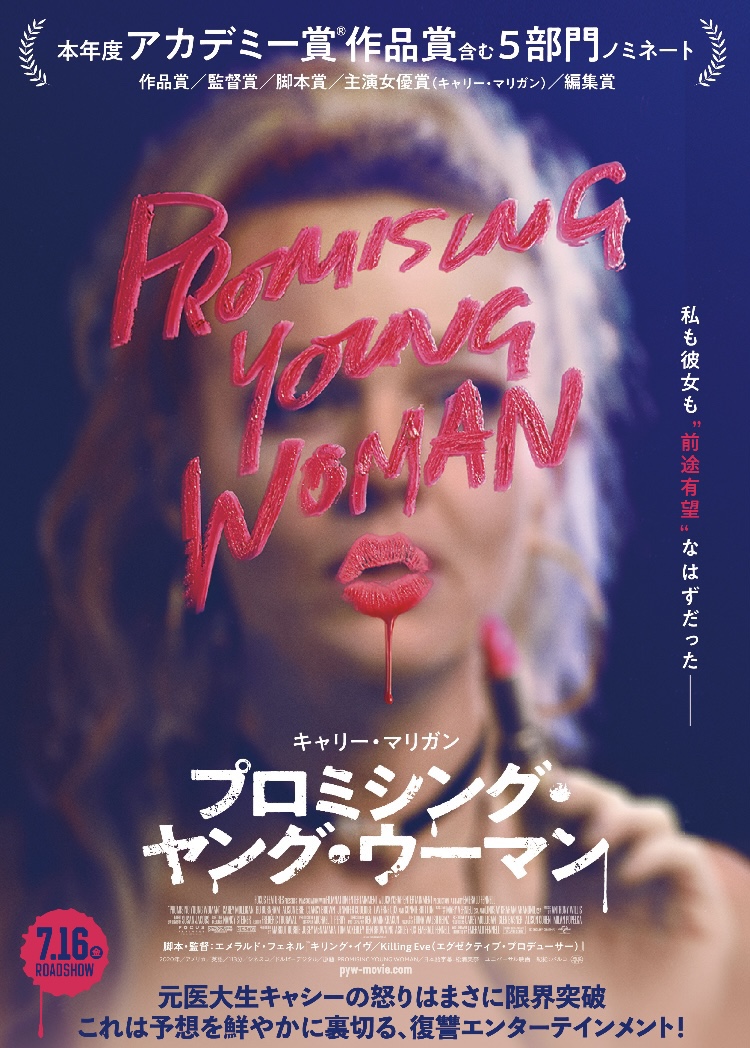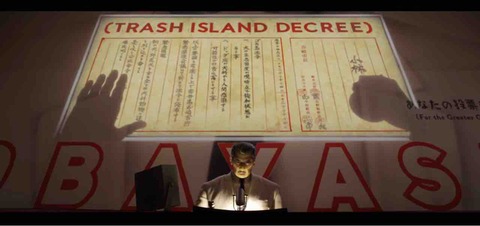みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『透明人間』についてお話していこうと思います。

『透明人間』という作品はそもそもH・G・ウェルズによって1897年に著された小説がオリジナル版です。
そもそものオリジナル版は、皆さんご存知の通りで主人公の科学者が薬品で、透明になり、数々の事件を起こしていくという内容になっております。
そして、同じく有名なのがジェイムズ・ホエールが監督を務めた1933年版の映画ですね。
こちらは原作とは設定が変わっている部分も多いので、直接的な映画化というよりは透明人間というアイディアを受け継いだ作品と言う側面は強いですし、これ以後も「透明人間」という設定を踏襲した作品が多く作られていく契機となりました。
ただ、VFXも当然ない時代なので、衣装や撮影の面で「透明人間」を再現するうえでかなり趣向が凝らされており、そういった部分でも高く評価されている作品となっています。
また、2000年に公開されたポール・バーホーヴェン監督の『インビジブル』もよく知られていますね。
こちらはケヴィン・ベーコンが主演ですが、やはりあの強烈な透明化シーンは有名です。
透明になる薬を身体に投薬すると、皮膚→筋肉→内臓→骨格の順番に身体が透明になっていくため、何だか身体が溶けていく過程を見ているようなグロテスクさがありました。
そして今回の2020年版の『透明人間』は、これまた大胆に現代風アレンジが為されているわけですが、これが非常に良く出来ているのです。
「透明人間」という設定に説得力を持たせる撮影や演出、録音などの素晴らしさは筆舌に尽くしがたいものがありますし、何よりプロットの脚色がお見事でした。
「見えない恐怖に苦しむ」というシチュエーションを、現代的なテーマにリンクさせて昇華させるというアプローチには驚かされましたし、今『透明人間』という作品を改めて映画で描く意義があると感じさせられましたね。
今回はそんな『透明人間』について個人的に感じたことや考えたことを綴っていきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事となっております。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『透明人間』
あらすじ
天才科学者エイドリアンの恋人であるセシリアは、身体的にも精神的にも彼から支配され、束縛された生活を送っていた。
ある日、そんな生活に限界を感じた彼女は、厳重なセキュリティで固められた彼の邸宅からの脱出を試みる。
何とか彼の邸宅から脱出するも、ガレージのセキュリティを作動させてしまい、眠っていたエイドリアンを目覚めさせてしまう。
セシリアは、妹の迎えがやって来る森の外れの道へと急ぐが、追う彼が徐々に迫って来る。
何とか、妹と合流し、車に乗り込み、その場から去ろうとする2人だったが、追いついてきたエイドリアンに車のドアガラスを割られ、狼狽する。
それでも何とか逃亡することに成功し、セシリアは、妹の知り合いで警察官のジェームズとその妹のシドニーが暮らしている一軒家に匿われることとなる。
エイドリアンは当然、彼らの家を知らないため、追ってくることはできないだろうとは思われたが、彼女は不安から逃れることができない。
そんなある日、彼女の元にエイドリアンが自殺をしたというニュースが飛び込んでくる。さらに、彼の弟であるトムからセシリアには莫大な彼の遺産の一部が残されていると連絡があった。
遺産を受け取り、彼から解放された生活への予感に期待に胸を膨らませる彼女だったが、その日から不審な出来事が身の回りで起き始める。
そんな状況に彼女は、エイドリアンが何らかの形で生きていて、自分に復讐を遂げようとしているのではないかと悟るのだった…。
スタッフ・キャスト
- 監督:リー・ワネル
- 原案・脚本:リー・ワネル
- 音楽:ベンジャミン・ウォルフィッシュ
- 撮影:ステファン・ダスキオ
- 編集:アンディ・キャニー
















ブラムハウス制作のホラー映画って本当にハズレが少ないというか、当たりだらけなのでいつも安心して見られますよね。
そして、監督・脚本には、『ソウ』シリーズのリー・ワネルが起用されました。
彼は『インシディアス序章』で長編監督デビューを果たし、その後『アップグレード』というSF映画も手掛け、こちらが高く評価されていますね。
劇伴音楽を担当したベンジャミン・ウォルフィッシュは、数々のホラー映画やSF映画の音楽を手掛けたことで知られており、2017年には『ドリーム』にてゴールデングローブ賞作曲賞のもノミネートされました。
撮影・編集には『アップグレード』にも携わったステファン・ダスキオ、アンディ・キャニーがそれぞれクレジットされています。
- セシリア・カシュ:エリザベス・モス
- エイドリアン・グリフィン:オリバー・ジャクソン=コーエン
- ジェームズ・レイニア:オルディス・ホッジ
- シドニー・レイニア:ストーム・リード
- エミリー・カス:ハリエット・ダイア
- トム・グリフィン:マイケル・ドーマン
















『ザ・スクエア 思いやりの聖域』や『Us』などの話題作に出演し、テレビドラマシリーズでの演技も高く評価されてきたエリザベス・モスが今作でも魅せてくれました。
何と言いますか、こんなにも「狂っているように見える女性」をに説得力を持たせられる演技をできる女優はなかなかいないと思います。
加えて、この「狂っているように見える」という部分が作品の肝でもあるので、ここが崩れると設定が崩壊してしまうわけですよ。その点で彼女の好演あっての作品なんですよね。
その他にも『ストレイト・アウタ・コンプトン』『ドリーム』に出演したオルディス・ホッジが出演していますね。
















『透明人間』解説・考察(ネタバレあり)
使い古された設定を巧みに魅せる演出と音響
(C)2020 Universal Pictures
この作品がホラーとして観客に一定のスリルを与えるためのハードルって実は非常に高いんですよね。
なぜなら、タイトルが『Invisible Man』ないし『透明人間』であり、「透明人間」というモチーフそのものについてはある程度ネタが割れてしまっている部分があるからです。
観客は、「透明人間」が登場するんだから、ある程度こういう驚かせ方や登場のさせ方をするんだろうなという予測は出来てしまいます。
















ただ、今回の『透明人間』に関して言うなれば、正直ネタを知っていても、普通に恐ろしいですし、しっかりと驚かせてくれます。
まず、音の作り方が非常に丁寧ですので、ぜひ音響の良い映画館で見て欲しいですね。
特に、本作は「足音」に非常に気を遣っている作品でもあり、その微妙な音の強弱や距離感が、絶妙に恐怖や不安を煽るように設計されているのです。
















当ブログ管理人の自宅の音響が2.1chなので、サラウンド環境がなく、そういった音響の楽しみを100%味わえていないため、歯がゆい思いをしております。
そして、カメラワークも本当に工夫されていて、前半から徹底的に「何もない空間」にカメラを向けるように意識されているんですよね。
セシリアがエイドリアンの邸宅から逃亡を図るシーンで、既に何もないはずの森や通りにカメラを向けてしばらく動かさないというシーンを取り入れていました。
その後、警察官のジェームズの家に移ってからのシーンでも、しばしば「何もない空間」にカメラを向けていき、そこでは特に何も起こらずに次の場面へと進行していきます。
この映像の積み重ねにどんな効果があるのかと言いますと、鑑賞する側に「透明人間」が登場するタイミングを分からないようにすることだと思うんですよ。
『透明人間』というタイトルの作品で、「何もない空間」にカメラが向けられれば、当然そこには誰かがいるのだろうと邪推をするのが当たり前と言っても過言ではありません。
しかし、そうしたショットが繰り返され、結果的に何もおきないという演出を繰り返され続けると、私たち観客は次第に「あれ?もしかして本当に何にもないんじゃないか?」というある種の疑心暗鬼の状態に追い込まれていきます。
そういう心理状態に追い込まれたとしたならば、もう完全にこの映画の術中に落ちてしまったも同然です。
私たちが高を括って油断しきった頃に、あの屋根裏からのペンキのぶちまけのタイミングで、いきなり「透明人間」が不気味かつ無機質に登場します。
















何だかんだ言っても人間が一番怖いのは、「顔がない」ものだと思うんですよね。
だからこそ、フォトショップの透過背景のようなキテレツなビジュアルで初登場するあの最初のカットで、観客は度肝を抜かれると思います。
つまるところ、本作は観客にネタが割れているからこそ、あえてそれを感じさせるような王道のカメラワークを繰り返し、観客を油断させることで、「透明人間」という使い古されたネタで「新鮮な驚き」を与えるという離れ業をやってのけているんですね。
加えて、ライティングにも工夫が見られます。というのも、今作はホラー映画でありながら「闇」や「影」にあまり頼っていないんですよ。
というよりもむしろ、明るい場所で観客を恐れおののかせることに心血を注いでいるかのようなそんな印象すら受けました。
やはり画面が明るいと、観客はどうしても安心感を感じがちですよね。どう考えても暗闇の方が「何か出そう」という印象は強まります。
しかし、『透明人間』という作品は、それどころか「明るい場所」で観客を怖がらせることに重きを置いているように感じられました。
明るい場所だと、どうしても視界が良好なので、観客は見えていないないし見えにくい部分がなく、不安要素が軽減されます。これは当然でしょう。
だからこそ、今作の「透明人間」の初登場シーンでも、恒例の真っ暗な屋根裏探検が終わった後、明るい廊下に下ろうとするときに、突如として不気味すぎる透明人間が現れました。
このように本作は、使い古されたネタを使うからこそ、他の作品よりもずっと演出面にこだわっていると思いますし、それが噛み合ったことで素晴らしい作品になり得たのだと思います。
見えない恐怖と戦い続けてきた「狂った女性」のリベンジ!
(C)2020 Universal Pictures
そして何と言っても驚かされたのは、今作が実に大胆にオリジナル版や映画版からストーリーをアレンジしている点です。
しかもただ単にストーリーを変更したわけではなくて、現代的なメッセージを有する作品になっているのがまた素晴らしいですよね。
とりわけ今作『透明人間』で、そのテーマに中心にいるのは「女性」であり、見えない圧力や社会的な不自由、そして虐待や暴力といった物事に苦しめられてきた「女性」が立ち上がる物語にもなっています。
















まず、今作に登場するエイドリアンは、セシリアを自分の意のままに操りたいと考えており、常に自分の支配下、管理下に置いていきたいという願望を持っています。
この設定が、長らく男性優位社会の中で虐げられ、男性の陰に隠れてきた女性たちの苦悩を表現しているようにも感じられますね。
そして、セシリアは必死にその管理や支配から抜け出そうとします。彼女は自分が受けいたDVないし暴力から逃れようと勇気を出して一歩を踏み出すわけですよ。
















インタビューの中でエリザベス・モスがこう語っています。
私はワネル監督と話して、女性の視点を提供することになった。女性として生きていると、何か意見を言っても、自分の考えが間違っているとか、自分が狂っていると思わされることはよくあるので。ワネル監督はとてもオープンで、積極的に私の意見を取り入れてくれた。おかげで、自分の意見を殺されてしまった女性の心境が、しっかり描かれていると思う。
(映画com.より)
男性上位社会の中で、女性が自分は虐げられている、暴力を受けていると声を上げたとしても、「あいつは狂っている」「あいつの方がおかしいんだ。」と一蹴されてしまうことは、幾度となく繰り返されてきた事象でしょう。
どう考えても自分が被害を受けていて、それを主張する側の自分に正義があるはずなのに、それを社会の流れの中で捻じ曲げられてしまい、正当に認知してもらえないわけです。
「透明人間」というモチーフはある種の「見えない圧力」を想起させるものであり、女性が男性優位社会の呪縛から逃れようとする力を抑え込もうとするものとして描かれています。
セシリアは、必死に「透明人間」の存在を訴え続けますが、次第には「オオカミ少年」のような扱いを受け、どんどんと立場が悪くなっていきました。
そして、この映画においてエイドリアンが彼女に執着する理由の1つに、セシリアが自分の子どもを妊娠しているからというものがあるのは興味深いポイントですよね。
つまり、彼はセシリアを自分の管理下に置いておきたいのであり、それでいて自分の子どもを産ませたいんですよ。
















「狂っている女」のレッテルを貼られた彼女は、ついにはエイドリアンに陥れられ、姉を殺害した容疑で収監されてしまいます。
加害者はどう考えてもエイドリアンであるはずなのに、なぜか彼女が逮捕されてしまうという正義がひっくり返るような事件が生じるわけですが、セシリアは諦めることはしません。
その後、追いつ追われつの戦いがあり、何とか彼女は「透明人間」を仕留めることに成功するのですが、これがエイドリアンではなく彼の弟だったんですよね。
私たちの社会でもそうですが、こういう時に本当の悪は雲隠れをし、「トカゲの尻尾きり」のように部下が罪を着せられてしまうものです。
そして、セシリアはそんな社会ないしエイドリアンという男の歪みや狂気を知っており、だからこそ彼の復縁の申し出にも、もはや騙されることはありません。
エイドリアンと直接会うことを選んだセシリアは、彼の甘い言葉に対して徹底的に不信用の立場を貫き通し、最終的には自分の姉を殺害された時と全く同じ手口で彼を自殺に見せかけて殺害します。
彼女は、どれだけ社会に、周囲の人に「狂っている」と言われようと、自分が正しいことを知っているし、だからこそ他人にどんなことを言われようとも、エイドリアンが悪であるという結論を揺るがすことはなく、行動に移しました。
弱者やマイノリティ、虐げられてきた人たちの叫びに対して「彼らの方がおかしいのである」という認識で一蹴し、それを聞き入れようとしないということは、歴史的に見ても、何度も起きてきたことでしょう。
そういった社会において優位にいる者が行使できる「見えない力」に悩まされ、自分たちの方が「狂っている」というレッテルを貼られた人は大勢いるのだと思います。
















見えない社会の圧力に屈してきたセシリアが、今度は「女性」の番だと言わんばかりに、エイドリアンの武器であった「インビジブルスーツ」を我が物のように着こなし、リベンジを果たすラストは痛快です。
「狂っている」と決めつけている側の方が「狂っている」のだと高らかに宣言するかのようなセンセーショナルな幕切れでした。
「透明人間」という題材に、上手く現代的なメッセージを盛り込み、昇華させたと思いますね。
グレーな結末を選んだことへの賛辞
『透明人間』は一見すると、単純な勧善懲悪の物語に見えるのですが、結構このラストに関しては賛否あると思うんですよね。
















そこがこの映画の重要なポイントでもあるのですが、私たちがエイドリアンを犯人であると断定できる情報って非常に限られていると言いますか、明確なものは存在していないとすら言えます。
まず、冒頭に逃亡したセシリアを追ってきたときに、車のドアガラスを割ったときの暴力性の表出は1つ重要なファクターと言えるでしょうが、それが決定的な決め手になるかと言われると難しいですね。
また、当然彼の家で「インビジブルスーツ」が開発されていたわけですから、最も犯人に近いのは、当然彼になるはずです。
しかし、一般的に見ると、今回の事件の顛末はトムがエイドリアンを監禁し、自らインビジブルスーツを着て、セシリアを襲い、彼女が精神錯乱の状態であるように世間に認めさせることで、遺産の相続権を放棄させようとしていたということになります。
この顛末自体には、筋が通っており、普通に考えるとおかしなところはないんですよ。
表面的な情報からだけで考えると、トムが黒幕だったという結論に当然なるわけで、トムがが嘘をついていると主張し続けているセシリアの方がやっぱり「狂っている」んじゃないかと思えてきます。
そんな物語において、セシリアが確信に至る1つのシグナルになったのが「サプラ~イズ」という言葉なんですよ。
透明人間が精神病棟でその姿を見せた時に「サプラ~イズ」という言葉を発していたかと思うんですが、ここでその何気ないワードセンスとその響きが合致するように意図されているのです。
それを聞いた彼女はトイレに赴くふりをしてインビジブルスーツを身に纏い、そしてエイドリアンを自分の妹が殺されたのと同じ手口で殺害しました。
この結末は個人的にも相当グレーだと思いますし、その描き方に疑念を呈する人もいらっしゃることと思います。
















本作『透明人間』は、こういった疑念の声を封じ込めることだって当然できたと思います。その方法は簡単で、エイドリアンが犯人であるという明確な証拠を出せば良いだけなわけですよ。
















あえてしていないということは、そこには何らかの制作側の意図があると考えるのが自然です。
私が考えるこのグレーな結末の意図は以下の2つになります。
- 「狂っている」というレッテルを貼られた女性が全く同じ手法で男性側にそれをやり返すこと
- 周囲から「狂っている」と虐げられてきた女性の正常性の担保
まず、前者はおそらく批判の争点にもなる部分だとは思うのですが、「カウンター」として描いたということであれば、有効だと個人的には思います。
つまり、長らく男性優位社会の中で苦しみ、虐げられて、「狂っている」というレッテルを貼られてきた女性の代表としてセシリアがそのレッテルをエイドリアンに貼り返すという構図ですね。
そして、2つ目の方が個人的には重要だと思っています。
なぜなら、これまで女性たちに「お前の方が狂っている」と決めつけてきたのは周囲の人間であり、彼女たちは自分が正常であるにも関わらず、その圧力を受けて自分が間違っているのだと心を病んできたわけです。
だからこそ『透明人間』という作品は、その意匠返しでもって結論づける必要があったのだと個人的には思っております。
つまり、観客が「お前の方が狂っている!」というレッテルを貼れてしまう隙を残したうえで、映画としてはセシリアの主張を全肯定するという結末こそが重要なんですよ。
結局のところ、彼女が恋人関係を続けていた頃にエイドリアンがどんな様子だったのかは、ほとんど描かれませんので、本当に彼が犯人だったのか、黒幕だったのかという問いについては明確に回答されていません。
ですので、真相が分かるのは、やはりセシリアだけなんですよ…。
私たちは、うわべだけの情報でその人がどんな人で、どんな苦しみを味わってきたのかを良く知りもせずに判断してしまうことがあります。SNS全盛期の現代においては、そういった判断をした個人がある種の「被害者叩き」のような行動を起こすことも珍しくありません。
そうして、苦しんでいる被害者が正義の訴えをしているにもかかわらず、世間から虐げられるという状況も散見されます。
そんな状況になったとすれば、匿名で被害者たちに悪意を向けた私たち自身が本作における「透明人間」のような存在になってしまうわけですよ。
私たちに、セシリアの苦しみや葛藤を理解することはできません。というよりもできないようにこの映画は意図的に描写を伏せてあります。
そのため、私たちはむしろこのエンディングを見て、セシリアに対して「狂っている」というレッテルを貼ってしまわないかどうかを試されているような気すらしてきます。
彼女は誰にもその苦しみを理解されない、孤独な状況の中で、たった1人で答えを出したのです。それは独善的で主観的だったかもしれません。
ただ、少なくとも、彼女の置かれていた状況を知り得ない私たちにその行動や決断を糾弾する権利はないのかもしれませんね。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『透明人間』についてお話してきました。
















もうこの題材で新しいものは作れないだろうと思っていた頃に、新しい風が吹いてきたような、そんな印象を受けます。
「お前が狂っている」と言い続けられてきた女性が立ち上がり、「違う、お前が狂っているんだ!」と痛烈に突きつける痛快なリベンジ劇でしたね。
また、プロットだけでなく演出面でも素晴らしく、特に音響にかなりこだわりがあるように見受けられますし、ぜひ劇場でご覧になって欲しい1本です。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。