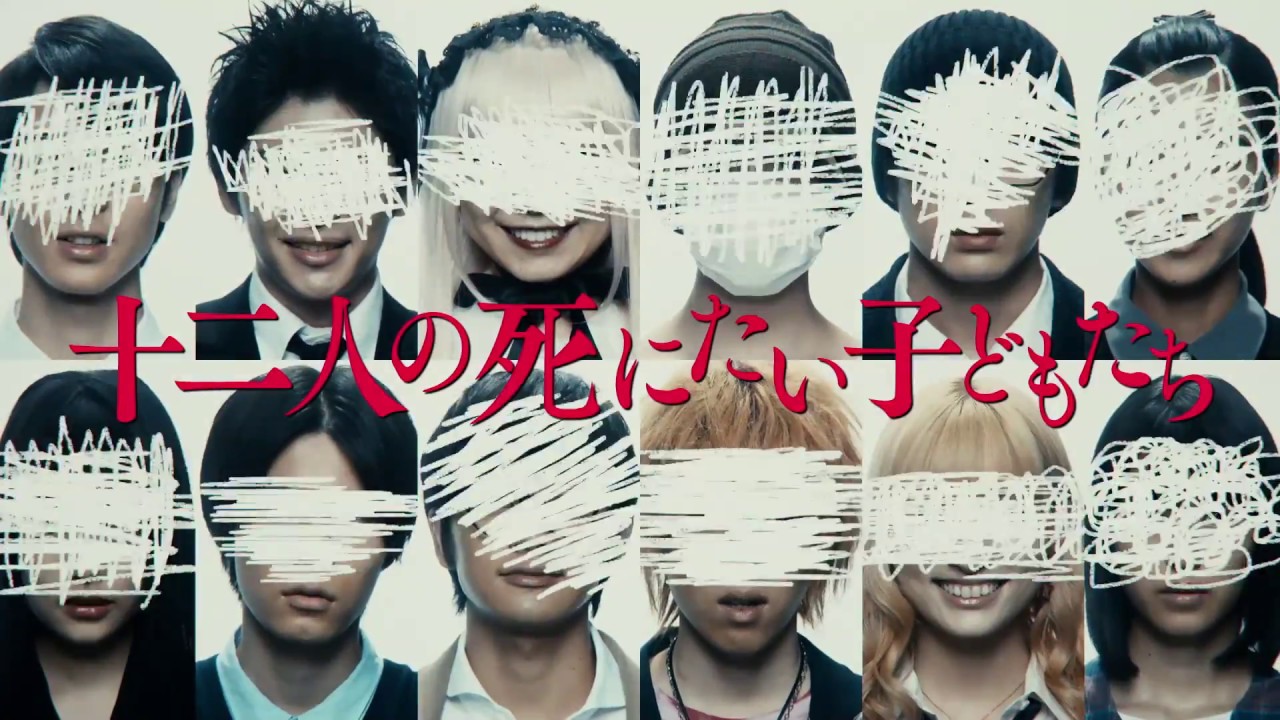みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『ファーストラヴ』についてお話していこうと思います。

小説が話題になっていることも知っていましたし、島本理生さんの作品は『シルエット』『ナラタージュ』『Red』なんかはチェックしてきていたのに、実は読めていませんでした。
読み進める中で、とんでもない小説であるということは容易に気がつきましたが、改めて調べておりますと、今作は直木賞も受賞していたんですね。
ただ、それも納得の出来栄えですし、とにかく物語の構造が閉じた世界の話なのに多面的・多層的で、人間軸と時間軸に基づいて物語を立体的に拡張していく手腕が卓越しています。
色々な見方ができる作品で、読む人によっては「救いの書」であるという印象を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
かくいう私も読みながら終盤の方は気がつくと涙がこぼれていましたし、何だか「救われた」ような気持ちになっていたのを覚えています。
そして、今回そんな傑作小説が映画化されるということで、メガホンを取ったのが堤幸彦監督です。
私のイメージですが、最近の堤監督は「駄作と良作を交互に作る人」です。
- 2016年:『RANMARU』
- 2018年:『人魚の眠る家』
- 2019年:『12人の死にたい子どもたち』
- 2020年:『望み』
あくまでも個人の意見ですが、上から「駄作、良作、駄作、良作」という印象を受けました。
そして、この順番からすると、今回の『ファーストラヴ』は「駄作」の方の打順なのですが、既に試写会で鑑賞された方からの評判を見ていても、堤幸彦監督作品のベストとの呼び声も高い1本となっています。
もちろん原作が抜群にいいので、物語面で大崩れするようなことはないと思いますが、難しいのは登場人物の描写の仕方でしょうね。
今作は、いろいろなキャラクターが、「他人に自分や誰かを重ねる」という行為を繰り返す中で進行していきます。
そういった人間間のシュミラリティにどのようにして説得力を与えて、観客に感じ取らせるかという部分では、監督の手腕が問われることとなるでしょう。
今回はそんな『ファーストラヴ』について自分なりに感じたことや考えたことをお話させていただきます。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
『ファーストラヴ』
あらすじ
臨床心理士として活躍している真壁由紀の元に出版社から執筆依頼が入る。
その内容は、アナウンサー志望の女子大生、聖山環菜が、キー局の2次試験直後に、父で画家の聖山那雄人を刺殺した事件について、1冊の本にまとめてほしいというものだった。
「アナウンサーになることを否定されたから父親を殺害した」というのがおおよその犯行動機の見立てだったが、取り調べの中での環菜の発言が話題になる。
「動機はそちらで見つけてください。」
由紀の義弟である弁護士の庵野迦葉は環菜の国選弁護人に選任されており、由紀は彼と共にこの事件に秘められた謎と、そして環菜の深い心の闇を追っていくこととなる。
被疑者である聖山環菜を取材していく中で、由紀は彼女の姿にいつの日かの自分を重ねるようになった。
それは、閉じ込めてきた壮絶な過去の記憶だった…。
スタッフ・キャスト
- 監督:堤幸彦
- 原作:島本理生
- 脚本:浅野妙子
- 音楽:アントンジュリオ・フルリオ
- 主題歌:Uru
- 挿入歌:Uru
















さて、本作の監督を務めるのは記事の冒頭でもお話したように堤幸彦監督です。
多くの人にとっては『TRICK』や『SPEC』の監督というイメージなのでしょうか。
ただ、このタイプの作品が得意だと思われがちですが、近年は小説原作のミステリヒューマンドラマ原作の実写化を次々に成功させています。
今回の『ファーストラヴ』も、近年の『人魚の眠る家』や『望み』の成功がありましたので、比較的期待値は高かったです。
脚本には、少女漫画の実写などを手掛ける傍らで『彼女がその名を知らない鳥たち』のような重厚なヒューマンドラマの脚本も執筆してきた浅野妙子さんが担当しています。
劇伴音楽には、アントンジュリオ・フルリオが、そして主題歌&挿入歌にはUruさんが起用されていますね。
Uruさんは『テセウスの船』や『罪の声』の主題歌で高評価され、今話題沸騰中のシンガーです。
今回の主題歌となっている『ファーストラヴ』も聞いているだけで、強烈なノスタルジーとエモーションを自分の内側からかきだされるような感覚を抱きます。
それくらいに不思議なパワーを感じる歌声と存在感がありますよね。
- 真壁由紀:北川景子
- 庵野迦葉:中村倫也
- 聖山環菜:芳根京子
- 聖山那雄人:板尾創路
- 小泉裕二:石田法嗣
- 賀川洋一:清原翔
- 聖山昭菜:木村佳乃
- 真壁我聞:窪塚洋介
















基本的に自分の内に不安定さを抱えたキャラクターが多い作品だと思います。
まず、主人公の由紀を演じたのは北川景子さんです。映画ファンの間でもしばしば「あまり演技が上手くない」という指摘が上がる女優さんですが、今回の『ファーストラヴ』での演技は「キャリアハイ」との呼び声も高いです。
そして、由紀の「閉ざしていた過去」に関係のある物語のキーマン庵野迦葉役として中村倫也さんが出演しています。
原作を読んでいて、このナチュラル「女たらし」感とミステリアスさ、軽薄さ、それでいて弁護士としての職務への情熱を兼ね備えたキャラクターを演じられるのは、中村さんしかいないのでは?くらいに思っていたので、イメージドンピシャです。
そして、何と言っても今作の中心にいる聖山環菜役には、芳根京子さんが起用されています。
『累』などで既にその演技が高く評価されている彼女ですが、今作での演技は女優としてもう1段上に進むためのきっかけになりそうですね。
また、個人的に窪塚洋介さんの演じる真壁我聞に本当に癒されました。
というより、このキャラクターって『ファーストラヴ』という不安定すぎる物語の中で唯一の拠り所というか「避難場所」のような人物なんです。
だからこそ、窪塚さんの少し風来坊的な雰囲気と、滲み出る優しさのようなものが完全にマッチしていました。
『ファーストラヴ』解説・考察(ネタバレあり)
オースター的でありながら、多層的・立体的な物語に
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
この『ファーストラヴ』という作品の大まかなあらすじを読んだり、映画館での予告編を見たりしていると、どうしても思い出すのはポール・オースターの『幽霊たち』でした。
探偵小説でありながら、探偵が対象を監視しているうちに、その対象が自分なのではないかと錯覚してくるという典型的なポストモダン小説とされるこの作品を思わせる要素が多かったのです。
主人公の由紀は自らの過去に「秘密」を抱えており、それを誰にも打ち明けることができずに自らの過去の中に閉じ込めてきました。
そんな彼女が取材のために正対することとなる環菜という女性もまた過去に並々ならぬトラウマを抱えて生きて来た人間です。
だからこそ、由紀は環菜に取材を重ねていくうちに、環菜の中に「過去の自分」の姿を垣間見るようになり、目を背けてきた自分の記憶と直面することを求められます。
このような他人を見ているうちに、その他人がいつしか自分自身に見えてくるという構造は、実に『幽霊たち』のそれを思わせるものなのです。
ただ、島本理生さんが著したこの『ファーストラヴ』の物語はこうした「構造」に主眼を置いているわけではなくて、むしろその「構造」的な広がりを登場人物の「感情」の受け皿にしています。
そして、その「感情」を描くための「軸」みたいなものが物語を立体的に拡張することに成功していました。
まず、『ファーストラヴ』という作品には時間軸ないし時代・世代軸のようなものが見え隠れしています。
時間軸という観点で行くと、当然それぞれのキャラクターが抱える過去とそしてその結果として立っている現在があり、そして裁判を契機としての彼らの未来にも言及されていました。
一方で時代・世代軸という観点で行くと、男性のキャラクターも女性のキャラクターもそうですが、メインキャラクターたちとそして彼らの親世代という2つの世代が対比的に描かれていることに気がつきます。
主人公の由紀が、過去に確執の合った母に「なぜあんな父と離婚を選ばなかったのか?」と尋ねるシーンがありますが、その答えを聞いた時の印象が次のように綴られていました。
言い訳めいては、いなかった。ただ本当にそう信じて疑わなかったのだ。若かりし頃の、この女性は。時代か、教育か、個人的な資質か。もう現代では機能していない、たくさんの過ぎ去っていったものたち。
(島本理生『ファーストラヴ』より引用)
ここにも「時代」という言葉が記述されていますが、親世代子世代での軸で見た時の対比構造やギャップも今作の物語をより立体的にしていく上で一役買っていると言えます。
そして、時間的なものとは別に、登場人物の人間軸が用意されていました。
まず、『ファーストラヴ』の中心にあるのは、由紀とそして環菜のシュミラリティです。
由紀が環菜の中に、自分の閉じ込めてきた過去を垣間見る中で物語が進行していくのですが、他のキャラクターたちも環菜を巡って、その向こう側に別の人物を見ているような構造が作品の中に埋め込まれています。
迦葉というキャラクターもまた彼女と関わる中で、大学時代に由紀と過ごした日々のことを思い出しているのでしょう。
そして、環菜の母親である昭菜にも複雑な事情があり、彼女もまた環菜の中にいつの日かの自分を見出しているという構造があります。
このように環菜という中心を媒介として、その向こう側に自分自身を見出していくという形で登場人物たちの「繋がり」が演出されていくのです。
こうした時間軸と人間軸がしっかりと作品の屋台骨として機能していることにより、『ファーストラヴ』の物語は実に立体的になっております。
そして、その物語としての空間的な広がりが、特大のエモーションを内包するためには欠かせないものだったのです。
1人の女性の裁判を通じて、そこに「自分」を見出したキャラクターたちが同時多発的に救われていくという展開を、これほどまでに感動的に描かれると文句のつけようもありません。
しかし、ただ「感情」にスポットを当てるだけでは、作品として散漫になっていたと思いますし、私小説のような主観的で一方的なものに感じられていたと思います。
『ファーストラヴ』は物語の軸や構造を確立させることによって、終盤に巻き起こる登場人物の感情の渦に対しても耐えうるだけの作品としての強度が備わっているわけです。
ここに、本作の小説としての、物語としての完成度の高さを感じました。
「自分が間違っている」と世界に折り合いをつけてきた全ての人へ贈る
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
さて、この『ファーストラヴ』という作品を鑑賞していて、私自身も思わず感動して涙してしまったことを記事の冒頭で明かしました。
















その正体を考えていた時に、私が『ファーストラヴ』から最も強く感じ取ったのは、「受容」という言葉でした。
この作品は、言わば誰にも受け入れてもらえなかった人間が、自分が受け入れられる場所や拠り所を見つけるという物語を描いているのです。
人間は常に他者と事故との間にギャップを抱えて生きているわけですが、それは同じ物事に際しても違った受け止め方をしたり、印象を抱いたりするという方委で現れることがあります。
小説の方の「あとがき」で作家の朝井リョウさんがまさしくこのことを指摘していて、強く共感したので、一部を引用させていただきます。
今作で描かれる環菜が置かれてきた様々な状況は、読者自身の肉体と世界との関係性によって受け取り方が大きく変わるものばかりだ。私自身、絵の世界から遠く離れている身として、「確かに画家の子どもだったらデッサンモデルとかやらされるのかもしれないなぁ」と感じたし…(略)
(『ファーストラヴ』あとがきより引用)
















自分が遠景から客観的に見ていると、何と言うかそれほど大事には思えないことも、その当事者からするととんでもない精神的・肉体的苦痛を抱いていることなのかもしれないのです。
劇中に「父親が環菜に自宅の戸締りをさせない」という描写がありましたが、私なんかは田舎育ちなので、まあ「戸締りしなくても大丈夫じゃない?」というイメージを持っていたのですが、社会人になって都会に出てきて見ると、そんな考えが甘すぎることに気がつきました。
おそらく、田舎にいた頃の自分がこの『ファーストラヴ』を鑑賞したとして、環菜が「夜に家に独りぼっちで戸締りができない」という状況からどれほどの苦痛を感じていたのかは理解できなかったように思います。
このように『ファーストラヴ』は、登場人物間でギャップを表出させていくことはもちろんとして、作品を鑑賞する主体である私たちにも環菜との「ギャップ」を感じさせるような作りになっており、これが何ともお見事なのです。
こういうことは、結局自分の身をもって知っているか、経験してきたかが理解するための鍵になって来ます。
そう思うと、環菜がこれまで誰にも愛されていない、自分の居場所がないと感じてきたのは、きっと自分の問題を遠景から眺めて、「そんなのは問題ではない」と言ってくるような人間ばかりだったからなのではないでしょうか。
何より大きかったのは、人間が最も帰属意識を抱きやすいコミュニティである家族にすら抱えている苦悩や葛藤を理解してもらえなかったこと、そしてむしろ環菜自身がおかしいのだと感じさせるように仕向けられたことが彼女の人生を狂わせてしまったように思います。
環菜は、元々自己主張をきちんとする子でしたが、父親や母親にそうした言葉を遮られ、否定されてきました。
「デッサンモデルに性的な視線を感じるお前がおかしい」
「夜中に戸締りをして父親を締め出すお前がおかしい」
「デッサンモデルをやりたくないがためにリストカットをするお前がおかしい」
こうした言葉を投げかけられながら育った彼女はいつしか自分が「望む生き方」ではなく他人に「望まれる生き方」をするようになります。
それは彼女なりの心を守るための防衛機制のようなものだったのだと思いました。
つまりは、世界や周囲の人間ではなく、自分が「悪い」「おかしい」のだという理屈で、他人を妄信的に受け入れることによって、何とか折り合いをつけてきたんですよね。
しかし、そんな環菜は同じような境遇を抱え、同じような問題に苦しみ、同じように理解してくれる人を探して生きて来た由紀というはじめての「理解者」に出会い、変わり始めます。
由紀は、環菜の人生の中で初めて「あなたではなく世界や、社会や、そして周囲の人間が間違っている」と言ってくれた人だったからです。
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
この言葉が、どれほど環菜に勇気を与えたのだろうか。希望を与えたのだろうか。そして彼女自身の尊厳と価値を取り戻させたのだろうか。
『ファーストラヴ』という作品は、まさしく「受容の物語」と言えます。
由紀も過去に家族に居場所を見出せず、そして誰にも受け入れられないと自暴自棄になった過去を持っています。
一方の迦葉も母親から拒絶されたことが大きなトラウマになっており、その後も人間関係を上手く築けずに生きてきました。
そんな2人が出会った過去においては、お互いに拒絶し合い、居場所になるはずだったはずの場所を壊してしまいました。
彼らは自らの言葉で、「受け入れられるはずだった場所」を反故にしてしまったという過去を引きずっているのです。
そうして由紀は自らの存在を全面的に受け入れてくれる我聞という夫に出会い、変わっていきます。しかし、彼女の思考の底にあるのは「いつか迦葉との過去が露呈し、この居場所も失われてしまうのではないか」という恐怖ですよね。
対照的に迦葉の方は、今も母親との関係を断絶しており、同時に自分の母親の面影を宿した由紀に拒絶されたことに葛藤を抱き続けています。
環菜に限らず、彼女に向き合う者たちも、自分自身を受け入れてくれる人間や場所の希求に苦しんできた人たちなのです。
だからこそ、彼らは環菜の苦しみに寄り添うことができます。
由紀は、カウンセラーとして環菜の心のもつれを紐解き、本当の思いを引っ張り出すことに成功しました。
そして迦葉は、弁護士としては「一転して無罪主張なんて展開」が裁判では不利になることが分かった上で、環菜の主張を全面的に受け入れます。
「自分が間違っている」と言われ続けて生きてきた人間が、初めて「あなたが正しい」と告げられる。
人生で誰かにかけて欲しかったたった一言。ずっともとめていたほんの一言。
その一言がもたらす「救い」の重さを『ファーストラヴ』という作品は、私たちに感じさせてくれます。
そして、何だか読んでいる自分自身も、何かに受け入れてもらえたような不思議な安堵が読後にじわじわとこみ上げてきて、無性に泣きたくなるのです。
「ファーストラヴ」というタイトルに込められた意味
さて、ここで本作の印象的なタイトルでもある「ファーストラヴ」について考えてみようと思います。
















作品を読んでいる最中は、当然環菜が自分の「初恋」を話をしているので、なるほど事件にそのことが関係しているからタイトルになっているのだろうと思わされます。
加えて、このタイトルは由紀と迦葉の関係のことをも表しているのだろうと何となく納得がいくわけです。
















私が思ったのは、この「ラヴ」と言うのは、「恋」というよりむしろ「愛情」という意味で用いられているのではないかということでした。
つまり、この世界で初めて自分に愛情を向けてくれる人との出会いのことを「ファーストラヴ」と表現しているのではないでしょうか。
そう考えていくと、やはり由紀に最初に愛情を与えてくれたのは、両親ではなく、迦葉でもなく、やはり我聞なんですよ。
過去にトラウマを抱え、自分のことを気持ち悪いとすら思っている彼女を初めて拒絶することなく受け入れてくれたのは、彼でした。
だからこそ、由紀にとっての「ファーストラヴ」の相手は我聞です。
一方で、そんな「ファーストラヴ」をこれまで経験することなく生きてきて、その果てにこうした事件になってしまった環菜は悲しいですよね。
彼女を初めて気遣い、そして支えようという素振りを見せてくれたのは、きっと小泉裕二だったのだと思いました。
しかし、彼は彼女を支えられるだけの勇気もなく、同時にそうした愛情を他の男たちと同様に性欲が上回ってしまったがために、彼女にとって大きなトラウマになってしまったのです。
それでも、大人になった彼は、何とか今の彼女を守ってあげたいと、公判の証言台に立ちました。
そして何と言っても環菜にとっての「ファーストラヴ」は他でもない由紀と迦葉なのだと思います。
この世界で初めて彼女の言うことを受け入れてくれた、そして愛情を向けてくれたのは、きっと彼らだったからです。
それ故に本作を見終わると、もっと環菜が早く「ファーストラヴ」に出会えていたら、あんなことにはならなかぅったのにというやりきれなさにも似た感情を抱いてしまいます。
せめて「ラヴ」を知った彼女のこれからが幸福な人生であって欲しい、愛情に満たされた人生であって欲しいとそう願いながら、本を閉じる手は少し震えていました。
映画版の演出面の凄み、原作との違いに迫る
さて、ここからは映画版を鑑賞してきましたので、その演出面の素晴らしさや原作との違いに込められたメッセージ性を掘り下げていこうと思います。
今回の『ファーストラヴ』ですが、事前の評判通りでして、堤監督作品の中でも屈指の出来栄えであり、加えて島本理生さんの原作の映画版としても最高傑作と言って相違ない内容だと感じました。
今回お話したいのは、以下の5つの観点です。
- 独特なショットやカメラワークの意図
- 白色系と暖色系の照明の使い分け
- モチーフやシチュエーションの反芻
- なぜ映画版では主人公夫婦に子どもがいないのか?
- ラストで環菜が自分の物語を書きたいという意味
















①独特なショットやカメラワークの意図
さて、映画『ファーストラヴ』ですが、実にカメラワークが独特なので、ここは要注目です。
まず、登場人物の会話を描く際にしばしば用いられるのが「肩越しショット」ないし「オーバーショルダーショット」と呼ばれる、1人の肩越しにもう1人の登場人物が話している様を捉える手法です。
しかし、今作では、このショットがほとんど使われていないと言っても過言ではありません。
基本的に、登場人物を切り返しのショットで交互に映し出していくか、少し引いた位置から2人の全身がフレームに収まる形で映し出すかのどちらかなんですよね。
「オーバーショルダーショット」はしばしば登場人物の関係性の表出、信頼感の表れであると指摘されますが、それを使わないことで、本作はキャラクター同士に欠如している安心感や信頼感を表出させています。
そして、序盤に関して言うならば、妙にカメラの挙動は安定していて、手ブレ感のようなものはありません。
















まず、大きな違いは、カメラに手ブレ感のようなものが出始めて、映像に「揺れ」が生じるんですよ。
これは言うまでもなく登場人物の感情の「揺れ」を表現していますし、序盤の妙に一歩引いていて、安定したカメラワークと対比されることで効果的に機能します。
加えて、後半になるにつれてクローズアップショットが圧倒的に増えていくのも大きな特徴です。
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
特に、環菜が由紀に自分の本心を告白するシーンでは、これまでとは比べ物にならないほどに2人の顔をクローズアップした映像になっています。
今作では、カメラと被写体の距離感がキャラクター同士の信頼感や安心感を表す尺度になっているような気がしました。
つまり、序盤のバストより上あたりを捉えるショットを切り返すだけの会話や、少し引いた位置からのショットによる会話の時点では、カメラと被写体に距離があり、それがそのまま登場人物同士の心の距離にリンクしています。
だからこそ、終盤にかけてカメラがどんどんと被写体に寄っていくことで、信頼感や親密さのようなものが際立つのです。
このカメラワークやショットの対比は非常に巧妙な演出だと感じましたね。
②白色系と暖色系の照明の使い分け
次にご紹介したいのが、本作における照明の使い分けですね。
序盤から何となく白色がかった映像が特徴的な本作ですが、これはおそらく意図的にそうした風合いの映像に仕上げているのだと思います。
劇中で由紀の大学時代の回想シーンが入りますが、回想パートの映像はほんのり白色がかったというより、「病的に白い」という表現が似合うくらいに映像が白くなりました。
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
















この映像の色味の対比は、とりわけ由香や環菜がその時間軸に対して抱いている感情を表現しているのではないかと感じました。
というのも2人は、それぞれに迦葉とそして小泉との過去の記憶を「隠したい」と願っていましたよね。
つまり、彼らの回想から色が失われているのは、彼らがその記憶を意図的に忘れたり、心の奥にしまい込んだりして、心の平穏を保とうとしていることの表れなんだと思います。
消し去りたいけれど、消すことができない。そういう複雑な感情があの病的な「白さ」に垣間見えていました。
そして、物語の終盤になるにつれて、徐々に夕暮れ時のシーンが増えていきます。
特に由香と環菜がそれぞれのトラウマを告白するシーンや由香が病室で夫の我聞に過去について打ち明けるシーンでは明確に暖色系の照明が際立っていました。
これは「ファーストラヴ」を得たことで、彼らの世界が愛の温かさによって少しずつ色づいていく様を見事に表現していると思いました。
ぜひ、この光の使い方の対比については注目していただきたいですね。
③モチーフやシチュエーションの反芻
まず、『ファーストラヴ』が優れているのは、記事の序盤でも書きましたが、キャラクターのシミュラリティを巧妙に演出していく点です。
そしてそれは登場人物の置かれている状況や、映像に登場する事物によって為されることもしばしばでした。
原作にも存在していますが、映画版でより際だったと感じるのは、「裁判」「デッサン会」「アナウンサーの面接」という3つのシチュエーションを重ね合わせて観客に突きつける場面だったと思います。
「デッサン会」は環菜が子どもの頃に経験したトラウマであり、多くの男子大学生から長時間見つめられることに恐怖感を抱くようになっていました。
そしてそれがリンクし、彼女が意識を失ってしまったのが、「アナウンサーの面接」でした。面接官が男性ばかりであり、彼らから見つめられることによって、彼女は過去のトラウマを思い出してしまったのです。
しかし、似たようなシチュエーションが最終的には「裁判」という形で再びスクリーンに映し出され、そこで環菜は堂々たる振る舞いを見せます。
この類似したシチュエーションの繰り返しと、変化によってキャラクターの成長を演出するという手法は、映画になり「視線」が視覚したことでより効果的になったと言えるでしょう。
そして、映画版として優れていたと感じたのは、「写真」というモチーフの使い方です。
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
思い返すと興味深いのですが
- 由紀が抱えているトラウマのきっかけ→写真
- 由紀が自分を愛してくれる我聞と出会ったきっかけ→写真
という具合に、由紀の人生の転機には「写真」というモチーフが密接に絡み合っていました。
そして、物語の終盤に、我聞の個展のシーンがあり、ここでは「家族」の写真が展示されました。
家族写真を見つめる由紀と我聞のラストカットは、2人が本当の意味で家族になれたことを表現したものだと推察されます。
つまり、由紀が家族という拠り所を失うきっかけになったのも「写真」であり、それを取り戻すきっかけになるのもまた「写真」なんですよ。
こういった同一のモチーフを反芻しながら、その意味づけを変化させていくという視覚的なアプローチが非常に効いていた映画版だったと感じましたね。
④なぜ映画版では主人公夫婦に子どもがいないのか?
(C)2021「ファーストラヴ」製作委員会
さて、『ファーストラヴ』の原作と映画版の大きな違いとして、由紀と我聞の間に子どもがいないという点が挙げられると思います。
そもそも原作では2人の間に正親という息子がいます。
この子は2人がうっかり妊娠してしまったという流れで生まれた子どもですが、原作では彼が生まれたことがきっかけで我聞が報道写真家の夢を諦めるという展開になっていました。
ただ、映画版ではこの息子の存在がカットされました。
もちろん、子どもがいないとその家族が上手く行っていないなんて言うつもりはありません。
しかし、彼らの間に子どもがいないという事実が何らかの事情を感じさせるのは事実です。
とりわけ『ファーストラヴ』において、原作にはいた2人の息子がいなくなったのは、由紀と我聞が本当の意味で分かり合えていないことを暗示するための1つの演出になっていたと言えるのではないでしょうか。
















ここだけを述べると反発がありそうなのですが、実は本作のラストには原作には存在していない「家族」という題の我聞の写真の個展の場面が存在しています。
この最後の最後で、2人がかつての我聞と迦葉が映っている4人の家族写真を見つめる描写がありました。
「子ども」という存在はこうしたフィクションにおいては、しばしば「未来」を指し示すモチーフとして扱われる場合があります。
そう考えると、このラストシーンは「過去」にばかり視線の方向が向かっていた本作が、初めて「未来」志向のベクトルを打ち出した瞬間でもあったのではないでしょうか。
2人はあの家族写真の向こうに、自分たちの子どもをもうけて…という未来を見ていたのかもしれません。
それは、由紀の幼少期のトラウマが解消され、本当の意味で我聞と家族になれたからこそ望める「未来」とも言えます。
この点で、原作にはいた2人の息子を映画では登場させないという選択をしたのは、物語的にも良い方向に作用したと言えるのではないでしょうか。
















映画版では描かれなかった由紀の子どもが映り込んだ家族写真が登場するので必見です。
⑤ラストで環菜が自分の物語を書きたいという意味
映画のクライマックスに環菜が獄中からの手紙で、自分の物語を自分で綴ってみたいと語る一幕がありました。
















と言うのも原作では、環菜の取材本の企画が無くなった後、出版社からの申し出で、由紀が「性的虐待を受けた女性たちのノンフィクション」を書くことになるという内容なのです。
当ブログ管理人としてはこの帰結が結構気に入っていて、環菜という1つの個別の事象に向き合ってきた物語が最後の最後で一般化・普遍化されていくような趣がありました。
そして、そこには由紀の経験も間違いなく絡んでいて、だからこそ由紀とそして環菜が2人でノンフィクション小説を作り上げて、自分たちを虐げてきた者たちにその苦しみを突きつけんとする試みになっていたんですね。
ただ、映画版ではここが、前述の通りで、環菜自身が自分の物語を書きたいと申し出るという内容に変更されています。
この変更についてですが、やはり映画版はこの『ファーストラヴ』という作品の中で、「未来」を示すということにすごくこだわったのではないかと思うのです。
先ほども述べたように、由紀には夫との家族としての未来が指し示されました。
一方で、環菜にとっての「未来」として映画版が示したのが、この彼女自身が自分の物語を綴るという意志なのです。
『ファーストラヴ』という作品はどこまでも登場人物の過去に焦点を当てていき、そこからの脱却と更生を描き続けた作品でした。
だからこそ、そんな物語の最後には「未来」を示すものが必要ですし、それを由紀だけでなく環菜にも用意するという映画版の粋な計らいには個人的には好感を覚えました。
















おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は『ファーストラヴ』についてお話してきました。
















とにかく物語を複数の軸で、立体的に拡張していくアプローチが卓越していますし、だからこそそこからもたらされるエモーションの量が桁違いなのです。
また、読んでいる人が何だか「救われた」気持ちになる、温かな「受容の書」であることも多くの人が惹かれた要因なのでしょう。
男性や女性の垣根を超えて、人間が「受け入れられる」ことの重要性を徹底的に描き切っています。
映画化をきっかけにして、映画の方はもちろんですが、原作の方もより多くの人に届いて欲しいですね。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。