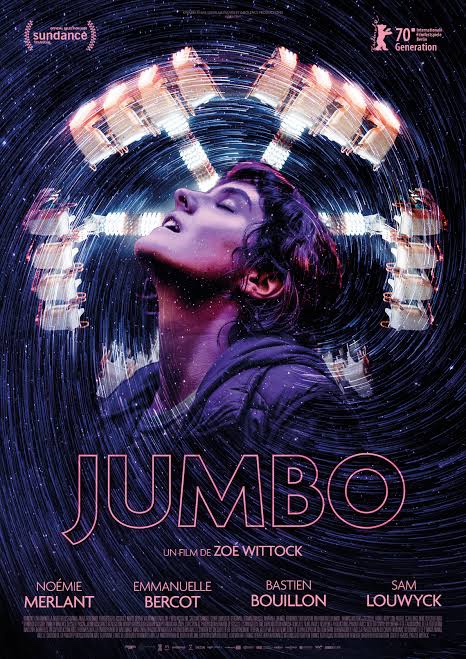『モダンラブ東京』シリーズの中でも異彩を放つ黒沢清監督の担当エピソード「彼を信じていた十三日間」の物語の冒頭にこんなやり取りがある。
「まあ、いいか。どうせ死んだら無なんだし。」
「いや、僕はそうは思わない。死んだらどうなるか、想像つかないけど、想像がつかないから、無だなんて乱暴だよ。」
(『モダンラブ東京』シリーズ「彼を信じていた十三日間」より引用)
「現代におけるさまざまな愛の形を描く」というのが、このシリーズのひとつのコンセプトになっているわけだが、このエピソードに関して言うなれば、そのコンセプトよりも黒沢清監督の色が全面に押し出されていた。
登場人物が醸し出す独特の怪しさ、物語を通底する言葉にならない不気味さ、生と死の交錯、川というロケーション。監督の名前を見なくとも、映像を見ただけで黒沢清監督の名前が浮かんでくるほどに「匂って」いる。
そして「彼を信じていた十三日間」が主眼を置いていたのは、愛というよりはむしろ上記の「死」にまつわる哲学的な問いだったように思う。
42分間の物語は、冒頭に示されたこのやり取りに答えを出していく内容となっているわけだ。
この普遍的な問いに対して、本作が出した結論そのものが何か斬新なものだとか、そういう風には思わない。ただし、そこに着地させるための映像によるストーリーテリングの手法があまりにも卓越している。
この記事では、「彼を信じていた十三日間」の映像表現に着目しながら、本作が描こうとしたものについて掘り下げて考えてみたいと思う。
目次
『モダンラブ東京』「彼を信じていた十三日間」考察(ネタバレあり)
通行人Aが「あなた」になる瞬間を描く
(『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形』特別映像より引用)
本作の中で最も印象的だった、あるいは思わず唸ったのは、物語の中盤に篠原桃子(永作博美)がコンビニに買い出しに行った鈴木洋二(ユースケ・サンタマリア)を探しに行くシーンである。
このシーンの何がすごいのか。
それは、桃子が洋二を見つけるシーンを彼女の背後からのロングショットで捉えたセンスだ。
坂の下にいるのが洋二であり、そこに向かっているのが桃子であるということを、クローズアップショットで捉え、2人が徐々に近づいていく様をカットを切り替えながら演出する方がドラマチックであると言える。
一方で、このシーンでは桃子の背後からのロングショットで、彼女が坂道の下へと小走りで向かっていく様子を映し出している。
では、これがどんな効果を生んでいるのか。
それは、通りの向こう側から歩いて来る通行人たちの中に洋二はいるのか、あるいはいたとしてどの通行人が洋二なのかを視聴者の中で曖昧なままに留め置ける効果と言えるだろうか。
桃子は何かに気がついた様子で坂道を小走りで下っている。つまり、彼女には通行人たちの中の洋二が見えている。しかし、ロングショットで提示されるために、視聴者はこの時点で洋二を判別することができない。
この桃子と視聴者の認識のギャップを生むことにこのショットの意義があると言える。
名匠ジム・ジャームッシュが初期のインタビューの中で、自身の作品『パーマネント・バケーション』における主人公とスペイン娘の出会いのシーンに言及して次のように述べている。
スペイン娘の場面の基本方針は、アリーがまだ知らないなにかの音を聞くということ、いいかえれば、カメラの視点が主人公の先回りをしないということだった。主人公が彼女を見るときに初めて彼女が映される。(中略)肝心な点は、観客が主人公と同じ通りに出来事を経験するということなんだ。
(『ジム・ジャームッシュ インタビューズ―映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』より)
同作の該当のショットは、モンタージュによる表現となっているが、演出意図で紐解くと共通点もある。
しかし、決定的に異なるのは、「彼を信じていた十三日間」のこのシーンでは、桃子は既に走り出しており、観客の視点(カメラ)は坂の上に固定されたままになっているという点だ。
つまり、カメラの視点が主人公の先回りをしないというよりも、カメラの視点が主人公の視点から切り離されるというのが、このショットの役割となっている。
あなた自身の日常生活に目を向けて見て欲しい。
例えば、あなたが結婚しているとして、夫あるいは妻にあたる人物は言うまでもなくあなたにとって特別な人だ。しかし、そんなあなたにとっての特別な人は、他の誰かから見れば群衆の中の1人に過ぎないわけで、通行人Aでしかない。
このように認識という観点から見ると、あなたの夫あるいは妻は、「大切な人」でありながら「通行人A」であると言えるわけだ。
そして、あなたにとってもそんな「通行人A」が「大切な人」になる瞬間やきっかけがあったはずである。
「彼を信じていた十三日間」のこのロングショットは、まさしくその瞬間を描き出していると言えるのではないだろうか。
また、このショットは2人が最初に出会った夜の別れのシーンとの対比にもなっている。
階段を下り、通りの向こうへと去っていく洋二。今日のひと時を共にした洋二という男性が群衆の中の1人、あるいは通行人Aに戻っていく過程を同じくロングショットで見せていた。
冒頭のカットがあったからこそ、その反転とも言えるこのカットが活きてくる。
あなたを「あなた」たらしめる何か。それは言葉にならないし、具体的なイメージで表現することも難しい、掴みどころのない「気配」のようなものなのかもしれない。
肩書きや年収でもない、名前でもなければ、姿かたちでもない。そうした可視のものを超越したところにある不可視の「気配」とも呼べるもの。
その生まれ、そしてあなたが他でもない「あなた」へと変わる瞬間が見事に演出されていた。
壁とマグカップ、「黄色」という偶然
(『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形』特別映像より引用)
ここまでに解説してきたのは、「あなた」が形成されるまでのプロセスと言ってもよいだろうか。
そして、「彼を信じていた十三日間」の物語の後半に描かれるのは、肉体や姿かたちとしての「あなた」の消失であり、消失を経ても消えないあなたの「気配」である。
この「気配」を表現する上で効いていたのが、黄色というカラーリング、それからマグカップというモチーフだった。
だが、そもそも部屋を黄色にするまでのプロセス、ないし桃子の部屋の棚に突っ張り棒を立てて修理するまでのプロセスが実に興味深い。
先ほどジム・ジャームッシュ監督のインタビューを引用したが、彼は別のインタビューでこうも述べている。
偶然の一致のほうが、観客の心を強く打つと思うんだ。ドラマチックな活劇、つまりカーチェイスとか、女と痴話喧嘩することなんかよりもね。
(『ジム・ジャームッシュ インタビューズ―映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』より)
「彼を信じていた十三日間」において、桃子の部屋に洋二がやって来るのは偶然性の連続によるものであった。
まずは、本当の洋二がプロフィールシートを落としたという偶然、それを「洋二」が拾ったという偶然、気まぐれに「洋二」が桃子に会いに来て意気投合したという偶然、そして棚が突然壊れたという偶然、さらには洋二が不動産業という住宅に関わる仕事をしていたという偶然。
ここまでのプロセスがすべて偶然性によって結びついているのだ。だがしかし、ジム・ジャームッシュ監督の言うように、この2人の出会いは偶然の一致、あるいは連続によるものだからこそ魅力的に映るのだと思う。
とりわけ、桃子というキャラクターは合理性や必然性に縛られた存在として描かれている。だからこそ、インタビューの仕事においても常に、相手の偶然性を否定し、必然性を追求する。
しかし、そんな彼女が偶然性の連続による出会いに魅力を感じる。そして、彼に魅力を感じれば感じるほどに、インタビューの仕事が上手くいかなくなっていく。
それを表現したのが物語の中盤に2人が森で迷子になるシークエンスだ。
桃子は来た道を戻ればテントに戻れるだろうという必然性を主張する。しかし、洋二はそれを否定し、別の道へと進む。つまり、帰れるとしたら、それは偶然性によるものだと彼は主張するのである。
必然性から偶然性へと誘われていく桃子の変化が、視覚的な表現とともに演出されている。
そして、この偶然性の連続は先ほど挙げたモチーフを介しても演出されている。
壁の色を黄色にしたことに対しては明確な理由づけは描かれないわけだが、この壁の色がのちに洋二のマグカップの色にリンクする。
ただ、洋二が桃子から2つのマグカップを提示され、黄色のマグカップを選択したのは、偶然の産物だ。
桃子が選んだ壁の色が偶然黄色だったのであり、洋二が選んだマグカップの色が偶然黄色だったに過ぎない。しかし、この2つの偶然が不思議な一致を見せることで、観客の心を打つドラマ性が生まれている。
物語の終盤に、桃子が洋二を探しに行くシーンでも、やはり彼女は彼の居場所を一義に突き止めたりはしない。
彼がいる可能性のある場所を巡り、偶然にも過去にキャンプをした森の中で、彼と再会したに過ぎないわけだ。
偶然の対義語である必然は「必ずそうなること。それよりほかになりようのないこと。」と定義される。
そんな必然の対義語として偶然という言葉を捉えなおすのであれば、それは「必ずしもそうはならないこと。他の可能性を想定すること」と言い換えられるのかもしれない。
洋二と桃子のやり取りは、まさしくそんな必然と偶然の引き合いに思える。
ここで洋二は、死ぬことだけが希望に思えてくると述べており、死が自分を救う唯一のものであるという必然性を主張する。
それに対して、桃子は自分が今、あるいは未来の時間に生きていることの偶然性を主張し、最後には今にだって希望はあるというオルタナティブを示す。
出会った日の夜の会話では、自分の考えに固執し、物事の必然性を信奉する桃子と、それに対するオルタナティブを示し、偶然性の存在を主張する洋二という構図になっていたわけだが、これまた2人の関係が反転している。
そして、この偶然という概念への到達と受容を、本作は「愛」として描いているように見受けられた。
自分1人で生きていれば、自分の意志によってある程度の物事は選択できる。しかし、他者と生きるということは他者の行動に伴う、予測不可能な事象を受け入れるということになる。
つまり、「偶然=他の可能性を想定すること」を受け入れる必要に駆られるのだ。
物語の最後に、映し出される彼女の部屋。
自室とは、彼女の自由にできる空間であり、必然性が支配できる空間とも言い換えられる。
しかし、冒頭のものとは違って、ここで映し出される彼女の自室には黄色く塗られた壁や補強された壁掛け棚といった偶然による介入の跡が見られるわけだ。
その偶然を愛おしく思えることこそが、他者の存在の受容なのであり、それがひとつの「愛」のカタチと言えるのではないだろうか。
突っ張り棒、残されたあなたの「気配」
(『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形』特別映像より引用)
先ほど、彼女の部屋の描写について言及したが、ここでもうひとつ注目していただきたいモチーフがある。
それは、洋二が壁掛け棚を修理した際の補強のために用いた突っ張り棒だ。
描かれ方としては、彼が修理した際にはそれがあって、映画のラストに彼女の部屋を映した際には無くなっているというだけのものである。
しかし、ここにこそ黒沢清監督の映像表現の真骨頂があると言っても過言ではない。
今作では、三段階に分けてこの突っ張り棒の演出を施している。
まずは、洋二が壁掛け棚を修理したシーンで、この時点では突っ張り棒が存在している。
次に、彼がフライパンの修理をするために自宅に来たシーンで、ここでは突っ張り棒は無くなっているが、まだ部屋に洋二の姿がある。
最後に、洋二が消失してしまったあとの自室のシーンで、ここでは突っ張り棒も洋二の姿も無くなっている。
ここで、少し頭のリセットをして見て欲しい。
この映画の一連のコンテクストなしで映画のラストシーンだけを見たと仮定するのである。あるいは、自分が、一連の事象が終わった後に、彼女の部屋に遊びに来た友人であると仮定して、ラストシーンの桃子の部屋を見て欲しいのだ。
そうすると、そこにはただ補強された壁掛け棚があるだけで突っ張り棒なんて最初から存在していなかったことになる。壁の色が少し前まで黄色ではなかったなんてことも想像がつかないだろう。当然だ。
しかし、この物語のコンテクストを踏まえて、最後のシーンを見ると、私たちは無意識にそこに彼の残り香のようなものを感じ取ってしまう。
もうそこにはない突っ張り棒があるように見えてしまうし、部屋の黄色が何となく彼の存在を思い出させるトリガーとして機能する。
これが本作の描こうとした、言語化も可視化もできない「気配」の正体ではないだろうか。
物語の部外者の視点で見ると、何も読み取ることができない事物に、あなたにしか感じられない「気配」のようなものが宿っている。
記事の冒頭でも紹介した死に関する問いにここでようやく立ち返るわけだが、本作が出した死の後に残されるものは何か?に対する回答は、まさしくこの「気配」だったのではないだろうか。
わたしにも、彼にも、彼女にも、彼らにも感じることができない。
あなたにしか感じ取ることができないもの。
それを感じられるということ、その特権こそが「愛」なのだ。
こう考えてみると、「彼を信じていた十三日間」もまた、黒沢清監督なりに「現代におけるさまざまな愛の形を描いた」作品だったのだと腹落ちする。