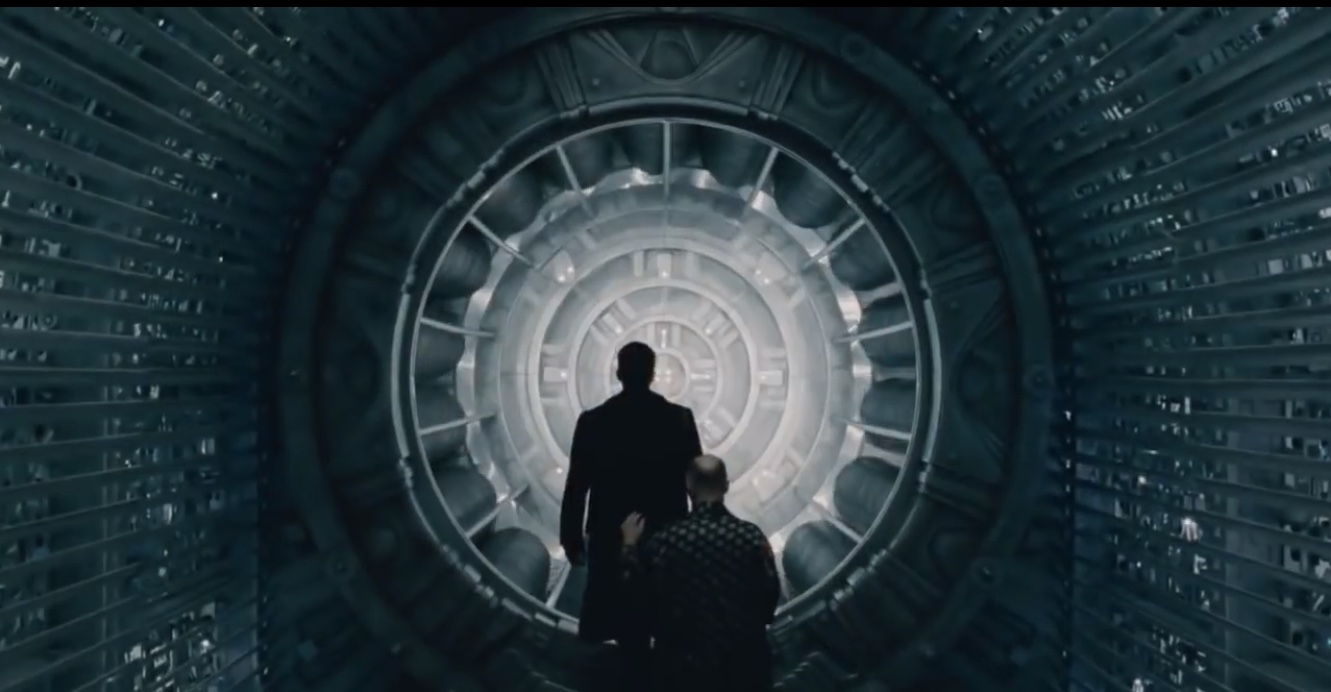みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『13人の命』についてお話していこうと思います。

地元のサッカーチームに所属するコーチ1人と少年12人がタムルアン洞窟に入ったところ、突然大雨に見舞われ、外に出られなくなってしまったという事故は、海を越えた日本でも報道され、当時注目を集めました。
結果的に、全員無事で救出されたのですが、その「奇跡」の舞台裏でどんなことが起こっていたのかについては、詳細を知る人は少ないのではないでしょうか。
この事故は、多くの映画クリエイターの目に留まり、今作を除いても『THE CAVE レスキューダイバー決死の18日間』やドキュメンタリー映画『THE RESCUE 奇跡を起こした者たち』などいくつかの映像作品が既に制作されています。
そんな中でAmazonプライム独占配信となった『13人の命』は、『バックドラフト』や『ビューティフル・マインド』などで知られるロン・ハワード監督が手掛けた映像作品です。
この手のレスキュー映画では、どうしても登場人物の背景情報や登場人物同士のエモーションのぶつかりを盛り込んで、ドラマ性を高める手法が取られがちだと思います。
しかし、ロン・ハワード監督はそうした表現の一切を排除し、ひたすら救助に関わる描写だけにフォーカスし続けました。
だからといって、ドラマ性に欠くこともなく、淡々とした描写の細部に人間性を表現する要素を忍ばせており、スクリーンの向こう側にはきちんと「人間」が描かれているのです。
例えば、救出活動の中核をなしたイギリスのレスキューボランティアのリーダーの男性の描写の中には、彼とその家族の関係性を伺わせるものがありました。
そこにパートを割いて、掘り下げるということはないのですが、その断片的な情報が垣間見えることで、「彼が作戦で命を落としたらどうなるんだろうか?」あるいは「彼が国外の救助活動に参加して自宅を留守にしていることを息子はどう思っているんだろうか?」といった想像が働きます。
『13人の命』のドラマ性は、こうした観客の想像力によって補完されるように作られており、それ故に作品にはたくさんの余白が残されているのです。
その余白が観客の感情の「器」として機能し、淡々とした救助劇をそれぞれの形で満たしていく構造が、何とも見事という他ないわけですね。
そんな『13人の命』ですが、作品の1つの特徴として、「信仰」という要素にフォーカスしていることが挙げられます。
これは『ダヴィンチコード』に始まる三部作やドラマシリーズが公開予定の『信仰が人を殺すとき』など信仰がテーマになった映画を多く手掛けてきたロン・ハワード監督らしい視点とも言えますね。
そこで、この記事では『13人の命』がどのように「信仰」というものを描こうと試みていたのかを個人的に掘り下げて考えてみたいと思います。
記事の内容の都合上、ここからは作品のネタバレになるような内容を含みますので、作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
映画『13人の命』考察(ネタバレあり)
関係主義的な世界観で事故を捉える
(映画『13人の命』より)
タイでは、国民の90%以上が仏教を信仰しているとされ、国内に3万以上存在していると言われる寺院はコミュニティの中心であり、信仰が生活に強く根ざしたものであることが伺い知れます。
その一方で、ピー信仰と呼ばれる精霊信仰が彼らの宗教観の根底を成しており、この教えが仏教信仰と混ざりあいながら、彼らの生活に入りこんでいるのです。
とりわけ『13人の命』のキーとなるのは、洞窟の前に安置された1人の「横たわった女性」の像でした。
洞窟のある一帯は「クン・ナム・ナン・ノン」という名前の森林公園であり、これはタイ語で「横たわった女性」を意味します。
劇中でも言及されていたように、南北に連なっている山脈が仰向けに寝ている女性のような形をしており、そこから来ている名前のようですね。
加えて、この山のモチーフとなっている「横たわった女性」には、同じく劇中で述べられていたように、ある言い伝えが残されています。
彼女はかつて山のある一帯を支配していた王国の王女でした。その王国が崩壊した際に、王女はおなかの子を身ごもったまま、王と共に処刑されてしまったという逸話があるのです。
こうした言い伝えがあることから、山から流れ出ている川は王女の血に例えられ、その山の内部にある洞窟は「王女の胎内」に見立てられます。
そのため、この事故は「子どもを産むことができないまま命を落とした王女の呪い」が原因ではないかという信仰に基づく解釈も成されているのです。
つまり、事実としては「子どもたちが洞窟に閉じ込められ、そこから奇跡的に救助された」なのですが、そこに信仰に基づくコンテクストが投影され、さまざまな見方を生んでいるわけですね。
タイは仏教(上座部仏教)に根ざした国であり、仏教の根底には「縁起」という考え方があります。「縁起」というのは「あらゆるものは深く関わりあっていて、それ単独で存在するものはない」という考え方のことですね。
縁起の法は「これがある時、それがある。これが生じる時、それが生じる。これが無い時、それが無い。これが滅する時、それが滅する。」と表現されることもあります。
この考え方に基づくと、タムルアン洞窟の遭難事故もそれ単独で存在するものではなく、さまざまなものが深く関わりあって表出した結果であるということになるわけです。
その中には、先ほど話題に挙げた「横たわった女性」の逸話も含まれており、こうした諸要素の関わり合いの結果が事故として表出したと捉えるのです。
こうした関係主義的な世界観の中でタムルアン洞窟の遭難事故を捉えていこうという視点が、今回の『13人の命』においては一貫していたように感じます。
そして、この考え方が、本作のクライマックスに訪れる「奇跡」の裏づけにもなっており、「信仰」を描いた意図にもつながっていくのです。
因果ではなく縁起がもたらした「奇跡」
(映画『13人の命』より)
「因果」と「縁起」という言葉は似たような意味として捉えられることも多いですが、この2つの違いについて東洋大学の竹村牧男氏が次のように述べています。
何かの現象(出来事)が起こるのには“因”が必要なのですが、因だけでは起こらないのです。そこには“縁”が必要です。“因”が直接的原因とすれば、“縁”は間接的な条件。直接的原因と間接的条件とがあいまって、初めて現象が生じるのです
本作で起きた事故の直接的な原因、つまり「因」に当たるのは、言うまでもなく大雨であるわけで、大雨によって洞窟が冠水し、子どもたちが閉じ込められたと捉えるのが「因果」の考え方です。
一方で「縁起」に基づく関係主義的な世界観の中で捉えると、大雨という直接的な「因」の他に、先ほど挙げたような「横たわった女性」の逸話のような「縁」が入りこんできます。
このように、タムルアン洞窟の遭難事故を「縁起」の考え方に基づく現象として捉えようというのが、本作が信仰を全面に押し出した意図にもなるのでしょう。
そして『13人の命』では実に多様なアプローチによって、閉じ込められた子どもたちとそしてコーチの救出が実現されます。
もちろん子どもたちを救出した直接的な「因」にあたるのは、イギリスのボランティアクルーたちですよね。洞窟から物理的に連れ出したのは、言うまでもなく彼らです。また、洞窟内に雨水が流入するのを防ぐためにダムを造って、雨水を逃がした人たちも「因」と言って差し支えないでしょう。
「因」に当たる人たちの功績は目に見えますから、国内外で報道され、彼らは英雄として讃えられることになります。
しかし「因」だけで、このような「奇跡」を実現することが果たしてできたでしょうか。
「縁起」の法に基づいて考えるのであれば、これは否です。
仏教では、「縁起」の法に基づき、苦しみには原因があり、その原因を消滅させることで苦しみが消えると考えられています。つまり、苦しみとして表れている結果の背後にどんなものが関連しているのかを探り、それを排除する、あるいはそこからの解脱を目指すことが、苦しみを消し去るための方法なのです。
『13人の命』は、タムルアン洞窟の遭難事故という苦しみを表出させている「因」とそしてこれに関連している「縁」を探り、それらを断ち切るというアプローチを、子どもたちを救助する救出劇に投影してあります。
「奇跡」という結果をもたらした「因」は、先ほども言及したようにダイバーたちによる救出作戦や市民によるダムの建造です。
一方で、映画の中で描かれていた市民による「横たわった女性」の怒りを鎮めるための信仰や仏僧による儀式、あるいは閉じ込められた子どもの母親が作ったお守り、コーチによる瞑想といったものは「縁」に属するものだと考えられます。
信仰や儀式、お守りあるいは瞑想それ自体が、洞窟からの脱出を実現してくれるわけではありません。しかし、13人全員の生還という「奇跡」という結果を関係性の中で捉えるのであれば、それらも「縁」という形で確かに関係していると考えられるわけですね。
プロフェッショナルによる淡々とした救助作戦を描く上で、一見すると、宗教や信仰という要素は相反するものです。ドライな見方をすれば、そんなもので子どもたちは救えないということになるでしょう。
しかし、ロン・ハワード監督は仏教における「縁起」の考え方を、タムルアン洞窟の遭難事故に投影することで、この救出劇に関わった全ての人たちを「奇跡」の立役者として肯定しようと試みています。
遭難した子どもの母親が作った小さなお守りが何の役に立つのかという見方ではなく、あのお守りもまた「奇跡」という結果の背後にある「縁」の1つとして捉える。
それが『13人の命』が「信仰」を物語の重要な要素に位置づけた意図なのではないでしょうか。
おわりに
いかがでしょうか。
今回は映画『13人の命』についてお話してきました。



これだけ描写を切り詰めて、プロフェッショナルな救助劇にフォーカスした作品において、信仰や宗教に関する描写は、ある種「不要」と判断されて、切り捨てられてもおかしくないものです。
しかし、あらゆる形でこの事故に関わった人が「奇跡」という結果をもたらしたのだという関係主義的な世界観が、信仰という形で救出劇に関わった人たちをも肯定しています。
私たちが目にする報道において、子どもたちを救った英雄として報じられるのは、この救出劇に関わった人の中でもごく一部の人です。
だからこそ「縁起」の法における「因」となった人たちだけでなく、直接的ではないけれども間接的にかかわった人たちを「縁」として掬い取り、彼ら全員が成し遂げた「奇跡」として、事実を再定義したところに、『13人の命』の美しさがありました。
ロン・ハワード監督の最高傑作と言っても過言ではない本作を、ぜひ多くの人にご覧になっていただきたいと、そう思います。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。