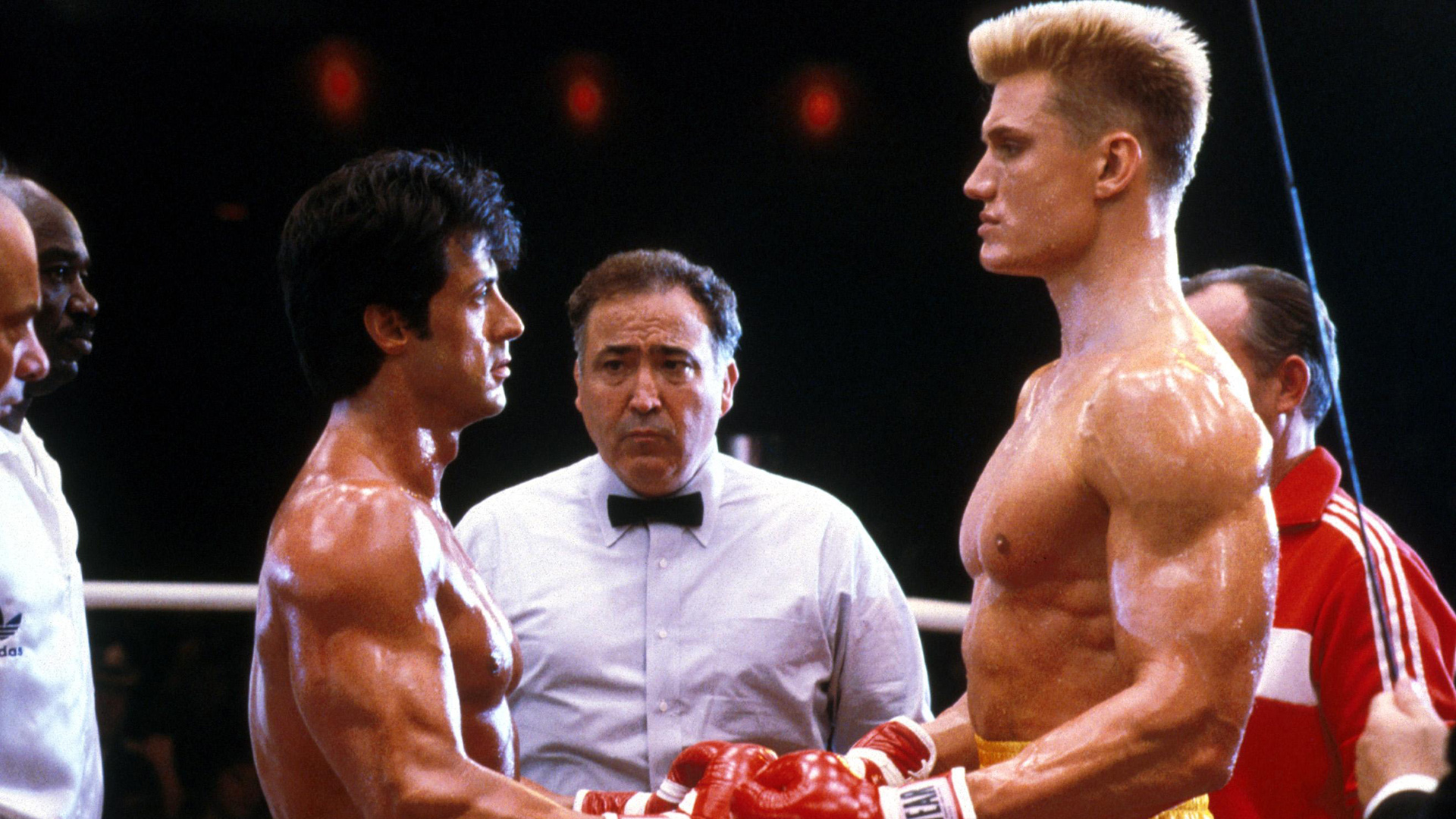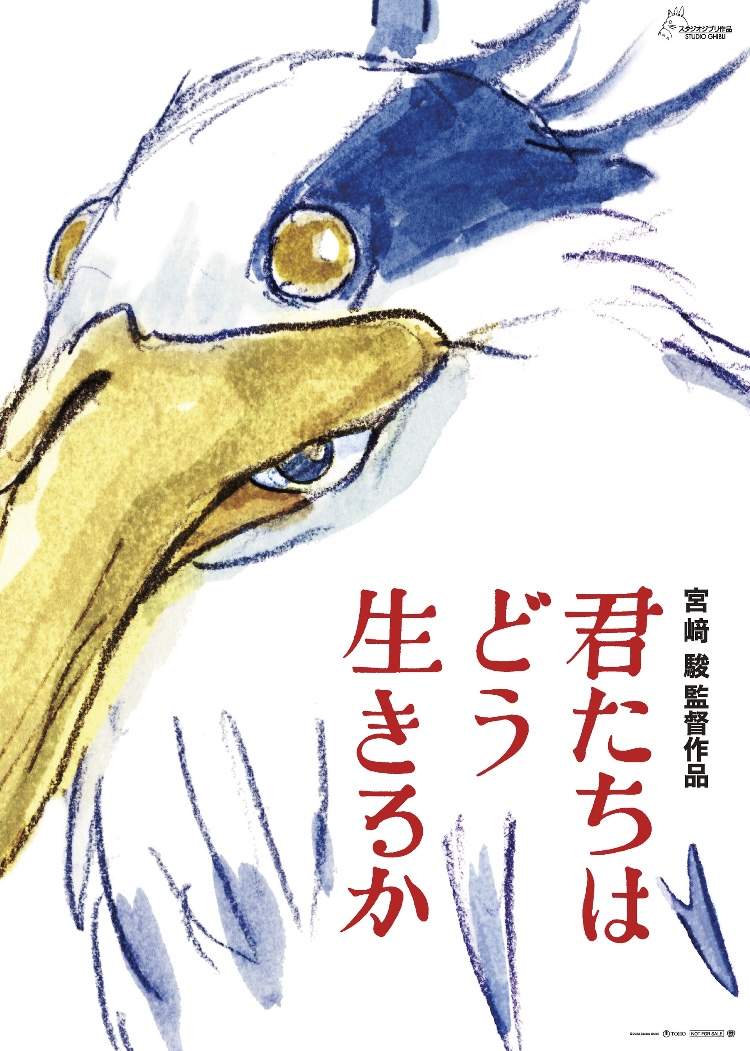みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね4K修復されて蘇ったヴィム・ヴェンダース監督の不朽の名作『夢の涯てまでも』についてお話していきます。

何を隠そう私はヴィム・ヴェンダース監督の大ファンでして、映画にハマるきっかけをくれた監督の1人でもあります。
ただ、彼の2000年代以前の作品の多くはDVDやレーザーディスクでしか見ることができず、Blu-rayで見られるのは『パリ、テキサス』や『ベルリン、天使の詩』などの一部の人気作のみとなっておりました。
そのため、この『夢の涯てまでも』についても大学の図書館でレーザーディスクで見たのが初見でしたね。
実は『夢の涯てまでも』は、当時としては珍しいNHKの全面協力によるハイビジョン撮影が敢行された作品で、かなり映像美にこだわって作られた映画なんです。
しかし、レーザーディスクで見ると、どうしても解像度が低く、その魅力を完全に味わえたとは言えない状況だったので、何となくモヤモヤを抱えておりました。
日本語字幕付きで高解像度で見られる状況というのがなかなか整ってこなかった作品と言うこともあり、この『夢の涯てまでも』の4K修復版を映画館で見ることができる幸せを噛み締めましたね。
本当に関わってくださった全ての方にお礼を申し上げたいです。
劇場公開版でも3時間30分ほど、そして今回上映されているディレクターズカット版は5時間弱もあるというかなり長尺の映画ですが、おそらく「ロードムービー」というジャンルにおける1つのマスターピースがこれだと私は思っています。
ですので、映画館で見られる機会が貴重であるということを強調しつつ、興味のある方にはぜひ今回のリバイバルの折に鑑賞していただきたいのです。
そこで、今回は『夢の涯てまでも』が一体何を描こうとした作品なのか?についてヴィム・ヴェンダースという作家についての解説も交えながら2つのキーワードを軸にお話していこうと思います。
その2つのキーワードとは、「イメージ」と「連続性」です。
この記事を読んで、「ヴェンダースリバイバル行ってみようかな!」「ヴェンダース作品見てみようかな!」という人が1人でも増えたら嬉しいですね。
良かったら最後までお付き合いください。
『夢の涯てまでも』を紐解く2つのキーワード
「イメージ」と夢を視覚化する装置
(C) Wim Wenders Stiftung 2015
まず、1つ目のキーワードは「イメージ」です。
『夢の涯てまでも』という作品の中心にあるのは、人の視覚から生じる脳の信号を他の人の脳に転送することにより盲目の人間にビジョンを見せる装置です。
そして、この研究が劇中で更に発展し、人が夢を見ているときの脳の信号を解析して、夢の風景を映像として可視化する段階にまで至りました。
この装置が面白いのは、写真や映像などを直接盲目の人に見られるようにするのではなく、写真や映像を見た人間の脳の信号を用いて見られるようにするという仕組みだと思います。
つまり、写真や映像そのものではなく、それを見た人間が抱いた「イメージ」を転送しているという構図に近いわけです。
そう考えたときに、この装置そのものがヴィム・ヴェンダースという作家がこれまで作り上げてきた作品群に通底する主題を背負ったモチーフであるという視点が垣間見えます。
1995年にヴィム・ヴェンダース監督は『ベルリンのリュミエール』という作品を世に送り出しています。
これは、リュミエール兄弟以前に、ベルリンのスクラダノウスキー兄弟がビオスコープという技術を開発していことに関する伝記映画なのですが、この映画が作られた背景には、原初的な映画の在り方に対する彼のリスペクトを見ることができます。
リュミエール兄弟が撮影した有名な作品の1つに『ラ・シオタ駅への列車の到着』というものがありますよね。
この作品は、汽車が到着し、駅から出てくる人々をただただ時間の流れに任せて撮影した映像作品です。
そもそも原初の映画は、ストーリー性があるというよりは、日常の何気ない風景を映像で見るものでした。
つまり、現実の追体験ないし再体験によって、日常の中に新たな発見を見出し、「イメージ」を膨らませていくとことに面白さがあったのです。
こうした原初的な映画に強く惹かれたヴィム・ヴェンダース監督の作品は、近年のストーリー性の強い映画に慣れた私たちにとっては、どこか淡白で無骨な印象を受けるかもしれません。
例えば、彼の代表作の1つである『パリ、テキサス』でもハリー・ディーン・スタントン演じる主人公のトラヴィスがいきなり荒野を彷徨っているシーンから始まります。
彼がここに至るまでどんな経験をしてきたのかは、私たちには明かされませんし、映画を最後まで見たとしても、それが明確になることはありません。
私たちは、あの荒野の風景とトラヴィスの佇まいから、彼の身に起きたことを「イメージ」することしかできないのです。
つまりヴィム・ヴェンダース監督の作品と言うのは、映像そのものの刺激を極めて意図的に落としてあり、映像を受け取った私たちの脳の中に生まれる「イメージ」に多くを委ねているんですね。
彼のこうした映画作りのアプローチを裏づける興味深い詩があります。これはヴィム・ヴェンダース監督自身が書いた『アメリカン・ドリーム』という散文詩の一節です。
これほど見ること(ヴィジョン)が衰えてしまった場所もない。
絶えず 先行する映像以上のものを
より強烈な映像を見つけれなければならない
単純なもの ありのままのものへのまなざしは失われてゆく。
アメリカの大きな自然公園ではまるで自然は公園以外の形では存在しえないかのように
(「美しい」ところには必ず公園があり、
その性質上必ずディズニーランド化していく。)
景色を眺めるために身を置くべき場所や
写真を撮るために身を置くべき場所や
写真を撮るに値する場所がいたるところで
あらかじめ指示されている。
こうして前もって撮影のための視点が与えられているので
何百万人という人々が作り出せるのだ
すでに存在している映像を確認しているだけの映像を(ヴィム・ヴェンダース『アメリカン・ドリーム』より引用)
ここには、自然公園を例にしながら、強烈な映像やあまりにも受け手の想像の余地のない映像に対する批判が綴られています。
ヴィム・ヴェンダース監督は、受け手が強烈なインパクトのあるものや予め見るべきポイントが定められたものにばかり集まるようになり、単純なものやありのままのものを受け入れようとする視線が失われていくことを危惧しているのです。
だからこそ、彼の作品は「ありのままの映像」の連続によって成立した形作られた余白の多い映画なんですよね。
その映画のどこを見るのか、その映画をどう見るのか、登場する場所やキャラクターをどう解釈するのかについての多くの点が観客に、もっと言うなれば視覚情報を受け取った観客の脳内に生まれる「イメージ」に委ねられています。
彼のそんな映画作りを象徴する有名なエピソードがあります。
映画『さすらい』の撮影に際して、ヴィム・ヴェンダース監督は脚本を用意せず、撮影のために立ち寄る場所を定めたマップを用意して、クルーと共に旅をしながら、徐々に脚本を書き進め、映画を完成させたのだそうです。
文字通り「さすらう」ように映画を作ったんですね。
こうしたエピソードからも、ヴィム・ヴェンダース監督が作り手の側から示される物語性や作為性といったものを極力排除し、ありのままに近い映像を提供しようとしている点が伺えます。
そして、『夢の涯てまでも』における「人の夢を可視化する装置」というのは、まさしく監督が重視している人の頭の中に生まれる「イメージ」を可視化する装置なのだと思いました。
これについては先ほどもご説明したように、写真や映像そのものではなく、それを見た人の脳の信号を用いるという設定からも明らかでしょう。
しかし、映画の終盤にも描かれていたように、この装置には大きな問題があります。
それは「夢の映像が孕む中毒性」でした。
人は一たび夢の映像を見てしまうと、それに憑りつかれ、その映像を見ること以外に対する興味を完全に喪失してしまいます。
この設定の根底には、おそらく彼が『ゴールキーパーの不安』のアメリカ公開の際に、初めてアメリカを訪れた際の経験があるのだと思いました。
一週間以上 私はテレビの前に座っていた
昼も夜も
原因不明の新しい病気に冒されて
深い麻酔状態に陥ったようになって。
それは一種の中毒症状だった だが個人的なものではなく
その反対に 完全に公的な中毒だった。
それまで私はテレビに興味を持ったことなど一度もなかった。
私をホテルの二六階の寝室に釘づけにしていたのは
ただのテレビ観賞であるはずはなかった。(ヴィム・ヴェンダース『アメリカン・ドリーム』より引用)
この詩の一節では、彼がテレビから流れる強烈で、人々の「イメージ」を奪うような映像が内包するある種の「中毒性」が指摘されており、それを彼自身が体験したことが明かされています。
つまり、『夢の涯てまでも』において、夢の映像を可視化するということは、人間の「イメージ」を可視化することであり、それは人間の想像力を外部化することに他ならないのです。
「イメージ」ないし想像力を自分の中から外部化してしまうと、それを提供してくれるメディアに依存せざるを得なくなるのは、自明ですよね。
また、その結果が、今作で描かれたようなモニターから目が離せなくなった人間であることも明らかです。
そう考えていくと、『夢の涯てまでも』という作品は、ヴィム・ヴェンダース監督が追求してきた「イメージ」の存在に迫る映画であり、それを失った時に人間がどうなってしまうのかを模索した実験的映画でもあるのだと思います。
では、彼はその答えをいかにして導いたのか。
ここにもう1つのキーワードである「連続性」が関係してくるのです。
「イメージ」を担保する「連続性」
(C) Wim Wenders Stiftung 2015
ヴィム・ヴェンダース監督作品ないし『夢の涯てまでも』という作品を紐解くためのもう1つのキーワードは「連続性」です。
みなさんは彼がなぜ映画を撮るようになったのかをご存じでしょうか。
というのも、ヴィム・ヴェンダース監督って元々画家志望だったんですよね。
彼は自分が画家から映画監督に転身したきっかけについて、コロッキウムで行われた講演会の際に話しています。
それは線路の見える無人の風景を撮ったものでした。カメラは線路のすぐ近くにセットしておりました。列車がいつ来るかは分かっていましたので、列車到着の二分前にカメラを回し始めました。そして、すべてはこの映画の他のカットと全く同様に進行していくように思えました。つまり、無人の風景として。しかし、二分後に突然、誰かが右から走って来てカメラの二、三メートル向こうを通り過ぎ、線路を跳び越え、画面を横切って消えていったのです。そして彼がフレームを離れようとするその瞬間、右手から列車が猛烈な勢いで走って来たのです。これは、直前に走りこんできた男よりももっと見る者を驚かせました。この些細な「アクション」、つまり一人の男が列車の通過直前に線路を横切ったということから、全く唐突にひとつの「物語」が始まったのです。
(ヴィム・ヴェンダース「映像<イメージ>の論理」より引用)
彼は「絵から別の絵に移る間に何かが欠けていた」と語っており、その空白が埋まった体験として上記の内容を語ったそうです。
つまり、何気ない映像の「連続性」によって、そこに「物語」が生まれた体験というのが、ヴィム・ヴェンダースという映像作家誕生のきっかけになったわけです。
彼の初期の作品に『都市の夏』という作品があるのですが、この中に車でトンネルの中を通過するだけの描写が1分以上続くシークエンスが存在します。
これは、まさしく映像を連続させることで、そこには何かが生まれ得ると信じていたヴィム・ヴェンダース監督だからこその演出でしょう。
今作『夢の涯てまでも』の中で、サムの母親であるエディスが亡くなる際に、「ようやく見ることができた。知ることができた。」と告げる一幕があります。
彼女がこの言葉を発したのが、装置によって断片的な親族たちの映像を見たときではなく、彼女が人生を終えるときだったことに注目していただきたいです。
なぜなら、彼女の「見えた」を支えているのは、あの装置ではなく、自分が積み重ねてきた人生の「連続性」だからです。
彼女は確かに8歳のころに視力を喪失してしまいましたから、視覚的に見ることは最早かないません。
それでも彼女は手で触れて、匂いをかいで、そして声を聴いて、自分なりに世界を知覚してきたわけで、それは他でもない「見る」という行為なのだと思います。
だからこそ、エディスは例え視覚を失ったとしても、そうした知覚の連続によって、ちゃんと世界を「見て」、そして知ることができたのだと、自分の人生を振り返って感じたのでしょう。
そして、この言葉の意味が理解できなかった夫のアントンや、息子のサムが視覚的に見ることに固執し、徐々に現実に戻れなくなっていく様は印象的でした。
彼らは自分たちの知覚の「連続性」ではなく、極めて断片的で刹那的な視覚情報に傾倒し、その中毒に陥ってしまうのです。
夢のビジョンは、先ほども述べたように人間の「イメージ」を外部化したものであり、それでいて強烈なインパクトを持ち、「連続性」に乏しく、閉じたメディアなんですね。
ヴィム・ヴェンダース監督は、そんな中毒症状に対する処方箋として、クレアに本を読ませています。
この本は、劇中でマリオが著したものであり、その内容はこれまでのクレア自身の旅の記録でもありました。
つまり、この本はクレアという女性が旅の中で歩んできた道のりそのものであり、彼女の体験や知覚の「連続性」を象徴するモチーフなのです。
だからこそ、このユージーンの著した本は、クレアを現実に引き戻す効果を発揮します。
しかし、想像力を失っていたクレアは、本を読み終えた後「続きは?」とマリオに問いかけます。
そんな彼女に対してユージーンは、頭に手を当てながら「それは君次第だ。」と返答しました。
これは、クレアがこれから歩んでいく道のりが、そこでの体験や知覚の「連続」こそが物語を生み出し、人間の「イメージ」を支える何よりも大切なものであることを、ヴィム・ヴェンダース監督が、マリオというキャラクターを通じて私たちに伝えようとしていたのではないでしょうか。
絵画には欠けていた「物語」をそして「イメージ」を持つことができたのは、彼が映像の「連続性」に触れたからであり、その初期衝動が『夢の涯てまでも』における描写の数々に宿っていました。
本作は、ヴィム・ヴェンダース監督がそのキャリアを通じて問いかけ続けている「イメージ」とそれを担保する「連続性」についての映画であり、それに対する答えを模索し続けた5時間弱にわたる長い長い「旅」なのです。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回はヴィム・ヴェンダース監督の『夢の涯てまでも』についてお話してきました。
5時間弱もある映画ということで、その時点で尻込みしてしまう人が多いかもしれませんが、その上映時間に値する「ロードムービー」のマスターピースであることは間違いありません。
そして、ヴィム・ヴェンダース監督の作家性が最も色濃く反映された作品であることも間違いありません。
「イメージ」に対する向き合い方。「連続性」の重要性の強調。またアメリカという国に対する視座やその描き方にもヴィム・ヴェンダース監督ならではの視座が目立ちます。
まずは『パリ、テキサス』や「ベルリン 天使の詩』、『都会のアリス』といった比較的見やすい作品から入っていただき、気に入れば今作『夢の涯てまでも』や『さすらい』のような作家性の強い作品もチェックしてみてください。



今回も読んでくださった方、ありがとうございました。