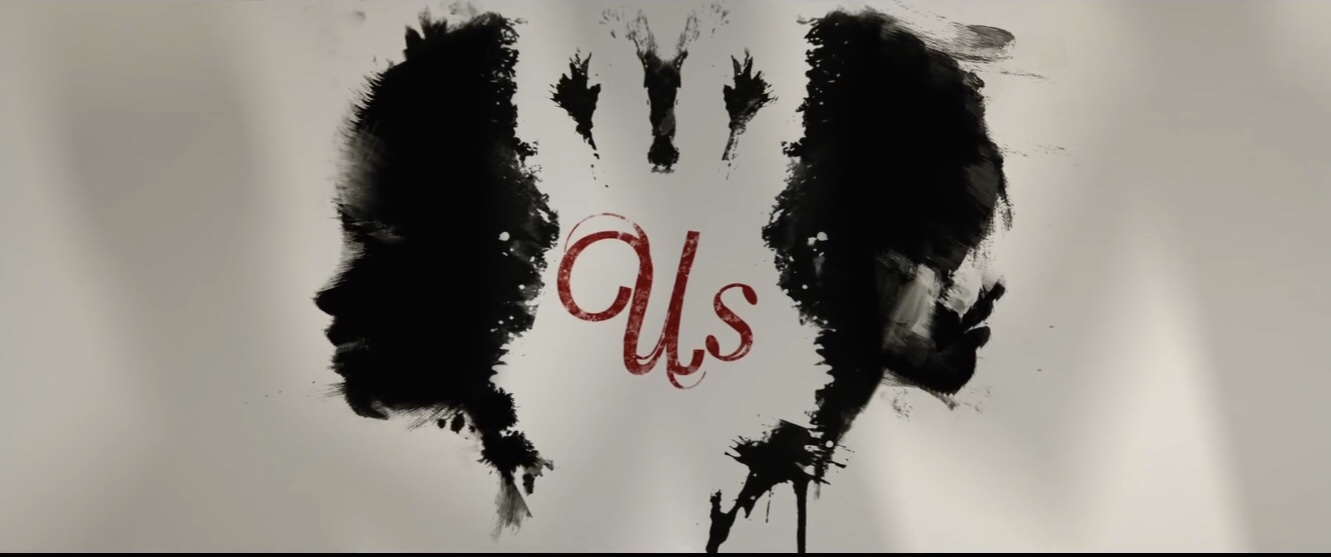みなさんこんにちは。ナガと申します。
今回はですね映画『マ・レイニーのブラックボトム』についてお話していこうと思います。

この作品は「ブルースの母」と称される実在の歌手マ・レイニーをモデルにして作られた戯曲が基になっています。
戯曲の方は、オーガスト・ウィルソンが1982年に発表した戯曲『Ma Rainey’s Black Bottom』です。
そこに今回、監督を務めたジョージ・C・ウルフと脚本を担当したルーベン・サンチャゴ=ハドソンがアレンジを加えて映画化する運びとなりました。
その「アレンジ」が脈々と近年まで続いてきたアメリカにおける黒人と白人の分断の軸を明確にしていて、非常に考えさせられる内容へとアップデートされています。
北米大手批評家レビューサイトのRotten Tomatoesでも98%の批評家から支持されるなど非常に高い評価でもって迎えられました。
加えて、本作は名優チャドウィック・ボーズマンの遺作としても知られています。
『ブラックパンサー』のティチャラ役で一躍有名になった黒人俳優で、彼が亡くなったときには世界中から追悼の意が届けられました。
彼は今作での演技でも高く評価されており、既にロサンゼルス映画批評家協会賞主演男優賞を受賞しています。
また驚きなのは、彼が今作の撮影に臨んでいたのは、がんとの闘病中で、しかもその晩年も晩年だということですよね。
迫りくる死に直面しながらも、迫真の演技を作品に残したことに心から敬意を表すると共に、改めて彼のご冥福をお祈り申し上げます。
そして、今回はそんな彼の遺作でもある『マ・レイニーのブラックボトム』という作品についてお話していこうと思います。
本記事は作品のネタバレになるような内容を含む解説・考察記事です。
作品を未鑑賞の方はお気をつけください。
良かったら最後までお付き合いください。
目次
『マ・レイニーのブラックボトム』
あらすじ
アメリカ南部で人気を博し、「ブルースの母」としても親しまれる歌手マ・レイニー(ヴィオラ・デイヴィス)は、北部のとあるスタジオでレコーディングをすることとなる。
バックバンドの面々は一足先にスタジオに到着し、リハーサル室で調整を行っていた。
そんな中で、バンドの最年少であり、野心家のトランペッター、レヴィー(チャドウィック・ボーズマン)は自分の夢を語り始める。
ピカピカの靴を背伸びして購入した彼は、自分がバックバンドという今の地位を脱して、自分のバンドを持つことを夢見ていた。
そして、マ・レイニーの名曲である「ブラックボトム」を自分のアレンジで演奏し、レコーディングできるという話を聞いて、意気揚々としていたのである。
しかし、いざマ・レイニーが遅れてスタジオに到着すると、空気がピリピリとし始める。
彼女がマネージャーやスタジオのオーナーと揉め始め、さらに彼女はレヴィーのアレンジでは収録しないと言い放つ。
たびたびレコーディングが中断される中で、レヴィーたちは自分たちの思いをリハーサルで吐露し始めるのだが…。
主演のチャドウィック・ボーズマンについて
映画『マ・レイニーのブラックボトム』予告編より引用
本作を語る上で、チャドウィック・ボーズマンという俳優の存在を避けて通ることはできません。
彼をスターへと押し上げたのは、やはり『ブラックパンサー』で演じたティチャラの役だったと思います。
一方で、彼が『ブラックパンサー』以前に出演した映画で演じた役は、どれもがアメリカの黒人の歴史を切り開く人物なんですよ。
黒人初のMLB選手となったジャッキー・ロビンソンを演じた『42 ~世界を変えた男~』
ソウルミュージックの帝王ジェームス・ブラウンを演じた『ジェームス・ブラウン 最高の魂を持つ男』
黒人で初めて連邦最高裁判事となったサーグッド・マーシャルを演じた『マーシャル 法廷を変えた男』
そんなキャリアを積んできた彼だからこそ、『ブラックパンサー』の主人公ティチャラを演じることに正統性がありました。
さらに言うなれば、黒人の歴史や悲劇的な運命を背負った人物を演じた『ザ・ファイブ・ブラッズ』や今作で演じたような役に説得力があったように感じましたね。
また、彼は黒人の子どもたちのための慈善活動や、自身も患っていたがん患者の人たちへの支援を続けていました。
彼への追悼の意を込めて、アメリカのディズニーリゾートに作られた壁画には、「ワカンダフォーエバー」のポーズでボーズマンと患者衣を着た子どもが向き合う絵が描かれています。
映画の中でだけでなく、俳優として1人の人間としても「ヒーロー」であり続けた彼が演じるティチャラないしブラックパンサーだからこそ多くの人に受け入れられたのだと思います。そしてそれがそのまま俳優としての彼へのリスペクトにも繋がりました。
こうした点からも、『ブラックパンサー』という映画の枠組みを超えて、チャドウィック・ボーズマンという俳優がアメリカに、世界に与えた影響の大きさ、残したものの偉大さを感じることができますね。
そんな彼の遺作が、今回お話している『マ・レイニーのブラックボトム』という作品です。
今作で彼が演じたのは、黒人の悲劇的な歴史を背負った人物でした。
そして、本作が戯曲原作というのも大いに関係していると思いますが、非常に「独白」を演じる場面が多かったのも特徴的です。
こうした「独白」が5分近く続くパートが中盤にありますが、チャドウィック・ボーズマンは私たち観客の目を文字通り釘づけにします。
その表情、声のトーン、仕草。そのどれもが演じているキャラクターの思いを表現することだけに寄与しているのです。
あまりにも圧巻の演技に、心を揺さぶられましたし、同時に『ブラックパンサー』のクライマックスの演説シーンを思い出しました。
チャドウィック・ボーズマンという俳優は、スクリーンやモニターの向こう側で話しているのに、その境界を崩壊させるような力強い演技と言葉を持っています。
つまり、目の前で今まさに彼が喋っている、動いていると錯覚させてしまう不思議な存在感があるのです。
だからこそ、彼は亡くなってしまったけれど、それでも彼はこれまでに遺した作品の中でこれからも生き続けるのだと、そう思えます。
素晴らしい演技に、作品に、そしてそれによって勇気を与えてくれたことに心から感謝しています。
『マ・レイニーのブラックボトム』解説・考察(ネタバレあり)
マ・レイニーが纏った傲慢さという名の鎧
映画『マ・レイニーのブラックボトム』予告編より引用
さて、本作『マ・レイニーのブラックボトム』を見ていると、真っ先に目につくのは「ブルースの母」として親しまれる人気歌手マ・レイニーの振る舞いです。
というのも、彼女の振る舞いは、誰の目から見ても「傲慢」そのものなんですよ。
あいさつ代わりにスタジオへの到着予定時間に大幅な遅刻をし、レコード会社からの要望やリクエストは全て跳ね除けます。
さらに、いざレコーディングがスタートする算段になると、コーラが用意されていないという理由で中断し、レコード会社の人間をイライラさせるのです。
なぜ、こんな振る舞いをするのだろうか、必死に彼女のために働いている人たちが可哀想じゃないか。観客までそんな思いに駆られます。
しかし、そこには彼女なりの理由があったのだということが、物語を通じて明かされていくのです。
なぜ彼女が、一見すると「傲慢」な振る舞いを続けているのか。それは彼女にとって自分を守るための「鎧」なんですよね。
冒頭に彼女が宿泊しているホテルから車へと乗り込んでいくシーンが描かれますが、ホテルのロビーで白人の宿泊者たちから向けられる視線ってすごく印象的ではなかったですか?
あの時、マ・レイニーはそうした視線の存在に気がつき、咄嗟にメイと腕を組み、シルヴェスターの肩に手を伸ばしました。
この行動には、若い彼らを自分が白人から向けられる冷徹な視線から守ってあげなければという使命感もあるのだと思いますが、同時に彼女自身が内に秘めた恐怖や不安も表出しています。
自分1人で立つのが、ふと怖く感じられる。だからこそ同胞に触れ、支え合うことで自らの心の安定を保とうとしているようにも見えるのです。
その後、スタジオの前で車の衝突に伴うトラブルが起きますが、周囲の白人たちは誰も彼女の主張を信じようとはしませんし、レコード会社の人間であるアーヴィンも彼女の言い分を聞くことすらせず、金銭で解決するだけでした。
こうした何気ない場面に、マ・レイニーという圧倒的な地位を確立し、人種を問わず敬意を獲得していると思われる彼女が受け入れる現実的な扱いが滲み出ているのです。
そして、彼女は自分がそうした危うい地位にいることも、そして自分に頭を下げる白人たちが自分の声とそれによって得られる金銭にしか興味がないことを知っています。
だからこそ、自分の身を自分で守るしかないわけですし、同時に自分を「安売り」してしまうわけにはいかないのです。
一たび「安売り」してしまえば、白人たちの都合の良いように扱われてしまい、搾取され、用済みになればお払い箱にされるだけだということを彼女が一番理解しています。
「傲慢さ」ないし「傍若無人さ」の鎧を纏うことで、マ・レイニーは白人のプロデューサーやマネージャーから嫌悪されながらも、自分自身の価値を保つことに成功していると言えるでしょう。
終盤に、彼女がレコード発売に関連した契約書にサインをすることを求められる一幕があります。
一度でも「こいつは簡単にサインしてくれる」と思わせてしまえば、それが先例となり、より程度の低い扱いを受けることになると、マ・レイニーは知っています。
それ故に、簡単にはサインをせず、白人のマネージャーに頭を下げさせた上で、渋々サインをするような素振りを見せるのです。
映画版で追加されたラストシーンは象徴的で、冒頭にレヴィーが書いた楽曲が白人のプロデューサーに買い叩かれ、そして白人のバンドによって演奏されていました。





当時の白人は「ブルース」の何たるかを知らず、楽曲だけを体よく搾取し、扱いやすい白人のバンドに演奏させてしまえば良いと平気で考えていました。現にこうしたケースが音楽業界の歴史には多々あったようです。
だからこそ、マ・レイニーのように黒人でありながら自分自身の価値を保ち続けるのは、非常に難しいことだったのです。
圧倒的な人気と知名度を誇り、そしてそれを白人社会の中で維持していくためには何が必要なのかを肌感覚で理解している彼女が身に纏う鎧。
それを徐々に可視化していくような物語の構成と演出には拍手を贈りたいですね。
どこにも続かない扉。どこにも行けない靴。
映画『マ・レイニーのブラックボトム』予告編より引用
本作は戯曲をベースに作られたということで、基本的には1つのスタジオの中だけで物語が進行していきます。
その中で、やはり印象的なのは小道具であり、とりわけそれは登場人物が履いている靴なのです。
レヴィーは物語の冒頭に靴屋でいかした靴を見つけ、11ドルという大金を払って購入してきました。
そんな彼とは対照的にくたびれた革靴を履いているのは、トレドというバンドの「父親」的な存在の男性です。
レヴィーは野心家のトランペット奏者であり、いつか自分のバンドを持ち、作曲家としても大成するのだという野望を持っています。
それ故に、マ・レイニーのバックバンドという地位に甘んじているメンバーのことを内心で下に見ているわけですよ。
そうした「見下し」が序盤から中盤にかけて続く会話劇の中でじりじりと表出していくのですが、逆に他のバンドのメンバーはそんなレヴィーを小馬鹿にしている節があります。





それを端的に表現しているのが「靴」というモチーフです。
レヴィーは新品でピカピカの靴を履いており、この靴であれば、どこへだって行ける、何者にだってなれるのだと自負しています。
対照的に、他のバンドメンバーとりわけトレドは、黒人が白人社会の中で生きる酸いも甘いも経験してきており、徹底的に打ちのめされ、その靴はボロボロになっていました。
つまり、トレドたちは白人社会の中で黒人たちが生きるために大切なのはある種の「諦念」であると実感しており、それを知らないレヴィーとの間に温度差が生まれているのです。
劇中で、トレドは2度ほどレヴィーの購入した新品の靴を踏みつけます。
それは、黒人として生きることの苦悩や絶望を知った先人からの「洗礼」にも思えるのですが、レヴィーはそれに激高しました。
レコード会社の白人たちに媚び、白人好みの音楽を作り、それでも拒絶され、楽曲に5ドルほどの安賃しか支払わないと告げられ、さらにはマ・レイニーのバックバンドをも解雇されたレヴィー。
そんな彼の自信や夢の象徴でもあった「靴」を踏みつけられること。
それは彼の全てを否定することと同義とも言えるでしょう。
今作では冒頭から幾度となく「開かずの扉」の存在が示唆されてきました。そしてその「扉」を開けようと試みているのが、レヴィーです。
しかし、マ・レイニーから解雇通告を受け、いざその「扉」を開けてみると、その先がどこにも続いていない行き止まりだということに気がつきました。そこでできるのは「ブラックボトム」から空を見上げることだけ。
結局のところ、彼はそれが白人社会における黒人の位置づけなのだと身をもって実感したのかもしれません。
そうした絶望と、そして夢や誇りを傷つけられたことへの怒りが、攻撃性へと転じ、ナイフとして形になり、あろうことかトレドを殺害してしまうのです。
ただ、レヴィーはトレドを刺すことはもはや運命としか言いようがありません。
彼はどこにも行けない、何者にもなれないという現実を突きつけられました。
彼の演じているキャラクターの名前は「Levee」であり、これは「堤防」という意味でもあります。
彼は自分の夢のためにエネルギーや野心をひたすらにため込んでいました。きっと自分のバンドを持ち、作曲家として活動するためのチャンスを得られれば、それらを発揮することができたでしょう。
しかし、彼は自分の中に眠る野心やエネルギーのやり場を失ってしまいました。それでも行き場のなくなったエネルギーをどこかに放出しなければならない。
だからこそ、それを暴力性に転じさせざるを得ず、トレドへの怒りに任せてぶつけてしまったのです。というよりはぶつけるしか術を持たなかったという方が正しいでしょうか。
ただ、これが「ブラックボトム」の悲しい現実なのだということを本作は物語っています。
白人社会の中で、夢や希望を断たれ、絶望と諦念の中で生きていくしかない中で、そうしたものへの憧れやエネルギーを一体何にぶつけたら良いのかというやりきれなさ。
「どう生きれば良いのか?」
作中のセリフでもありましたが、まさしく本作が伝えたい思いはこの言葉に集約されています。
本作『マ・レイニーのブラックボトム』はそうした無情感を見事に描き切りました。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は映画『マ・レイニーのブラックボトム』についてお話してきました。
戯曲ベースの映画ということで、特に役者の技量が求められる映画だったと思いますが、チャドウィック・ボーズマンは本当に圧倒的な存在感ですよね。
夢や野心を持ちながら、それを打ち砕かれ、絶望の中でそのやりきれなさを暴力に変えるしか術を持たなかった男の悲哀を見事に演じてみせました。
また、本作は戯曲からのアレンジ面も素晴らしく、特にラストシーンにレヴィーの血の通った音楽が、白人たちのバンドによって簡素に演奏され、レコーディングされていく様を持ってきたのはアイロニックな演出でした。
作り手が地下のリハーサル室で絶望し、その一方で地上のレコーディング室では彼の音楽だけが白人たちによって金儲けの道具にされていく。
そんなことが音楽業界に限らず、アメリカの歴史の中で幾度となく繰り返されてきたのだと強く実感させられます。
マ・レイニーのように生きられる黒人は一握りであり、多くの才能あふれる黒人たちはきっと「ボトム」の世界で地上の光を見ることもなく、白人たちに搾取され生涯を終えたのでしょう。
そんな悲哀を90分ほどの短い時間の中でまざまざと突きつけるこの作品は、非常に優れていると思います。





ぜひ、多くの人にご覧になっていただきたい1本です。Netflixで配信中ですのでチェックしてみてください。
今回も読んでくださった方、ありがとうございました。